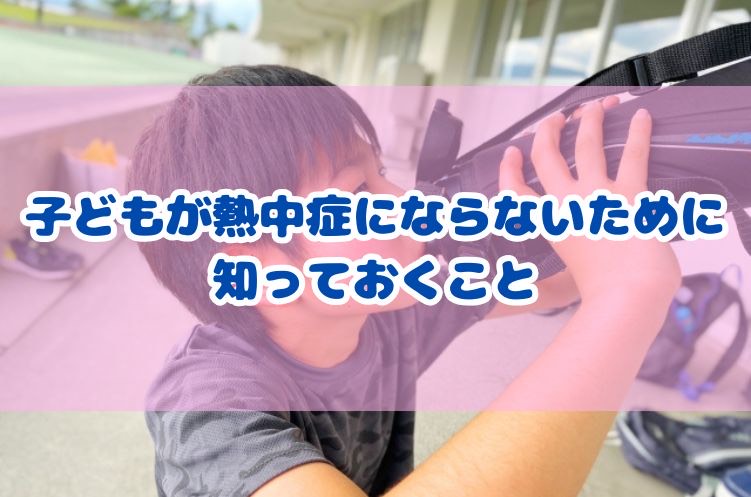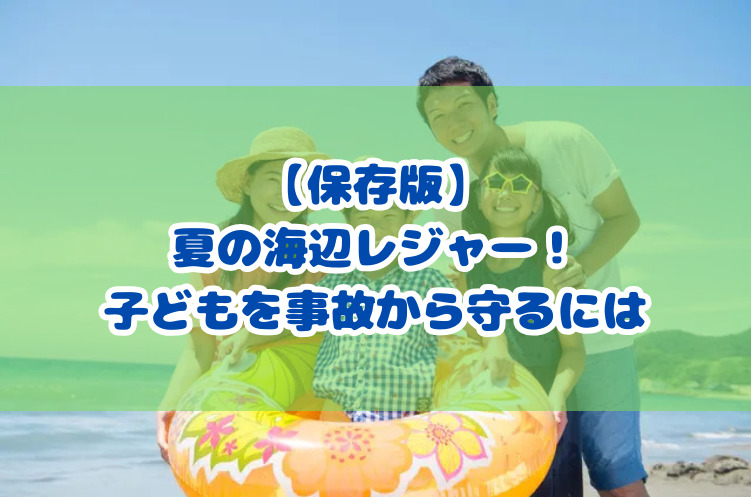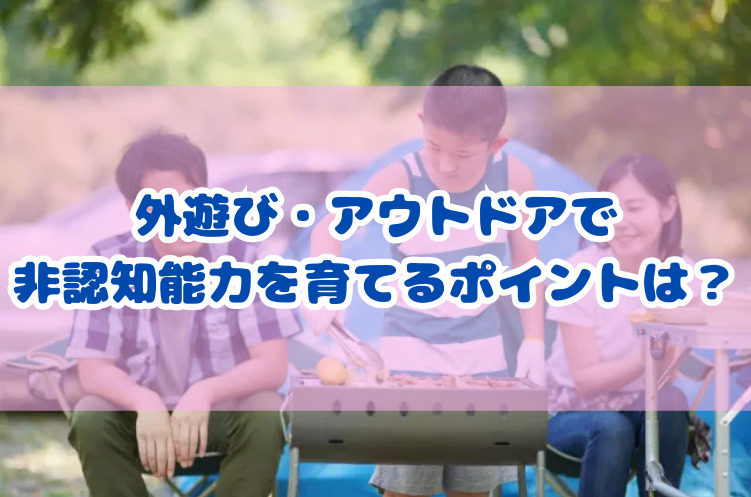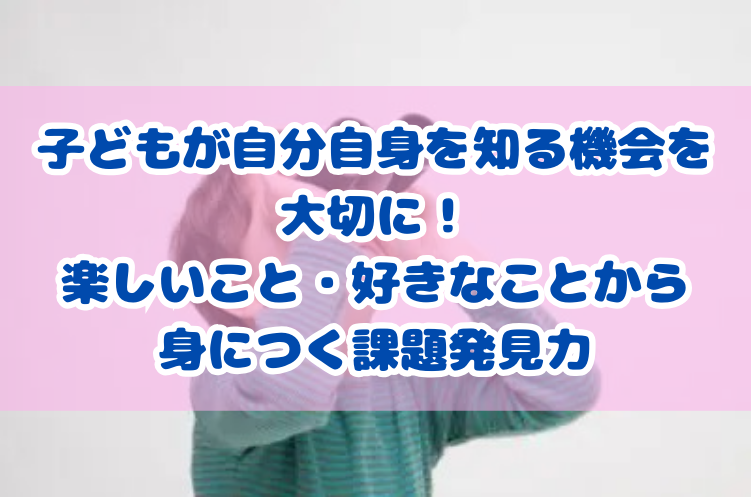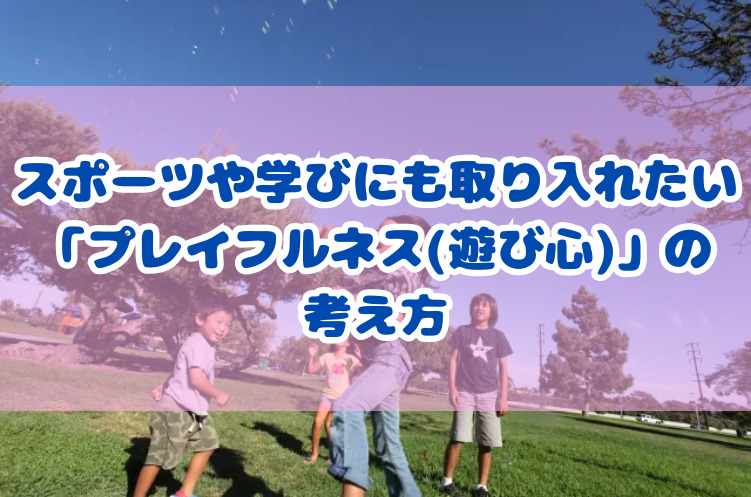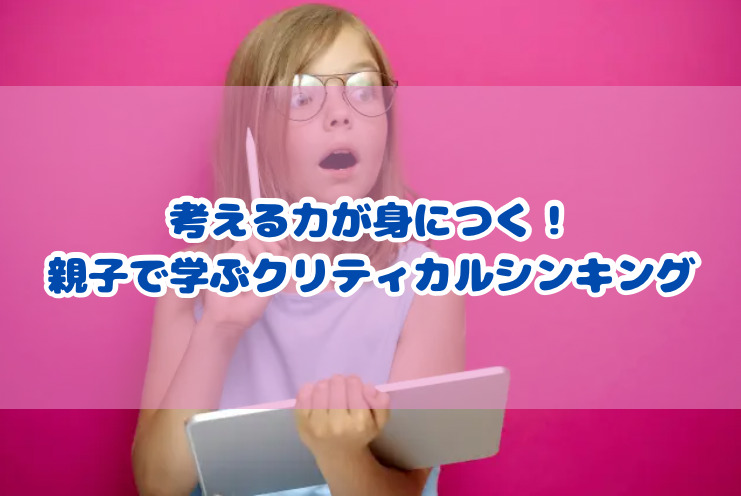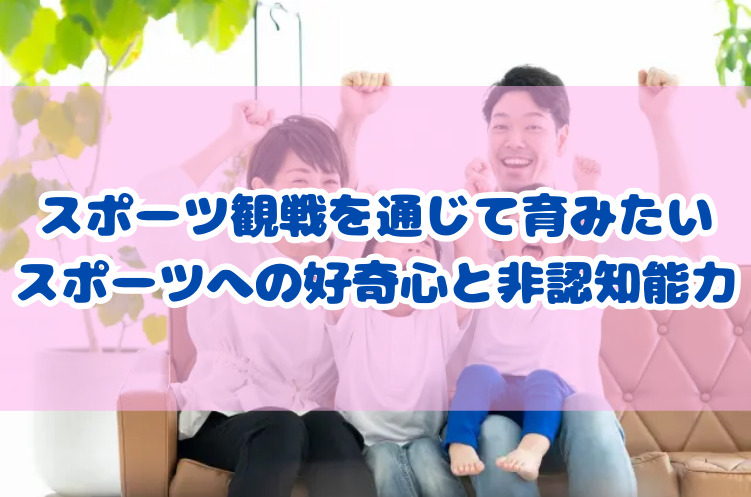自然が最高の遊び場!夏にやりたい親子の外遊び体験
更新日: 2025.08.01
投稿日: 2025.08.19
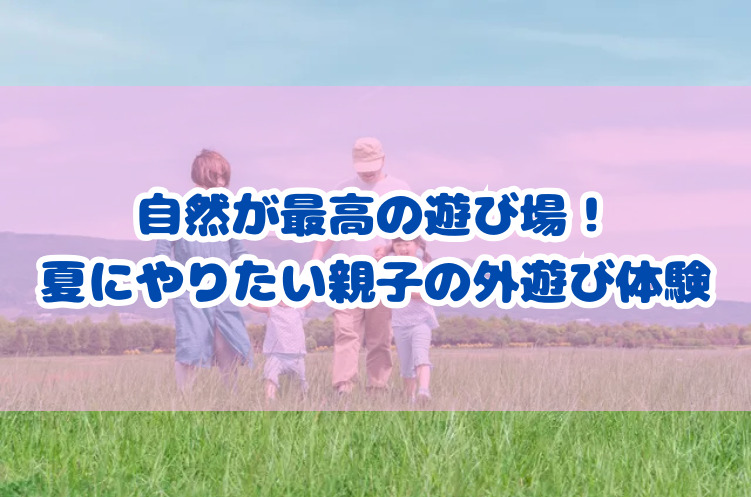
子どもが将来生きていくうえで大切な力として、世界的に注目を集めている「非認知能力」。
挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、問題解決力などからなる非認知能力は、乳幼児期から育むことができるといわれています。
乳幼児期の子どもには「自然遊び」が欠かせませんが、この遊びのなかには、非認知能力を高める要素がたくさんつまっています。
子どもの非認知能力を伸ばす「自然遊び」とは、どのような遊びなのでしょうか。
また、親はどのように関わればよいのでしょうか。
今なぜ「外遊び」なのか?

情報化社会の今、スマホひとつあれば、子どもからの「なぜ?」「どうして?」といった質問に対する答えが出てきます。
とても便利で効率的ですが、それだけに頼っていると、子どもが自分で考えることや、工夫すること、想像することなどの機会が減り、非認知能力を育むことができません。
乳幼児期の子どもの非認知能力を育むいちばんの“舞台”は、「自然」です。
自然にふれていると心も体も開放的になって五感がとぎすまされ、葉っぱの色や形の違いに気づいたり、鳥のさえずりや風の音、川の水が流れる音に耳をすましたりします。
海も山も公園も、身近な自然の遊び場です。
たとえば、たくさんの植物が生い茂る公園では、子どもは木の枝や石、葉っぱなどを拾って積み上げたり、組み合わせたりして “作品”を作るなどして楽しみます。
事前に用意されたものではなく、子ども自身が自由に選び、完成形をイメージしながら自分の想像力だけを頼りに作り上げていくという行動が生まれます。
「どうしたらいいんだろう」「どうなってるの?」と考える→「こうかもしれない」と解決策を思いつく→「じぁあ、こうしてみよう」と実行する・・といった過程はまさに、非認知能力を育むことに直結しています。
では自然遊びによって子どもに備わる非認知能力には、どんなものがあるのでしょうか。
自然から育まれる非認知能力

自然のなかで遊んだり、探索をすることで育まれる非認知能力について、見ていきましょう。
○ 想像力や発想力
○ 主体性や積極性
○ 探究心や好奇心
○ 問題解決力
○ 五感
○ 忍耐力やレジリエンス
想像力や発想力
自然のなかに存在するものは、樹木や花、水、石、葉、空など、シンプルなものばかり。
そこで遊ぶには、自由な発想で遊びの幅を広げ、想像力を働かせて発展させる必要があります。
テレビやゲームから一方的に受ける刺激とはまったく違う、能動的で自主的な遊びが身につくはずです。
自然のなかで工夫をしながら遊ぶことで、想像力や発想力が育まれるでしょう。
主体性
自然のなかの遊びは、ルールもなく「こうすべき」という指針もありません。
自分たちで楽しさを見つけ、それを発展させて遊ぶので、「こうしたらどうだろう」「あれもやってみよう」と自ら考えて動く力が身につきます。
そういった遊びを繰り返すうちに、子どもの主体性・積極性が養われるでしょう。
探究心や好奇心
普段の生活ではなかなか目にすることのない虫や自然の環境は、子どもの探究心や好奇心を刺激します。
落ち葉がひらひらと落ちてきたり、水が砂にスーッと吸収されて消えてしまったり、急に雨が降ってきたり…大人にとっては当たり前のことでも、子どもの目には美しく新しい風景として映るでしょう。
その小さな感動が、「これはどうなってるの?」「次はどうなる?」といった子どもの探究心や好奇心を育てるのです。
問題解決力
自然のなかには子どもが知らないこと、経験したことのないものがたくさん詰まっています。
せっかく作った砂の山が崩れてしまったり…どうしても登れない山道があったら…子どもは「どうしたら次はうまくいくか」を考え、問題を解決するために努力するでしょう。
そんな時、大人が横から口出しをしたり、答えを先に言ってしまうのはNG。
危険がないようにだけ見守り、子どもの問題解決力を育てましょう。
五感
木々の間から見える木漏れ日、葉を揺らす風、葉の下で動く虫たち、川のせせらぎなど、自然には子どもの五感を刺激することがいっぱい。
普段の生活ではなかなか立ち止まることができない、ささやかな自然の現象にゆっくり向き合える機会です。
視覚・聴覚・嗅覚・触覚といった感覚を研ぎ澄まして、子どもの「感じる力」を鍛えることができます。
忍耐力やレジリエンス
自然の中で遊ぶと、
・雨が降ってやりたいことができない
・川の流れが早くて遊べない
・苦手な虫が近くにいる
など、思い通りにならないことに何度もぶつかります。
いつもはわがままな子でも、自然相手になれば仕方がないと諦めたり、代わりの行動を考えたりすることもあるはず。
その思い通りにならないことが、子どもの忍耐力やレジリエンスを育ててくれるのです。
子どもの非認知能力を伸ばす「自然遊び」

公園での遊び
身近な公園でも、さまざまな自然遊びのチャンスがあります。
砂場に水を組み合わせると「どろんこ遊び」ができ、遊びの幅が広がります。
親としては服が汚れるためあまりしてほしくないかもしれませんが、子どもは泥に触れながら「科学」を体験しています。
どろだんご作りは簡単そうに見えますが、根気やちょっとしたコツが必要です。
また指を使って泥に触れることで、五感も研ぎ澄まされ、想像力も養えるでしょう。
そして木の下や草むらを探せば、たくさんの虫や生き物たちに触れ合うことができ、セミの抜け殻などを見つけられるかもしれません。
写真を撮って家に持ち帰り、図鑑やインターネットで調べてみても面白いですね。
海での遊び
海に遊びに行ったら、おすすめは磯遊び。
透明の容器を用意し、水族館をつくるつもりで、いろいろな生き物を探してみましょう。
カニやヤドカリ、イソギンチャクや海藻など、真剣に探すと驚くほど多種多様な生き物が生息しています。
また水の中に目を向ければ、小魚や小さなエビなどが泳いでいることも。
潮の満ち引きに注意して、マリンシューズなどを履いて怪我をしないように気をつけましょう。
川での遊び
川の流れが穏やかなところでは、浮き輪やライフジャケットをつけて水遊びができます。
また浅瀬に集まる川の生き物に注目してみると、ゲンゴロウなどの水生昆虫やカニ、小さな魚などが見えることも。
石を見つけて積んでみたり、水切りをしたり、石ひとつでもさまざまな遊び方を発見できるでしょう。
川で遊ぶ際は、急な増水や水位の上昇に注意しながら、必ず大人と一緒に遊ぶことが重要です。
山での遊び
山に行けば、公園とは違ったダイナミックな遊びができること間違いなしです。
例えば枝やツルを集めて、小さな秘密基地を作ってみたり。
山道を登って探検ゲームをしてみたり。
親子で木登りをしてみるのも、楽しいでしょう。
普段は「ちょっと危ないかな」「周囲の人たちに迷惑かな」と思うようなことでも、せっかくなら安全圏内でトライさせてみるのもいいでしょう。
子どもと「自然遊び」をするときの親の関わり方

遊びを通して養われる非認知能力を引き出し、大きく育てていくキーパーソン、それは「親」です。
自然遊びの中で、親は、
・ 命に関わるケガをしないように遊ぶこと
・ 命に関わる危険を犯さないこと
以上2つを基本に子どもを見守りましょう。
多少のすり傷・きり傷、ドロドロに汚れた服は、「子どもが思い切り遊んだ証」と大らかに構えることが大切です。
また、親が子どもに接するときにありがちなのが、「大人目線」から抜けられないことです。
子どもが変わった形の木の実に興味を抱き、「これは何の木の実?」と質問してきたときなど、「自分は知らない=はずかしい」という気持ちが先に立ってしまい、話をそらしたり、ごまかしてしまいがちです。
大人だってわからないことはあるのですから、「わからないから、あとで一緒に調べよう」でOK。
自然遊びの最中は、雨に降られて走って濡れない場所に逃げたり、大きな葉っぱで頭を隠したりなども、自然の中だからこそできる豊かな体験がふんだんに詰まっています。
子どもの「なんだろう」「面白い」「やってみよう」という自由な発想を大切にして、自主的な遊びを見守り、子どもの生きる力を育んでいきましょう。
・ 「自然遊び」が乳幼児期の子どもの非認知能力を高める
・ 公園へ、山へ、海へ。親子で出かけよう
・ 自然の中では命に関わるケガをしないように遊ぶことが大切だが、制限しすぎはNG
・突然の雨など天候の変化も受け入れ、楽しもう
非認知能力を高めるためには、たくさん自然の中で遊ぶ外遊びが効果的ということが分かりました。
情報社会となっている今の世の中では、経験せずに知識を取り入れることは可能です。
ですが、それ故に「なぜ?」「どうしてなんだろう?」という疑問すらも感じづらい世の中であるとも言えます。
子どもはたくさんの体験を実際にするからこそ、子どもの経験値として糧になり、様々な想像力が生まれ、学習するようになります。
また、より自然遊びを効果的にするためには、親と一緒に遊ぶことが重要です。
一緒に体験し、一緒に考え、一緒に発見する環境を子どもたちの成長のために作ってみましょう!
(参考文献)
・自然あそびで子どもの非認知能力が育つ(長谷部雅一著・東洋館出版社)
・非認知能力が育つ 3〜6歳児のあそび図鑑(原坂一郎監修・いこーよ協力・池田書店)
・HugKum|身近な遊びでOK!? 非認知能力の育て方(大豆生田啓友監修)