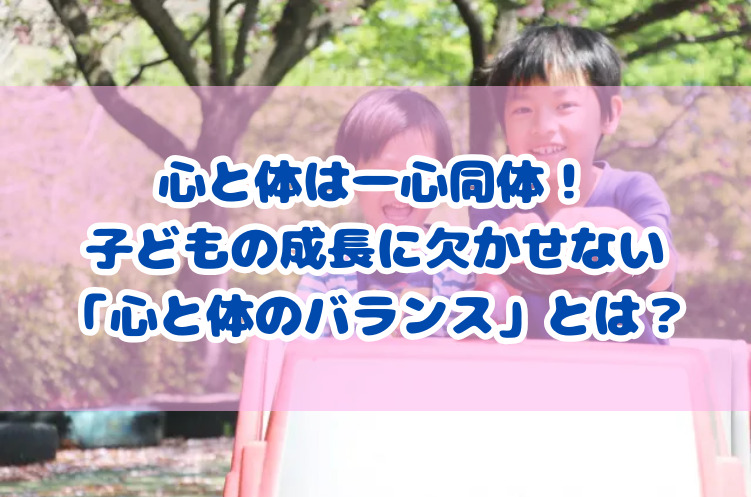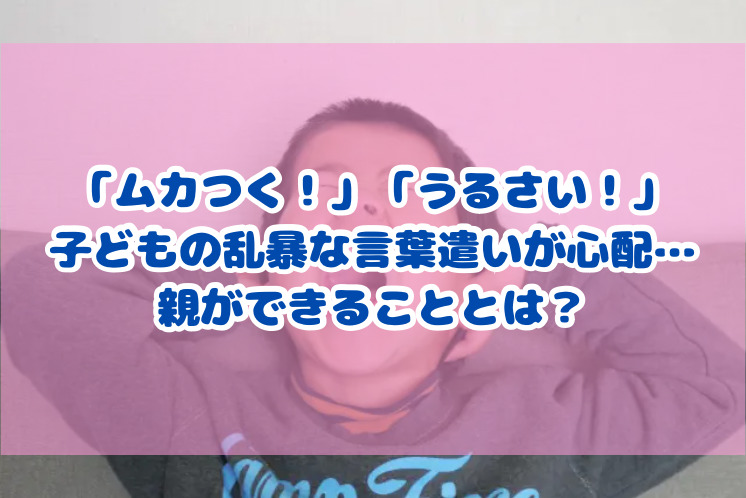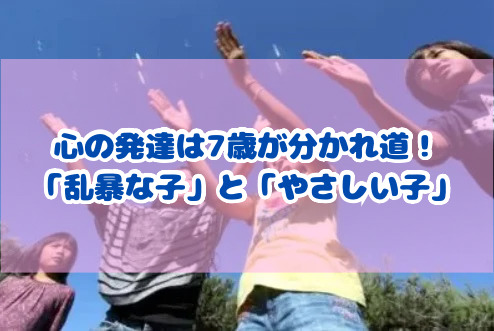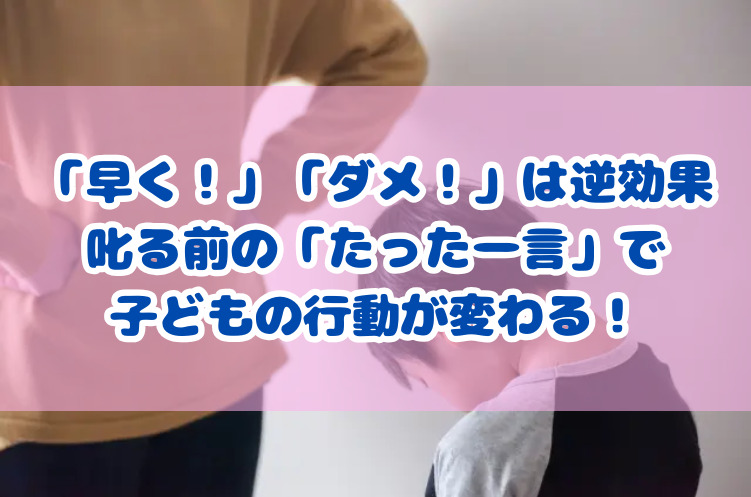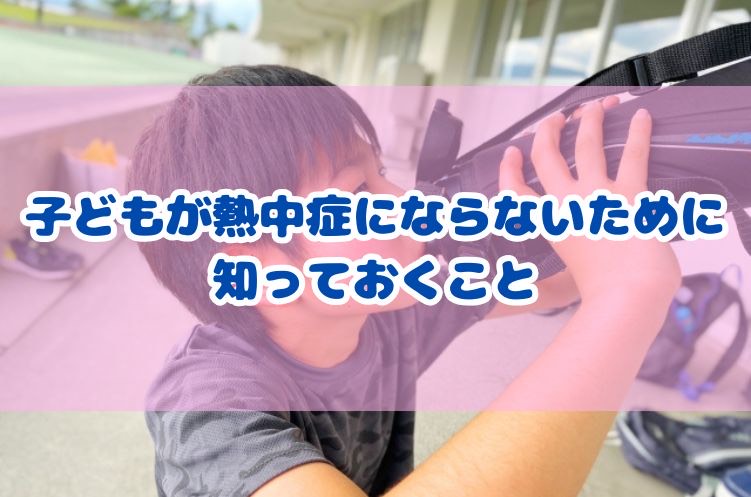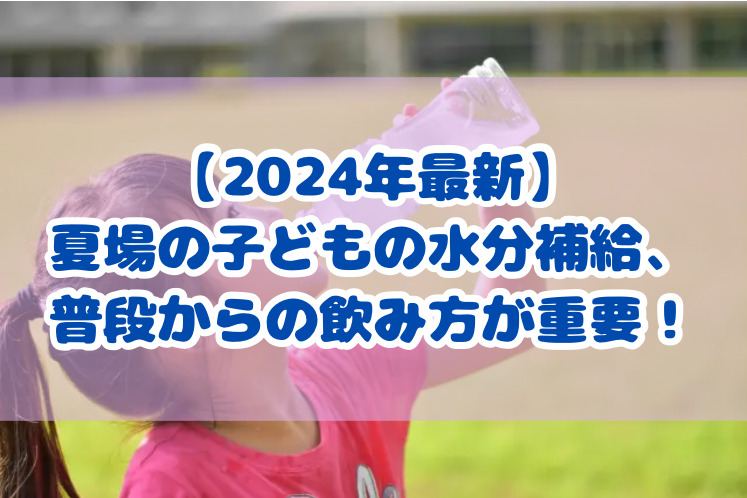気づいたらスマホばかり!YouTubeやゲーム依存の子どもにしないために
更新日: 2024.11.29
投稿日: 2024.12.03

YouTubeやゲームに没頭し、不健康な生活に陥るケースが増えています。
将来そんな事態に陥らないように、親子とも、YouTubeやゲームに振り回されるのではなく、「YouTubeやゲームでの遊びをコントロールできる力」を持てるようにするための方法や関わり方について考えます。
もくじ
適度に遊ぶのは問題ないけれど・・。注意したい「YouTube・ゲーム依存」

子どもの日々の生活と切っても切り離せないYoutubeやゲーム。
好きな動画は何度視聴しても飽きないですし、子どもだけでなく親子で楽しめるゲームや知育関連のゲームもたくさんあります。
これらで適度に遊ぶこと自体は問題ありませんが、「没頭しすぎて他のことをやろうとしない」「夜遅くまでゲームを続け、『やめなさい』と注意をすると逆ギレする」などの様子が見られる場合、もしかしたら「YouTube・ゲーム依存」の状態に陥っているかもしれません。
まずは、お子さんがYouTubeやゲームに依存している状態かどうか、簡単にチェックしてみましょう。
⬜暇さえあれば、YouTubeやゲームをしようとする。
⬜見たり遊んだりするのをやめさせようとすると、怒ったり攻撃的になる。
⬜ YouTubeやゲームの時間や頻度を自分でコントロールできない。
⬜日常生活で、YouTubeやゲームの時間を最優先にする。
ひとつでも当てはまることがある場合は、既にYouTube・ゲームに「依存的」になっている状態といえます。
このような状態を放置してしまうと、お子さんの状態は悪化し、「依存症」に移行する可能性も高まってしまいます。
ちなみに、2018年6月、WHO(世界保健機関)は「ゲーム依存症」を病気として認定し、精神疾患として位置付けました。
YouTubeやゲームに依存しすぎると、
・外で遊ぶ機会が減り、体力が低下する。
・肥満、視力低下、頭痛など健康状態が変化することもある。
・生活リズムが乱れがちになる。
・注意力、集中力が低下しやすくなる。
などの報告があります。
楽しく刺激的なYouTubeやゲームは、「使い始めたらやめられない」という状況をつくりやすいもの。
だからこそ、「YouTubeやゲームでの遊びをコントロールできる力」を育むことが大切なのです。
スマホやタブレットに依存的になると、どんなことが起きるの?

スマホやタブレットの使いすぎが子どもによくないことはうっすらと理解しているものの、具体的には一体どんなことが起きるのでしょうか。
実は想像以上の弊害があることがわかっています。
○ 成績が下がる
○ 睡眠の質が下がる
○ 親子の対話が減る
○ 言葉遣いが乱れたり語彙が減る
○ ながらスマホの危険性
○ 知らないうちに課金してしまい、多額な費用を請求される
成績が下がる
東北大学加齢医学研究所の榊浩平氏が仙台市の小中学生7万人を対象に、インターネット接続できる電子機器の使用時間と国語・算数(数学)・理科・社会の4教科のテスト成績の相関関係を調査しました。
その結果、1日のうち勉強以外で電子機器の使用時間が1時間以内のグループが最も成績がよくなり、それ以降、2時間以内、3時間以内、4時間以内と増えるにつれて右肩下がりに成績が低迷したという結果になりました。
つまりスマホやタブレットを使う時間が長くなればなるほど、成績が下がるというわかりやすい結論が導き出せたのです。
これはスマホなどの使用によって「勉強時間が少なくなってしまった」「睡眠時間が削られてしまっている」ことが原因と考えられるでしょう。
睡眠の質が下がる
スマホやテレビ、パソコンから発せられているブルーライトはとてもエネルギーが高いため、夜にたくさん浴びると、脳が昼間と勘違いして興奮してしまい、睡眠の質が下がってしまいます。
睡眠の質が下がると、脳や体を休めることができないため、朝すっきりと起きられなくなることも。
また昼間に学習した記憶の整理ができなくなるため、成績にも影響が出てしまうでしょう。
親子の対話が減る
スマホなどの電子機器の使用時間が増えると、それに反比例して家族内の会話や対話の時間が減少します。
これは子どもだけでなく、大人が依存傾向にあっても同じです。
よく子どもが一生懸命話しかけているのに、「ちょっと待ってね」とPC作業を優先したり、上の空で返事をしながらスマホをいじっている大人の姿を見かけることがあります。
子どもと一緒の時間は、できれば子どもとの会話を優先したいですね。
言語の発達が阻害され、言葉遣いが乱れる
カナダ・トロント大学の研究者の発表によると、生後6ヶ月〜2歳の乳幼児はスマホやタブレットなどを見る時間が長いほど言葉の発達が遅れる可能性があるといいます。
これは親からの働きかけが少なくなり、アイコンタクトを取りながらのコミュニケーション時間が減ることが一因なのだそう。
語彙や表現方法、コミュニケーション力の習得は乳幼児期のみならず、学童期〜思春期に人と交わり、関わり合いを持つ中で育まれるものです。
また電子機器上でのやり取りは、最低限の言葉や仲間内だけでわかる言語に頼りがちなので、言葉遣いが乱れる傾向があります。
ながらスマホの危険性
歩きながら、自転車に乗りながらスマホを操作する「ながらスマホ」は、事故につながりやすくとても危険です。
2023年にはスマホ使用による死亡事故は25件、重症事故は97件ほど起きています。
スマホを見ながら歩いたり自転車に乗ると、ディスプレイに邪魔されて足元が見えず、車やバイクなどの接近にも気づけないので、大事故に発展する可能性があります。
特に子どもは大人よりも視点が低く、視野が十分に取れないので、さらに危険度が高まります。
知らないうちに課金してしまい、多額な費用を請求される
ゲーム中、プレイヤーに課金させる仕組みは非常に巧妙です。
課金できないようにブロックをしていても、子どもの方が上手で、そのブロックを外してしまうこともあります。
「数百円ならいいかな」から始まり、気がついたら数万円に積み上がっていた…なんて可能性もゼロではありません。
この課金を大人が「仕方がない」と肩代わりしていると、「誰かがどうにかしてくれる」と金銭感覚がズレたまま成長してしまうことになり、とても危険です。
子どもにスマホを持たせる時期や注意点について

今や小学生でもスマホを持つ子は少なくありません。
子どもにスマホを持たせるなら、時期を検討したり、約束を取り決めるなど最初が肝心です。
子どもにスマホを持たせる時の注意点をおさらいしましょう。
スマホを持たせる時期はいつがいい?
モバイル社会研究所の調べによると、「スマホを持ち始めた時期」は中学入学前の12歳が30%ともっとも多く、中学入学をきっかけとして子どもに持たせる家庭が多いようです。
子どもは仲の良い友だちが持ち始めると、「みんなが持ってる」「持ってないと仲間外れになる」などと言い出すかもしれませんが、「ウチはウチ」と流されないようにしましょう。
スマホを持ち始めると、交友関係なども大人が把握しづらくなり、様々なトラブルに発展することもあります。
まずは親が話し合い、持たせる時期についてしっかり考えることが第一歩です。
親がしっかり関与する
スマホを持つのは子どもですが、使用料金を払うのも、何かあった時に責任を取るのも大人です。
ログインパスワードは共有し、小学生のうちは履歴を確認するようにしましょう。
携帯会社や検索エンジンが提供するアプリなどを利用すると、子どもの使用履歴がチェックできます。
またフィルタリングは必ずかけて、「見てよいもの・ダメなもの」を伝え、「課金はしない」などの約束事を親子で決めましょう。
親がイニシアチブをしっかり握り、使用制限をかけることは犯罪やトラブルから子どもを守ることにもつながります。
ルールの制定
子どもにスマホを与える時は、最初のルール制定がとても大切です。
・食事中は触らない
・友だちを傷つけるようなことはしない
・時間制限
などの約束を最初に決めて、「それを守れないなら、まだ持つ時期ではない」ということを伝えましょう。
ルールを決める際、大人が決めたものを一方的に伝えるのではなく、親子で一緒に話し合って決め、「自分もルールづくりに参加して決めた」と子どもが納得できることが大切です。
またルールを守れない時は、「時間超過を3回したら、一週間使用禁止にする」などのペナルティも同時に決めておくと、親の対応も迷わなくなります。
「ルールを破ってもペナルティがない」のは、子どもをスマホ依存に近づけてしまうことと考え、文句を言われても毅然と対応しましょう。
ルールを守れないことが続いた時は、再度親子で話し合い、ルールそのものを見直すことが必要かもしれません。
YouTube・ゲーム依存の子どもにしないための関わり方

YouTube・ゲーム依存の子どもにしないためには、親がどのように関わればよいのでしょうか。そのポイントを6つ紹介します。
時間や回数などを決める
子どもがYouTubeやゲームを利用する時間や回数、「必ず宿題を終わらせた後で」などのルールを、親子で話し合って決めましょう。
子どもの年齢や性格、生活リズムなどを考慮し、適切な時間や回数について子どもが納得できるよう、一緒に話し合って決めます。
「今日は雨が降っていて外遊びできないから使おうね」「今日は第3話まで見るの?」など、利用する時間だけでなく利用目的や範囲についても親子で確認し合うよう心がけましょう。
終わったあと、内容について会話する
YouTubeやゲームを見た・遊んだあとは、内容について子どもと会話をしましょう。
ゲームで遊んだ場合は、どんなゲームをしたか、どんなことをしたかなどを聞いて、子どもの興味や関心を理解するようにします。
また、YouTubeで視聴した動画の内容について、子どもの意見を聞いたり感想を述べたりすることで、子どもの思考力や理解力を育むことができます。
やめようとしないときは別の行動を促す
YouTubeやゲームをやめようとしない場合は、別の行動を促しましょう。
外遊びやスポーツ、読書、勉強など、子どもが楽しめる他の活動を提案します。
また、子どもがYouTubeやゲームをやめられない理由を聞き、その理由を解決できるようにサポートすることも大切です。
子どものYouTubeやゲームの利用状況を把握する
子どもがYouTubeやゲームをどのくらいの時間利用しているか、どのような内容を視聴・プレイしているかを把握しておきましょう。
子どもの利用状況を把握することで、子どもの興味や関心を理解し、適切な関わり方を考えることができます。
必要に応じて時間制限のアプリを入れるのも一案です。
子どものYouTubeやゲームの利用にネガティブなイメージを持たせない
YouTubeやゲームを完全に禁止してしまうと、子どもが逆に興味を持ち、依存症のリスクが高まる可能性があります。
YouTubeやゲームを悪いものとして否定するのではなく、適切に利用すれば、子どもの成長に役立つものであることを伝えましょう。
子どものYouTubeやゲームの利用に親が一緒に関わる
子どもと一緒にYouTubeやゲームを楽しむことで、子どもの興味や関心を理解し、適切な利用方法を教えることができるでしょう。
また、子どもがYouTubeやゲームに没頭しすぎないよう、親が一緒に時間を管理することも大切です。
お母さんお父さんも、デジタル機器との関わり方を振り返ろう

YouTubeやゲームは、子どもだけでなく大人も楽しめるものだからこそ、子どもにYouTubeやゲームの制限をかけるだけでなく、自分自身のデジタル機器との関わり方を振り返る必要があるかもしれません。
YouTubeやゲームを悪いものとして否定するのではなく、適切に利用すれば、子どもの成長に役立つものであることを伝えましょう。
お母さんお父さんも、「1日あたりの利用時間を決める」「就寝前や食事中の利用は控える」「スマホに子守りをさせない」「子どもが寝る時はスマホではなく本や絵本を読む」など、これを機に自分なりのルールを見直しましょう。
また、デジタル機器の利用を一定期間中断する「デジタルデトックス」もおすすめです。
デジタルデトックスをすることで、デジタル機器への依存度を下げ、心身をリフレッシュすることができるといわれています。
デジタルデトックスを行う時には、旅行やキャンプ、家族で楽しめるスポーツ、散歩、アナログゲームなど、リフレッシュできる楽しみを探して、家族一緒にデジタル機器から距離を取るのがポイント。
デジタル機器に奪われていた時間を取り戻すことによって、直接的なコミュニケーションの機会が生まれます。
視線を交わし合い、ゆっくりと会話するだけでも親子の信頼関係が育まれ、子どもにとって何よりの楽しい時間になるでしょう。
YouTubeやゲームから与えられるものではなく、現実生活から得られる多様な経験が、子どもの心身の成長には不可欠です。
また、親自身の成長という意味でも、子どもとの直接的な関わり、日々のふれあいの中で学べることや感じることがたくさんあるはず。
YouTubeやゲームと適度に関わり、ときには共に楽しみながら、電子機器を介さない親子の時間も大切にしましょう。
・「ゲーム依存症」は、精神疾患として位置付けられている。
・ルールづくりは親子でじっくり話し合いながら決めよう。
・親自身もデジタル機器との向き合い方を振り返ることが大切。
参考文献)
「YouTube依存は改善可能 子どもへの悪影響と今すぐできる8つの対処法」(出典:コノミライ)
「スマホ依存の子どもにしないために」(監修:石川結貴、出典:PHPのびのび子育て)
「脳科学からみた男の子のちゃんと自立できる脳の育て方」(著:成田奈緒子、PHP研究所)
「デジタルデトックスの効果とは? 親子でできるおすすめの方法を専門家が解説」(出典:ウチコト)
「研究者が思わずゾッとした「子どものスマホ使用時間と偏差値の関係」小中学生7万人調査でわかった衝撃の事実(出典:プレジデントオンライン)
「ウチの子は大丈夫?ながら歩き・歩きスマホの危険」(出典:セコム)