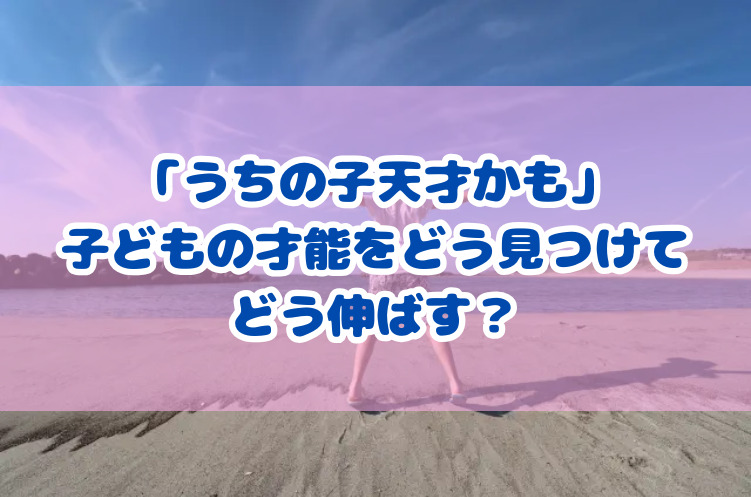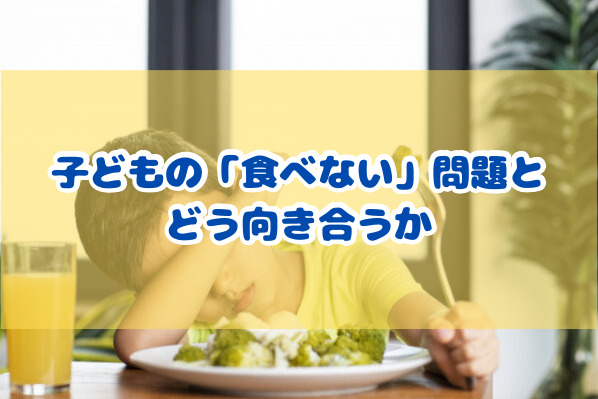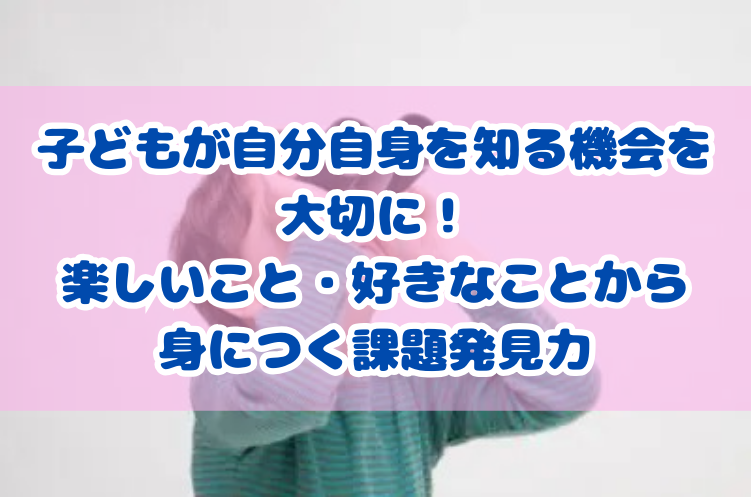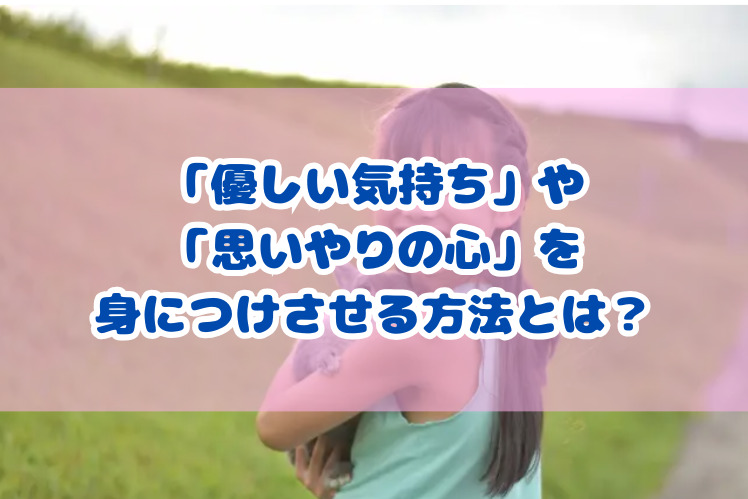苦手克服よりも「得意」「好き」をぐんぐん伸ばそう!
更新日: 2025.04.16
投稿日: 2023.06.23
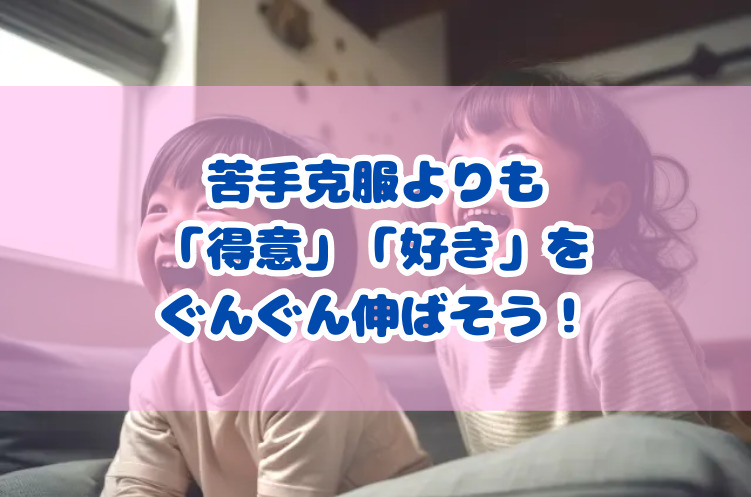
大人はつい子どもの苦手とするものや弱点が目について、
「ドリブルが苦手だから、もっと練習をしなさい」
「弱点の算数にもっと力を入れなさい」
などと、克服させようとしてしまいます。
しかし苦手分野を引き上げて、弱点克服に時間を割くのは、本当に子どものためになるのでしょうか。
今回は、苦手克服よりも「得意」や「好き」を伸ばすメリットを紹介していきます。
もくじ
「弱点克服」は子どもにプラスになるのか
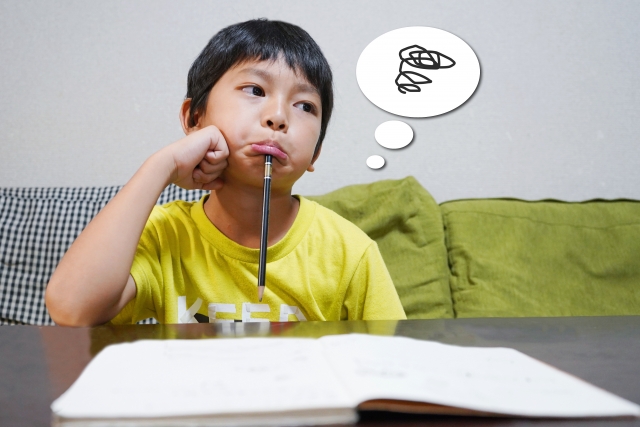
保護者の人は、「苦手分野に力を入れろ」「弱点を克服しよう」と言われて育ってきませんでしたか?
日本の教育はどんな教科もまんべんなくできることを求めるので、「得意なことを伸ばす」よりも「できないことをなくす」ことに注力されがちです。
例えばテストや受験、スポーツのメンバー争いなど、点数がついたり、ライバルと差をつけなければいけない場面では、「苦手克服」が必要なこともあるかもしれません。
しかし苦手分野や弱点の克服をするよりも、実は「好き」「得意」を伸ばす方が子どもも前向きに取り組むことができ、いつのまにか苦手を克服していることも多いのです。
では「弱点克服」と「得意を伸ばす」のメリット・デメリットを考えてみましょう。
子どもにとって弱点を克服するメリットはある?

不得意なことに取り組んだたり、弱点を克服すると、
・弱点を知ることができる
・苦手意識がなくなる
などのメリットはあります。
そして苦手分野に取り組まないと、「弱点から目をそらす」「わがままになる」「忍耐力が育たない」といったイメージがあり、教育的観点から子どもに「やらせなければ」と思ってしまう保護者が多いのです。
一方、苦手なことに取り組むことで生まれるデメリットもあります。
◯ 必要以上に時間がかかる
◯ 前向きに取り組むのが難しい
◯ 自信喪失につながることがある
◯ 得意だったこともやる気が喪失する
必要以上に時間がかかる
誰にとっても「嫌いなこと」「苦手なこと」に取り組むのは辛く、好きなことをするよりも時間がかかります。
エンジンがかかるまでの時間も長く、取り組んでいる間の集中力もキープするのが難しいでしょう。
しかも時間をかけて克服できればいいですが、それは未知数。
見ている保護者もイライラを感じ、不必要に怒ってしまいそうです。
前向きに取り組むのが難しい
不得意分野や苦手を克服しようとするのですから、子どもにとっては楽しく感じられないでしょう。
それでも「やらなければ」という使命感や責任感、もしかしたら大人に言われて無理やり頑張るケースもあるかもしれません。
後ろ向きな気持ちで取り組むと、ますます苦手意識が強くなりかねません。
自信喪失につながることがある
自分のダメな部分に向き合わなければならないので、「やっぱりダメだ」「自分にはできない」と、苦手を克服する前に自信を喪失する可能性も。
そして見守る大人が「こうしなさい!」「なんで分からないの」などと厳しく指導してしまうと、「できない自分」「ダメな自分」にフォーカスしてしまい、負のスパイラルに突入するかもしれません。
得意だったこともやる気が喪失する
大好きなサッカーなのに、苦手なドリブルばかりを練習させられることで、サッカー自体が楽しくなくなってしまったり。
得意な教科はやらずに、苦手な勉強ばかりをやらされることで、机に座ることが苦痛になったり。
「苦手」や「弱点」に取り組むうちに、「得意なこと」「好きだったこと」が萎んでしまうのでは本末転倒です。
子どもは「長所進展法」で伸ばそう

かの吉田松陰は自身の教育法のなかで、「長所を見て短所を見ない」「短所にはさわらない」と言っています。
弱点を改善するよりも、よい部分を見つけて伸ばす「長所進展法」が、子どもや弟子を育てるには有効であると、200年も前に説いていたのです。
この長所進展法は、楽観性や自己効力感、やる気や自分を信じる力など、非認知能力を育てるにも非常に役立ちます。
目につきやすい子どもの苦手分野を克服させる労力より、一つでも得意な部分を見つけて応援する方が、保護者にとっても気持ちが楽ですね。
・頑固 → 意志が強い
・流されやすい → 協調性が高い
・落ち着きがない → 好奇心旺盛
など、弱点だと思っていたことを逆から見てみたら、意外にも長所になるかもしれません。
長所進展法は、子どもへの視点を転換するきっかけになるかもしれません。
「好き」「得意」を活かせば、苦手もカバーできる!

弱点や苦手な部分はとりあえず一度横に置いて、子どもの得意なことや好きな分野に注目してみましょう。
・目をキラキラさせているのは何をしている時か
・集中して読んでいる本はどんな分野か
子どもの様子をよく見て、子ども自身が選ぶ「好き」「ワクワク」「得意」を理解することから始めてみましょう。
「努力」「くじけない気持ち」「創意工夫」といった前向きで強い気持ちは、好きだからこそ生まれてくるものです。
また好きなこと、得意なことを深く突き詰めているうちに、苦手なことの突破口が不意に見つかることも。
例えば、国語好きで算数が苦手な子が、文章問題を解くようになったら俄然算数も得意になったり。
自己主張が苦手なおとなしい子が、話を聞くのは好きだからと友だちの話をよく聞いてあげていたら、いつの間にか人気者になっていたり…。
大人が考える子どもの「短所」や「苦手」が、その子にマイナスに働くとは限りません。
子どもの「好き」を応援する方法とは

「ゲームに夢中だけど、それってどう伸ばせばいいの?」と大人が理解しづらい「好き」もあるでしょう。
子どもなりの攻略法をノートにまとめて、本のように編集させてみたり、ゲームの世界観を絵やマップに書き起こしてみたり、ただひたすらゲームに没頭させずに次のステップを提案してあげるのも保護者の役目。
子どもの気持ちが向かう方向へ、ヒントを与えながら背中を押してあげるだけで、子どもは驚くような力を発揮する可能性もあります。
何より楽しいこと・好きなことをしている子どもは、やる気がどんどん補充されて、元気で明るく前向きな力に満ちてくるでしょう。
そして何か突出したものを手に入れられれば、それが子どもの一生の「武器」になるかもしれません。
・日本では「得意を伸ばす」より、「苦手をなくす」に注力しがち。
・弱点克服は、子どもが前向きになれず徒労に終わることも多い。
・苦手をなくそうと努力するうちに、得意だったことにも興味を持てなくなることも。
・子どもの「好き」を伸ばす「長所進展法」がおすすめ。
・好きなことを思い切り伸ばせば、一生の「武器」になる。
(参考文献)
NHKすくすく子育て情報 | どう伸ばす?子どもの可能性
東洋経済オンライン | 子どもの「苦手意識」を根本から変える3法則
Nobiko | 短所ばかり見ていませんか? 親の「目線」が子どもの性格を決める!