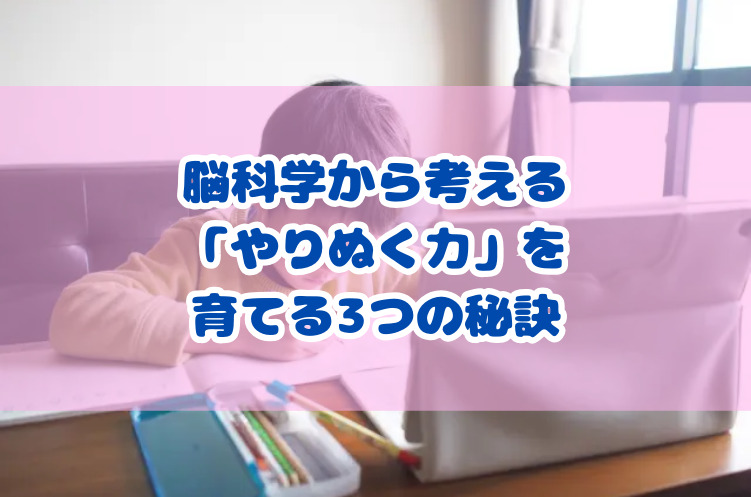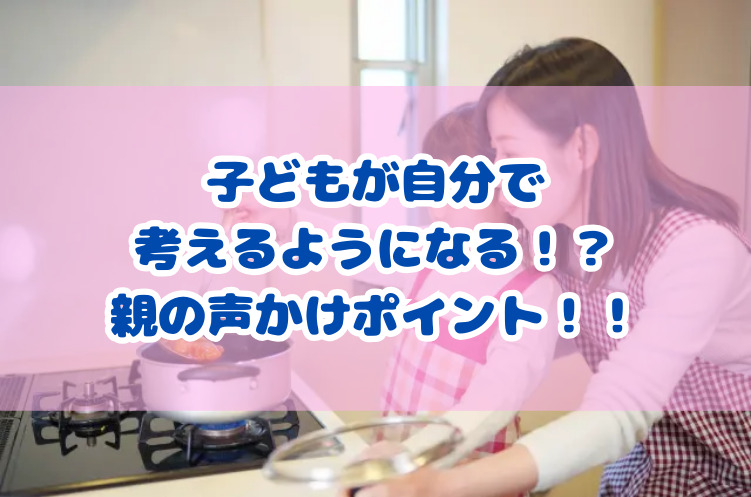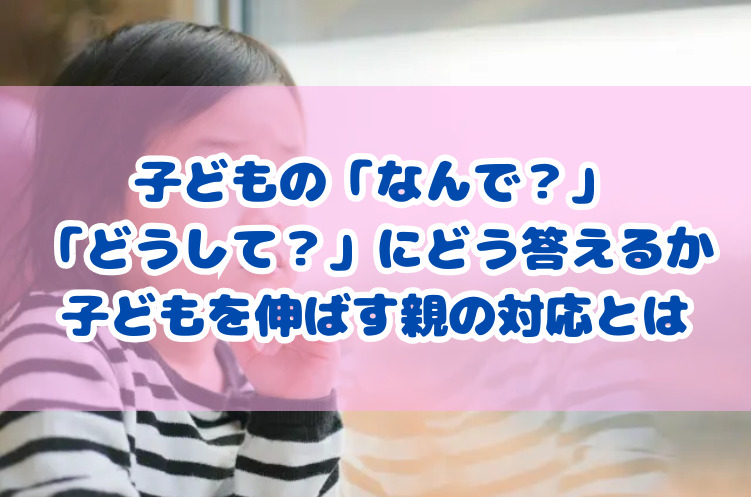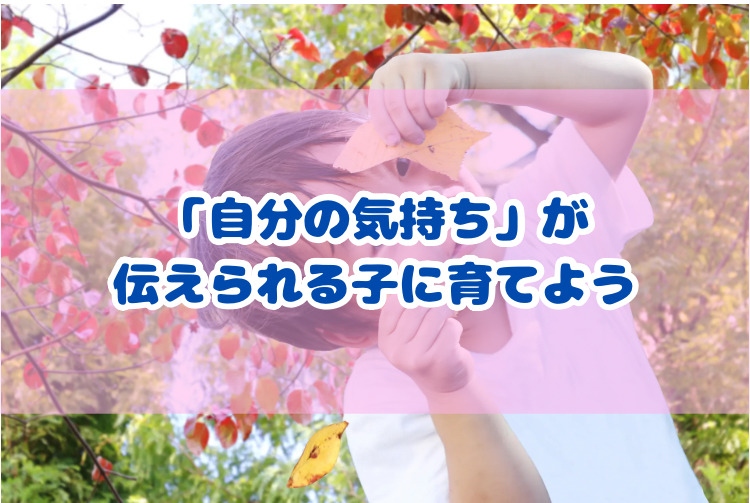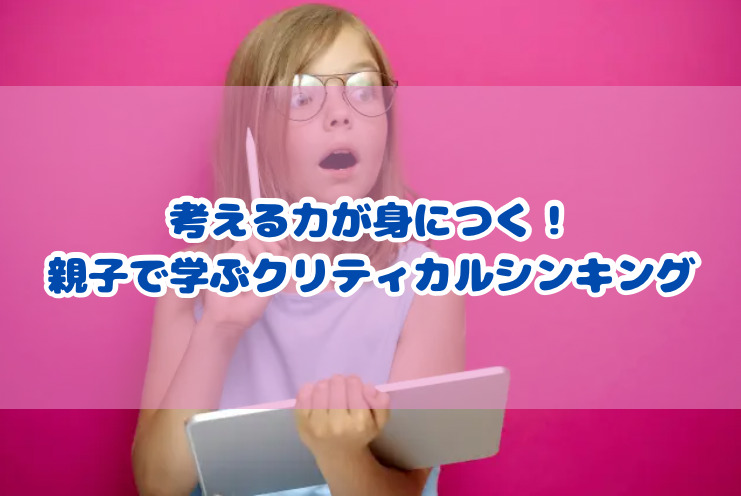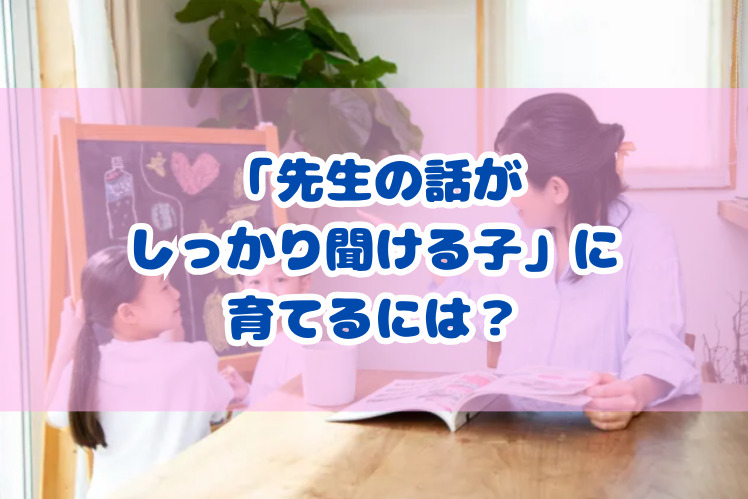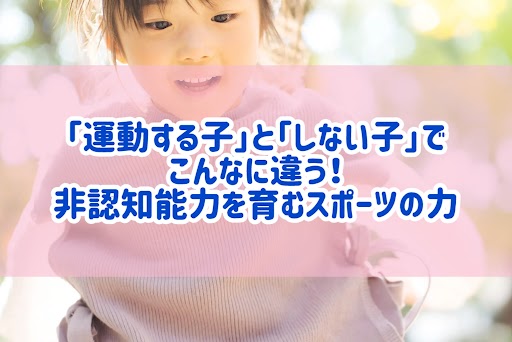3歳・7歳が決め手!年齢別 子どもの「考える力」の伸ばし方
投稿日: 2025.11.18
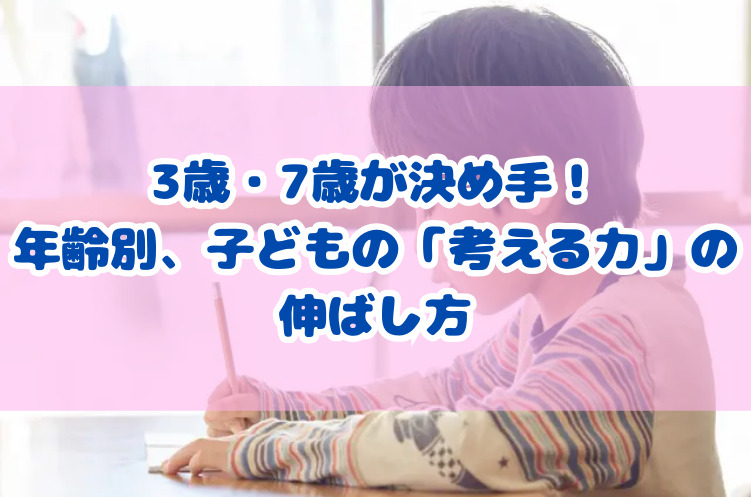
親なら誰しも、わが子に対して、「自分で考え、自分で行動できる子になってほしい」と思うものです。
「考える力」を伸ばすためには、子どもの成長や発達に応じ、親をはじめとする周りの大人が適切に、丁寧に関わっていくことが大切です。
それにより自立心が育まれ、自分で行動できる子に成長していきます。
子どもの「脳」の成長や発達を考えたとき、「考える力」の素地が作られる時期は、3歳から7歳です。
自分で考える力をぐんぐん伸ばしていく時期が、7歳から10歳と言われています。
「脳の成長」という視点から、子どもの「考える力」の伸ばし方を、年齢別に紹介します。
子どもの「考える力」を育むために、「脳の成長」を知っておこう

子どもの頭の中=脳は、体の成長に負けないくらい、日々驚くほど生まれ変わっています。
0歳から3歳の脳は、まだまだ未熟な状態で、脳神経細胞が爆発的に増えていく時期です。
どんどん増えた細胞の数がピークに達するのが、3〜4歳頃です。
ここから7歳くらいまでの子どもの脳内では、不要な細胞を間引いて脳細胞の選別が行われます。
「脳の成長」という視点で考えると、3歳から7歳の時期は、「考える力」の基礎づくりの時期ともいえます。
7歳から10歳は、脳細胞の選別が完了し、残った脳細胞が情報伝達回路をどんどん進化させていく時期です。
この時期の子どもは、自分で考えたことをやり遂げることに喜びを感じることで、思考力をどんどん伸ばしていきます。
子どもの成長は、いわば、「脳の成長」に値します。
子どもの脳の成長に合わせ、関わり方や導き方を変えていくことで、「考える力」を伸ばしていくことができるのです。
3歳、7歳って、どんな時期?
子どもの発達には、成長のリズムがあります。
スキャモンの発育曲線によると、神経系の発達は生まれてからおよそ7歳頃までに、成人の約90%に達すると言われています。
つまり、3歳から7歳は「脳の黄金期」。
この時期に、感じ取る力・覚える力・考える力の土台が一気に育っていくのです。
3歳——自我の芽生えと「魔の3歳」
3歳前後は「魔の3歳」とも呼ばれる時期。
自我が芽生え、「自分でやりたい!」という気持ちが強くなります。
大人にとっては手がかかる時期ですが、実はこの“反抗”こそが「自分で考える」ための第一歩。
言葉を通して気持ちを表現したり、原因と結果を少しずつ理解したりと、論理的思考の芽が出はじめます。
7歳——論理と社会性が芽生える「脳の黄金期」

7歳前後は、心と頭がぐんと成長する時期です。
この頃の子どもは、他人の気持ちを理解したり、物事を筋道立てて考えたりする力が発達します。
学校生活が始まり、社会の中で自分の役割を意識し始めるのもこの頃です。
その一方で、「なんで?」「どうして?」と理屈を求める場面が増え、「親と自分は違う」という気持ちが強くなり、口答えや反抗的な態度が増えて、口出しされたり干渉されることを嫌がります。
「中間反抗期」とも呼ばれますが、これも健全な成長の証です。
子どもの「考える力」が育つと、どのような影響があるの?

子どもの「考える力」は、単に勉強ができるようになるための力ではありません。
自分で課題を見つけ、解決策を考え、行動に移す力──それが、これからの時代に最も求められる“生きる力”の基盤になります。
学びの意欲と理解力が深まる
「なぜ?」「どうして?」と考える習慣がある子どもは、与えられた知識をそのまま覚えるのではなく、自分の中で整理して理解しようとします。
たとえば、算数の問題でも「なぜこの答えになるの?」を考える姿勢が育つため、応用力が自然と身につきます。考える力が育つと、学ぶこと自体が「楽しい」と感じられるようになり、主体的な学びが広がります。
問題解決力・自己決定力が育つ
考える力がある子どもは、失敗や困難に直面したときに「どうしたらうまくいくかな?」と自分で方法を探そうとします。
これは、社会に出てからも必要不可欠なスキル。
子ども時代から「自分で考え、選ぶ」経験を積むことが、自立の第一歩になります。
感情のコントロールや他者理解が進む
考える力は、感情を言葉で整理し、他人の立場を想像する力にもつながります。
「どうして友達は怒ったのかな?」「自分はどうしたかったんだろう」と考えられる子は、トラブルを受け止める経験を重ねながら、相手と建設的に関われるようになります。
思考力とともに、社会性や共感力も育っていくのです。
将来にわたって“生き抜く力”になる
AIやテクノロジーが進化し、情報があふれる時代では、「与えられた答えを覚える」だけでは通用しません。
必要なのは、状況を見極め、自分なりの答えを導き出す力。
幼児期・児童期に育まれた「考える力」は、将来の進路選択や仕事、人間関係など、人生のあらゆる場面で子どもを支える「生き抜く力」となります。
3歳から7歳の子どもの「考える力」の育て方〜
子どもの好きなことを尊重して考える力の基礎をつくる

前述したように、3歳から7歳は、脳内で爆発的に増えた細胞から不要な細胞を間引き、脳の神経回路のベースを作って考える力の基礎をつくる重要な時期です。
大切なことは、以下の3つです。
好きなこと、興味のあることを尊重する
日々の遊びの中で、好きなことや興味のあるものができるのがこの時期です。
自分の気持ちのおもむくままに好きなことをたくさんさせてもらった子は、親から指図されなくても自分で考え、さまざまなことに自主的に取り組むようになり、自立心が育ちます。
子どもの好きなこと、興味のあることを尊重するような関わりを心がけましょう。
・「すごいね、それどうやって思いついたの?」
・「前より上手にできたね。次はどうしてみようか?」
・「これが好きなんだね。どんなところが面白いの?」
くり返し遊びを中断しない
同じ遊びを何度もくり返している様子を見るとつい、「いつまで同じことやってるの?」などと言っていませんか?
子どもは、くり返し遊びをすることによって、ちょっとした違いに気づいたり、よりよいやり方を考える力が養われていきます。
この時期のくり返し遊びは、できるだけ見守りましょう。
・(積み木を崩してしまったとき)「あ、崩れちゃったね。次はどうしたら倒れないかな?」
・(同じ遊びを続けているとき)「何か新しい工夫をしてるの?」
・「さっきより高く積めたね。どうしてだと思う?」
親子でたくさん会話する
子どもの気持ちに共感し、「どうしてそう思うの?」などと理由を聞いたりして言葉のキャッチボールを重ねましょう。
・子ども「なんで空は青いの?」
親「いい質問だね! 空って本当は何色だと思う?」
・子ども「これ難しい…」
親「そうだね。どこが一番難しいと思う?」
・子ども「やりたくない!」
親「そっか、やりたくないんだね。どうしたら楽しくできるかな?」
子どもからの「なぜ?」「どうして?」にもできるだけ受け止め、「すごいことに気づいたね」「あなたはどう思う?」などと会話を重ねていきます。
これを続けることにより、自ら考えることができ、自分に自信が持てるようになります。
7歳から10歳子どもの「考える力」の育て方〜
「やり遂げる」関わりを心がけ自分で考える力を伸ばす

脳細胞が情報伝達回路をどんどん進化させていく時期です。
自分で考えたことをやり遂げることに、いちばんの喜びを感じます。
この時期に親が心がけたいポイントは、以下の3つです。
先回りして指示や命令しすぎない
「今から明日の学校の準備をしておきなさい」「ハンカチはこれを持っていきなさい」など、親の先出し指示が多すぎると、言われたことはできるけれど、自分で考えて動く子にはなりません。
子どもに対する“先回り”は、極力控えましょう。
「やり遂げる」ことができるよう応援する
7歳からの子育ては、「自主性」がテーマです。
「自分で決めたことを自分で達成したい」という気持ちが強くなります。
子どもががんばっていることを見つけてほめ、失敗したり悩んだりしている時は、「このやり方とこのやり方があると思うけど、どっちを選ぶ?」など、「指示」でなく「提示」を。
最後までやり遂げる経験を積み重ねましょう。
本を読むことで、考えを組み立てられるように
小学校に入学し、自分で本を読めるようになるこの時期は、本を読むクセをつけることも大切です。
一緒に図書館に行って本を探したり、家で教科書を一緒に読み、「今どんなことを勉強しているの?」と聞くのもよいでしょう。
読書を通して正しい日本語を吸収し、自分の考えを組み立てられるようになります。
子どもの「考える力」を育てるには親の声かけや体験活動が大切

子どもの「考える力」は、机の上の勉強だけで育つものではありません。
日々の生活の中で、親や周りの人がどんな言葉をかけ、どんな体験を一緒にするかが、子どもの思考の芽を大きく伸ばしていきます。
たとえば、散歩の途中で見つけた花を見て「きれいだね」と終わらせるのではなく、
「どんなにおいがするかな?」「前に見た花とどう違う?」などと問いかけることで、子どもは“自分の頭で考える”きっかけを得ます。
こうした何気ない声かけが、観察力や想像力、言葉で考える力を自然に引き出していくのです。
また、体験活動も大切な学びの場です。
料理や工作、自然遊びなどの中で、子どもは「うまくいかない」「もっとこうしてみたい」といった試行錯誤を重ねます。
親が「どうしたらできると思う?」「次はどんな方法を試す?」と寄り添うことで、自分で考えて解決する力がぐんと育ちます。
カギは、親が“正解を教える”のではなく、“考える時間を一緒に楽しむ”こと。
日常の小さな会話や体験こそが、子どもの思考力を大きく伸ばす土台になるのです。
・子どもの「考える力」を育むには、脳の成長=年齢に応じた働きかけや関わりが重要
・3歳から7歳の時期は、子どもが好きなこと、興味のあることと、とことん向き合える関わりを心がける
・7歳から10歳の時期は、最後までやり抜く経験を積み重ねられるよう応援する
・子どもの「考える力」は、親や周りの人からの声かけや体験によって育まれる
子どもの考える力を伸ばすためには、子どもが主体的であることが大切です。
親が無理矢理やらせようとしても逆効果になりますので、子どもの興味のあることや好きなことからもっと興味を引かせるような問いかけや声掛けをすると子どもの考える力はどんどん伸びていきます。
子どもの年齢や状況に合わせて、大人がどのように関わっていくかがとても大切です。
(参考文献)
・ 子どもの才能は3歳、7歳、10歳で決まる!(著者: 林 成之 出版:幻冬社)
・ 叱り方・甘えさせ方は、3歳、7歳、10歳で変える(PHPのびのび子育て編集部編 出版:PHP研究所)
「子どもの考える力を伸ばす取り組みと注意するポイントについて」(出典:TENJIN)
「子どもの考える力をはぐくむために 家庭でできる思考力アップのコツ」(出典:学研教室)