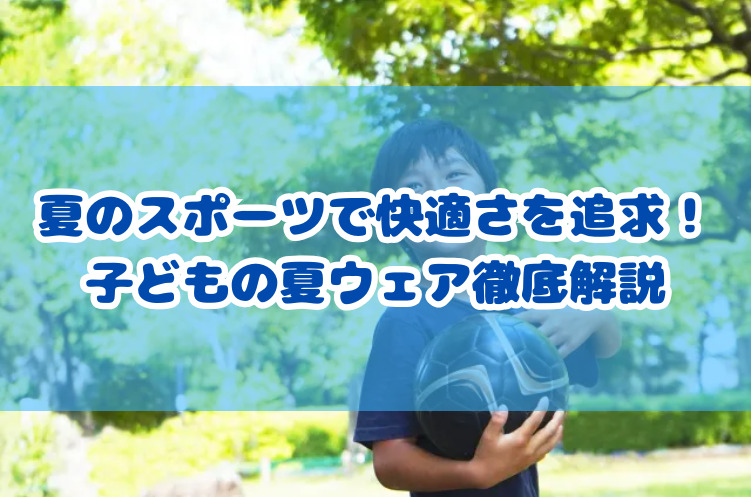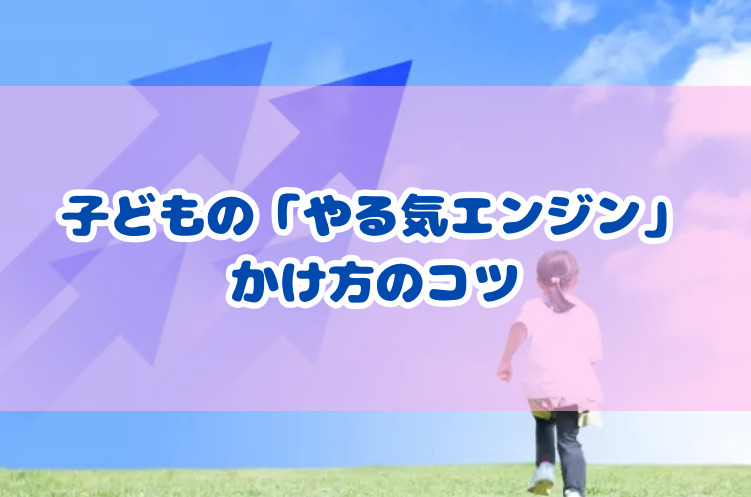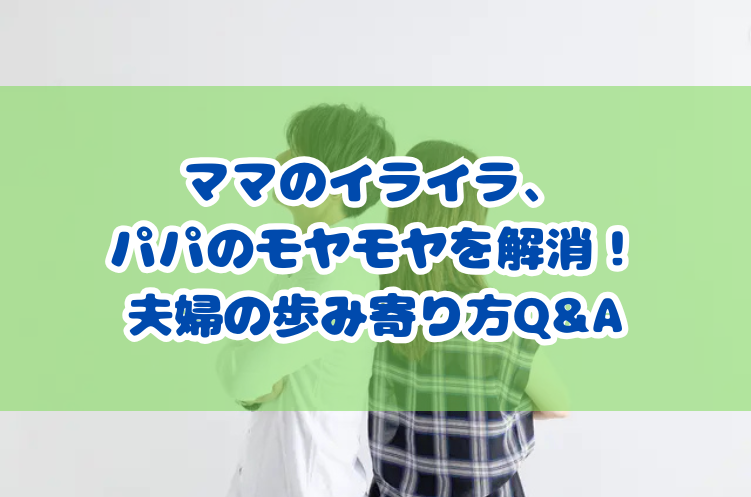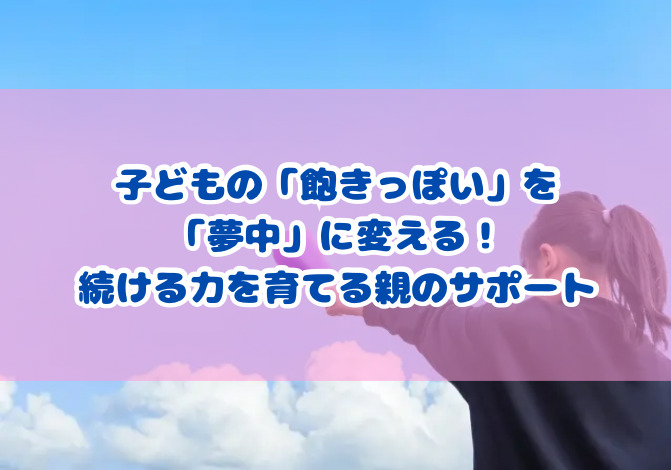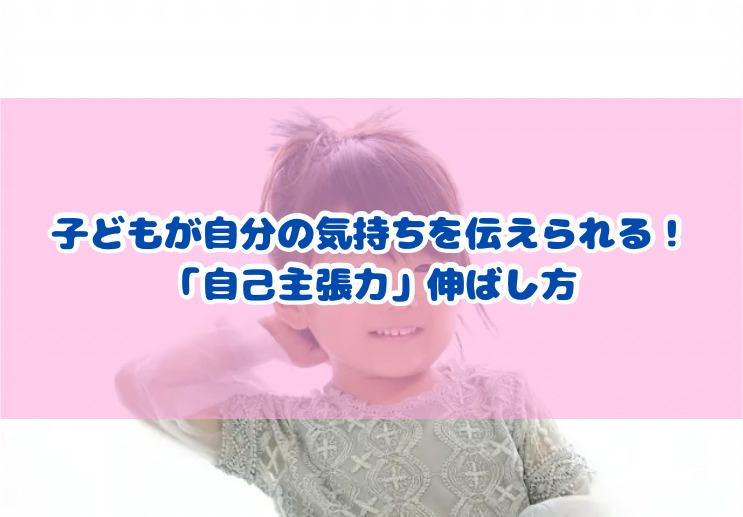異常気象から子どもを守る!家庭でできるやさしい安全対策
更新日: 2025.10.14
投稿日: 2025.10.10
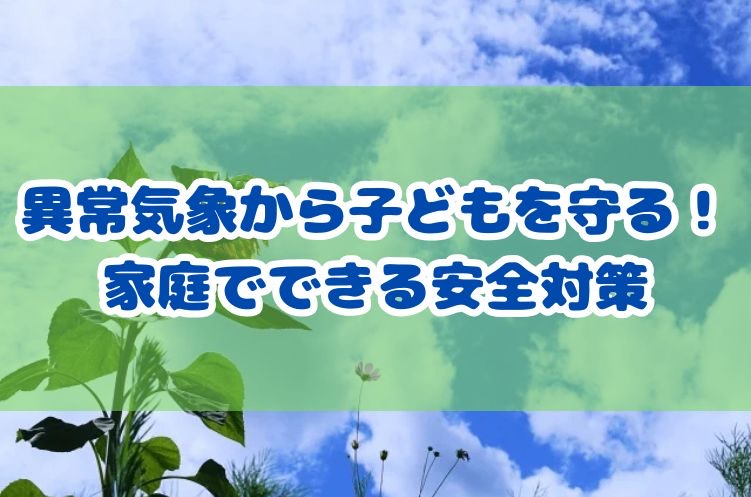
近ごろ「秋が短くなった」と感じることはありませんか?
昔なら涼しい風が吹くと同時に運動会や遠足の季節が訪れたものの、最近では夏のような暑さが10月頃まで続くことも珍しくありません。
季節の変わり目を感じる間もなく、猛暑やゲリラ豪雨、台風、寒波など、極端な天気=異常気象が増えています。
子どもたちは大人より体が小さく、体温調節もまだ上手ではありません。
だからこそ、家庭でのちょっとした工夫が、子どもの命と健康を守ることにつながります。
この記事では、保護者の方に向けて日常生活の中でできる安全対策をまとめました。
もくじ
猛暑が長引く今、親ができる“暑さ対策”
昔と比べて、夏の暑さは格段に厳しくなりました。
気象庁のデータによると、日本の平均気温はこの100年で約1.3℃上昇。
とくに近年は「猛暑日(35℃以上)」が全国的に増え、子どもの熱中症搬送数も過去最多となっています。
家の中でも油断しないで
熱中症は屋外だけでなく家の中でも起こります。冷房を我慢せず、室温は28℃前後・湿度は50~60%を目安に。
風通しをよくするためにサーキュレーターを使ったり、直射日光を遮るカーテンをするのも効果的です。
夜も熱帯夜が続くときは、無理せずエアコンをつけたまま寝ましょう。
水分補給は「喉が渇く前」に
子どもは夢中になると水分を取るのを忘れがち。
「30分に一度はお茶を一口」「外遊びの前に必ず水を飲む」など、ルールを決めて“予防的に飲む”ことが大切です。
汗をたくさんかいた日は塩分補給も忘れずに。経口補水液や塩タブレットを上手に取り入れましょう。
服装と持ち物のひと工夫
通気性のよい薄手の長袖や、熱を吸収しにくい淡い色の服を選びましょう。
帽子はメッシュ素材で通気性のあるものを。
学校の許可があれば日傘をさしたり、ランドセルに冷感シートを入れても◎。
「暑さを避ける工夫」は、体だけでなく心にもゆとりを与えます。
大雨・台風に備えてできること

最近は、季節外れの台風や突然の大雨も増えています。
ニュースで「線状降水帯」や「経験したことのない雨」という言葉を聞く機会も多くなりました。
家族で“事前準備”を
まず大切なのは、「自分の家がどんな場所にあるのか」を知ること。
自治体のハザードマップを確認し、浸水や土砂災害の危険があるかチェックしておきましょう。
避難場所や連絡先を家族で話し合い、すぐに行動できるようにしておくと安心です。
おうちの外まわりを点検
台風が近づく前に、ベランダの植木鉢や物干し竿を片付けておきましょう。
雨どいのゴミを取り除くだけでも、水があふれにくくなります。
窓には養生テープを貼り、飛散防止フィルムを貼っておくのもおすすめです。
備蓄と停電対策
懐中電灯、乾電池、モバイルバッテリー、非常食、水は3日〜1週間分を目安に用意しておきましょう。
小さなお子さんがいるご家庭では、おむつや粉ミルク、安心できるおもちゃも忘れずに。
「好きなお菓子を入れておく」と、避難生活でも少し心が和らぎます。
子どもへの声かけ
子どもには「川や用水路には近づかない」「雷のときは高い木の下に行かない」と、
短くてわかりやすい言葉で伝えることが大切です。
遊び感覚で“防災ルールごっこ”をして伝えるのも効果的です。
寒波・大雪にも気をつけて
冬も油断は禁物。寒暖差が大きい年ほど、体調を崩す子が増えます。
暖房が使えなくなる停電に備えて、湯たんぽ・毛布・カイロを常備しておきましょう。
窓に断熱シートを貼るだけでも暖かさが保てます。
外出時は帽子・手袋・マフラーでしっかり防寒し、靴は滑りにくいものを選びましょう。
大雪の日は無理に登校させず、「命を守る行動」と考えてお休みもひとつの手です。
雪かきや外遊びは、必ず大人が見守りましょう。
登下校時の安全をどう守る?
異常気象の中で特に心配なのが、登下校時の事故。
台風や豪雨の日は、警報が出ていなくても「危険」と感じたら学校に連絡を入れ、状況を共有しましょう。
猛暑日の通学では、帽子・日傘・保冷剤を活用して涼しく。
寒波や大雪のときは、滑らない靴・明るい服で視認性を高める。
何より「子どもの命を守る判断を最優先にする」という考えを家庭で共有しておきましょう。
親子でできる“防災教育”

防災は「怖い話」ではなく、「命を守るおまじない」として伝えるのがポイントです。
絵本や防災すごろくを使って、「非常袋の中に何を入れる?」と一緒に考えてみるのも良いですね。
子ども自身が準備に関わることで、「自分で身を守る力」が育ちます。
お気に入りのぬいぐるみやお菓子を入れて、「これがあれば安心だね」と声をかけてあげましょう。
日常の中でも、「今日は暑いから水筒を忘れずに」「台風が来るから早く帰ろうね」など、小さな会話の積み重ねが、子どもを守る大きな力になります。
おわりに ― 季節の変化が薄れた今だからこそ
夏が長く、秋が短くなった今、季節の境目を感じにくい日々が続きます。
どんな気候でも子どもたちが安心して笑顔で過ごせるように家庭の小さな備えが、未来の安全を守ります。
今日からできることを一つずつ始めてみませんか?
「備える=怖がること」ではなく、「安心を積み重ねること」。
異常気象に負けない、あたたかいおうちの防災習慣を、家族で育てていきましょう。