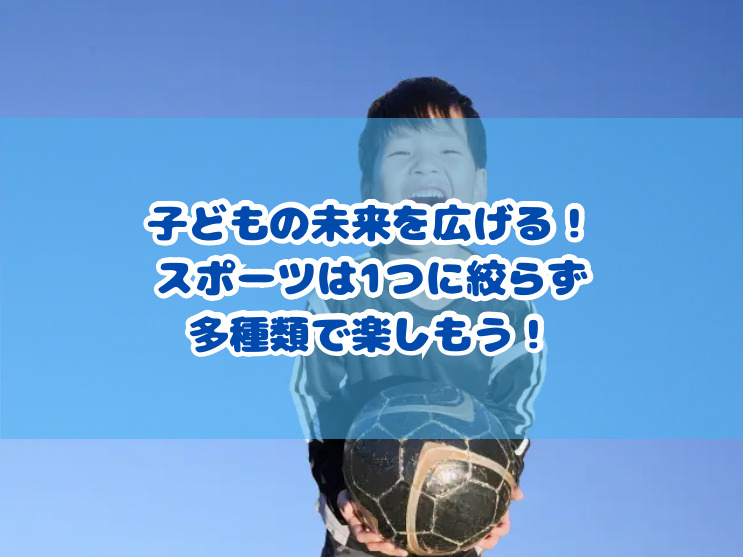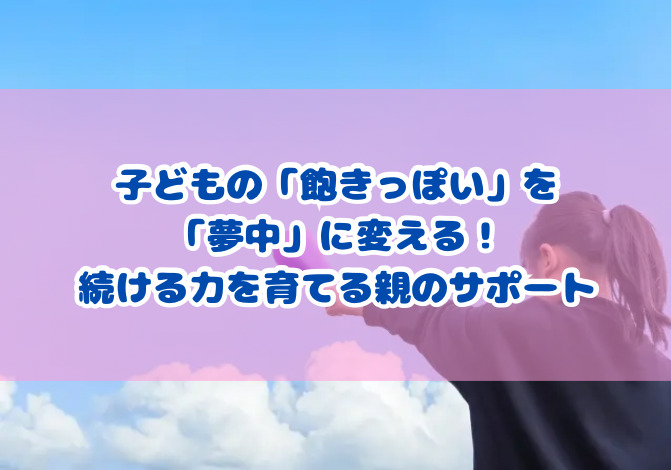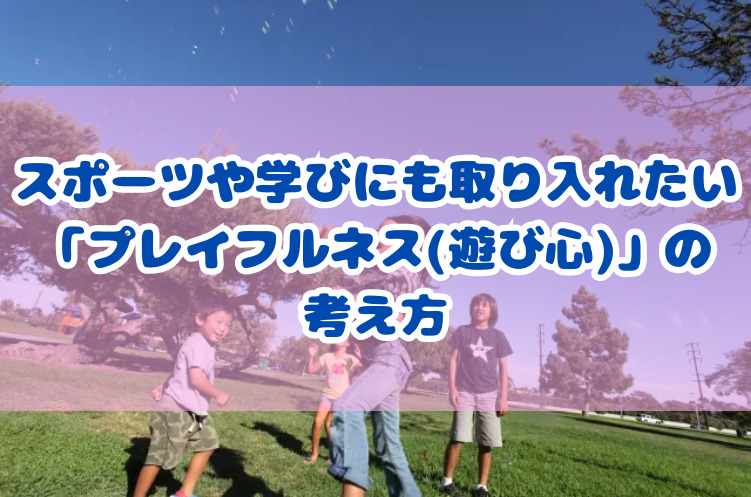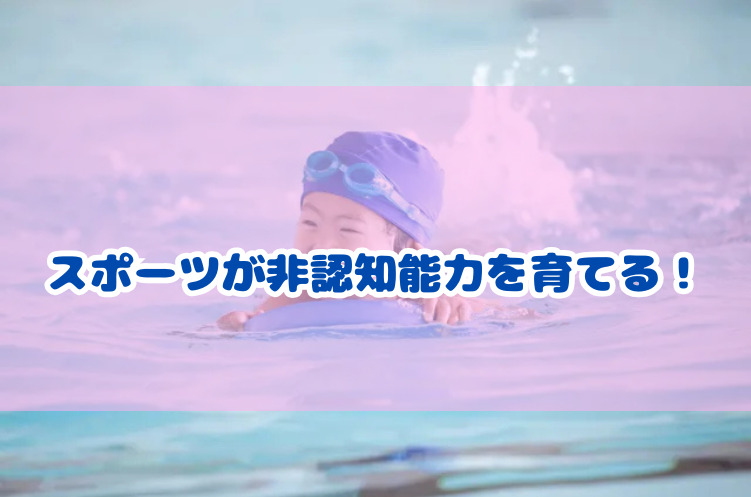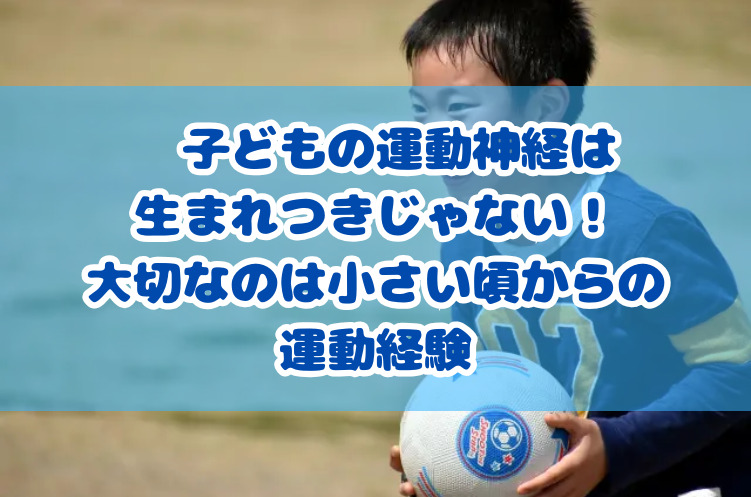子どもの「スポーツって楽しい!」を引き出す スポーツとの上手な付き合い方
更新日: 2025.09.25
投稿日: 2025.09.26
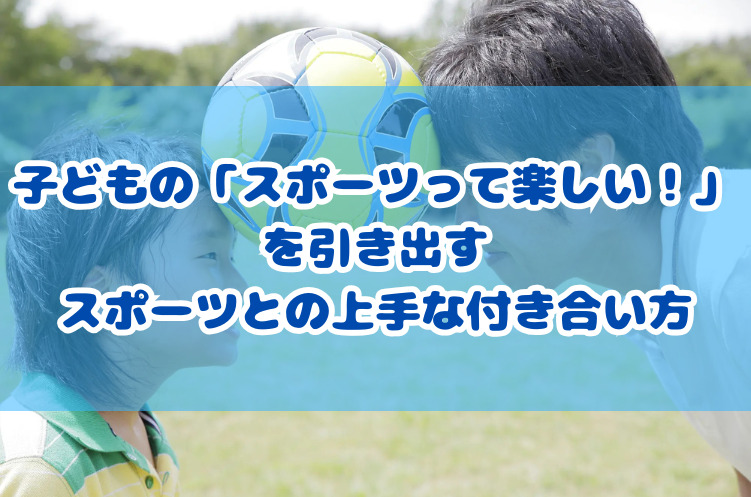
スポーツの楽しさは、子どもの運動習慣を一生支えてくれる大切な感覚です。
しかし子どもだからといって、誰もが「スポーツ大好き」とは限りません。
子どもがスポーツに取り組んでいると、大人はついダメ出しをしたり、厳しく指導をしてしまったりして、子どもがスポーツ嫌いになるケースは多いもの。
そんなことで子どもが「スポーツって苦手…」になってしまったら、もったいない!
付き合い方を工夫すれば、子どもは「スポーツって楽しい!」を実感できます。
どうしたら子どもがスポーツを心から楽しめるのか、一緒に考えていきましょう。
もくじ
スポーツを楽しむための基本のポイント3つ

スポーツとの付き合い方を学ぶ前に、理解しておきたいポイントがあります。
◯ スポーツは遊びの延長
◯ スポーツは真剣にやった方が面白い
◯ スポーツを楽しむのは子ども
スポーツは遊びの延長
スポーツの試合は「ゲーム」とも言いますよね。
それは相手と競い合って勝敗を決める真剣勝負の場でもありながら、根底には「遊びの要素」があるからです。
もしスポーツが「勝つこと」や「上手にプレーすること」だけを目標にしているとしたら、そこに楽しみを見つけることは難しくなるでしょう。
遊びの延長にあるからこそ、新しいことに挑戦したり、自由な発想で楽しむことができるのです。
スポーツは真剣にやった方が面白い
「遊びの延長なのに、真剣にやるの?」と思うかもしれません。
子どもの「楽しいから夢中になる」という感覚は、とても自然で純粋なものです。
夢中で練習して真剣にプレーすることで、本来の意味の「楽しい」「面白い」という感情に到達できます。
もちろん、悔しさや不甲斐なさを感じる場面があるかもしれません。
しかし反対に、適当に不真面目にスポーツをやったとしても、おそらく「楽しい」という気持ちにはならないでしょう。
子どもなりにまっすぐにスポーツに向かう気持ちが、「楽しい!」を連れてくるのです。
スポーツを楽しむのは子ども
自分が経験したスポーツに子どもが取り組んでいると、つい「上手になってほしい」「こうすればもっとうまくいく」と思って、大人は必要以上にアドバイスをしてしまいがち。
時にはそれが、子どもの「スポーツって楽しい!」を邪魔することがあります。
大人は「上手になりたいはず」と思っていても、子どもは「友だちと楽しくやるのがいい」と思っているかもしれません。
親のアドバイスや助言は、子どもが聞いてきたら教えるくらいがちょうどいいのです。
子どもが安全に楽しくスポーツするためのサポートや見守りに徹しましょう。
「スポーツって楽しい!」を引き出す10のアプローチ

子どもの「スポーツって楽しい!」を無理なく引き出すためには、親もじっとしてはいられません。
親子でスポーツの楽しさを実感するために、いろいろと試してみましょう。
◯ 親も一緒にやってみる
◯ 取り組むプロセスに注目
◯ 休むことを前向きにとらえる
◯ うまくできるかを心配しすぎない
◯ 生活習慣を整えてみる
◯ プロスポーツを観戦
◯ 成功体験をたっぷりと
◯ 子どものファンになって応援
◯ 道具に愛着を持つ
◯ 親子スポーツ大会を開く
親も一緒にやってみる
お父さんやお母さん、きょうだいと一緒に体を動かしている時、子どもは「楽しい!」を一番感じやすいでしょう。
子どもが習っているスポーツ、好きなスポーツを親も一緒にやってみてください。
見ているよりも難しいことがわかって、子どもに教えてもらう場面もあるかもしれません。
「スポーツは苦手で…」という人でも、鬼ごっこやフリスビーでも親子で真剣にやってみると意外とハードでいい運動になります。
そして家族で楽しむからこそ、いろいろな運動に挑戦するチャンス。
そのなかから、子どもが「好き」「楽しい」と思うスポーツを始めてみてもいいですね。
取り組むプロセスに注目
スポーツは結果にこだわりすぎてしまうと、楽しむ気持ちからは遠のいてしまいます。
「自主練を頑張っている」「先週できなかったことができるようになった」など、子どもが取り組んでいることや頑張っていることに注目してみましょう。
子どもも自分の努力を認めてもらえると、取り組んでいることが無駄ではないと感じられ、前向きになるはずです。
休むことを前向きにとらえる
子どもが疲れていたり、前向きに取り組めない様子が見られたら、時には休むことも必要です。
適度な休息やオフは、長く楽しんでスポーツを続けるうえでも重要なポイント。
気持ちをリセットして、「次回に楽しく取り組めるように休む」という気持ちで前向きな休みを取りましょう。
うまくできるかを心配しすぎない
「うちの子は運動神経が悪くて…」「いつまで経っても上達しない」など、子どものことを考えるからこそ、親はいろいろと心配になりますね。
小さいうちから遊びながら体を動かすことで、体感やバランス能力が鍛えられ運動やスポーツが好きになります。
教えたらすぐできるようになる飲み込みの早い子もいれば、じっくり取り組んだ後に習得する子もいます。
「できること」に注目して、「できないこと」はそのうちできるようになるさ、くらいの気持ちでゆったり構えましょう。
まずは「楽しく」「夢中になれること」を見つけて、取り組むことから始めてみてください。
生活習慣を整えてみる
スポーツをするうえで、体は資本。疲れていたり、寝不足では楽しめるものも楽しめません。
起きる時間と寝る時間を30分早めてみたり、朝食をしっかり食べたり、夜のゲーム時間を前倒しするなど、少しずつ生活習慣を整えると、自律神経も整って体がシャッキリします。
また昼間しっかり体を動かすと、夜は深い睡眠が取れるようになります。
親子でスポーツをすることで、生活習慣を整えてみましょう。
プロスポーツを観戦

子どもが好きなスポーツや取り組んでいるスポーツがあれば、プロの試合や大きな大会などを観戦してみましょう。
上手なプレイヤーの試合運びやテクニックはよい刺激になり、目標ができるかもしれません。
「今のプレー、すごかったね!」「今度やってみようか」など、親子で感想を共有することでやる気も刺激されます。
成功体験をたっぷりと
「ドリブルが先週よりも長くできるようになった」「ボールが遠くまで届くようになった」など、目標をクリアしていくワクワク感を持たせましょう。
子どもが「できた!」と自分で成長を感じられる成功体験が大切です。
大きな目標も大切ですが、達成しやすい小さな目標(スモールステップ)を設定し、たくさんの目標クリアをしていくと楽しさを感じやすくなるでしょう。
子どものファンになって応援
子どものスポーツする姿をポスターにしてみたり、子ども向けの応援グッズを作って部屋に飾ったり、親が子どものファンになってみるのも面白い試み。
「お、◯◯選手が懸命に走っております!素晴らしい〜」「行け!行け!やったーゴールだ〜!」など、子どものプレーを大げさに実況中継してみると、子どもの気分も盛り上がるかもしれません。
うまくいかない時も「大丈夫!」「何があっても応援してるよ」と声をかければ、「何があっても家族は味方になってくれる」と自信が持て、思い切りスポーツに挑戦できるようになるでしょう。
道具に愛着を持つ
スポーツをする人にとって道具は大切な仲間であり、相棒であり、自分のプレーを支えてくれる存在です。
一流の選手ほど道具の手入れを丁寧に行い、いざという時にしっかり働いてくれる道具に育てています。
シューズやボール、グローブやラケットなど、使い終わったら汚れを拭き取り、次に使うための準備もしっかり行いましょう。
道具に愛着を持ち大切に扱うことで、責任感と自立心が育まれ、そのスポーツがより好きになります。
手入れの仕方がわからない子どもには、大人が見本を見せてあげましょう。
親子スポーツ大会を開く
特定のスポーツでなくても親子で楽しく体を動かす「親子スポーツ大会」を開催してみれば、子どものスポーツへの興味がかきたてられるかもしれません。
出たサイコロの目だけ進めるサイコロリレーや、新聞紙を刀にして戦うチャンバラ合戦、誰が一番ボールを遠くへ飛ばすかの競争など、競技はなんでもOK。
親子だけでもいいですし、親しい親子仲間に声をかけても楽しいですね。
親子でヘトヘトになるまで楽しく遊べば、子どもは「スポーツって勝っても負けても楽しい」「スポーツで笑い合えるのって最高!」と感じ、体を動かす爽快さを実感できるでしょう。
「楽しい!」はモチベーションの源になる

オリンピアンやプロのスポーツ選手の切磋琢磨する努力の底には、その競技への愛情と「楽しい」という気持ちが必ずあります。
「楽しい」「面白い」という気持ちは、人の心を動かすとても重要な感覚であり、モチベーションの源になるものです。
子どものスポーツへのポジティブな気持ちを引き出すためには、親や家族と一緒にスポーツに取り組み、「今日は楽しかったね」と気持ちを共有できる環境が不可欠。
そして子どもがスポーツに挑戦し、本当の意味の「楽しさ」を感じるためには、失敗した時や辛い時に戻れる安全地帯があることも大切です。
子どもがスポーツを心から楽しむために、「失敗しても大丈夫」「いつも味方だよ」「いつも頑張ってる姿、見てるよ」という温かいサポートと声かけをしていきたいですね。
・子どもの「スポーツって楽しい!」を引き出すには、スポーツは「遊びの延長」「でも真剣にやる」「主役は子ども」を心がける。
・親が子どもと一緒に楽しく体を動かすことが、子どもの「楽しい」という気持ちを引き出す。
・「楽しい」はスポーツをする時のモチベーションの源になる。
(参考文献)
・スポーツ庁 | 運動ができるようになると、アタマもよくなる!? 専門家に聞く!子どもの能力を引き出すためのメソッド
・パラサポWEB | スポーツで子どもはどれだけ成長する?親が注目すべきなのは、勝利ではなくセカンドゴール!
・マナビスタ | スポーツメンタルトレーナーに効く 子どものやる気をぐんと引き出す声かけ