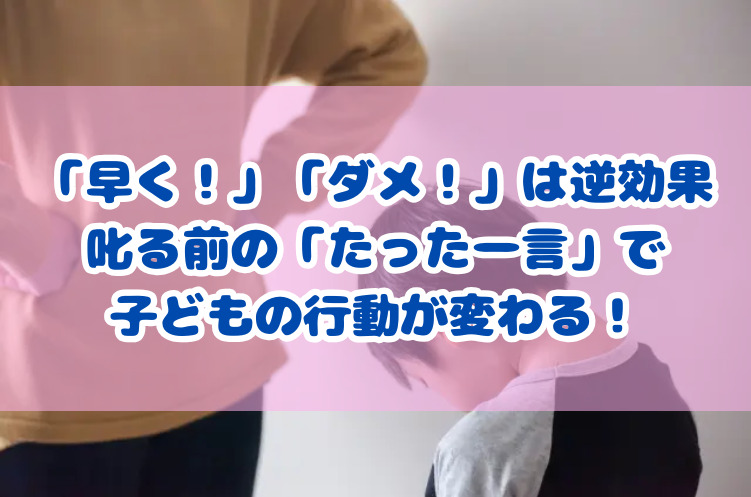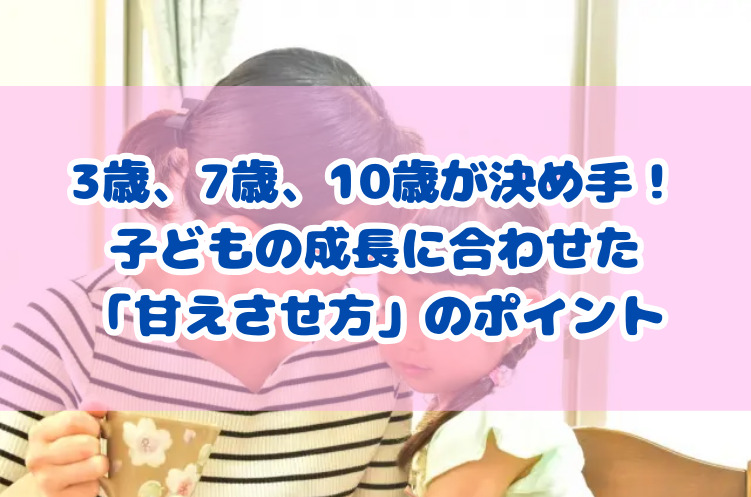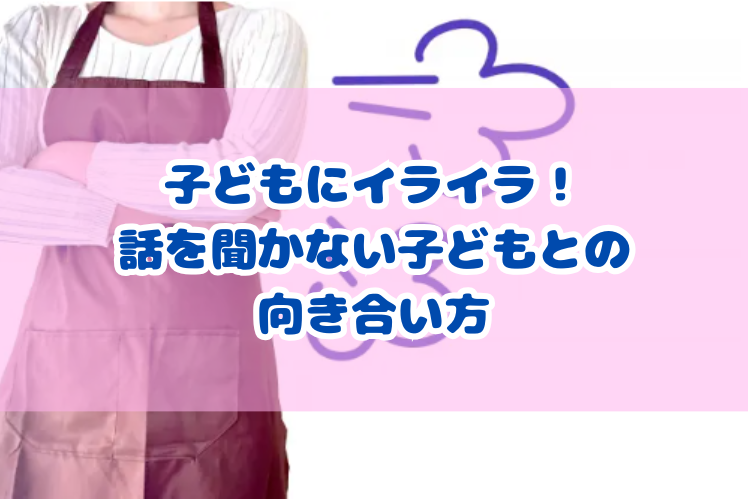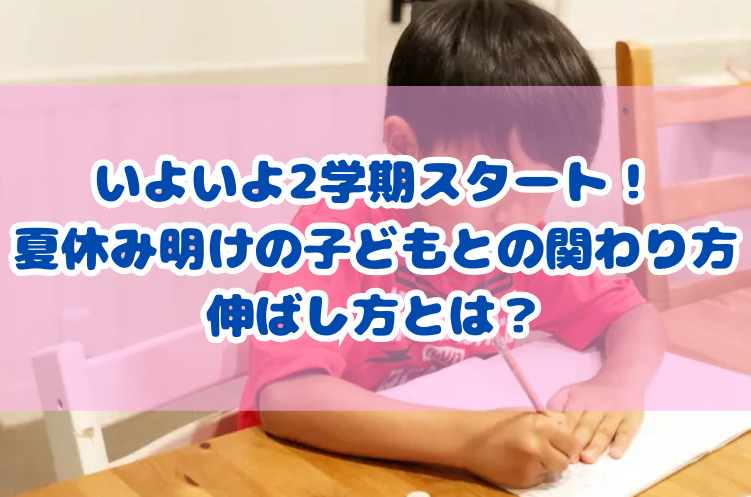え、そんなことで?子どもたちが感じるきょうだい間のモヤモヤ
投稿日: 2025.09.09
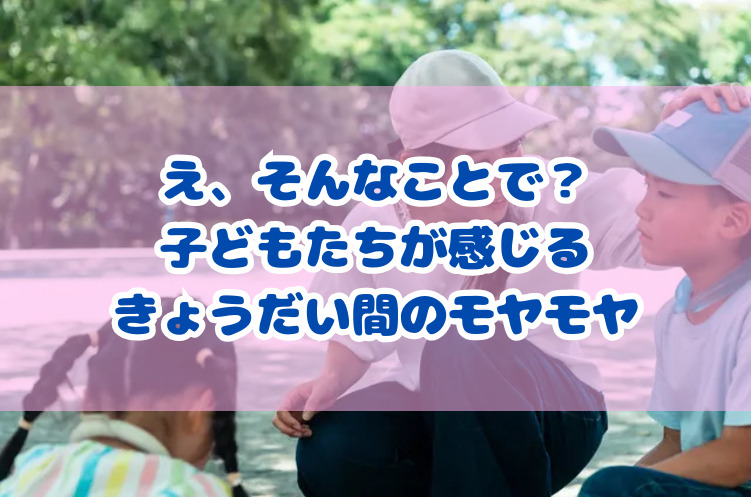
「きょうだい仲良くしてほしいのに、いつもケンカばかり」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。
一方で、きょうだいげんかの原因は、意外なほど些細なことだったりします。
たとえば、「お兄ちゃんだけ新しいゲームを買ってもらえた」「妹だけお母さんに褒められた」といった、大人から見れば「そんなことで?」と思うような出来事。
しかし、子どもにとってはそれが「不公平だ」「自分は愛されていないのかもしれない」という不満や悩みに発展することも少なくありません。
この記事では、そんな子どもたちの心の中にあるモヤモヤを解き明かします。
そして、子どもたちがお互いを思いやり、良好な関係を築いていけるよう親ができる関わり方について紹介します。
もくじ
多くの保護者が抱える悩み「きょうだい平等に育てているつもりだけど、心配!」

複数の子どもを育てていると、「きょうだいと平等に関わっているつもりなのに、なんだか不満そう…」と感じたことはありませんか?
親が「平等」だと思っていることと、子どもが「不公平」だと感じることの間には、実は大きなギャップがあることがあります。
例えば、お菓子を同じ量ずつ分けたつもりでも、子どもの目には「なぜかお兄ちゃんのお菓子のほうが大きく見える…」と映るかもしれません。
また、習い事の送迎や宿題を見る時間など、親はそれぞれの都合に合わせて対応しているつもりでも、子どもにとっては「お姉ちゃんのときはたくさん遊んでくれたのに、私のときはいつも忙しそう」などと感じてしまうことがあります。
このように、親にとってはごく些細なことでも、子どもたちは親の言動を敏感に感じ取り、心の中にモヤモヤをため込んでしまうことがあるのです。
上の子・中間子・末っ子、男女それぞれで感じやすい不満

きょうだい間それぞれで感じやすい不満は、生まれ順や性別によっても変わってきます。
以下、具体例を紹介します。
上の子が感じやすい不満
上の子、特に長男や長女は、きょうだいが生まれるまで親の愛情を独り占めしていました。
しかし、下にきょうだいが生まれると、親の関心は新しい家族のほうに向きがちになります。
また、上の子は「お兄ちゃんだから、我慢しなさい」「お姉ちゃんなんだから、お手本になりなさい」などと言われる機会が増え、寂しさや不満を感じることがあります。
さらに、親は無意識のうちに、上の子に多くの期待をしていることがあります。
それにより、本人は無言のプレッシャーを感じ、本来の自分を出せなくなってしまうこともあります。
中間子が感じやすい不満
真ん中にいる中間子は、上のきょうだいが親の期待を背負い、下のきょうだいが甘やかされているように見えるため、「自分だけが置いてきぼりにされている」と感じることがあります。
「上にはかなわないし、下には譲らなければならない」という板挟みの状況になりやすく、自分の居場所がないように感じてしまうことも。
他のきょうだいと比較され、個性や頑張りを認めてもらえないと感じると、自己肯定感が低くなってしまうこともあります。
末っ子が感じやすい不満
末っ子は、親や上のきょうだいから可愛がられ、甘やかされて育つ傾向があります。
これは一見幸せそうですが、本人にとっては「どうせ自分は末っ子だから」と、軽く見られているように感じる原因になることもあります。
また、服やおもちゃはお下がりで、「自分だけのものが少ない」と感じ、不満を抱くケースも。
性別の違いが不満の種になることも
きょうだいの不満は、性別によっても異なる場合があります。
男の子、特に長男は「男の子だからしっかりしなきゃ」「長男だから我慢しなさい」といった期待をかけられ、それがプレッシャーになることがあります。また、「男の子なのに泣くの?」「男の子だから〇〇できるはず」といった言葉に傷つき、モヤモヤを抱えてしまうことも少なくありません。
一方で、女の子、特に姉は「女の子だから家事を手伝って」「お姉ちゃんなんだから弟の面倒を見てあげて」と、性別や立場による役割を求められることに不満を感じることがあります。
また、年齢や性別が近い場合でも、女の子は比較されたり、「お兄ちゃん/弟には優しくしてあげなきゃ」とさとされたりすることで、不公平感や不満を募らせることもあります。
親が気を付けるポイント

子どもたちの不満やモヤモヤを解消するために、親ができることはたくさんあります。
以下、ポイントを4つ紹介します
親を独り占めできる時間を確保する
子どもは、親に「自分だけを見てほしい」と強く願っています。
もし、忙しくてなかなか時間が取れないと感じているなら、、「ママ独り占めタイム」を作ってみましょう。
たった10分でもOK。その時間だけはスマートフォンを置いて、その子の話を聞いたり、一緒に好きなことをしたりしてとことん向き合ってみてください。そうすることで、子どもは「自分は大切にされている」という安心感を得ることができるでしょう。
「毎日そんな時間は取れないよ…」と思うかもしれません。
それでも大丈夫です。
朝の支度の時間に「今日の学校の給食は何?」と話しかけたり、寝る前にベッドの中で絵本の読み聞かせをするだけでも、子どもは「自分にだけ向き合ってくれている」と感じ、子どもにとって嬉しい時間になります。
きょうだいげんかで親が「裁判官」にならない
子どもたちのけんかを目の当たりにすると、親はつい、「お兄ちゃんが我慢するところでしょ!」「あなたがいけないよ!」などと断定してしまいがちですが、これはNGです。
親が一方の味方につくと、「負けた」と感じた子どもは不満を募らせ、親への不信感や相手への敵意を強めてしまうこともがあります。
まずは親自身がなるべくイライラを抑え、両方の話を聞くことに徹しましょう。
「〇〇はそう感じたんだね」「××はそれが嫌だったんだね」と、それぞれの気持ちを代弁してあげることで、子どもたちは「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じます。
その上で、「どうしたら仲良くできるかな?」と、子どもたち自身で解決策を考えさせるように促してみましょう。
親は「裁判官」ではなく、解決をサポートする役割に徹する姿勢が大切です。
「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんだから」は禁物
「お兄ちゃんだから泣かないの」「お姉ちゃんなんだから我慢しなさい」といった言葉は、上の子にとって大きなプレッシャーとなります。
これらの言葉は、「年齢が上」というだけで無条件に我慢や役割を押し付けてしまうことになり、不公平感を募らせる原因になります。
上の子も、時には「甘えたい」「わがままを言いたい」と思うことがあります。
年齢や立場ではなく、きょうだい一人ひとりの個性や気持ちに寄り添って声をかけましょう。
「〇〇ちゃんは〇〇ができるからすごいね」と特定の行動をほめたり、「今日は甘えたい日なんだね」と気持ちを受け止めたりすることで、子どもは「自分自身を見てくれている」と感じることができます。
自分に置き換えてイメージする
「自分が親から愛情を注がれていないと感じたらどう思うか?」「きょうだいがえこひいきされているとしたらどんな気持ちになるか?」など、自分の気持ちに置き換えて考えてみましょう。
悲しいと感じるなら「やめなくては」と思い、努力できるはずです。
不平等に育てることによる影響

親が子どもたちに不平等な対応をしてしまうと、子どもたちの心の成長にどのような影響を与えるのでしょうか。
以下、具体例を紹介します。
嫉妬や競争心、劣等感が増加し、自己肯定感が低下しやすい
親からの愛情や注目が一方に偏ると、子どもたちは互いをライバルと見なし、親の関心を奪い合うようになりがちです。
これによりきょうだいの絆が弱まり、常に競争する関係になってしまうことがあります。
また、不平等な関わりは、「自分は愛されていない」「自分は価値がない」といった感情を子どもに抱かせ、強い劣等感や自己肯定感の低下につながることもあります。
親への不信感を抱きやすくなる
子どもは、自分を公平に扱ってくれない親に対し、不信感を抱くようになります。
これにより親子のコミュニケーションが減り、信頼関係が損なわれることがあります。
不満を抱えた子どもは、親に直接不満を伝えることができず、きょうだいに八つ当たりをしたり、問題行動を起こしたりすることもあります。
コミュニケーション能力が低下しやすくなる
不平等な家庭環境は、子どもたちのコミュニケーション能力に深刻な影響を与えることがあります。
不満を抱えた子どもは、「どうせ話してもわかってもらえない」「自分の気持ちを言ったら、また怒られるかもしれない」という諦めや恐怖から、自分の感情をうまく表現できなくなることがあります。
また、常に親の顔色をうかがう癖がつき、本心を隠して話すことが当たり前になってしまうことも。
このような経験は、他人との関係性においても「本音で話す」ことを難しくさせ、表面的な付き合いしかできなくなってしまう可能性があります。
比較はせず、それぞれの子どもの個性を見ていこう

子どもたちが不満を抱く理由は、親が考えている以上にささいなことです。
最も大切なのは、きょうだいで比較しないこと、そして一人ひとりの個性や気持ちを大切にすることです。
きょうだいは、ときに人生で最も長く続く関係です。
親の愛情の示し方一つで、子どもたちの心の成長や、将来のきょうだい関係は大きく変わります。
ぜひ、それぞれの個性を尊重し、子どもたちが安心して成長できる環境を築いていきましょう。
・無意識のうちに、きょうだいに不平等に接しているかもしれないことを自覚しよう。
・生まれ順や性別などにより、その子が抱える思いは異なることがある。
・「比較しないこと」「個性を尊重すること」が、きょうだい育ての肝。
「きょうだいの子育てにおける平等と公平とは?~元保育士パパが教える【きょうだいの子育て】」(出典:yahooニュース)
「親からの兄弟・姉妹平等は、上の子にとって不平等?」(出典:マダムフィガロ)
「兄弟差別の影響は? 親の愛情格差・ひいき原因の兄弟コンプレックス」(出典:オールアバウト)
「きょうだいに対して平等に接することができない」(出典:浜松市子育て情報サイト ぴっぴ)