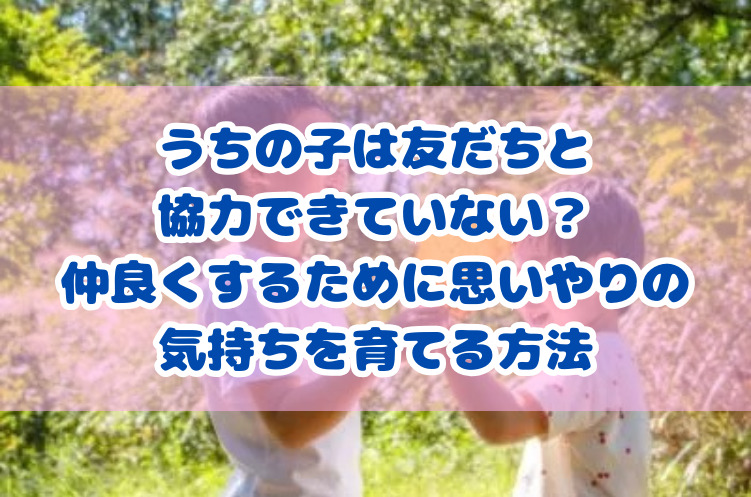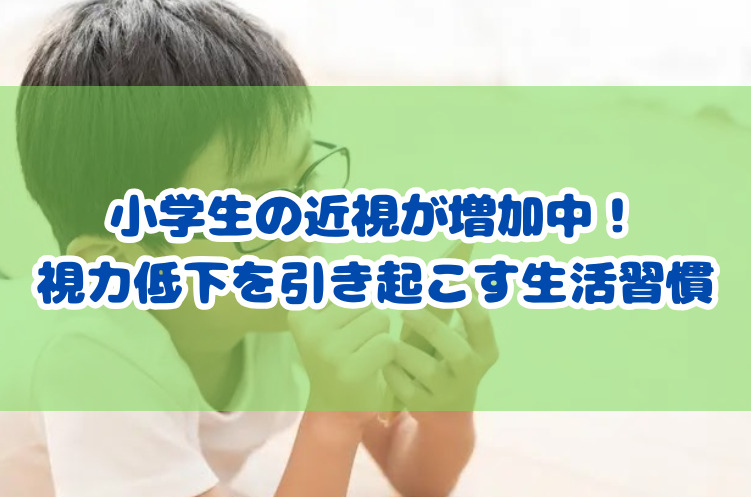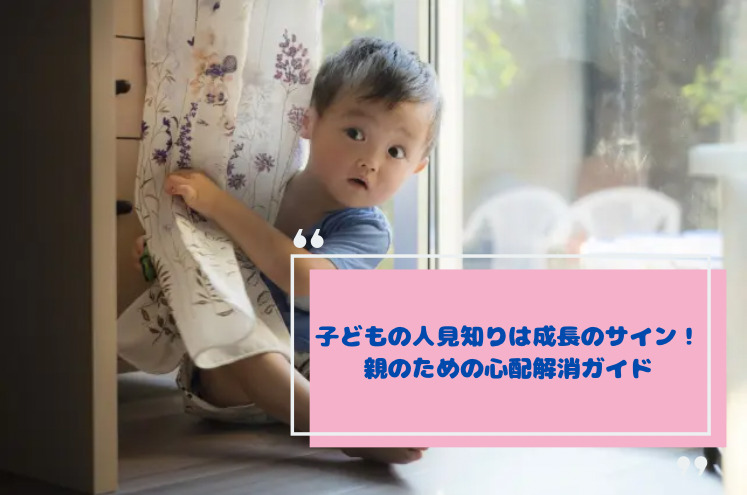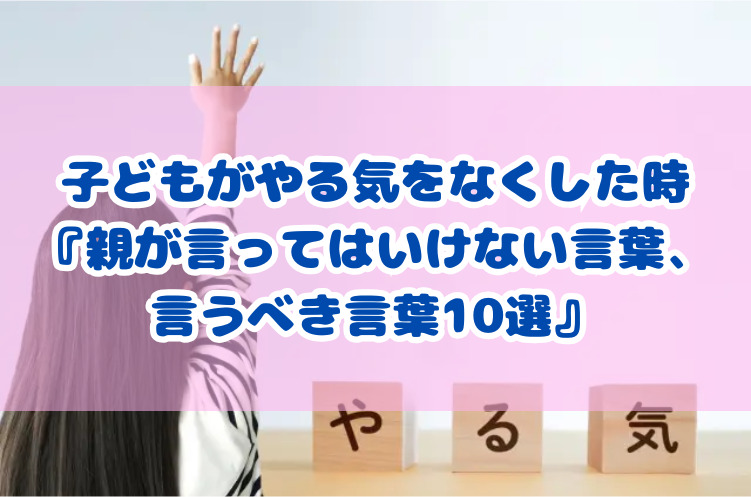スポーツで伸びる子ってどんな子?
更新日: 2025.09.25
投稿日: 2025.09.08
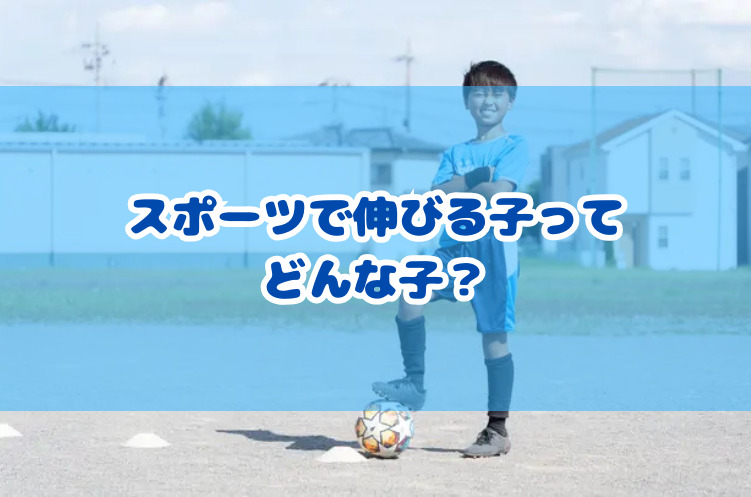
「うちの子、どうしたらスポーツが上達するのだろう」。
そう考えたことのある保護者の方は多いのではないでしょうか。
スポーツで伸びる子は、単に運動神経が良いだけではありません。
むしろ技術よりも、その子の内面や、スポーツに対する向き合い方に鍵が隠されています。
この記事では、サッカーや野球をはじめとするさまざまなスポーツで才能を開花させる子どもたちが共通して持っている特徴について紹介します。
身近にいる「伸びる子」の行動や考え方からヒントを得て、わが子の才能の芽を育むための関わり方を見つけていきましょう。
スポーツで伸びる子が持つ7つの特徴

スポーツで大きく成長する子どもには、以下のような特徴が見られます。
ミスしてもくよくよせず、負けず嫌い
スポーツで伸びる子は、挑戦の過程で転んだり、ミスをしたりしてもくよくよせず、「次はどうすればいいか?」と建設的に考え、立ち上がる強さがあります。
また、負けず嫌いな性格は、自分をさらに高めるための原動力となります。
単なる感情的なものではなく、「どうすればもっとうまくなれるのか」という目標達成に向けたエネルギーに変換できるのです。
自分で考えて行動できる
コーチの指示をただ聞くだけでなく、自分で考えてプレーする力は、子どもの成長に大きく左右します。
例えば、試合中に予期せぬ状況が起きたとき、指示を待つのではなく自分で考えて策を判断して行動する。
その行動が結果的に成功に終わっても失敗に終わっても、「自分で考える」思考が身についている子どもは、成長スピードが早いと考えられています。
コツコツ努力を続けることができる
才能があるだけではトップにはなれません。
地道な努力を続けられる力こそが、成長の鍵です。
練習が辛いときや成果が出ないときでも、日々コツコツと努力を重ねることで、少しずつですが確実に実力は向上します。
この継続力は、スポーツだけでなく、学業や将来の仕事など、あらゆる分野で成長するための基本となります。
人の話を素直に聞くことができる
コーチや先輩、友達からのアドバイスを素直に聞き入れられる謙虚な姿勢は、技術の向上に不可欠です。
自分のやり方に固執しすぎず、周りの人の意見に耳を傾けることで、新しい視点や技術を吸収できます。
これは、チームスポーツにおいては特に大切で、仲間との連携を深める上でも大切な資質です。
コミュニケーション能力が高い
特にチームスポーツにおいて、コミュニケーション能力が大きな鍵を握ります。
練習の時や試合中に仲間と声をかけ合い、互いの意図を共有することで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。
また、練習や試合以外の場でも、仲間やコーチとコミュニケーションをとり、良好な人間関係を築くことができる子どもは、チームの信頼を得ることもできるでしょう。
自己管理能力がすぐれている
スポーツで伸びる子に共通する自己管理能力は、小さいうちから身につけておきたい重要な資質です。
スポーツでは「最近〇〇の練習をしていないから、今日やってみよう」、スポーツ以外でも「友達と遊びに行く前に宿題を終わらせよう」など、自己管理しながら行動できる子どもは、心身ともに健康な状態を保ち、良いパフォーマンスを発揮できます。
また自己管理能力は、スポーツと学業の両立にもつながります。
協調性が高い
チームスポーツでは、協調性が不可欠です。
自分の成功だけでなく、チームメイトの成功を心から喜べる子どもはチーム全体の雰囲気を良くし、結束力を高めることにつながります。
自分の役割を理解し、チームの勝利のために最善を尽くすことができる協調性は、個人の成長だけでなくチーム全体の成長にも貢献します。
スポーツで子どもを伸ばす親の特徴

ここでは、子どもの心と体を健やかに育みながら、スポーツでの成長をサポートする親の特徴を紹介します。
日々の関わりの中で、実践できることばかりです。
ぜひ実践してみてください。
子どもの気持ちに深く共感し、一緒に喜ぶ
子どもがスポーツで何かを達成したとき、その喜びを共有することが、子どもの成長に不可欠です。
たとえば、練習で新しい技が成功したといった小さな成功でも、「すごい!」「やったね!」と心から一緒になって喜ぶことで、子どもの自己肯定感と意欲が向上します。
子どもの感情を受け入れ、頭ごなしに否定しない
子どもが「もうサッカー辞めたい」と言ったり、親が望まない行動をしたりしたときでも、いきなり「ダメ」と否定しないことが重要です。
まずは、「そうか、〇〇は今、辞めたいと思っているんだね」と、子どもの気持ちを言葉にして繰り返すことで、子どもは「自分の気持ちを理解してくれた」と感じて安心します。
この「感情の受け入れ」は、信頼関係を築く上で欠かせません。
日頃からこうしたコミュニケーションを心がけることで、親子間の絆が深まり、スポーツを続ける上での困難も乗り越えやすくなります。
子どもをひとりの人間として尊重する
子どもは未熟な存在だからと、親が先回りして「この子はこれが苦手なので」「まだこれは早いです」と口を出すのは、子どもの自主性を奪うことにつながります。
能力を伸ばす親は、子どもを尊重し、意思決定の機会を与えます。
子どもが自分で選んだからこそ、困難に直面しても「自分で決めたことだから頑張ろう」と粘り強く取り組む力が育まれます。
これは、スポーツだけでなく、将来の人生においても大きな財産となります。
スポーツで子どもが自信を失ってしまう親の特徴

逆に、スポーツで子どもをダメにする親にはどのような特徴があるのでしょうか。
「向いている」と決めつけ、過度な期待をかける
親は「うちの子は足が速いからサッカーが向いているはず」など、子どもの適性を親の視点から決めつけてしまいがちです。
しかし、どれほど身体的な特性が合っていても、子ども自身が興味を持てなければ、それは苦痛でしかありません。
さらに、子どもが頑張りはじめると、親の期待は徐々にエスカレートし、「試合に勝ってほしい」「レギュラーになってほしい」と結果を求めてしまいがちです。
こうした過度な期待は子どもにプレッシャーを与え、スポーツを「楽しいもの」ではなく「親の期待に応えるためのもの」に変えてしまうことがあります。
結果、子どもはプレッシャーに押しつぶされ、本来の力を発揮できなくなります。
口出しとダメ出しを繰り返す
練習や試合を観戦している際に、親が「あの場面ではこうすべきだった」「もっと周りを見ろ」などと細かくダメ出しをすることは、子どものやる気を著しく削ぎます。
外から見ている親は冷静に判断できますが、子どもは緊張感の中で必死にプレーしています。
親からのダメ出しは、子どもにとって「自分はダメな人間だ」という否定的なメッセージとして受け取ってしまい、成長のスピードが鈍ってしまいます。
スポーツで子どもを伸ばすために親が心がけること

子どもの可能性を大きく広げるのは、特別な練習法や技術指導だけではありません。
むしろ、毎日の親の接し方こそが、子どもの心と体を健やかに育み、スポーツを長く楽しめる秘訣です。
この記事では、子どもの自立心ややる気を引き出しスポーツで成長するための、具体的な関わり方をお伝えします。
子どもが主体で考え、行動する機会を与える
スポーツの主役は子どもです。親はコーチではありません。上から一方的にアドバイスをするのではなく、子どもが自分で考える力を育むよう促しましょう。
たとえば、「今日の試合、どうだった?」「強くなるにはどうしたらいいと思う?」などと質問を投げかけ、子ども自身を振り返りや目標設定に導きます。
自分で考え、選択する経験は、子どもの成長に欠かせません。
スポーツは「楽しむもの」であることを再確認する
スポーツの根本的な目的は、それ自体を楽しむことです。
しかし、勝ち負けがあるスポーツでは、いつの間にか結果にばかり目が向いてしまいます。
親が「試合に勝つこと」や「得点を決めること」ばかりに焦点を当てると、子どもは「失敗したらどうしよう」という恐怖心から、楽しむ気持ちを失ってしまいます。
子どもが「プレーしていて楽しい!」と思えるよう、勝敗にこだわらない声かけを心がけましょう。
チームメイトと仲良くできているか、笑顔でプレーしているかなど、子どもの「様子」に目を向けることも大切です。
親も共通の趣味として一緒に楽しむ
親が心からスポーツを楽しんでいる姿は、子どもに良い影響を与えます。
共通の趣味として一緒に楽しむことができたらいいですね。
また、お弁当作りやユニフォームの洗濯などを「大変な作業」と捉えるのではなく、子どもの成長を支える「楽しい共同作業」として捉えることも大切です。
親が楽しんでいる姿を見ることで、子どもも「スポーツって楽しいものなんだ」という印象を強く持ち、自ら積極的に取り組むようになります。
子どものスポーツの成長は、親のサポートにかかっています。
大切なのは、親がコーチになるのではなく、最大の理解者として寄り添うことです。
結果だけでなく過程を褒め、子どもの「楽しい」という気持ちを大切にする。
そして、子どもが自分で考え、選択する機会を与える。
こうした日々の関わりが、子どもの自主性を育み、スポーツを通して得られる学びや喜びをより大きなものにします。
今日からできる小さな心がけで、子どもの可能性を大きく広げていきましょう。
・スポーツで伸びる子は、「才能」だけではなくその子の内面が大きな影響を及ぼす。
・親の関わり方次第で、スポーツで子どもをダメにしてしまうこともある。
・親がコーチになるのではなく、最大の理解者として寄り添うことが大切。
参考文献)
「スポーツで伸びる子の特徴」(出典:キッズスポーツ親のサポート)
「伸びる子ってどんな子?」(出典:サンビスカススクールコラム)
「少年サッカーで伸びる子とは」(出典:松ケ崎FCコラム)
「スポーツで子どもを伸ばす親・ダメにする親の特徴とは?」(出典:ドリームコーチング)