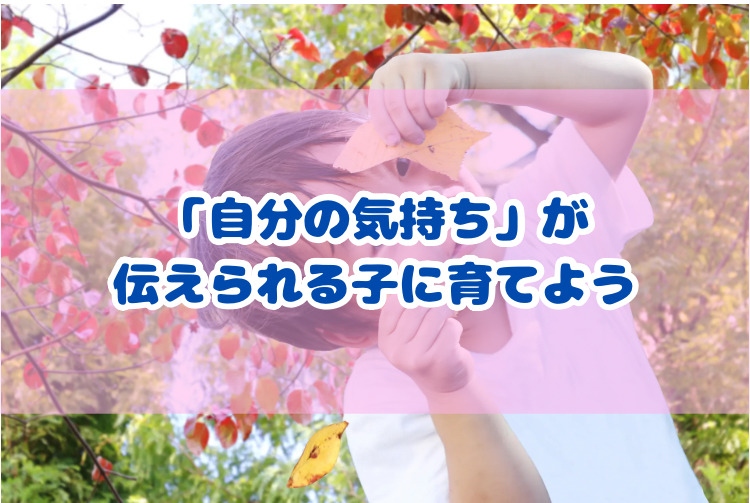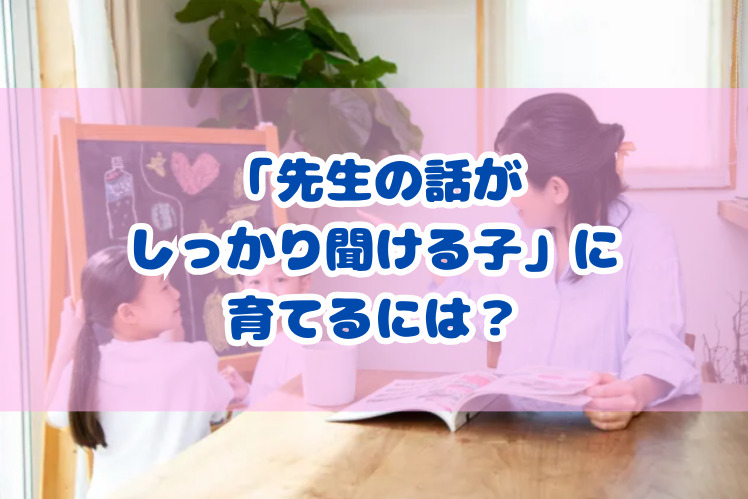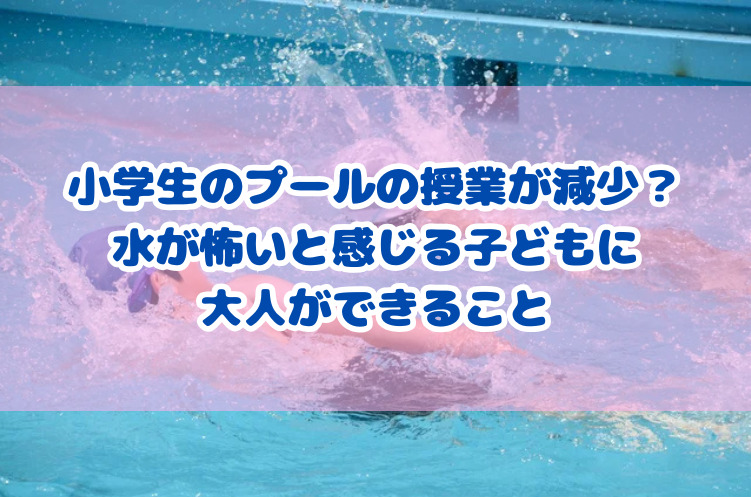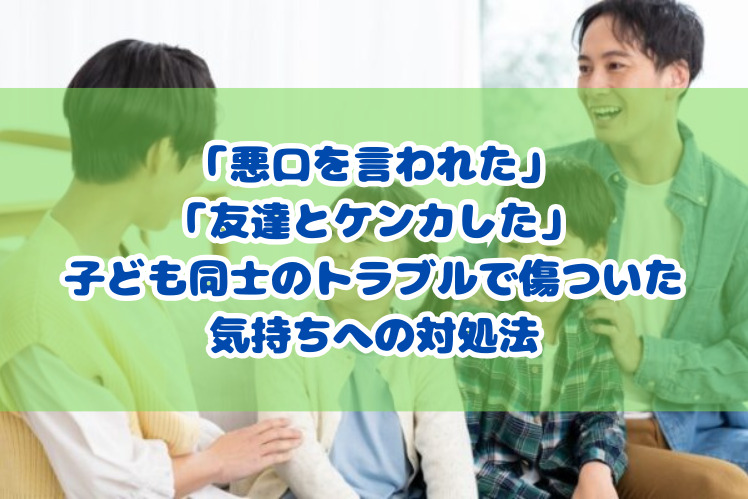「子離れ」考えたことありますか?小学生のうちに始めたい子離れ準備
更新日: 2025.05.14
投稿日: 2025.05.20
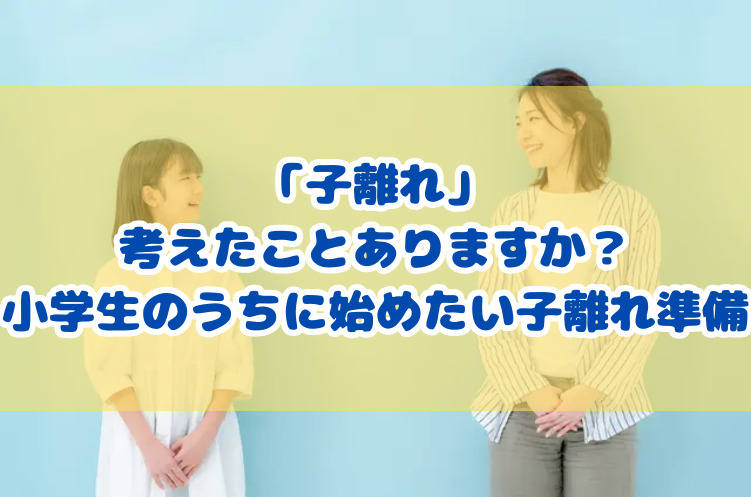
24時間目が離せない赤ちゃんの頃から、日々成長して、いつのまにか一人前な会話をするようになっていくわが子。
いつかは巣立っていく日が来るとわかっていても、「まだまだ手がかかる」「いつのことやら」と思いながら過ごしているお母さん・お父さんは多いでしょう。
しかし「いつか子離れする」とぼんやり考えていると、必要以上に干渉してしまったり、子どもの自立で寂しくなってしまったり…子離れがスムーズにいかないこともあります。
子どもが小学生のうちからできる「子離れ」の準備を、自分のためにも子どものためにも、ゆっくりと確実に進めておきませんか?
もくじ
子離れとは?

子離れとは子どもが成長し、自立していくのにともない、親の保護・干渉をやめて子どもを一人の人間として尊重できるようになることです。
本来は、子育てをしながら親自身も成長し、子育ての仕上げとしてスムーズに子離れすることが理想でしょう。
もちろん「寂しいな」「もう少し一緒にいたいな」という気持ちを心に抱えても、時には手を離して自立を促す必要があるのです。
なぜなら親が子どもを一生守り続けることは不可能で、子どもは子ども自身の責任で人生を切り開き、生きていかないといけないからです。
スムーズな子離れのために、子どもが小学生のうちから少しずつ子離れの心の準備をすることは、決して早すぎることはありません。
子離れの時期っていつ?

ネイティブアメリカンに古くから伝わる「子育て四訓」を知っていますか。
1)乳児はしっかり肌を離すな
2)幼児は肌を離せ、手を離すな
3)少年は手を離せ、目を離すな
4)青年は目を離せ、心を離すな
幼い頃は肌から伝わる愛情・安心感をしっかり伝え、少しずつ手や目を離して、最後は心だけを残して自立させていくプロセスを伝えています。
また同時に、少しずつ子離れをしていくことの大切さを教えているようにも見えます。
子離れの時期について、「準備期」「開始期」「子離れ期」の3期に分けて考えてみましょう。
子離れ準備期(小学校5〜6年生頃)
少しずつ子離れの準備が始まる小学校高学年頃。
子ども自身、友だちとの関係が深まり、友だちと約束して出かけたり、塾や習い事の帰りに寄り道をしたり、一人での行動が増えてきます。
友だちとのトラブルや悩みなども自分で解決しようとする時期なので、親は「話はいつでも聞くよ」という雰囲気を作りながら、本人の意思を尊重する態度を示しましょう。
子どもからSOSが出た時はサポートが必要ですが、それ以外は見守るようにできるといいですね。
子離れ開始期(中学生頃)
思春期を迎え、「うざい」「うるさい」「知らない」など親を遠ざけようとする言動が増えます。
体の変化に心が追いつかなかったり、好きな子ができたりと、自分でも戸惑ってしまう時期かもしれません。
実はここが子離れをスタートさせる最大のチャンス。
子どもが急に背を向けたように感じて寂しくなりますが、腹を決めて少しずつ手を離しましょう。
そして「これまでと同じコミュニケーション方法」や「慣例」の見直しも少しずつ進めるといいでしょう。
・学校への持ち物を一緒にチェック
・好きな子を聞き出す
・口うるさく注意
・聞かれていないのにアドバイスする
・子どもが決めたことに干渉
などをやめ、失敗するのを承知で遠くから見守るようにしたいですね。
このタイミングで少しずつ子離れの試運転をしておくと、高校→大学と進学する時にもスムーズな独り立ちへとつながります。
同時に「何かあればいつでも相談にのるよ」「あなたの味方だよ」というメッセージだけは伝えておくことも大事。
思春期は「自立したい」「でもまだ不安」という気持ちの間で揺れ動く時期なので、ふとした瞬間に甘えられる場所も必要になるでしょう。
子離れ期(高校卒業)
いよいよ本格的な子離れが始まります。
大学進学のために家を出る子、就職のために遠方に行く子など、物理的に親から離れる子も多いでしょう。
自宅から学校や勤め先に通う子でも、アルバイトや異性との付き合い、仕事の人間関係など、子ども自身の世界が広がり、完全に大人として扱う必要が出てきます。
進学先や進路に関しても親がコントロールしようとは思わないことも大切。
子離れをしても他人同士になるわけではなく、お互いを思い合う、大人同士の付き合いはもちろん続きます。
このタイミングで「子どもは子ども」「親は親」と切り分けて、子離れをするのが理想です。
子離れチェックリスト

自分の子離れ準備はできているのか、それとも子離れが苦手なタイプか、一度チェックリストで確認してみましょう。
◻︎ 自分の希望どおりに子どもが行動するとホッとする
◻︎ 子どものことはなんでも知りたい
◻︎ 子どもの問題はすべて親も一緒になって解決すべきと思う
◻︎ 自分が叶えられなかった夢を子どもに叶えてほしい
◻︎ 持ち物や宿題など、心配でつい親が確認してしまう
◻︎ 子どもの話を聞くのが苦手
◻︎ 夫婦で過ごす時間より「子どもとの時間」が心地よい
◻︎ 「宿題」「就寝」「起床」などに細かく口出ししている
◻︎ 自分の趣味や友だちより、子どもが生きがい
チェックが多いほど、子どもへの依存度が強い傾向があるので、少しずつ子どもを信用し、手をかけないように心がけたいですね。
「子離れできないタイプかも…」とわかれば、普段から心がけることで少しずつ準備ができるでしょう。
子離れできない親の特徴は?

なかなか子離れできない親は、共通する特徴があります。
自分を冷静に見つめて判断することはなかなか難しいですが、少しでも思い当たることがあれば、意識的に子離れするようにしましょう。
○ 子どもの成長や変化を喜べない
○ 子どものすべてを把握しようとする
○ 「自分がいなきゃダメ」と思っている
○ 子どもの話を聞かない
○ 自己肯定感が低い
○ 仲の良すぎる友だちタイプ
子どもの成長や変化を喜べない
「子どもの成長」は、親から離れていくことを意味しています。
それまでは「お母さんがいないと嫌」だったのが、「お母さんは来ないで」「一人で大丈夫」と、少しずつ手を離れていくでしょう。
子離れできない親は、それらの変化を受け入れられずに、いつまでも子どもに頼ってほしい、離れないでほしいと思いがちです。
子どものすべてを把握しようとする
子どもが大きくなればなるほど、親に言わないことは増えていきます。
それを不安に感じて、「寄り道したの?」「誰と出かけたの?」「今日は何をした?」と子どもの全てを把握しようとする親は、なかなか子離れが難しいタイプ。
親の関心事のすべてが「子ども」、子ども以外のことに夢中になれないという状態は、実はとても危険なことなのです。
「自分がいなきゃダメ」と思っている
子どもは親がいなくても、案外うまくやるものです。
ガミガミ言ってもやらないけど、放っておいたら自分で宿題を終わらせていた。
親が外出していた日は、いつもより早く寝た。
などはよくある話。
「自分がいなきゃダメ」と思っている親は、「そう思ってほしい」という願望が強く、子どもに依存している状態かもしれません。
子どもの話を聞かない
子離れをするということは、「子どもを一人の人間として扱う」ことにつながります。
子離れできない親はいつまでも子ども扱いをして、子どもの話を聞かない傾向があります。
子どもを尊重せず、子ども扱いをすることで、「自分のそばにいてほしい」「離れないでほしい」という気持ちを表しているのでしょう。
自己肯定感が低い
自分の行動に自信がない、自己肯定感の低い親は、その自信のなさを子どもで埋めようとしてしまいます。
子どもに尽くして、「いい親」を演じることで、満足感を得て懸命に自分を支えようとするのです。
子離れをしてしまうと自分の役割が奪われてしまうため、無意識に子どもを抱え込もうとしてしまいます。
仲の良すぎる友だちタイプ
「どこに行くのも一緒」「なんでも話す親子」は微笑ましいようでいて、実は危険をはらんでいます。
親はいつまでも子どもが近くにいて安心し、子どもは「友だちがいなくても親がいるからいい」という、双方で頼り合う共依存の関係になりやすいでしょう。
親は子どもの自立を認めたがらず、過干渉になりがちで、子どもも自分の気持ちを押し殺してしまうことがあります。
子離れしないことによる影響

子離れの話になると、「親が子どもに愛情を注いでなにが悪い!」という気持ちなる人も多いでしょう。
しかし、いつまでも親が子どもに張り付いて干渉することで、子どもには大きな弊害が生まれてしまいます。
子離れしないことで、どんなことが起こるのでしょうか。
○ 子どもの判断力や主体性が育たない
○ 子どもの自立を邪魔してしまう
○ 子どもに自信がなくなる
○ 親子のほどよい距離感がわからない
○ 依存体質になる
子どもの判断力や主体性が育たない
子どもの成長とは、自分自身で判断し主体的に動けるようになることです。
子離れ・親離れができていないと、子どもはいつまでも親をアテにして、判断力や主体性、積極性などが育ちません。
子どもが自分自身の判断や行動に責任を持つためには、子離れは必要なプロセスです。
子どもの自立を邪魔してしまう
親離れ・子離れができていないと、子どもはいつまでも親の言うことを聞いていれば平和なので、自立心が育ちにくくなるでしょう。
親が子離れできなくても、子どもの方が親離れできていれば大丈夫ですが、双方が依存する関係になると子どもは自立できないまま大人になってしまうことも…。
「親の仕事は子どもを自立させること」と考え、しっかり子離れをしたいものですね。
子どもに自信がなくなる
親に守られて、親の言うことだけを聞いていると、「自分の判断で行動する」ことが極端に少なくなります。
親に言われた通りにしていれば怒られず、失敗しないので、いわゆる「指示待ち」の子が育つのは、子離れしていない親にも原因があります。
子どもは自分の考えで行動し、失敗してもなんとかリカバリーすることで、少しずつ自信を蓄えていくので、その機会を奪うことになってしまうでしょう。
親子のほどよい距離感がわからない
子離れをしないと、いつまでも子どもに干渉したり、ズケズケと子どものプライバシーに踏み込んだり、必要以上に子どもに冷たくしてしまったり、本来取るべき距離感がわからなくなります。
親子が密着していた時期から、少しずつ距離ができ、最終的には大人同士の付き合いになるはずの親子の距離感。
ほどよい距離を保つには、親離れ・子離れをするのが近道です。
依存体質になる
子離れが適切にできないと、子どもは親や家族、周囲の人たちへの依存体質の傾向が強まります。
自分の意思で行動することが減り、何か失敗したり、トラブルになっても「◯◯のせい」と責任を他人に押しつけたり、「自分のせいじゃない」と責任逃れをする体質になりやすいといわれています。
依存体質の人は社会人になった後も仕事や人間関係で問題を持ちやすく、親になっても子どもに依存をしてしまい、「子離れできない連鎖」が生まれてしまう可能性もあります。
上手に子離れするための準備方法は?

ではどのように子離れの準備をしたらいいのでしょうか。
ここでは、「自分自身」「パートナー」「子ども」の3つの視点から、スムーズな子離れ準備を考えてみましょう。
⬛ 自分自身
子どもや家族を一番に考えて、子育てに邁進してきた自分を、まずはねぎらいましょう。
そして少しずつ人生の主役を「自分」にシフトしていくために、挑戦してみたかったことを始めてみたり、昔の趣味を復活させたり、子どもから自分へフォーカスを変えていくことが、準備の第一歩です。
大袈裟なことでなくても、「観たかった映画に行ってみる」「懐かしい友だちに連絡を取ってみる」など、小さなことから「自分の時間」「自分の思考」を少しずつ確保してみるのもいいですね。
親が自分自身のことを大切に、丁寧に扱えるようになると、子どもへの視点も変化し、子どもを尊重できるようになります。
子離れ準備は、少しずつゆっくり進めた方がスムーズなので、子どものこともケアしつつ、自分の趣味や将来のことなども少しずつ考えてみましょう。
⬛ パートナー
子離れした後、パートナーがいる場合は、その人との関係性がより密接になるでしょう。
これまでは子どもを中心に成り立っていた「家族」という単位が、パートナーと自分という最小単位になります。
子どもが巣立った後の生活のことやお金の計画、パートナーと一緒にすること、一人で取り組むことなど、今すぐではなくても将来必ず訪れる時のために、考えておきましょう。
子離れできない親はパートナーとの関係がうまくいっておらず、その穴埋めを子どもに求める傾向があると言われます。
パートナーとの関係を見直すのも、子離れの準備の一環になるでしょう。
⬛ 子ども
子どもを信頼して、「子は子・親は親」という気持ちを親子で共有しましょう。
日常的に「子どもができることは任せる」「子どもから求められた時にだけ助ける」といった対応を少しずつ増やし、子どもを尊重する姿勢を子どもに見せましょう。
そうすることで子どもも信頼されていると感じ、「自分で考える」「自分で行動する」という自主性が育ちます。
親が子離れを意識すると、子どもも自然と親離れの必要性を感じ、準備を始められますね。
子離れは「子育ての総仕上げ」

子離れと聞くと「寂しさ」を感じたり、「親が子どもを心配するのは当たり前だ」と腹立たしい気持ちになる人もいるでしょう。
そして、いつかはやってくるその時までズルズルと先延ばしにしたい気持ちになってしまいますよね。
しかし「子離れ」は子どもへの愛情を減らすことでも、子どもを突き放すことでもありません。
子離れは単に子どもと離れることではなく、「この子は大丈夫」と親が自信を持って思えること、子どもを1人の人間として扱えるようになることです。
子離れ・親離れは、これまで子どもを育ててきた総仕上げになる、大切なプロセス。
生涯続いていく良好な親子関係のためにも、鮮やかに気持ちよく子離れしたいですね。
・子離れとは子どもの成長にともない、親の干渉をやめて、子どもを尊重できるようになること。
・小学校高学年になったら子離れの準備を始め、中学校→高校と段階的に子離れをしていくのがベスト。
・子離れできないタイプの親は、自分自身で自覚をして、子離れする必要がある。
・子離れできないと、子どもの成長や自立の邪魔になってしまったり、子どもが依存体質になるなどデメリットが多い。
(参考文献)
・ココロコミュ | 上手に子離れ、親離れする方法とは?
・ミラシル | 子離れできない親の特徴って? 子どもが巣立った後も幸せに暮らすコツ
・見守る子育て | 子離れするのはいつ?ベストなタイミングとその方法
・プレジデントオンライン | 子離れできない親が繰り返す、子どもの生活力を奪う“NGワード”
・ハピママ | 18歳までにチャンスは3回!ベストタイミングと距離のとり方