心の知能指数「EQ」って知ってる? どうすれば子どもの「EQ」は伸びるの?
更新日: 2025.04.03
投稿日: 2025.04.08
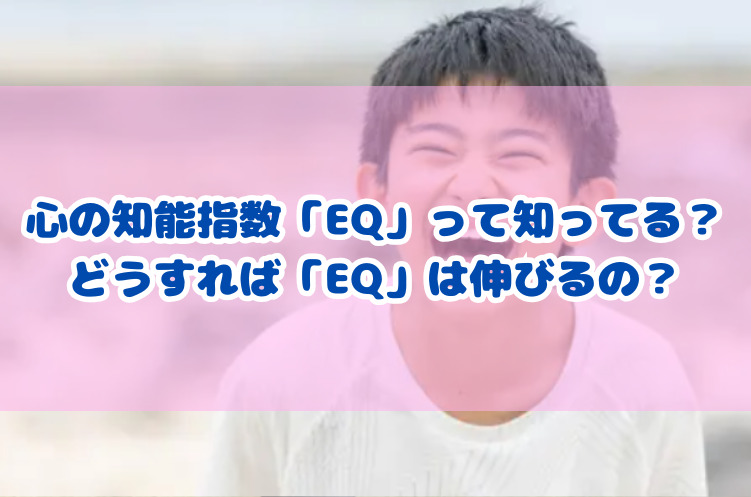
ウエルビーイングの時代、わが子は将来「勉強ができる子」よりも「心の豊かな子」に育ってほしいと願う保護者は多いのではないでしょうか。
近年、注目を集めている「EQ(心の知能指数)」は、感情を理解し、コントロールする能力のこと。
EQの高い子は、コミュニケーション能力が高く、ストレスにも強いと言われています。
「EQは生まれつきのものではなく、後天的に伸ばすことができる」という点が、IQとは大きく異なります。
この記事では、EQの大切さや、子どものEQを伸ばすための親の関わりについて解説します。
もくじ
心の知能指数「EQ」とは。「IQ」との違いは?

「EQ」という言葉、聞いたことはありますか?
EQとは、「Emotional Intelligence Quotient」の略語。
アメリカの心理学者、ダニエル・ゴールマンが、著書『Emotional Intellegence』の中で提唱した概念で、自分や周りの人の気持ちを理解する能力や、自分の感情をコントロールする能力のことを指します。
一方、IQ(Intelligence Quotient)は、「知能指数」と呼ばれ、主に記憶力・計算力・読解力といった認知能力を測定するものです。
EQとIQの大きな違いは、以下の点です。
EQ:感情を理解し、コントロールする能力=非認知能力
IQ:記憶力、計算力、読解力など=認知能力
EQ:トレーニングや経験によって後天的に伸ばすことができる
IQ:遺伝的な要素が大きく、後天的な成長は限定的
EQ:人間関係、コミュニケーション能力、ストレス耐性などに影響する
IQ:学業成績、論理的思考力などに影響する
IQが「頭の良さ」を示すのに対し、EQは「心の賢さ」を示すと言えるでしょう。
EQが高い子どもは、「友だちと協力して目標を達成する」など、他者と上手にコミュニケーションを取ることができるといわれています。
また、「テストで失敗しても、次のテストに向けて対策を立てられる」など、前向きに気持ちを切り替え行動できます。
さらに、自己肯定感が高く、何事にも前向きにチャレンジできると言われています。
これらの能力は、学校だけでなく、社会に出てからもとても大切です。
社会のグローバル化や多様化が進む現代においては、子どものEQを高めることが、よりよい未来につながると考えられているのです。
子どもの「EQ」を伸ばす親の関わりと、家庭で取り入れたい習慣

ここでは、子どものEQを伸ばす親の関わりと、家庭で取り入れたい習慣について紹介します。
子どもの感情を言葉にすることを心がける
日々の生活の中で、子どもの感情を積極的に言葉にしましょう。
例えば、公園で楽しく遊んでいるときには「ブランコに乗れてうれしいね!」、おもちゃがこわれて悲しんでいるときには「大事にしていたおもちゃがこわれて悲しいね…」のように、具体的な状況と感情を結びつけて言葉で伝えることが大切です。
子どもの気持ちを受け止める
子どもが感情をあらわにしたとき、たとえそれが親にとって理解しがたいものであっても、否定せずに受け止めることが大切です。
「そんなことで泣かないの!」などと頭ごなしに否定するのではなく、「そうか、〇〇したかったんだね。でも、今はできないんだよ」というように、子どもの気持ちに寄り添い、共感する関わりを心がけましょう。
子どもと一緒に絵本や物語を読む
子どもと一緒に絵本や物語を読むことで、さまざまな感情があることを知ることができます。
読み終わった後に、「〇〇ちゃんはどうして泣いていたのかな?」「△△くんはどんな気持ちだったのかな?」など、登場人物の気持ちについて話し合うことで、想像する力を養うことができます。
「感情カード」で対話を楽しむ
さまざまな感情が描かれたカードを使い、感情の名前や意味について親子で対話しましょう。
例えば、「うれしい」「悲しい」「怒っている」などのカードを用意し、子どもにカードの表情を真似してもらったり、カードの感情がどんな時に起こるかを話し合ったりします。
カードを使って、感情を表現するゲームもおすすめです。
例えば、カードを引いて、その感情をジェスチャーで表現するゲームや、カードの感情にまつわるエピソードを話すゲームなどもあります。
このような対話を通して、周りの人に気持ちを伝える術を学ぶことができます。
子どもが「今この瞬間」に集中できる状況をつくる
ノースカロライナ大学の精神医学部の研究によると、マインドフルネスは、感情認知において重要な「自己認識」を高める要素として働く可能性が示唆されています。
つまり、「今この瞬間への集中」が促されることで自己認識が深まると考えられています。
過去や未来ではなく、今、ここで起こっているものごとを体験し、ただ目の前のことに集中する状態のこと。
瞑想などの方法を利用して、呼吸に意識を集中し、何も考えず「無」の境地をつくり出す心の訓練を表します。
マインドフルネスは、ヨガなどのイメージが強いですが、自然に触れることでもマインドフルネスのような状態を作れることがわかっています。
親子で自然の中を散歩したり、キャンプに出かけたりすることで「今この瞬間」に集中できる状況をつくれることもあります。
子どもの「EQ」を伸ばす親の愛情表現とは

子どものEQを育む上で、何よりも大切なのは、温かい愛情を伝えることです。
それは、子どもの心の土台を築き、自信と安心感を与える魔法のようなもの。
日々のスキンシップややさしい言葉を通して、愛情をたっぷり伝えていきましょう。
言葉で愛情を伝える
「言わなくても伝わる」と思いがちな親の愛情。
しかし子どもの心は繊細で、時に不安になることもあります。
「ママは忙しそうだし、僕の話を聞いてくれない。もう僕のこと、好きじゃないのかな…」そんな風に、小さな心が揺れてしまうこともあります。
だからこそ、愛情を言葉で伝えることが大切です。
朝起きた時に「今日も大好きだよ」と伝えたり、絵本を読みながら「ママは〇〇ちゃんが宝物だよ」と語りかけたり。
何気ない瞬間に、わが子を思う言葉を添えてみましょう。
スキンシップで心をつなぐ
スキンシップは、愛情を伝える強力な手段です。
幼い頃は自然とハグしていた親も、子どもの成長と共に機会が減ってしまうかもしれません。
子どもが嫌がる場合は、無理強いする必要はありません。
・ ほめる時に頭をなでる。
・ 嬉しい時にハイタッチする。
などのさりげない触れ合いも、立派なスキンシップです。
子どもと話す時に、そっと手を握ってみましょう。
「〇〇って言われた時、どんな気持ちになったかな?」と問いかけたり、子どもの話にじっくり耳を傾ける時も、手を握ることで心が通じ合います。
スキンシップで子どもの心に寄り添い、温かい親子のつながりを感じさせてあげましょう。
わが子のEQを伸ばすことは、親としての大切な役割のひとつです。
共感力を高め、自分の気持ちを正直に伝えられる環境を作りつつ、相手の感情を理解し受け入れる力を育んでいくことが大切です。
子どもが大人になっても真の共感力や思いやりを持ち続けられるよう、今からその基盤を築いていきましょう。
悩みや不安がある時こそ子どもと一緒に考え、成長をサポートしていきたいですね。
・ 「EQ」は心の知能指数で非認知能力。「IQ」との違いを知っておこう。
・ 持続可能な社会を担う子どもたちに必要なのは、「IQ」よりも「EQ」。
・ 子どもの感情を言葉にすることが、「EQ」の成長につながる。
・ 子どもの年齢に即した親の愛情表現を惜しまずに。
「心の知能指数EQとは?幼児期からできるEQの伸ばし方を紹介」(出典:CONOBAS)
「子どものEQ力(心の知能指数)が絵本の読み聞かせで伸びる理由と、効果的な絵本の読み方選び方」(出典:ベネッセ教育情報)
「EQが高く、思いやりがある子どもを育てるためには?心理学の観点からアドバイスも紹介」(出典:子育てのとびら)
「子どもの将来を左右する非認知能力EQは “親の愛” で高まる」(出典:こどもまなびラボ)



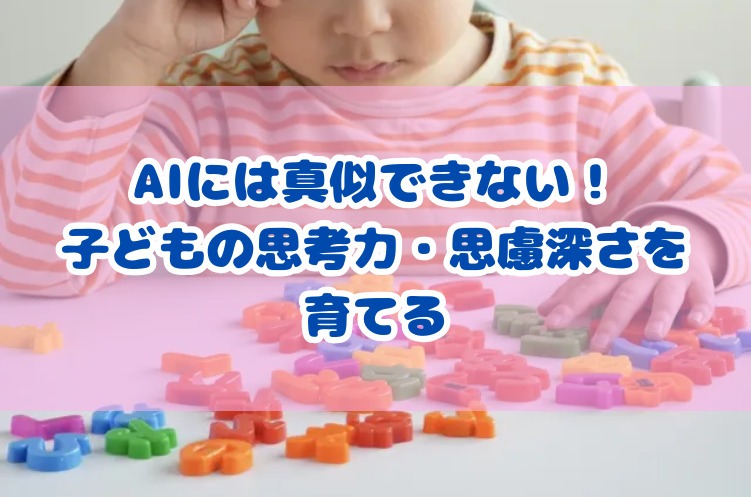
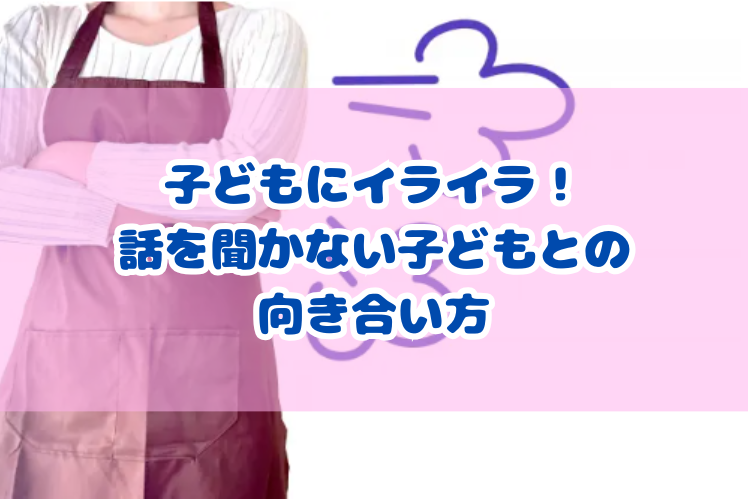

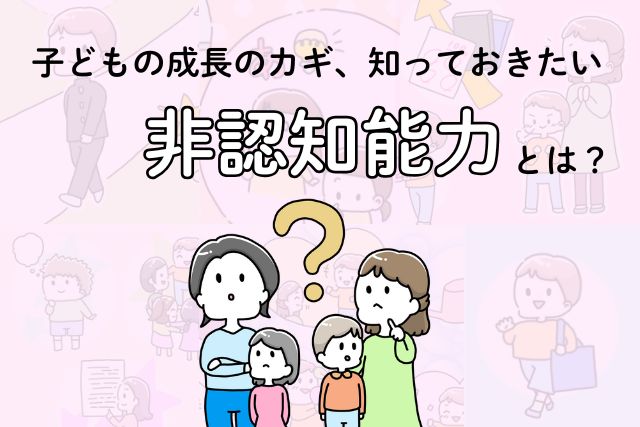
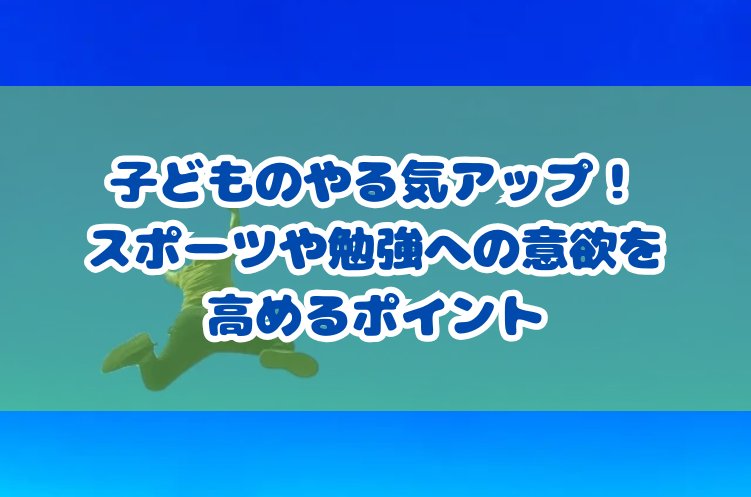










専門家コメント
フリーライター・エディターとして、育児、教育、暮らし、PTAの分野で取材、執筆活動を行っています。息子が所属していたスポーツ少年団(サッカー)では保護者代表をつとめ、子ども時代に親子でスポーツに関わることの大切さを実感しました。PTA活動にも数多く携わり、その経験をもとに『PTA広報誌づくりがウソのように楽しくラクになる本 』(厚有出版)などの著作もあります。「All About」子育て・PTA情報ガイド。2 児の母。