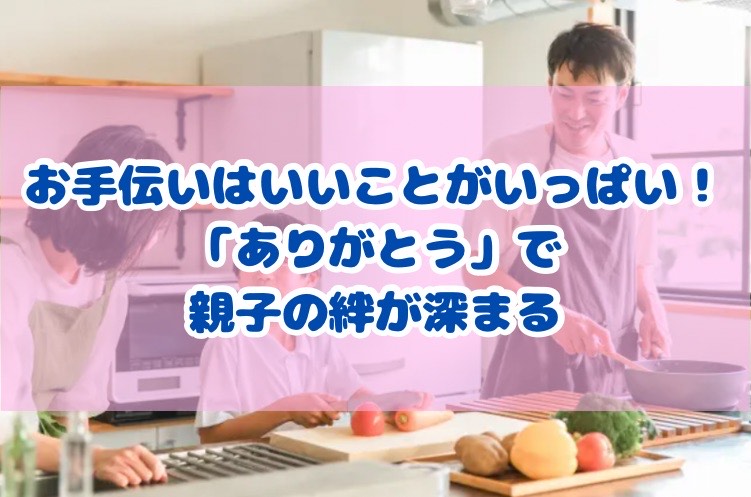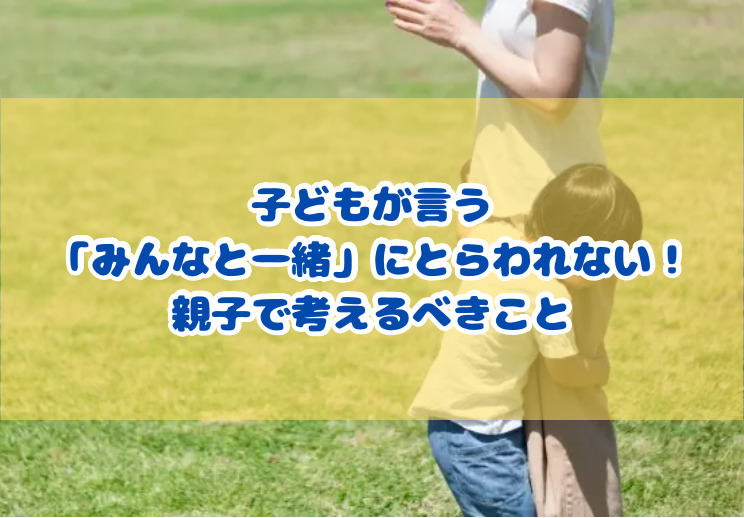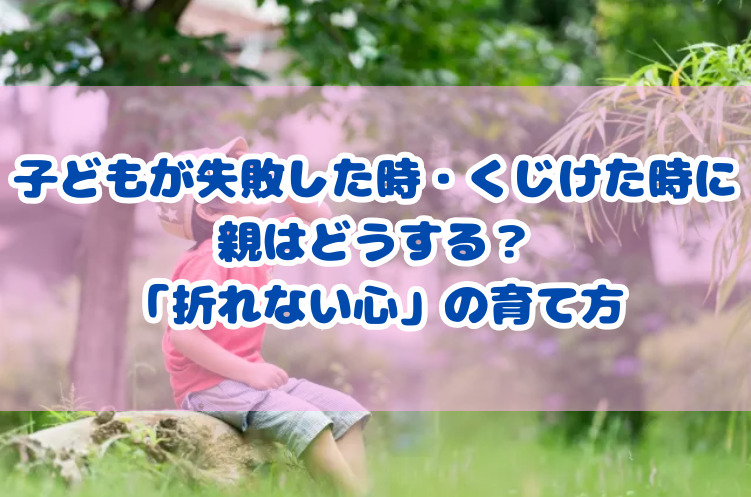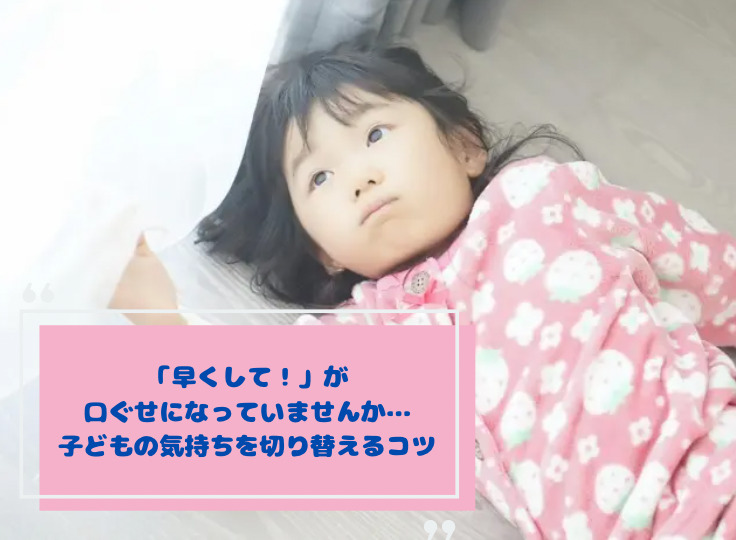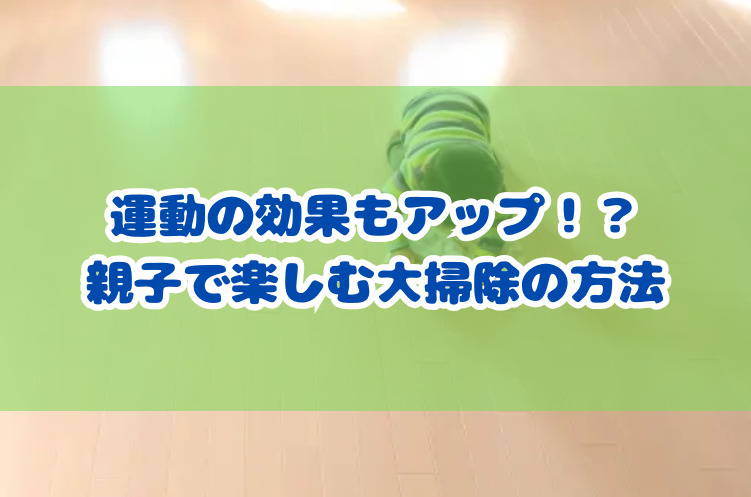困った時に「手伝って」「助けて」が言える、ヘルプシーキングスキルとは?
更新日: 2025.03.13
投稿日: 2025.03.14
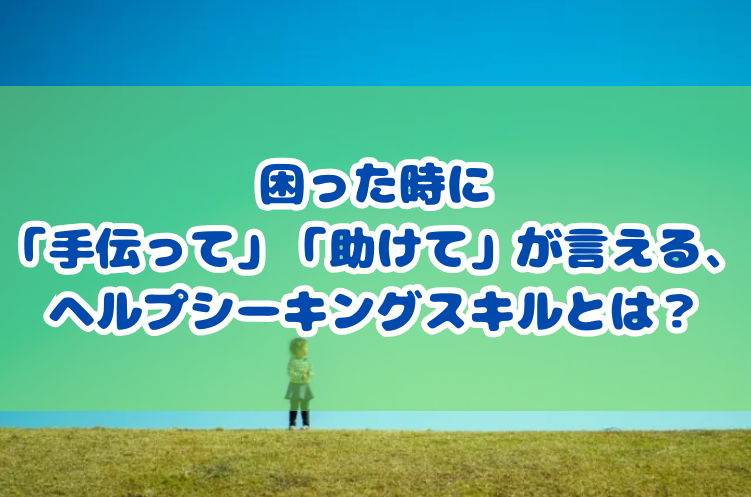
困った時や助けが必要な時に、「困ってる」「助けてほしい」と人に伝えるのは、簡単なようで意外と難しいものです。
特に子どもは「怒られるかな…」「こんなこと言ったら変かな?」と、自分の気持ちを抑えてしまいがち。
しかしこのSOSを発信する力は、子どもが成長するうえでも、大人になってからも役立つスキル。
今回はこの「助けて」や「手伝って」を言える「ヘルプシーキングスキル」について考えてみましょう。
もくじ
ヘルプシーキングスキルとは?

ヘルプシーキングとは、文字通りHelp(助け)をSeeking(探し求める)という意味です。
ヘルプシーキングスキルは、自分の手に負えない時、どうしようもない時に周囲を頼る力のことで、最近はビジネスの世界でよく使われる言葉になっています。
日本では「人に迷惑をかけないように」「自分でできることは自分で」という考え方が根強く、なかなか「助けて」「手伝って」と言いにくい文化がありますね。
しかし問題を一人で抱え込まず、人を頼って助けてもらうことも長い人生の中では必要なこと。
ビジネスで使われるようになったのも、周囲を巻き込んでお互い助けたり、助けられながらチームで仕事をしていく方が効率がよく、成果が出やすいことが理由です。
「自分ではなにもしない子になるのでは…」「人を頼ってばかりの子になってほしくない」と心配する必要はありません。
ポジティブなヘルプシーキングスキルを身につければ、上手に人を頼る方法を覚えて自立心も促すことができるのです。
なぜヘルプシーキングスキルが必要なのか

ヘルプシーキングスキルを身につけると、どんなよいことがあるのでしょうか。
○ 人との信頼関係が築ける
○ コミュニケーション力があがる
○ 自立心が芽生える
○ 自分を冷静に見られるようになる
○ 協調性が高まる
人との信頼関係が築ける
周囲に助けを求め、助けてもらう経験を積むと、「人を頼っていいんだ」「SOSを出すと助けてもらえる」ということがわかり、子どもは安心します。
また人を頼り・頼られることで、周囲の人たちと親密な関係が作れるようになり、信頼関係を構築できるようになります。
それが自信になって、今度は自分から人をサポートすることができるようになるでしょう。
コミュニケーション力があがる
SOSを発信するには、「どんな現状なのか」「なにを助けてほしいのか」を人に伝える必要があります。
そのため言語化する力や意思疎通の能力が高まり、コミュニケーション力がアップするでしょう。
また言い出すタイミングを見計らったり、相手の状況を見たりと、基本的な社会的スキルも養われます。
自立心が芽生える
「助けを求めれば、サポートしてもらえる」と理解できると、子どもは周囲を信頼できるようになります。
その信頼や安心感をもとに、子どもは「やってみよう」「挑戦してみよう」と前向きになり、自立心が育つでしょう。
「自立」と「頼ること」は相対するものではなく共存するものなのです。
自分を冷静に見られるようになる
人に助けを求めるには、まず「自分一人だけでは難しい」ことを理解して、それを受け止めなければいけません。
そのためには、自分自身の現状を冷静に見つめて、把握することが必要になります。
ヘルプシーキング力を高めると、自分を冷静に見て判断する力が養われるのです。
協調性が高まる
人に助けてもらう経験をすると、困った人を見た時、助けを求められた時に迷わずサポートする姿勢が培われます。
頼り・頼られる経験を通して、人と協調することや思いやる気持ちを学ぶことができます。
ヘルプシーキングスキルを高めるために、日頃からできること

子どものヘルプシーキングスキルを高めることは、子どもが成長していくうえで大きな助けになります。
しかし「人を頼ること」「助けを求めるスキル」は、突然身に付くものではありません。
日頃から親や周囲の大人が気を付けることで、子どものヘルプシーキングスキルをあげることができます。
困っている人を助ける姿を見せる
人との付き合いが希薄になっている昨今、人を助ける機会も少なくなっているかもしれません。
例えば
・ベビーカーの乗り降りを手伝う
・電車で席を譲る
・町内会のボランティアに参加する
など小さなことから始めてみましょう。
親が率先して誰かを助け、その背中を見せることで「人の役に立つって気持ちがいい」「困った時は助けを求めてもいい」と子どもは実感できます。
子どもに手伝いを頼む
例えば「お皿を並べてもらう」「タオルや靴下などの洗濯物を干してもらう」など、小さなことでも、あえて手伝ってもらうようにしましょう。
大人がやってしまえば簡単なことでも、子どもが手伝うことに意味があります。
そして「ご飯の用意が早く済んだ」「いつもより楽になった」など、具体的にどう役に立ったかを伝えて、お礼を言いましょう。
人に何かを頼まれて手伝うことを経験すると、「人を頼る」ことのハードルが下がります。
困りごとミーティングを定期的に行う
子どもに「困ったことがあったら人を頼るのよ」と教えても、実行にうつすのは勇気がいります。
そのためには「SOS発信」の習慣を日頃からつけておくことが大切です。
週末の夕食時や、習い事の帰り道など、日を決めて定期的に「困りごとミーティング」を開いてみましょう。
ポイントは親が最初に「困りごと」を話して、子どもの助けを借りてみること。
例えば、「もっと本を読む時間がほしい」という困りごとには、子どもたちから「夜、寝る前に一緒に読書の時間を作ろう」というアドバイスがもらえたり…。
「お父さんが家事を手伝ってくれない」という困りごとに、子どもからお父さんへ注意してくれるかもしれません。
「大人も困ることがある」「助けを求めてもいいんだ」とわかれば、子どもも困ったことを話しやすくなりますね。
子どもの貢献意欲を大切にする
本来、子どもには「お手伝いしたい」「人を助けたい」という気持ちが備わっています。
成長の過程で「自分のことは自分で」「人に迷惑をかけないように」と教育されることで、同時にその貢献意欲を抑えてしまっていることも多いのです。
子どもから「一緒にやりたい」「お手伝いしようか?」と言われたら、喜んでやってもらうようにしましょう。
手伝ってもらうことで、より手間がかかることもありますが、ここは目をつぶります。
人と関わり、助けてあげるという行動が、子ども自身のヘルプシーキングスキルにつながるのです。
ヘルプシーキングスキルで、上手に人を頼れる子に!

東京大学先端科学技術研究センターの熊谷晋一郎教授は言います。
「自立とは、頼れる人を増やすことである」
熊谷氏は生まれてすぐ脳性麻痺を患い、車椅子生活で周囲の助けを借りながらも小児科医になったという人物です。
「困った時は周囲を頼ろう」「助けを求めてもいい」と理解している子どもは、自信と安心を持って挑戦することができるでしょう。
そして「前はこんな時に助けてもらった」と振り返り、「もしかしたら、次はこんな時に困るかも」と予想して対処することができるかもしれません。
人を頼れる人は、頼られた時、きっと温かく人に接することができるはず。
誰もがヘルプシーキングスキルを身につけて、人にやさしい社会になってほしいですね。
・ヘルプシーキングスキルとは、「困った時に周囲を頼る力」のこと。
・ヘルプシーキングスキルを身につけると、自立心が芽生えたりコミュニケーション力があがったり、社会的スキルがあがる。
・日頃から「困っている人を助ける」「子どもにお手伝いを頼む」などの行動をすることで、子どものスキルがあがる。
(参考文献)
・東洋経済オンライン | 「自分のことは自分で!」子どもに実は逆効果な訳
・こどもまなびラボ | 「人に頼る力・甘える力・助けてもらう力」の高い子が、“なんでも自分でできる子”よりも強いワケ
・大人んサー | 「なんでも一人で」じゃなくていい 子どもの誰かに“頼る力”を育てよう!