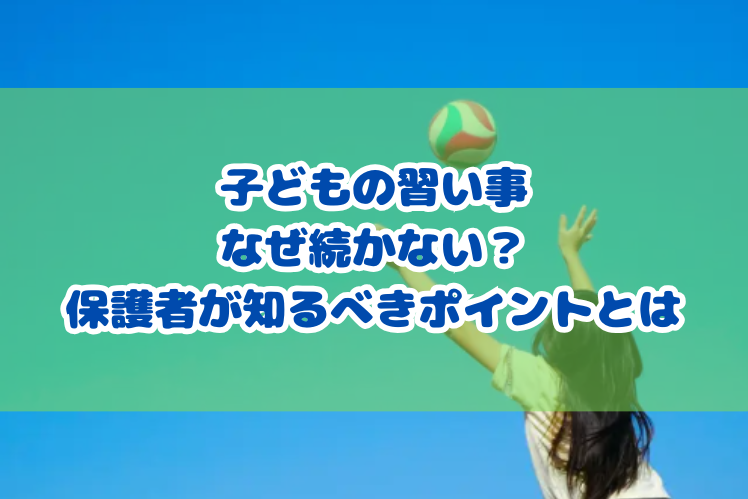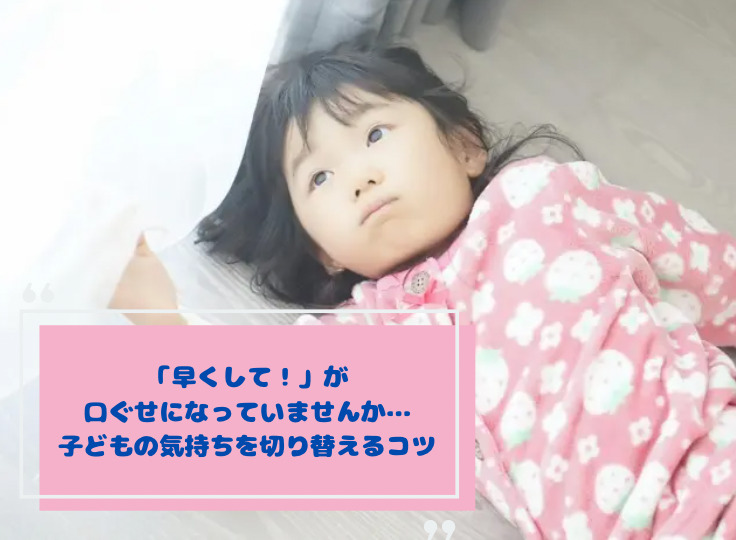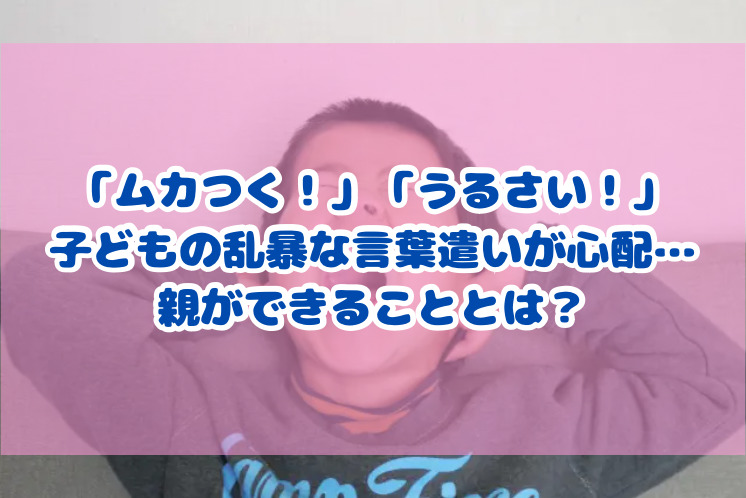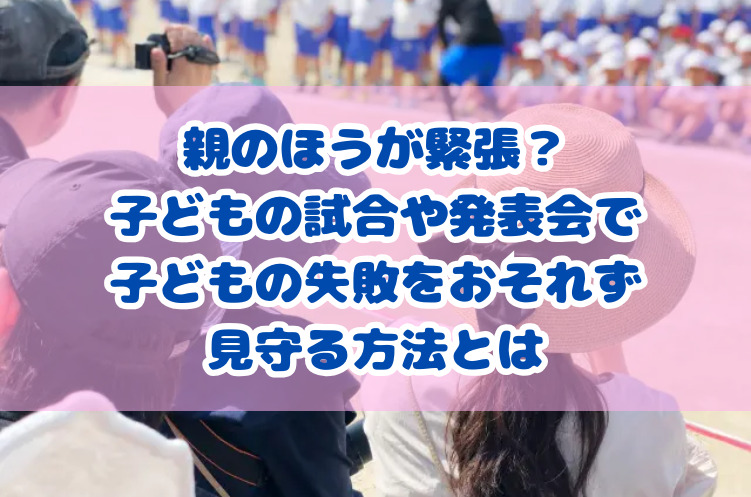子どもが言う「みんなと一緒」にとらわれない!親子で考えるべきこと
更新日: 2025.01.16
投稿日: 2025.01.21
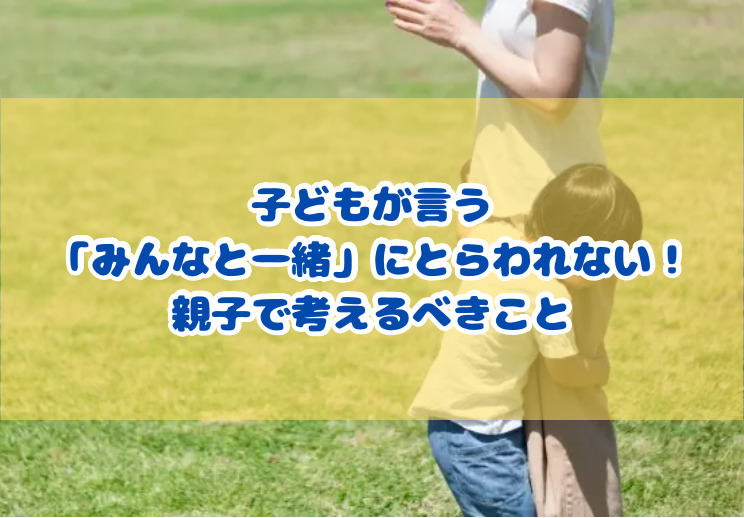
子どもから「みんなが持ってるからほしい」「みんなと同じようにしたい」と言われた経験、ありますよね。
「みんなって誰?」「本当かな…」と思いつつ、「自分の子どもだけが取り残されていたら心配」と迷うことも多いでしょう。
「みんな」を引き合いに出す子どもの心理や対応の方法について、一緒に考えていきましょう。
もくじ
子どもによくある「みんな○○だから」という言葉の背景

子どもが「みんな○○だから」という言葉を使う時、実際は「仲の良い友だちが数人持っているだけ」という場合が多いかもしれません。
親としては「みんなって誰?」「何人くらい?」と問い詰めたくなるところですが、子どもの「みんな○○だから」という言葉には、「強く魅力を感じている」という気持ちや「親を説得しよう」という子どもなりの試みが隠れています。
子どもが「みんな」を引き合いに出すのは、学校に通い始めてクラスメイトの話を聞いたり、友人の家に遊びに行くなど行動範囲や交友関係がグッと広がる小学校以降だといわれます。
子どもだけでなく、大人も「みんな」や「周囲」を気にする傾向は東アジアの国々、特に日本では強く、「自分(自己)」についての考え方は文化的な背景が要因になっているようです。
これは「文化的自己観」と呼ばれ、さまざまな文化において歴史的に作り出されたもので、誰からいわれたわけでもないのに、暗黙のうちに共有されている「自分」への考え方。
例えば欧米では、他者と自分は切り離された存在だと考える「相互独立的自己観」が主流であるのに対し、日本では周囲とのつながりや調和を大切にする「相互協調的自己観」を持つといわれます。
この相互協調的自己観が強いことで、「みんなと同じ・一緒がいい」「悪目立ちをしたくない」「みんなから遅れを取りたくない」という気持ちが生まれ、「みんな○○だから」という説得方法を試みるのでしょう。
また親側も「みんな○○だから」と言われると、「わが子だけ持っていなかったらどうしよう」と心配になり、気持ちが揺らいでしまうのです。
親も無意識のうちに「みんなと一緒に」を求めている?

日本では周囲との調和や協調を大切にする「相互協調的自己観」が強いため、「みんなと一緒」の状態が心地よく感じられるという文化的背景があります。
周囲の状況になじんで、多くの人とうまく関係が作れている時は居心地よく感じられますが、「他人と違う」と感じる場面に出くわすと不安になってしまいます。
そしてそれは子育ての環境でも同じ。
赤ちゃんの頃は定期検診の場で、わが子が同じ月齢・年齢の子と同じように成長していることを確認して安心したり…。
幼稚園や学校、習いごとなどの集団で「うちの子はうまくやっているか」「突飛な行動をしていないか」をチェックしたり…。
親の中にもわが子が「みんなと一緒」であることを、望む気持ちが大きくなってしまうのです。
また「相互協調的自己観」が強いと、周囲の評価を気にしすぎたり、人と比較してしまいがちだという研究結果があります。
兄弟や友だちと比べられたことで、子どもが「頑張ってみよう」「私にもできるかも」と前向きに思えるならいいのですが、「どうせ自分なんて…」と自信喪失や劣等感につながってしまうかもしれません。
もし自分が人と比べてしまうタイプなら、
・友人たちと遊ぶ機会を少し減らして、わが子とじっくり付き合う
・インターネットで子どもに関する情報を調べるのをやめる
・SNSなどの投稿を見ない
など、比較対象の情報から距離を取ることも有効です。
ママ友や社会の目、そのプレッシャーとの向き合い方

子どもを育てていると、ママ友の目が気になって必要以上に子どもを厳しく叱ってしまうことや、面倒なことに付き合う場面もあるでしょう。
また電車や公園などで、必要以上に「人に迷惑をかけないように」とヒヤヒヤしてしまう人も多いのではないでしょうか。
日本では協調性や調和が重視されがちで、足並みを揃えることが美徳とされるため、周囲の目や友だちの意見が知らずにプレッシャーになってしまいます。
そしてそのプレッシャーが子どもに向けられると、
・自己主張することが苦手になる
・やる気が出ない
・失敗を怖がる
・自分で考えることができなくなる
・親の前でだけ「いい子」を演じる
など、子どもの成長に影響することもあります。
周囲の目が気になったり、他人の子どもが優れて見える時があったら、下記のことに意識を集中してみましょう。
○ 他人由来の注意ではなく「何をすべきか」に集中する
○ マイナスに見えることをプラス転換して考えてみる
○ 比べるなら「過去のわが子」と
他人由来の注意ではなく「何をすべきか」に集中する
例えば…
電車の中で騒いでいる時、「怖いおじさんに叱られるから静かにしよう」と注意する。
習いごとで一人だけ違った行動をした時、「なぜみんなと同じようにできないの!」と叱る。
など、「誰かに怒られるから」「周囲と行動を合わせるべき」と注意されていると、子どもは「なぜその行動をしなければいけないか」という本質的な理由が理解できません。
周囲の目を気にして行動を正すのではなく、「公共の場では周囲の迷惑にならない行動をする」など、ルールや社会的規範を子どもに伝えると、子どもは次第にその場面でベストな対応を主体的にできるようになるでしょう。
マイナスに見えることをプラス転換して考えてみる
子どもの言動に注意をしたくなったら、別の視点からとらえ直す「リフレーミング」をしてみましょう。
例えば…
→「自分の考えを持っている」「意思が強い」「あきらめない」
・調子がいい…
→「コミュニケーション力が高い」「明るい」「機転がきく」
・先生から注意ばかりされる…
→「先生に目をかけてもらっている」「直すところが多いのは伸び代がある」
など、リフレーミングの癖をつけると注意したくなるようなことがプラスに転換できるようになり、ポジティブなとらえ方が習慣になるでしょう。
比べるなら「過去の我が子」と
集団の中にいると、どうしても自分の子の「できないこと」や「マイナス面」ばかりに目が行きがちです。
しかし子どもが小さい時のことを考えたら、ずいぶんできることが増えたと思いませんか?
比べるなら他人の子ではなく、以前のわが子と比較してみましょう。
すると、以前はできなかったことができるようになっていることに気づき、成長を実感できるでしょう。
親が自分に言い聞かせる「まぁいいか」の効果

周囲の目を気にし過ぎることは子どもへはもちろん、お母さん・お父さんにもプレッシャーがかかり、自分を追い込んでしまいがちです。
またSNSなどで軽やかに楽しそうに子育てをしている友人やインフルエンサーを見ると、「私はなんてダメな親なんだろう」と落ち込んだり、「もっとできるはず」と無理をしてしまいそうになりますね。
しかし子どもにとって唯一の安全地帯である親が「こうあるべき」「こうしなければ」とキリキリ・イライラしていたら、子どもは安心できません。
・栄養満点の夕食が手作りできなくても…
・聞き分けが悪いわが子に泣きたくなっても…
「まぁいいか」と声に出して、自分や子どもにOKを出してみましょう。
言葉遊びのように感じるかもしれませんが、この「まぁいいか効果」は絶大で、ありのままの自分と子どもをポジティブに受け止められて、自信が持てるようになります。
心の中で唱えるのもいいですが、できれば声に出して「まぁいいか」と言ってみるとより脳に定着しやすく、すべてを許せるような広い気持ちになり、気分が前向きになるでしょう。
「みんな」にとらわれ過ぎずに、自由に考え判断する

子どもが「みんな○○だから、〜したい」と親に言う時、「強く魅力を感じている」という気持ちや、「どうにかして親を説得しよう」という子どもなりの努力があるのでしょう。
もしかしたら自分でも気づかないうちに、「自分の気持ちはさておき、周囲と合わせなければ…」というプレッシャーがあるのかもしれません。
そんな時は、「子ども自身がどう思っているか?」「本当にそうしたいのか」を深掘りして問いかけることが大切です。
「みんなと一緒」はとても心地よく安心できる状態ですが、独立心を持ち、自由な考えを身につけるには、そこから飛び出す勇気も必要になります。
親側も「みんな」という見えない多数派を脅威に感じたり、「うちの子だけ置いてきぼりになってる?」と焦る必要もありません。
「わが家のルールや方針は、家族で話し合って決める」くらいの自信を持って対応していれば、子どもも自然と自分の意見を持つようになるでしょう。
これからの時代、周囲と足並みを揃えることよりも、オリジナリティや表現力、挑戦する気持ち、探究心、創造性などの非認知能力がもっと必要になります。
「みんな◯◯だから」と言われたら、そこから一歩踏み出すチャンスと考えてみてもいいですね。
・子どもの「みんな◯◯だから」には、「強い魅力を感じている」気持ちと「親を説得しよう」という試みが隠れている。
・周囲を気にする考え方は、東アジア圏である日本の「相互協調的自己観」が関係している。
・子どもだけでなく、親も他人の目を気にしたり、「みんなと合わせたい」という気持ちが強い。
・親がプレッシャーを感じないことが、子どもの自由な考えを伸ばす。
(参考文献)
・ベネッセ | 子どもから「みんな〜だから」とお願いされたとき、どう対応したらいい?
・All About | 日本のままはなぜ気にしすぎ?育児中はさらにその度合いが倍増!?
・FNNプライムオンライン | 「“みんな持ってるから”買って!」「…みんなって何人?」子どものおねだりにどう対応するのがいい?