子どもが自分の気持ちを伝えられる!「自己主張力」の伸ばし方
更新日: 2024.10.10
投稿日: 2024.10.18
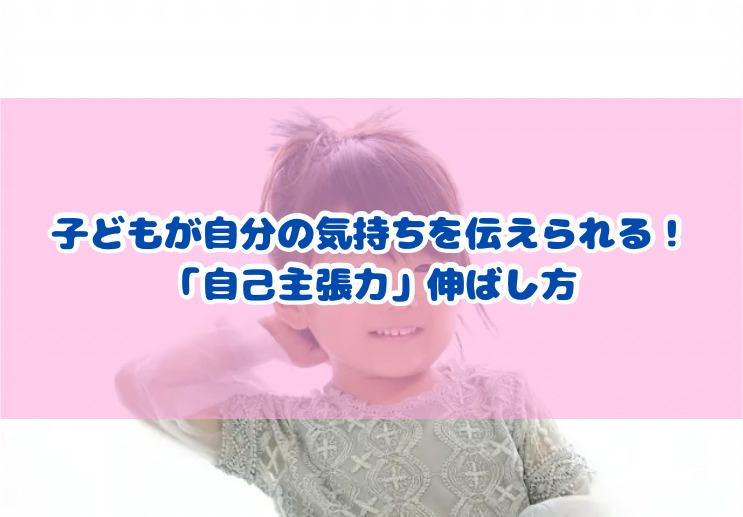
「自己主張」と聞くと、「わがまま」や「我を押し通す」といったイメージがあるかもしれません。
しかし必要な場面で自分の意見を冷静に相手に伝える「自己主張」は、大切な社会的スキルのひとつ。
なぜなら自己主張をするには、判断力や決断力など、多くの非認知能力が必要であり、リーダーシップや仲間をまとめるには欠かせない力だからです。
今回は、子どもの自己主張力について考えてみましょう。
もくじ
子どもが自分の意見を言えずに心配になったことはありませんか?

わが子がおとなしくて、あまり自分の意見を主張をしないと、友だちとの揉め事も少なく、「協調性がある」「やさしい」と周囲から褒められることも多いでしょう。
しかし親からすると、そう単純ではないようです。
など、心配は尽きません。
「周囲と上手にやり取りしながら、自分の意見は堂々と言ってほしい」
「相手の話を聞きつつ、自己主張もしっかりできる子になれば…」
と親は願うものですが、子どもの自己主張力はゆっくり育ちます。
根気よく焦らずに、毎日のやりとりから少しずつ自分の意見を言えるようにしていきましょう。
子どもが自己主張できない理由とは?

自己主張ができるか、できないかは子どもの持っている個性・性格によるものが大きいようですが、その後ろには子どものどんな気持ちが隠れているのでしょうか。
子どもが自分の意見を言わない・言えない理由をみていきましょう。
意見を言うのが怖い・恥ずかしい
「意見を言った時に否定されたことがある」「人前で間違いを指摘された」などの経験から、自己主張ができない場合があります。
また小さい頃から、自分が意見を言うことで親が「怒る」「がっかりする」「そもそも意見を聞いてくれない」という経験を重ねてしまうと、意見を言わなくなる傾向も。
意思表示や自己主張は、「習慣」を変えるとできるようになるので、普段の生活から親は子どもの意見を聞くように心がけましょう。
意見がない・わからない
意見を求められた時に、それに対する意見がない場合、また本気で「どっちでもいい」「特になんとも感じない」と思っている場合は、意見を言わないでしょう。
また聞かれた内容に関して、ある程度の知識や語彙がないと、答えることができません。
そんな時は選択肢を与えてみたり、情報を追加してみると意見が出ることもあります。
周囲の反応に敏感すぎる
人間なら誰しも「人からどう思われるか」は気になりますね。
子どもは経験が少なく、学校や習い事といった限られた世界で暮らしているため、周囲の大人や友だちの存在が重要になり必要以上に敏感になります。
周囲に敏感な子は、自分よりも相手を尊重するやさしい性格ともいえます。
また親が普段から「そんなこと言ったら恥ずかしい」「周囲からどう思われるか…」と、人からの反応を気にしすぎる傾向があると、子どもも人からのリアクションに敏感になるでしょう。
自分に自信がない
「こんなことを言ったら笑われるかな」「変な子と思われるかも…」と、自分に自信が持てないと、意見を言えないことがあります。
幼い頃から、「子どもが意見を言っても否定しない」「まずは一度子どもの考えを受け止める」という対応をしていると、自尊感情が育ってしっかり意見を言えるようになるといわれます。
成長して経験を重ねることで少しずつ自信がつき、自己主張できるようになるケースも多いようです。
自己主張が苦手な子には、どんな関わり方がいいのか?

幼い頃から引っ込み思案で、あまり自己主張をしたくないという子もいれば…。
本当は言いたいことがあるのに、「言い出せない」「我慢している」という子もいるでしょう。
いずれにしても、これから成長していく子どもたちには、上手に自分の意見を伝える方法は身につけてほしいですね。
自己主張が苦手な子に、親としてできることはあるのでしょうか。
子どもの先回りをしない
親であれば、子どもが考えることや言いそうなことが、わかってしまうこともあります。
忙しい時や急いでいる時、「○○でしょ」「わかった、○○だよね」などと子どもの言葉を待たずに先回りしてしまいそうになりますが、そこはグッと堪えましょう。
自己主張ができない子どもの親は、よかれと思って子どもの代弁をしたり、先回りしてしまう傾向が強いようです。
先回りする代わりに理解できないふりをして、「それって、どういうこと?」「わからないから、教えて」と言葉にさせてみることで、自己主張力が育ちます。
あえて反対意見を出してみる
子どもの自己肯定感を育てるために、子どもを全面的に受け入れ、肯定することは大切です。
しかし時々、子どもの考えとは違う意見を親が言ってみると、子どもの思考力や判断力が刺激されます。
そして自分の考えをまとめたり、意見を主張するための言葉を探したりと自己主張の練習ができます。
時々は「物分かりの悪い親」を演じてみることで、子どもはそれを乗り越えようと努力し、さまざまな非認知能力を身に付けられるでしょう。
先読みせずに話を聞く
子どもの話は最後まで聞かないとわからないことも多いですよね。
「苦手な子の話かな…」と思って聞いていると、「すごく面白かった」で終わることもあれば。
仲良しの子の話をしていたと思ったら、「この頃、少しいじわるなの…」という結末だったり。
大人は先を予測したり、決めつけたりせずに、結末がわからない物語を聞くようなワクワクした気持ちで、子どもの話を聞いてみましょう。
自分の話に興味を持ってくれていると感じると、子どもは話をしやすくなり、その発信力が自己主張にもつながります。
ゆったりとした気持ちで向き合う
「先回りしない」「反対意見をぶつけてみる」といった対応は、親の気持ちに余裕がないとできませんね。
もし子どもの力を伸ばしたいのであれば、急かさずに子どもの考える時間を待ち、ゆったりとした気持ちで子どもと向き合う時間が必要です。
「忙しい」「時間がない」という大人の都合が、もしかしたら子どもが自己主張力を身につけるチャンスを奪っているのかもしれません。
「スマホを切る」「お母さん独占タイムを作る」など、大人も日常から切り離す時間を作ると、子どもに向き合う時間を確保できますね。
家庭での声かけはどうすればいい?

自己主張ができない子には、いったいどんな声がけをすればいいのでしょうか。
場面別に考えてみましょう。
意見を聞きたい時は選択肢を示す
自己主張のチャンスを与えようと、「今度の休日、どこに行きたい?」「なにがしたい?」と質問をぶつけると、「どこでもいい」「なんでもいいよ」といつもの答えが返ってきてしまうかも。
そんな時は、選択肢をいくつか示して選ばせるようにすると、子どもも意思が言いやすくなります。
例えば…
・「夜ご飯、なにが食べたい?」ではなく、「から揚げか肉団子、どっちがいい?」
・「日曜日、なにがしたい?」ではなく、「自転車に乗る? それとも遠くの公園まで電車で行ってみる?」
など、具体的に選択肢を挙げると、子どもは自分の考えや気持ちに近い方を選ぶでしょう。
そして子どもの中に情報や経験値が溜まれば、そのうち「なにがしたい?」「どうする?」というふんわりした質問にも、その情報の中から選び出して答えられるようになります。
子どもの話を聞きたい時は、具体的な質問をする
「どうだった?」「楽しい?」などの抽象的な質問をすると、子どもは「別に」「普通」「楽しいよ」と当たり障りのない返答を返してくるでしょう。
子どもから考えや意見を引き出すには、もう一歩踏み込んだ具体的な質問をしてみます。
例えば…
(子)今は小数点をやってる。
(親)小数点、苦手だったなぁ。なんで1より小さい数があるのか、わからないよね。
(子)難しくないよ。1より小さいけど0より大きいんだよ。
(親)それって、どういう意味?
(子)それはね…
(子)つま先や甲じゃなくて、指で押すんだよ。
(親)だって靴を履いてるから押せないじゃない。
(子)だから…
など具体的な質問をして、子どもとの会話をより深くしていくためには、子どもに関心を持ち情報を仕入れる必要があります。
大人が自分に関心を持ってくれることで、子どもは嬉しくなり、自分の言葉で説明をしようと考えるでしょう。
具体的な質問をするには、大人側のリサーチ力や質問力も試されます。
本音を引き出すには、大人の情報開示も
相手の意見や気持ちを引き出すには、まずは大人が自分の話をして、情報を開示することが大切です。
今日あったことや失敗したことなどを、先に子どもに伝えてみましょう。
例えば…
(子)どうしたの?
(親)えらい人に「やっといて」って言われたことを「後でやろう」と思って置いておいたら、「いつできるんだ!」って怒られちゃった。
(子)「後でやろうと思ってました」って言えばいいのに。
(親)言い訳みたいでカッコ悪いからさ。○○も経験ある?
(子)僕もさ、この前…
(子)ええー!
(親)でもその子のお母さん、ちゃんと「すみません」って謝りに来たよ。それもえらいと思った。あなたも知らない人に怒られたことある?
(子)あるよ。公園でさ…。
まずは大人が話し、「次はあなたの番よ」という風に話し手のバトンを渡すと、子どもも自分の意見や感想を言いやすくなるでしょう。
子どもが話しはじめたら、途中で話の腰を折らないように、急かさないように注意しましょう。
「伝えることの大切さ」を子どもに理解してもらうために

自己主張できないことは、決して悪いことではありません。
しかし「嫌なことは嫌と言う」「自分の気持ちを発信する」ことも大切なこと。
自己主張力は習慣なので、家庭内で日常的に行うことで確実に伸びる能力です。
毎日の親子の対話から、気持ちの押し引きやさじ加減を学び、適切な自己主張ができるように子どもを育てたいもの。
子どもの話を先回りせず、本当の気持ちを引き出しながら、子どもが少しずつ意見を伝えられるようにサポートしていきましょう。
・自己主張力は「わがまま」とは違い、周囲の意見を聞きながら自分の気持ちを発信できる力。
・子どもが自己主張できない理由は、「恥ずかしい」「自信がない」「周囲の反応に敏感すぎる」などがある。
・自己主張ができない子には、「先回りしない」「あえて反対意見を出す」などの関わり合いがおすすめ。
・適切な自己主張力は、生きていくうえで大切なこと。
(参考文献)
・こども学びラボ | 「自分の意見が言えない子ども」には4つのタイプがあった。我が子を認めていますか?
・コノバス | 自分の意見が言えない「自己主張」できない我が子への親の関わり方
・PHP nobico | やさしすぎて心配…「自己主張が苦手な子」の親がやりがちな間違ったサポート
・ジャニアス | 自分の意見が言えない子に効果あり!親子で出来る表現上手のトレーニング法


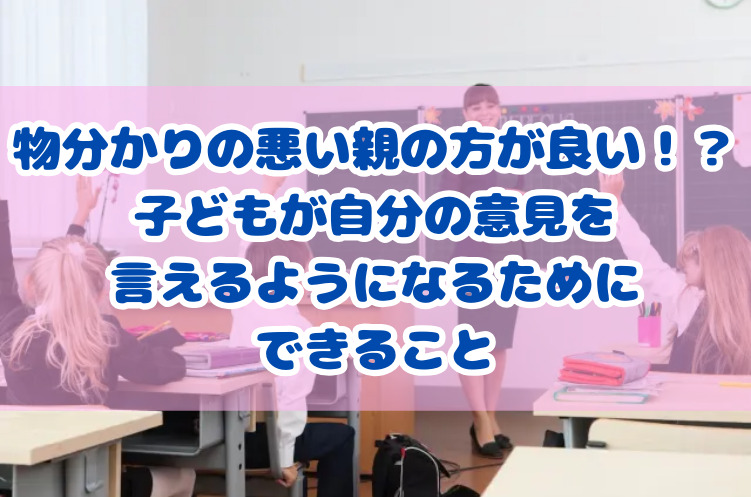


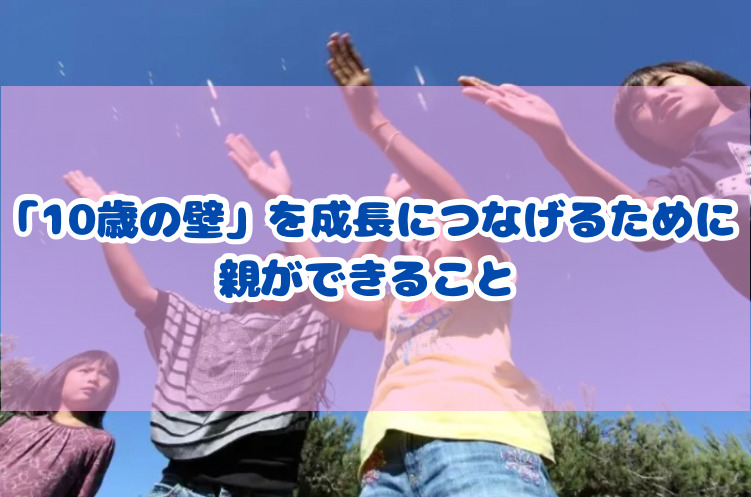

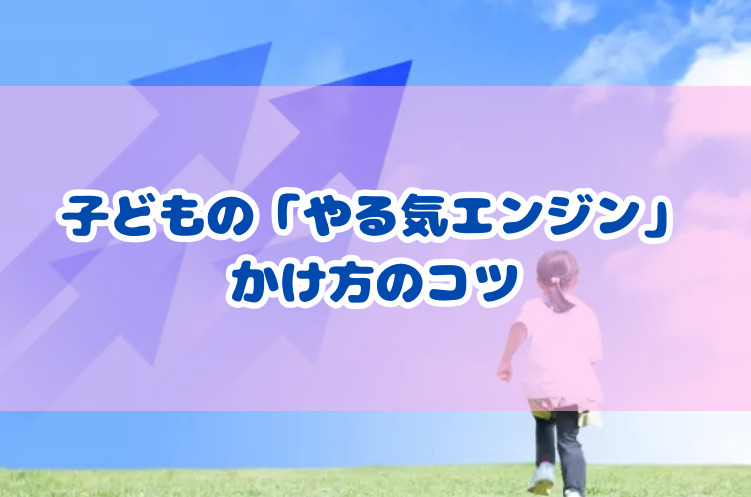
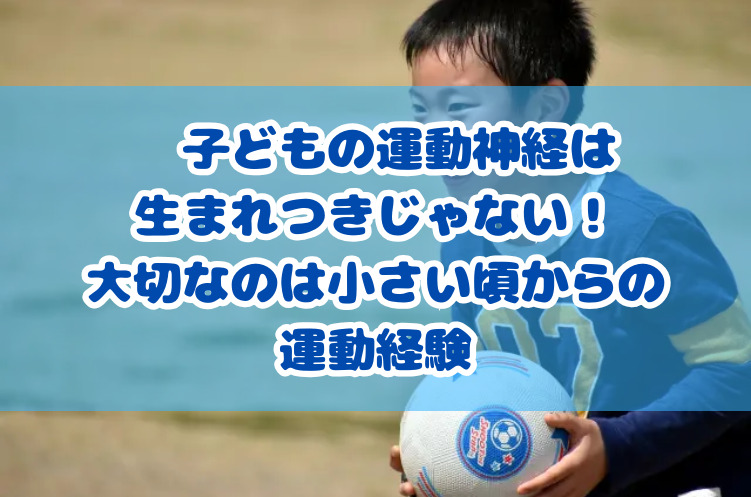









専門家コメント
実用書の編集・ライティング、人物インタビューを中心に活動中。子育てや街紹介のポータルサイトでは1000件以上の学校や教育施設、子育て支援施設を取材。「学業とスポーツは必ず両立する」を信条に、息子2人を大学まで野球漬けに育てあげる。趣味は、はた織り・耳かき・スポーツ観戦。好きな言葉「中庸」。