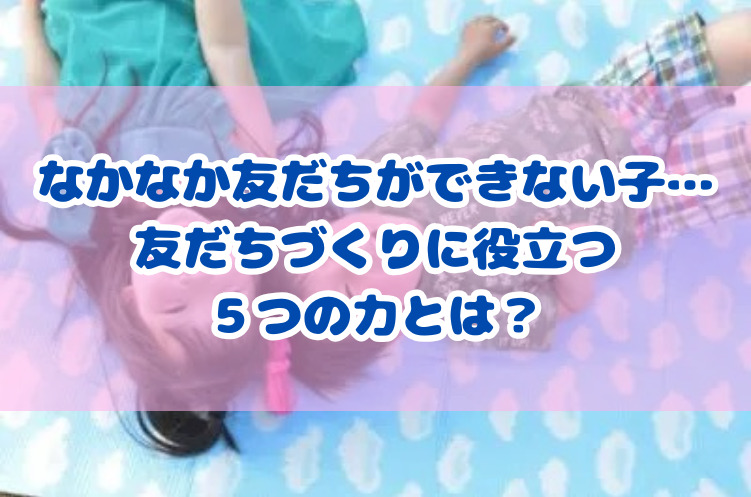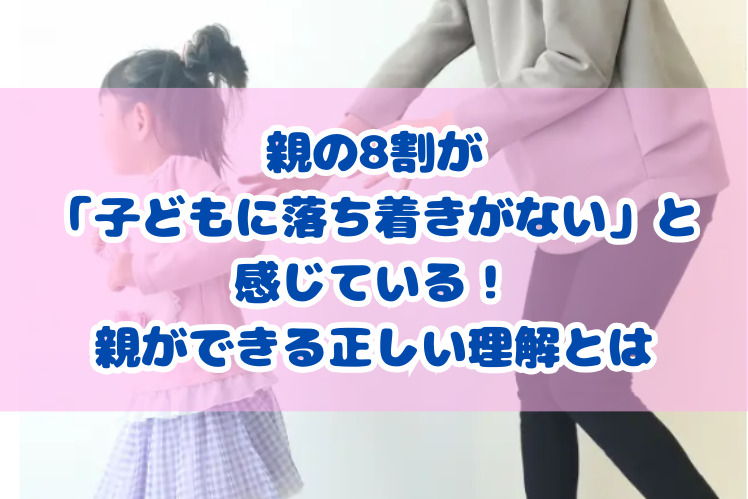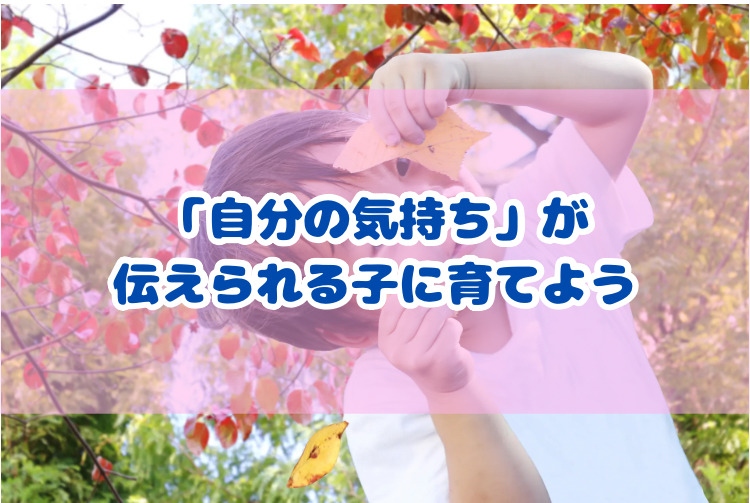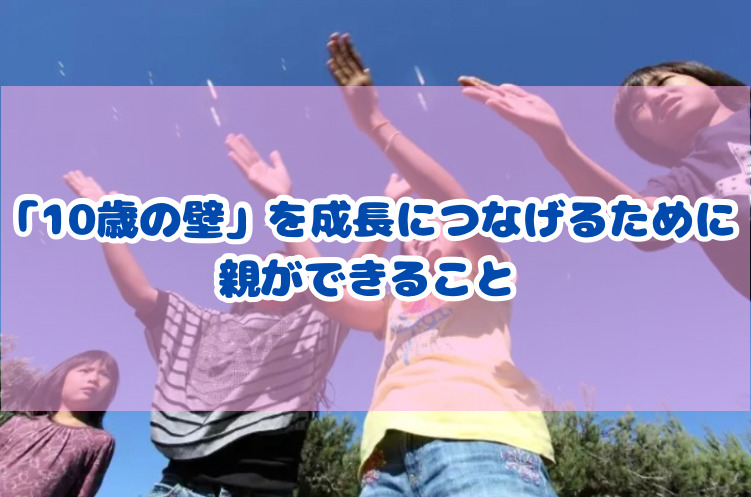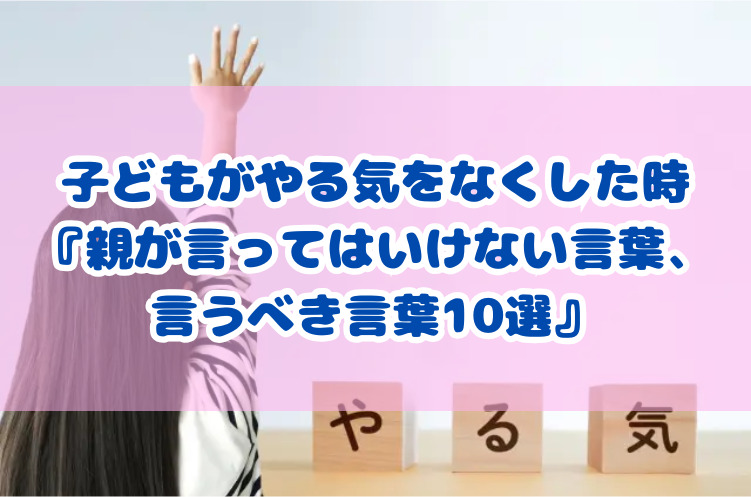子どものペースでOK!焦らず集団行動をサポートする親の姿勢
更新日: 2024.06.17
投稿日: 2024.06.14

幼稚園や保育園、小学校、そして習い事など、子どもは集団の中で育っていきます。
そんななか…
「友だちといるより、一人で遊んでいることの方が多い」
「集団行動が苦手」
「マイペースなわが子が心配」
など、わが子の集団行動に関して悩んでいる親は意外と多いもの。
今回は集団行動をサポートする際の親の考え方や姿勢について、考えてみましょう。
なぜ集団行動が必要なのか?

幼い頃は家族との関わりだけだった人間関係が、幼稚園や保育園から小学校と年齢が進むにつれて多くの人たちと交わり、集団での行動が増えていきます。
なぜ集団行動・集団生活は子どもの成長に必要だと考えられているのでしょうか。
・友だちや先生など、家族以外の人たちとの関係をつくる
・周囲の人たちに関心を持ち、思いやりを育む
・協調性や想像力、コミュニケーション力を身につける
・友だちや仲間と協力し合い、助け合う習慣をつける
・集団のルールを身につけて、チームワークを学ぶ
・集団のなかでの役割や責任を理解する
・他者からの刺激があり世界が広がる
では反対に、集団生活でのデメリットはどんなことがあるのでしょうか。
・自由に行動できない
・周囲の意見や行動が気になる
・なにか決めるのに時間がかかる
・自我や個性が育ちにくい
・自主的、自発的に行動しなくなり他人任せになる
などがあり、よい面もあれば悪い面もあることがわかります。
近年は、個性を活かして、自分の世界観を大切にする生き方が尊重されていますが、周囲と協調しながらコミュニケーション力を育み、社会性を養うことも大切です。
双方のバランスを上手に取れる子どもに育てていきたいですね。
何歳から集団行動ができるようになるのか?

人は何歳頃から集団行動ができるようになるのでしょうか。
ここでは幼児期〜学童期にかけての子どもの行動心理を見ていきましょう。
3歳までは集団行動よりも「一人遊び」が中心
少しずつ人とコミュニケーションが取れるようになるのが3歳です。
3歳くらいまでの子どもは、周囲に同年齢の子どもがいても関わり合わず、一人一人がそれぞれ好きな遊びをする「平行遊び」が多いでしょう。
集団行動をするには、気持ちを伝える「言語能力」と、相手を理解する「社会性」が必要になるため、3歳くらいまでは集団行動よりも一人遊びが中心になります。
4〜5歳くらいから友だちや仲間の意識が芽生える
4〜5歳くらいになると、「友だち」の存在を理解して、意思疎通ができるようになります。
まだまだ自我が強く、自分の気持ちを押し通してケンカになったり、物の取り合いになることもありますが、ルールのある遊びをしたり、子ども同士で役割を持ち始めるのもこの頃です。
4〜5歳の2年間で子どもの社会性は驚くほど発達し、「相手の気持ちを想像する」「譲る」「助ける」「共感する」などの内面的な成長も感じられます。
6〜7歳で集団生活・集団行動の基礎が身につき始める
幼稚園や保育園の年長〜小学校1年生くらいになると、社会的スキルのレベルがかなり上がってきます。
友だちと協力し合ったり、相手の意見を聞いたり、コミュニケーション力がついて集団行動の基礎が身に付く時期です。
まだまだ自己中心的な部分も多く、意見のぶつかり合いやケンカなどもありますが、少しずつ集団行動の際のルールや振るまい方が理解できるようになります。
子どもが「集団行動って苦手」と感じる理由は?

「子どもが集団生活に馴染めない…」「園や学校がつまらなそう」などの様子を見ると、親としては心配になりますね。
しかし集団行動に苦手意識がある子どもには、子どもなりの理由があるはずです。
どんな理由があるのか、みていきましょう。
○ 他人に合わせた行動が嫌
○ 周囲とのコミュニケーションが苦手
○ 周囲に興味が持てない
○ 集団行動の意味を理解していない
○ 自分の行動に自信が持てない
○ 感覚が鋭くて過敏
○ 不安感や緊張が強い
他人に合わせた行動が嫌
「自分のペースで行動したい」「作業や行動を途中で止められるのが嫌」など、マイペース傾向が強い子は、集団行動で自分のペースを乱されるのを嫌がるでしょう。
特に「早くしなさい」などと叱責されたり、友だちから心無い言葉をかけられて傷ついた経験があると、余計にその傾向が強くなるかもしれません。
好きなことに好きなだけ取り組む時間を家庭でつくり、学校や集団行動の時は周囲に合わせた行動が取れるように少しずつサポートしてあげられるといいですね。
周囲とのコミュニケーションが苦手
「引っ込み思案で人と話せない」「おとなしい性格で何も言えない」「自分勝手なことばかりを言って、周囲から浮いてしまう」など、人とのコミュニケーションが苦手な子も、集団生活や集団行動を嫌がる傾向があります。
失敗を重ねて、少しずつ身につけられるコミュニケーション力ですが、最初はうまくいかずに挫折してしまうことも…。
普段から大人が先回りせず、子どもに自分の気持ちを語らせてみたり、言葉で伝える練習をさせてみましょう。
意外に盲点なのが、友人関係ではなく先生との意思疎通がうまくいかないケース。気になることがあれば、先生も交えた話し合いなどを設けてみましょう。
周囲に興味が持てない
自分以外の人に興味が持てないと、集団行動が苦手になる傾向があります。
興味が持てないということは、「好き」「嫌い」といった感情を持つことができず、人との関わりが極端に少なくなってしまうかもしれません。
自分のことに集中でき、他人に惑わされずに生活できるというメリットもありますが、人は一人では生きていかれないので、親としては心配になりますね。
「○○くんもサッカーが好きらしいよ」「○○ちゃんの家の猫って面白いの」などと、日常的に友だちに関する話題を出して興味を持たせるようにしてみましょう。
集団行動の意味を理解していない
「どうしてみんなと一緒に行動しなきゃいけないの?」という基本的な疑問があると、自分一人の行動を取ってしまうかもしれません。
この場合は、集団行動がなぜ必要か納得できれば、すんなりと集団に溶け込めるかもしれません。
集団行動は協調性や社会性が養われるだけでなく、災害時に自分の身を守る役割などもあります。
子どもの意見をよく聞いたあとに、大人がその必要性を伝えてあげられるといいですね。
自分の行動に自信が持てない
子どもは社会的な経験や成功体験が少ないため、自分に自信が持てずに、集団での行動に気後れしてしまうことがあります。
集団のなかでは人との違いを比べてしまい、自信がないと周囲が気になりすぎてしまうかもしれません。
「人と違っても大丈夫」「そこがあなたのいいところね!」などと日常的に子どもを肯定し、強みを伝えて自信を持たせましょう。
感覚が鋭くて過敏
「大きな音が苦手」「光が気になり落ち着かない」など、感覚が鋭く、人がなんとも感じないようなことにも敏感に反応してしまう子どもは、集団行動ではストレスを感じやすくなります。
先生にその内容を伝えて対処してもらったり、道具を使って軽減するなど、対処方法を考えましょう。
周囲の友だちに理解を求めることも有効です。
不安感や緊張が強い
イベントや行事のみならず、日常的な学校生活にも不安がり、すぐに緊張してしまう子は集団行動にも尻込みしてしまうでしょう。
緊張してしまうと、普段は簡単にできることもできなくなり、その失敗が原因でまた緊張してしまうという負のスパイラルに…。
お守り代わりの文房具を持たせたり、仲良しのお友だちを一人見つけるなど、安心材料があるといいですね。
不安や緊張を訴える子どもは多いですが、年齢とともに緩和するケースが多いので、大人はゆったりした気持ちで見守ることも必要です。
集団行動ができるようになるまでのプロセスとは?

集団行動のポイントは、「集団の中で適切に行動できること」です。
子どもは少しずつ言葉を覚え、他者との遊びや感情のやり取りを通して社会性を身につけていきます。
その社会性こそが集団生活・集団行動の核となるものです。
子どもはどんなプロセスを経て社会性を身につけ、集団生活・集団行動に適応していくのでしょうか。
アメリカの発達心理学者パーテンによる「遊びの6分類」に沿って、集団行動へのプロセスを追ってみましょう。
①何もしない行動
「何もせずに見ているだけの状態。興味があっても行動には移さない」
ただぶらぶらと歩き回ったり、興味のある対象をただ見ているだけの状態です。
何もしていないように見えますが、本人はいろいろな刺激を受けて「遊び」に入る前の準備をしています。
②ひとり遊び
「近くに友だちがいても、興味を示さずに一人で遊ぶ。ほかの子と関わろうとはせず、自分の遊びに熱中する」
この一人で没頭して遊ぶことが、その後の仲間との遊びや集団生活に入っていくうえで重要だといわれます。
また保護者との愛着や信頼関係を築く時期でもあり、アイコンタクトを取ったり相手の表情を読んで、少しずつ言葉を蓄積していきます。
この言葉の習得は、その後のコミュニケーションや遊びに影響を与える大切なプロセスです。
③傍観者的行動
「友だちの遊びをただ眺める。話しかけたり、口出しすることはあるが、一緒に遊ぼうとはしない」
2歳〜3歳頃になると、このような行動が見られ、少しずつ「友だち」の存在が意識しはじめたという証です。
「友だちの遊び見る」ことが、その子にとって「遊び」になっているのかもしれません。
④ 平行遊び
「友だちの近くで遊ぶが、一緒に遊んだり関わり合うことはなく、独立し平行して遊んでいる状態」
平行遊びでは、友だちの近くで同じような遊びをします。
子ども自身は「お友だちと一緒に遊んでいる」という感覚は多少あるようですが、関わり合っている様子はありません。
⑤ 連合遊び
「子ども同士の意思疎通があり、道具の貸し借りができるようになる。同じ遊びをしているように見えて、それぞれが好きなことをしている状態。役割分担やリーダーシップを取る子はいない」
平行遊びからぐっと他社への関心が深まり、関わり合いが生まれますが、同時に意見のぶつかり合いや言い合いなどトラブルも増えます。
4〜5歳の子どもに多く見られる「遊びの段階」で、この頃から相手とコミュニケーションを取ったり、勝ち負けを意識したり、社会性が身についていきます。
この時期にたくさん「遊び」を経験しておくことで、その後の集団生活や集団行動への準備ができるでしょう。
⑥ 共同遊び
「役割分担があり、決まったルールのなかで一つの遊びを友だち同士で展開する。友だちと一緒に楽しみ、相互交渉など社会的行動を多く含んだ遊び」
遊びの中でルールを守り、譲り合ったり意見を主張しながら、集団行動に少しずつ慣れていきます。
この6つのプロセスは、①から⑥になるにつれて遊びが高度になりますが、発達過程を示しているものではなく、あくまでも遊びの種類として理解しましょう。
言葉や社会性の発達にともない、遊びの質や種類が変化していくと考えるといいでしょう。
親や周囲ができる集団行動のサポート

すぐに友だちもできて、先生とも物怖じせず話せる子を見ると、「なぜあんなふうにできないのかしら」「うちの子、大丈夫?」と不安になってしまいます。
しかし大人にとっては当たり前の集団行動も、初めて体験する子どもにとってはわからないことや難しいことばかり。
子どもに苦手そうな様子が見られたら、大人が少しだけサポートしてみましょう。
子どもの気持ちを聞き出す
まずは子どもが「集団の中に入っていきたい」「園や学校で友だちとうまく関係をつくりたい」と思っているのかを確認しましょう。
まだ他人に興味がなく、自分の遊びや勉強に集中したいのであれば、無理に集団に馴染ませる必要はないかもしれません。
家族の時間をたくさん作り、愛着をたっぷり感じて家族内での関係に満足すると、少しずつ社会的な活動を始めたくなります。
特に集団行動に対して興味を持てないのであれば、「今はまだ力を蓄えている時期」と考えて、ゆっくり見守りましょう。
小さな橋渡し役をする
他者への興味が少しずつわき、友だちや学校(園)の話が話題に出てくるようなったら、「集団生活・集団行動で友だちと仲良くやりたい」と思っているのかもしれません。
なかなか自分から積極的に動けないようなら、公園や親子ひろばなどで一緒に話しかけたり、遊びが交わるようにサポートしてもいいでしょう。
「あの子、面白い遊びをしてるね」「一緒に遊んでもいい?」「すごいね、これ作ったの?」などと、やりとりの最初の一歩を大人が橋渡しするとスムーズに。
大人のようにずっと話を続けなくても、子どもは横にいて別の遊びをしていても「一緒に遊んでいる」という感覚を持つものです。
家に帰ってから「今日はお友だちと遊んで楽しかったね」「上手に遊べたね」と言葉がけすると、「また遊びたい」「友だちと遊ぶと楽しい」という成功体験として印象づけができますね。
得意なことから集団へ
自分の苦手なことで「集団行動」をさせられると、「集団=嫌い」というイメージが定着してしまいます。
例えば運動が好きならスポーツの習い事やイベント、工作が好きなら工作教室やワークショップなど、好きなこと・得意な分野から集団行動を始めると楽しくスタートが切れるでしょう。
普段から子どもの「好き」「得意」を増やしておくと、どんな場面でも苦手意識なく集団に入っていかれるかもしれませんね。
言葉で表現する習慣づけ
家族内では以心伝心で、言葉を使わなくても「なんとなく伝わる」「言われなくてもわかる」ことが多いですね。
しかし他人の集まりである集団の中に入れば、そうはいきません。
集団行動で子どもが困らないためにも、あえて大人が子どもの気持ちを察したり、先回りすることはやめましょう。
「お腹がすいた」「外に遊びに行きたい」など、自分がどうしたいか、どんな気持ちかを子どもが言葉で語る習慣をつけます。
そこで大人が「じゃあオヤツにしよう」「宿題が終わったら公園に行こう」などと動くのを見て、自分から言葉で発信すれば事態が変化することを学べます。
言葉によるコミュニケーションが当たり前になると、集団の中でも発言することが苦にならなくなり、周囲との関係性に変化が生まれるでしょう。
周囲が躍起になって「友だちと遊ぶのは楽しい」「集団行動をできるようにならなければ」と子どもを追い立てても、事態は好転しません。
特に「集団行動に苦手意識がある子」にとっては、マイナスなイメージが先行しているのでので、「もっと友だちと仲良くしなさい」「どうしてできないの!」などと叱ってしまうと、さらに集団行動に対して萎縮し緊張してしまいます。
親や周囲の大人はじっくりと子どものペースを見守りながら、なぜ集団行動をするのか、友だちと交流する楽しさ、将来につながる意義などをさりげなく伝えていきたいですね。
・集団行動には「協調性やコミュニケーション力がつく」「仲間意識ができる」「ルールを覚える」などのメリットもあるが、自由度が低く自我や個性が育ちにくいというデメリットもある。
・友だちの存在を認識し始めるのが4〜5歳頃、集団行動ができるようになるのは6〜7歳頃から。
・集団行動が苦手なの子は、「他人に合わせた行動が苦手」「周囲に興味がない」などの特徴がある。
・大人は焦らず、子どもの発達を見ながら少しずつ集団に慣れさせることが大切。
(参考文献)
・CONOBAS | 集団行動が苦手? 子どもの発達心理と親ができる「遊び」のサポート
・ママソレ | 集団行動が苦手な子ども。親ができるサポートとは?
・LITALICO | 集団行動が苦手な子どもの特徴や対応方法を解説します
・ほいくふぁん | 遊びの分類を覚えよう【パーテンの遊びの分類を解説】
・Gakken | 子どもの社会性をはぐくむために いつからどんなサポートをすればよい?
・KIDS LABORATORY | 【年齢別】遊びの発達段階をわかりやすく解説!子どもの成長で遊びはどう変わる?