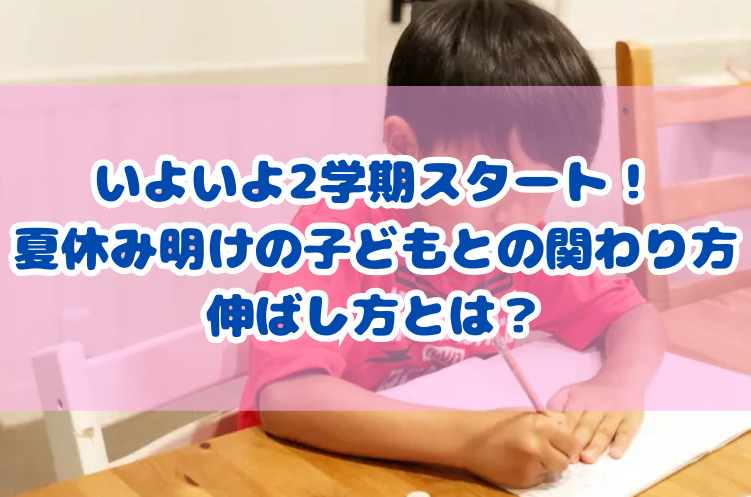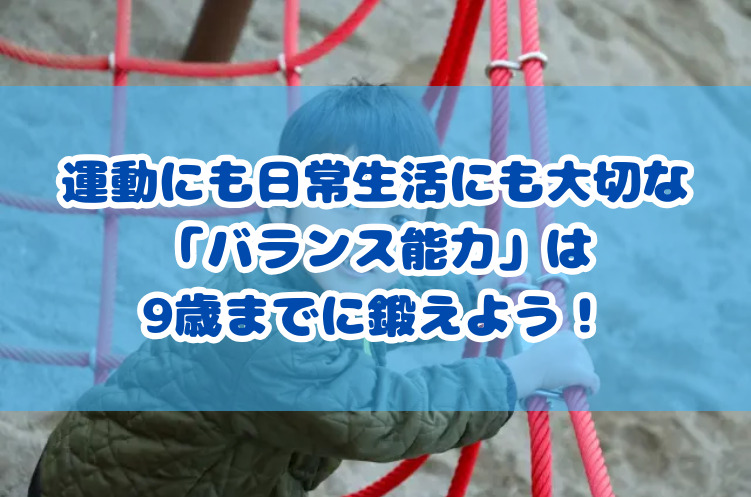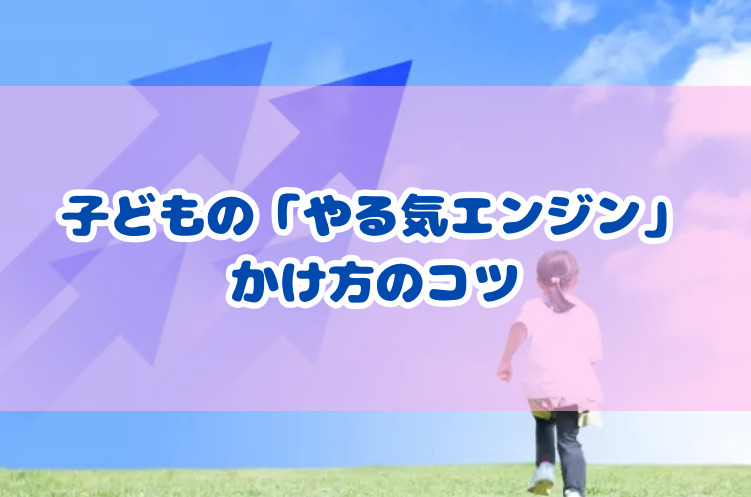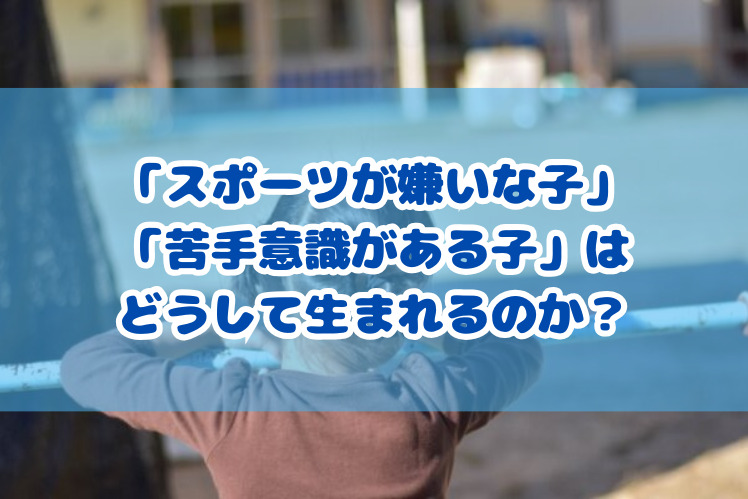「なわとび」で運動能力がアップ!園・学校で活躍するための練習法
投稿日: 2025.11.11
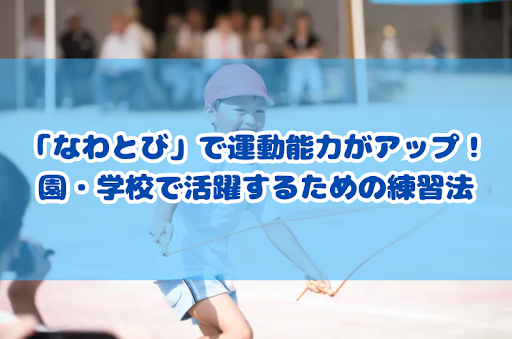
「体育でなわとびが始まると、うちの子はちょっと苦手そう……」と感じていませんか?
なわとびは、全身運動として優れているだけでなく、リズム感や集中力を育む素晴らしい運動です。
そして何より、新しい技ができるようになった時の達成感は、子どもの自信を大きく育みます。
この記事では、なわとびが持つ魅力や心身への効果を紹介するとともに、「うまく跳べない」を「得意!」に変える具体的で楽しい練習方法を解説します。
親子で楽しみながら取り組んで、なわとびがの練習時間がワクワクに変わるようサポートしましょう!
もくじ
子どもの体と心、両方を育む!なわとびの効果

冬になると、園庭や校庭に「いち、に、さん!」と元気な声が響きます。
寒い季節でも体を温めながら楽しめる運動として、なわとびは昔から子どもたちに人気です。
でも実は、なわとびは「遊び」を超えた全身トレーニングでもあります。
なわとびの動きには、体にうれしい効果がたくさんあります。
以下、なわとびの効果を紹介します。
⚫️跳ぶたびに全身の筋肉がリズミカルに使われ、特にふくらはぎや太もも、体幹が強くなる。
⚫️一定のリズムで跳び続けることで、持久力・心肺機能が自然に鍛えられ、リズム感が養われる。
⚫️着地の刺激が骨に伝わり、骨密度の発達を助ける(成長期の子どもに特に効果的)。
⚫️両手・両足・目の動きを同時に使うことで、脳の連動性(運動神経の統合力)が高まる。
⚫️なわとびや外遊びで運動をした後は、ドーパミン分泌量が上がり集中力が高まる。
つまり、なわとびは「小さな全身運動」。
短い時間でも、ジョギングやリズム運動に匹敵するほどの運動効果があるのです。
さらに、なわとびが持つ魅力は、“できるようになる達成感”を味わえることにあります。
最初はなわに引っかかっても、何度も挑戦するうちに1回、3回、10回と回数が増えていく。
その「努力が形になる体験」は、子どもたちにとって何よりの自信になります。
園や学校では、友達と一緒に跳ぶ「長なわ」もよく行われます。
お互いのリズムを合わせたり、失敗しても励まし合ったりする中で、協調性や思いやりの心も育ちます。
体と心の両方を育ててくれる、それがなわとびという運動の大きな魅力です。
なわとび上達のコツと楽しい練習法
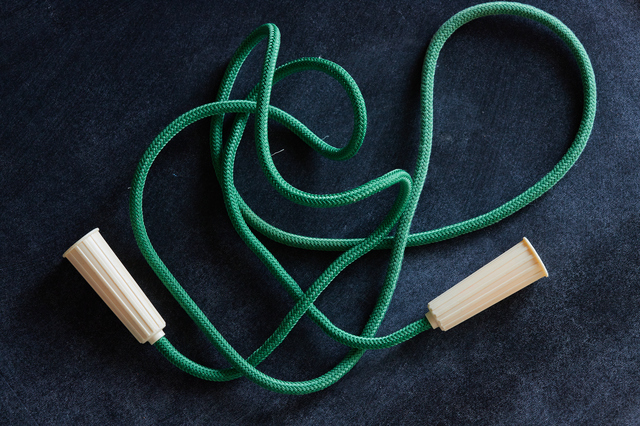
なわとびを上達させるには、フォーム・リズム・継続の3つがポイントです。
まずは、前回し跳びから。
コツをつかむと、軽やかに跳べるようになります。
ステップ1:なわと姿勢をチェック
子どもにとって、なわの長さは重要です。
また、姿勢が崩れると、うまく跳べないだけでなく、体への負担もかかります。
まずは“正しいなわの長さ”“正しいフォーム”を身につけることから始めましょう。
•縄の長さ:足で踏んで、持ち手が胸の高さにくる長さが理想。
•姿勢:背筋を伸ばし、軽くひざを曲げる。視線は地面ではなくまっすぐ前を。
•腕の位置:体の横でコンパクトに。大きく回さず、手首でコントロール。
姿勢が崩れると、うまく跳べないだけでなく、体への負担もかかります。
まずは“正しいフォーム”を身につけることから始めましょう。
ステップ2:手首のスナップを意識する

なわを「腕全体」で回すと疲れてしまいます。
手首の小さな動きで軽く回すことがコツ。
最初は縄を後ろから前に1回回して、足の前で止める練習から始めましょう。
この感覚をつかむと、連続跳びが一気に安定します。
グリップの持ち方も大切になってきます。
小さな子どもは手のひら全体でギュッとグーで握りやすいですが、リモコンを持つように人差し指を前にして指で軽くにぎります。
手に力が入ると腕や肩全体にも力が入り、縄を回す動作がスムーズにいかなくなります。
指で軽く握って力加減を調整できるとうまく跳べるようになります。
ステップ3:リズムジャンプで感覚をつかむ
なわを持たずに「その場ジャンプ」をしてリズムを練習します。
テンポのいい音楽に合わせて跳ぶのもおすすめ。
つま先で軽く弾むように跳び、かかとは床につけないようにしましょう。
これだけでも心拍数が上がり、ウォーミングアップに最適です。
ステップ4:1回→3回→10回!少しずつ増やそう
実際になわを持ってチャレンジ。
最初は縄を跳ぶ瞬間のコツがわからない子どもたちが多いため、前に回して縄を跳ぶ瞬間に、大人が「はい!」と声をかけてあげるとコツをつかみやすいでしょう。
1回成功したら、それだけで立派な成長です。
すぐに連続跳びを目指さず、「昨日より1回多く跳ぶ」ことを目標にすると続けやすくなります。
記録カードを作って回数を書いたり、動画で成長を振り返ったりするのも効果的です。
ステップ5:技にチャレンジしてみよう!
基本の前跳びが安定したら、少しずつ新しい技にも挑戦してみましょう。
•後ろとび:縄を後ろから回します。リズムを少し遅めにしましょう。
•走りとび:走るように、片足ずつ交互に跳びます。
ステップを変えることで足の協調性を高める練習になります。
•片足とび:片方の足で連続して跳びます。バランス感覚や、片足でのジャンプ力を鍛えるのに役立ちます。

•二重とび
1回のジャンプで縄を2回回します。
縄を回すスピードも速くする必要があるため、手首の使い方を習得する練習にもなります。
•あやとび
縄を交差させて跳びます。
手の動きが前回し跳びとは異なるため、腕の動きと足のジャンプのタイミングを合わせる練習になります。
どの技から始めるかは、子どもの体力や興味関心に合わせて。
焦らず、少しずつステップアップしていくことが上達のコツです。
今日から試せる! 親子で楽しむなわとび練習法

なわとびは、続けるほど上達します。
そのために大切なのが、保護者の温かい声かけです。
上手に跳べたときはもちろん、うまくいかなかった時こそチャンス。
「惜しい!」「今のリズム、すごくよかったよ!」
「昨日より縄が高く回せてるね!」
そんな言葉が、子どものモチベーションを支えます。
また、「失敗してもいいよ」という安心感があると、挑戦意欲がぐんと高まります。
親子で一緒に練習することで、「運動=楽しい時間」として定着していくでしょう。
ここでは、家庭でできる応援の工夫について紹介します。
短時間でOK!「毎日コツコツ」が最強の上達法
練習は、長く続けることよりも集中力と継続が大切。
「遊びの延長」のように1日10分程度でも、練習場所や時間をルーティン化し「今日は5回跳べればOK」などと心理的ハードルを低く設定することからスタートしましょう。
「できた!」で終われるように意識しながら毎日少しずつ取り組むのが効果的です。
「見える記録」で達成感を積み重ねる
頑張りを記録して「見える化」することで、子どもの努力が報われ自己肯定感が育まれます。
カレンダーやノートに跳べた回数や新しくできた技を親子で一緒に書き込み、記録を振り返りながら「先週より5回も増えたね!」など努力の過程を具体的にほめることが、モチベーションの維持につながります。
親も「一緒にチャレンジ」でやる気を引き出す
親が楽しそうに取り組む姿を見せることは、子どもの最高の見本となり意欲を自然と引き出します。
親が苦手な技に挑戦したりリズムよく跳んだりする姿を見せたり、「どちらが長く跳べるか競争!」といった遊び要素を取り入れたりしながら一緒に楽しみましょう。
成果を共有してモチベーションアップ
自分の成果を誰かに認めてもらうことは大きなやる気の原動力となります。
おじいちゃんやおばあちゃんに動画で送る、週末に公園でパパにお披露目するなど誰かに見せる機会を意識的に作り、成功体験を共有しつつ「一生懸命練習したから跳べるようになったね」と努力と成果を結びつけて言語化しましょう。
練習を習慣化するためには、「やらされている」ではなく「やりたい!」という気持ちが不可欠です。
なわとびをゲームや遊びに変えることで、飽きずに楽しく続けられるアイデアをご紹介します。
•30秒チャレンジ:「30秒で何回跳べるか」をタイム計測!
•親子リレー跳び:親が回して子どもが跳ぶ→交代してみよう。
•音楽なわとび:好きな曲に合わせて跳ぶと気分が上がる。
子どもの挑戦を心から楽しもう
なわとびは、手軽でありながら奥が深い運動です。
体の発達・運動神経の育成・心の成長——そのすべてを支える“万能スポーツ”。
上手に跳べるようになることも素晴らしいですが、
何より大切なのは、「挑戦を楽しむ心」を育てること。
親子で笑い合いながらなわを回す時間は、体だけでなく心も温めてくれる時間です。
この冬、ぜひご家庭でも「なわとびタイム」を取り入れてみてください。
・なわとびは、子どもにとって心身の成長につながる「教具」。
・姿勢やなわの持ち方から順番に覚えていくことが大切。
・慣れてきたらどんどん挑戦する。
・親子で楽しく遊びながら学ぶことが、上達の近道。
参考文献)
「小学生でマスターしたい、縄跳びの飛び方の基本5種類」(出典:ドリームコーチング)
「縄跳びができない!?子どもに苦手意識を持たせない練習方法」(出典:JPCスポーツ教室)
「縄跳びの教え方は手順がポイント!苦手な子でも跳べるようになるコツとは?」(出典:スポットライト)
「【簡単】なわとび(縄跳び)のコツは5つ!上達するための練習方法も」(出典:スポスル)