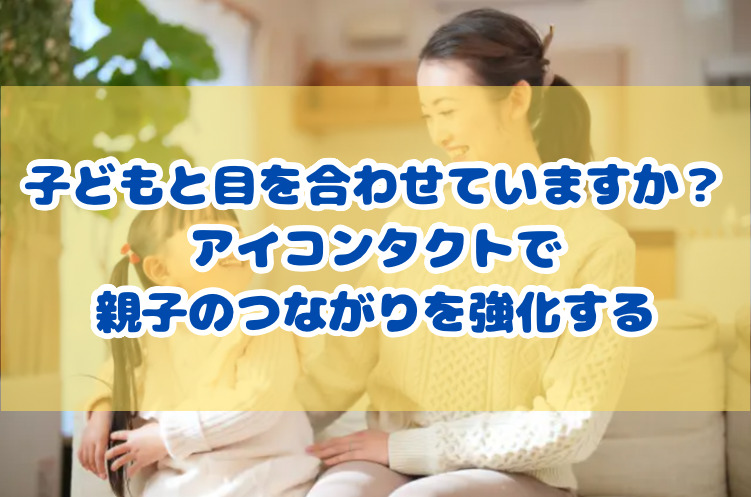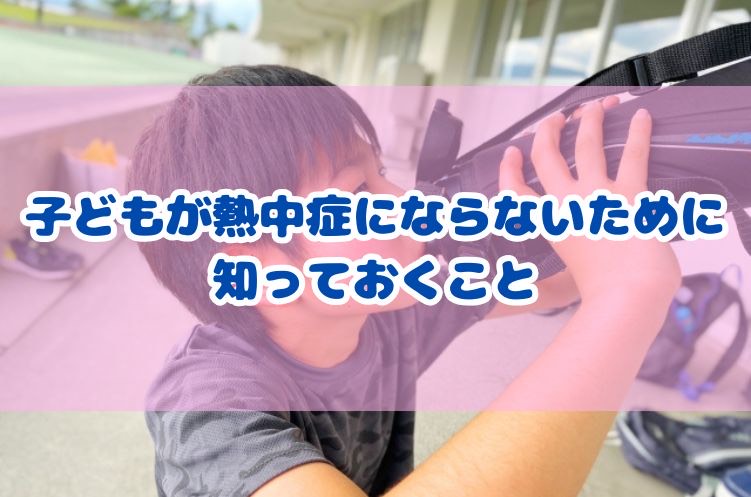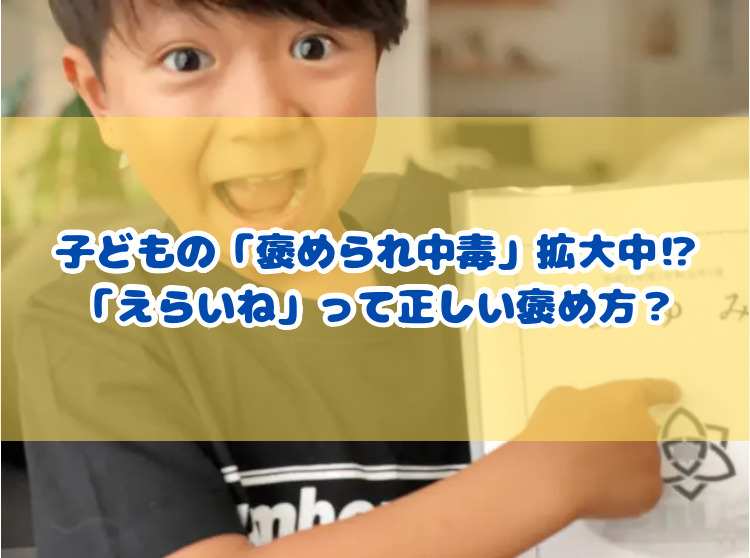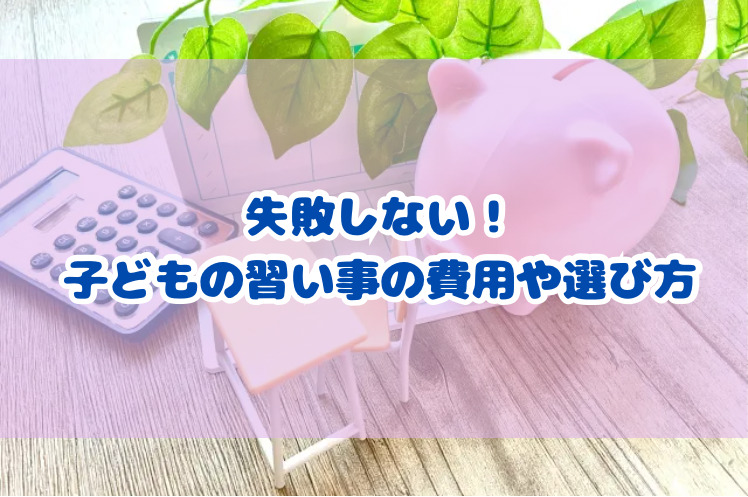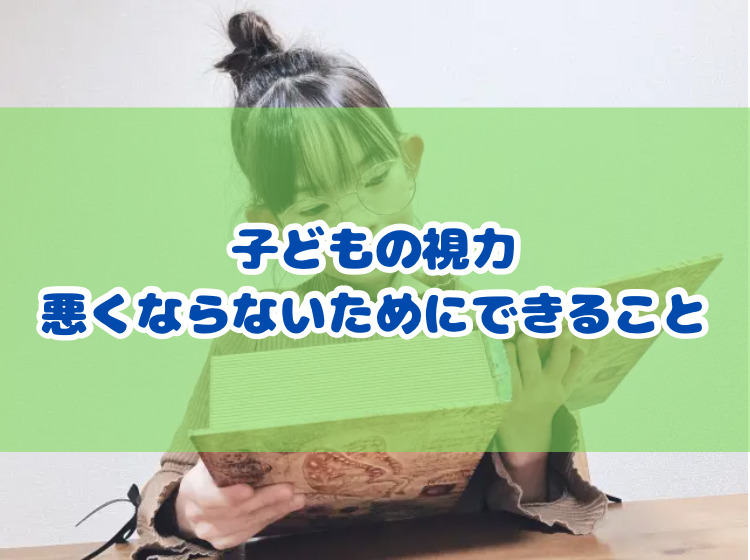実は「隠れ便秘」かも?子どもの便秘に悩むママ必見の便秘解消法とは
投稿日: 2025.11.04
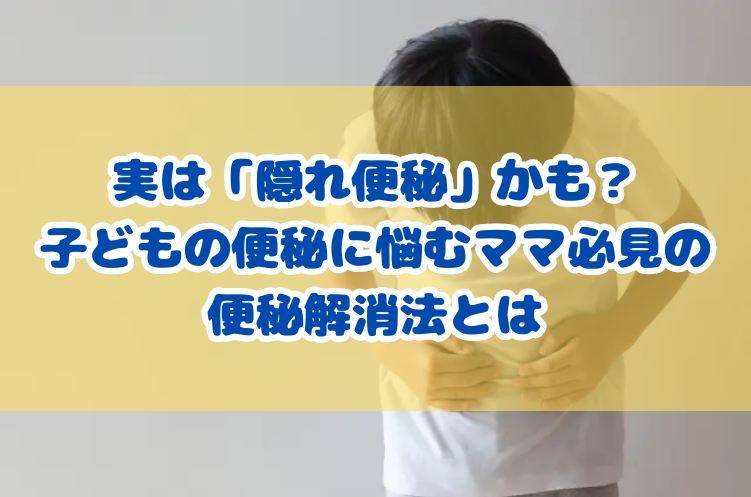
「うちの子、最近お腹のあたりがポッコリしている気がする」「うんちが出るのに時間がかかって苦しそう…」そんな心配をしている保護者の方は多いのではないでしょうか。
実は、子どもの便秘は珍しいことではありません。成長とともに食事内容や生活リズムが変わり、学校や園での環境にも影響を受けやすい時期だからこそ、起こりやすいのです。
放っておくと、お腹の痛みだけでなく、食欲不振や集中力の低下など、日常生活にも影響が出てしまうことがあります。
しかし、日々の暮らしを見直し、少し意識を変えるだけで、ぐんと改善できることが多いもの。
この記事では、子どもの便秘の現状や原因、家庭でできる具体的な解消法などをわかりやすく紹介します。
子どもの便秘の割合、意外と多い?

「子どもは元気だし、食べて動いていれば大丈夫」と思われがちですが、NPO法人日本トイレ研究所が小学生の排便と生活習慣に関する調査を行ったところ、便秘状態であった児童は約2割と報告されています。
幼児期は、排便の時に特に痛い思いをすると、排便を我慢してしまい、便秘につながるケースが多いようです。小学校に入って環境が変わる時期も、学校でトイレに行くことをためらい、便秘状態になることもあります。このほか、腸や肛門の病気などが原因で便秘になることもあります。
毎日排便があっても、「コロコロしたうんちが続く」「出すときに痛がる」「残っている感じがある」などの症状がある場合は、“隠れ便秘”の可能性があります。
「うちの子は毎日うんちが出ているから大丈夫」と思っていても、実は、スッキリ出し切れていないケースも少なくありません。
便秘が続くと、お腹が張って食欲が落ちたり、イライラしやすくなったりすることもあります。子どもの小さなサインを見逃さず、日々の様子を観察することが大切です。
子どもの便秘とは?こんな症状があると便秘かも?

そもそも、子どもの便秘とはどんな状態を表すのでしょうか。
子どもの便秘は、単に「数日うんちが出ない」だけではありません。
小学生ぐらいの子どもの場合、排便は、1日に1回から3日に2回ほどが目安です。
次のような様子が見られたら、便秘を疑ってみましょう。
・便が硬く、出すときに痛がる。
・便の形がコロコロしている。
・お腹が張っている、さわると嫌がる。
・食欲がない、機嫌が悪い。
・トイレに行くのを嫌がる、我慢する。
特に「出すと痛い」という経験があると、子どもは「うんちは怖い」「トイレはイヤ」と感じてしまい、我慢するようになります。
すると腸の動きがさらに悪くなり、便が硬くなってまた痛い——という悪循環に陥ってしまうこともあります。
便秘は、子どもの心と体の両方に影響する不調なのです。
便秘の原因とは?

便秘は「病気」というよりも、「生活習慣に注意!」のサインと言えます。
以下、便秘の原因について、詳しく解説します。
運動不足
最近は外遊びの時間が減り、室内で過ごす子どもが増えています。
体を動かす機会が減ると、腸のぜん動運動(便を押し出す動き)が鈍くなり、便が腸内にとどまりやすくなります。
また、同じ姿勢で長時間座り続ける習慣も、腸の働きを弱める原因のひとつと考えられています。
水分不足
便秘の原因として見落とされがちなのが、水分不足です。
水分が足りないと便が硬くなり、排便時に痛みを感じやすくなります。特に、汗をかきやすい季節や乾燥する冬は要注意です。
食生活
朝ごはんを抜くといった食生活の乱れも、便秘の大きな原因です。
朝食を食べることで胃腸が刺激され、自然と「うんちしたい」という反応が起こるのですが、朝にバタバタして時間がないと、このリズムが作れません。
また、食物繊維は便の量を増やし、水分は便を柔らかくして排便をスムーズにする働きがありますが、現代は加工食品が多く、食物繊維の摂取量が不足しがちです。
これが便秘の原因となることもあります。
さらに、食事量が少ないと便の量も減り、便秘になりやすくなります。
ストレス
腸はとてもデリケートな臓器で、私たちのちょっとした感情の動きにも大きく影響されます。
これは腸の働きが、自律神経に支配されているからです。
自律神経は、感情と密接に結びついています。「入園、入学など環境が変わった」「友達関係がうまくいかない」などのストレスにより自律神経が乱れると腸の働きも乱れ、便秘につながることもあります。
トイレ環境
家庭では洋式便座が普及していますが、学校によっては腰を浮かせてする和式のことも。
和式トイレに慣れていない子どもたちにとっては、中腰を保つだけでも体力を消費するため、ますます出しにくくなってしまいす。
しかも、恥ずかしいという羞恥心も生まれ、ついつい排便をガマンし便秘がちになってしまうことがあります。
便秘に効く食べ物や飲み物

便秘を防ぐには、毎日の食事がとても大切です。
腸を元気にする食べ物を、無理なく生活に取り入れましょう。
ここでは、便秘に効く食べ物や飲み物を紹介します。
食物繊維を多く含む食品
食物繊維には、便のかさを増やしてスムーズに出す「不溶性食物繊維」と、腸内で水分を含んで柔らかくする「水溶性食物繊維」があります。
どちらもバランスよくとることがポイントです。
⚫️野菜:かぼちゃ、ごぼうなど根菜、芋類、ブロッコリーなど
⚫️果物:りんご、バナナ、ブルーベリーなど
⚫️海藻類:わかめ、ひじき、寒天など
⚫️穀物:玄米、オートミール、全粒粉パンなど
腸内環境を整える発酵食品
・納豆
・味噌汁
・チーズ
これらの発酵食品には乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌などの善玉菌が含まれ、積極的に摂取することで腸内環境を整え便秘解消に役立つと言われています。
ただし、すべての人に効果があるわけではなく、体質に合うか合わないか個人差があります。
オイル類
オリーブオイル、ごま油、エゴマ油、ココナッツオイルなどのオイル類もおすすめ。
オイルに含まれる成分が腸を刺激して動きを活発にし、排便を促すと考えられています。
炒め物などに使うのはもちろん、パンにつける、サラダやスープにかけるなどして取り入れてみましょう。
飲み物も大切
・りんごジュース、プルーンジュース
・温かいスープやお味噌汁
冷たい飲み物は腸の動きを鈍らせてしまうことがあるので、できるだけ常温または温かい飲み物を。
「朝はお味噌汁で体を温める」「外遊びの後はお水をコップ一杯」など、習慣づけが大切です
親子でできる便秘に効く解消法

便秘薬に頼る前に、まずは日常の工夫から。
難しい方法ではなく、「楽しい」から続けられることが便秘解消の近道です。
ここでは、日々の生活の中で親子の絆を深めながら、子どものお腹の調子を整える効果的な方法を紹介します。
運動で腸を元気に
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、心と体の両方の調子に深く関わっています。
軽い運動でも、腸のぜん動を促す効果があります。
おすすめは、なわとび、鬼ごっこ、かけっこ、フラフープ、ラジオ体操など。
毎日10〜15分でも続けることで、体の中からポカポカしてきます。
お腹のマッサージ
おへそのまわりを「の」の字に沿って時計回りに優しくさするマッサージは、滞りがちな腸の動きを促し、1回5分程度で便秘解消をサポートします。
入浴後など体が温まっているリラックスタイムに行うことで、手のぬくもりが子どもへの安心感とリラックス効果を高め、より排便しやすい状態へと導きます。
排便しやすい体勢をつくる
洋式トイレの場合、子どもがまだ小さく足がぶらぶらしていると、お腹に力が入りにくく排便しづらくなるため、足元に踏み台を用意しましょう。
足がしっかりと台につき、ひざが股関節より少し高くなる姿勢になることで、自然にいきみやすくなります。
ツボ押しでサポート
おへそから指3本分外側のあたりにある「天枢(てんすう)」というツボを、やさしく押してあげましょう。
お風呂上がりや寝る前のリラックスタイムに3秒押して3秒休む、を数回繰り返します。
強く押さず、軽くトントンと刺激する程度でOKです。
毎日のルーティンで排便習慣をつくる
「排便したい」というサインを逃さないこと、そして「リラックスして出す」習慣をつくることが大切です。
胃に食べ物が入ると、腸が活発に動く「胃結腸反射(いけっちょうはんしゃ)」が起こります。
そのため、朝食後30分以内が最も便意を感じやすい時間帯です。
忙しい朝でも、この時間にゆったりとトイレに座る時間を設けましょう。
心と体の緊張を解くサポートが大切

子どもの便秘は、「食べる・動く・出す」という大切な生活習慣のバランスが崩れたサインですが、難しく考えず、日々のちょっとした工夫で改善に向かうことがほとんどです。
具体的な習慣として、腸に優しい食物繊維や発酵食品を取り入れ、水やお茶で水分をしっかり補い、腸の動きが活発になる朝食後にトイレタイムをつくり、親子で運動や優しくお腹のマッサージを行い、トイレを安心できる空間に整えるといった対策を講じましょう。
何よりも大切なのは、「出なくても大丈夫だよ」と子どものペースに寄り添い、心と体の緊張を解きほぐすことです。ただし、
・強い腹痛や嘔吐を伴う。
・血便がある。
などの症状がある場合は、便秘以外の病気が隠れているかもしれません。
自己判断せずに必ずかかりつけの小児科を受診してください。
焦らず、体と心の両面からサポートを続けることで、体の中がスッキリ整い、我が子の笑顔はぐんと増えるでしょう。
・子どもの便秘は珍しいことではないことを知っておこう。
・便秘解消のために、まずは日々の食生活を見直そう。
・便秘に効く生活習慣を取り入れ、体と心両面からサポートすることが大切。
参考文献)
「子どもの便秘予防、便秘解消のために!腸活をはじめよう」(出典:KUMON)
「意外と知らない⁈こどもが便秘になる原因」(出典:イーベン)
「小学生の間でも増加中!?親子で取り組む子どもの便秘解消術」(出典:大正製薬)
「子どもが便秘のときにおすすめの食べ物は?」(出典:キッズドクターマガジン)
「子どもの便秘」(出典:山と空こどもアレルギークリニック)