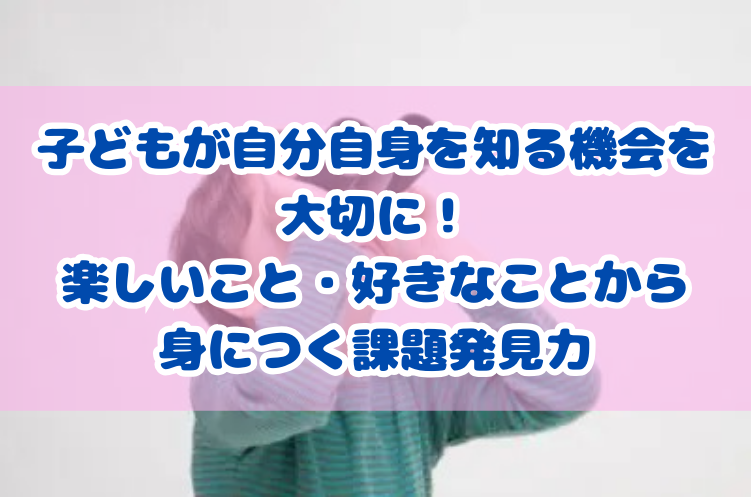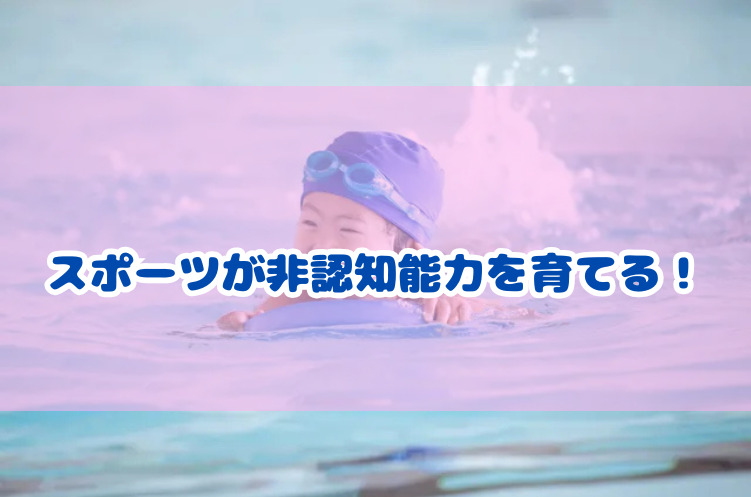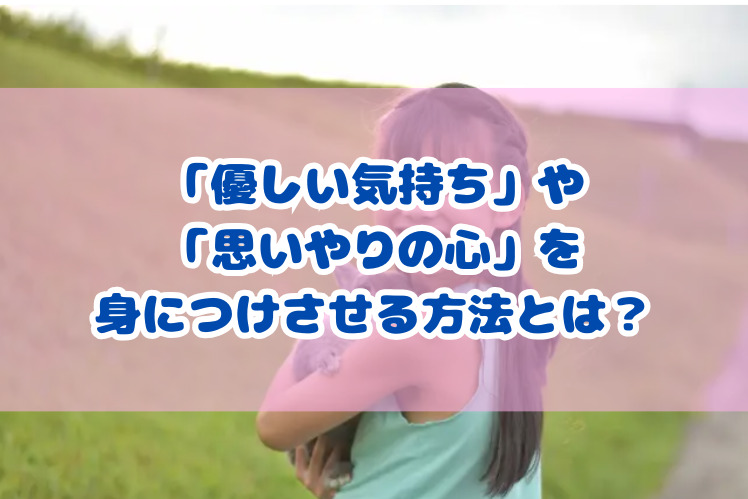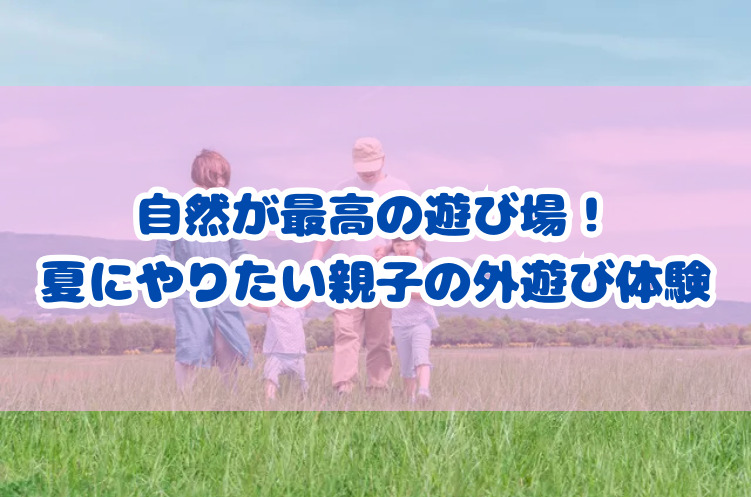学校でも将来の仕事でも役立つ! 子どもの「キャプテンシー」を育てよう
更新日: 2025.10.08
投稿日: 2025.10.06
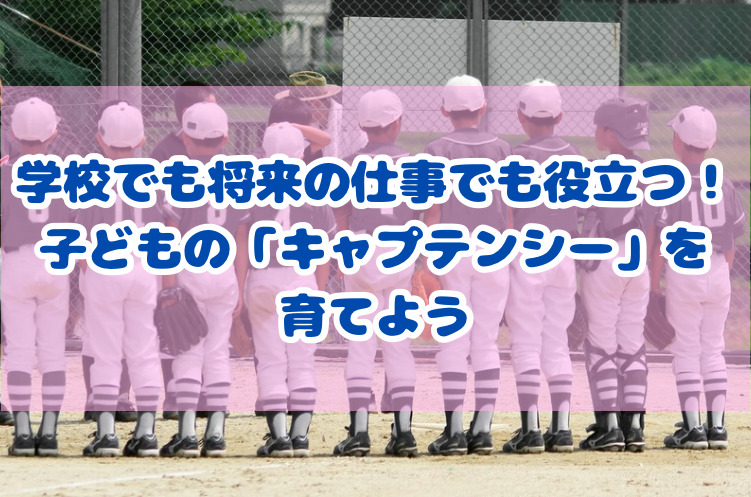
子どもがキャプテンや主将になると、「うちの子にできるの?」「大丈夫かしら」と心配になりますね。
しかしチームの代表、リーダーに任命された後は、「子どもが変わった」「チームのことを考えるようになった」とよい変化を感じる親が多くいます。
キャプテンや主将になると大変なことも多い反面、苦労を乗り越えて子どもは大きく成長します。
そこで身につくのは、これからの人生に役立つ大切な非認知能力。
子どものキャプテンシーとはなにか、そしてキャプテンシーの育て方を考えいきましょう。
キャプテンシーとはなにか

キャプテンシーとは、チームのキャプテンや主将など、代表者に求められる「チームをまとめる力」「集団を統率していく力」のこと。
元気がないメンバーに声をかけたり、仲間の気持ちを代弁してコーチに伝えたり、チーム全体がよい雰囲気になるような行動が必要になってきます。
キャプテンの仕事としては、
・試合の先攻後攻を決めるじゃんけん
・積極的な声かけ
・練習準備などをリードする
・チームメンバーをまとめる
などがありますが、所属するチームによって役割は変わってくるでしょう。
これを見ると、「うちの子には無理かも」と思うかもしれませんが、キャプテンとしての振る舞いや考え方は、なってみてから少しずつ育つものです。
また「キャプテンとはこうあるべき」というきまりもありません。
ラグビー日本代表のキャプテンを務めた廣瀬俊朗さんも、インタビューのなかでキャプテンに任命された際の気持ちを語っています。
このように「その子の考えるキャプテン像」になっていくことが大切なようです。
大人が考える「キャプテン」「主将」のイメージを一旦脇に置き、一緒にキャプテンについて考えるところから始めてみませんか。
キーワードは「一生懸命さ」

ある研究によると、キャプテンに求められる資質は、① 仲間や監督からの信頼を得られる、② 一生懸命さ、③ 目標を持っていること、というアンケート結果があるそうです。
特に②は泥臭い言葉のように感じるかもしれませんが、懸命にキャプテンの役割を果たそうとする姿を見て、それが①の「信頼」につながると言っていいでしょう。
また③の「目標」も、チームとして「何を目指すか」「そのためには何をすべきか」をしっかりと考え、それをメンバーたちと共有することが大切です。
これもチームの目標に対して真摯に考え、行動する「一生懸命さ」です。
つまりキャプテンシーのキーワードは「一生懸命さ」。
この一生懸命に取り組む気持ちがあれば、キャプテンとしての素質は十分ということです。
過剰に「チームのために献身的にならなくては…」「自分を犠牲にして行動しよう」と思う必要はありません。
子どもが「スポーツを楽しむ」という最優先すべき気持ちを、置き去りにしないようにしましょう。
(高知工科大学経済・マネジメント学群の「大学スポーツにおけるキャプテンの役割と在り方とは」)
リーダーシップとキャプテンシーの違いとは

少し似ているように感じる「リーダーシップ」と「キャプテンシー」。
リーダーは特に任命されるものではなく、チームの方向性を示したり、メンバーを引っ張っていくイメージ。
一方、キャプテンや主将はコーチや監督などから任命されるもので、ある意味「役職」です。
キャプテンはチーム全体の調整を行ったり、チームをまとめる役割を担っています。
キャプテンを経験することで身につく非認知能力

大変なこともある一方、その役を担った後は劇的に成長することも多い「キャプテン」「主将」という役割。
キャプテンを経験することで、子どもにはどんな非認知能力が身につくのでしょうか。
○ 責任感
○ コミュニケーション力・調整力
○ 忍耐力・感情のコントロール
○ 課題発見力・問題解決力
○ 協調性・思いやり
○ 失敗から起き上がる力・レジリエンス
○ 時間管理能力
責任感
練習や試合前後の挨拶、チームへの声かけなど、キャプテンや主将になるとチームの代表者としての仕事が増えます。
最初は言われてから動くことが多いかもしれませんが、次第にキャプテンらしさが板につきはじめ、言動が変化していくでしょう。
「役割が人をつくる」といわれるように、与えられた役割にふさわしい行動をしようと努力するため、子どもは劇的に進歩していきます。
「キャプテンとしてふさわしい行動をしよう」という思いが、子どもの責任感を育むのです。
この責任感は中学・高校と進学した際にも、社会人として仕事を始めた後もとても役立つ能力です。
コミュニケーション力・調整力
キャプテンになるとチームをよくするために、メンバーの意見を聞いたり、それをコーチや監督に伝えたりと、チーム内の情報共有をする場面が増えるでしょう。
話が苦手な子でも、積極的なコミュニケーションが求められ、声を出す機会が増えるため、必然的にコミュニケーション力がアップするはずです。
また様々な立場の人と話すことも増えるので、調整力も磨かれます。
このコミュニケーション力は小さいうちから身につけておくと、生涯に渡って自分を支えてくれる力になるでしょう。
忍耐力・感情のコントロール
キャプテンになると、これまでの立場から一段ステップアップすることになります。
これまで横並びで仲良くしてきた仲間と、壁を感じることもあるかもしれません。
思い通りにならない時も、言い訳をしたくなる時も、感情を爆発させずに、気持ちをコントロールする術を自然と身につけるでしょう。
「頭にきたら、1・2・3と数を数える」「3回大きく深呼吸」など、感情をコントロールする方法を身につけるよい機会でもあります。
課題発見力・問題解決力
なかなか試合に勝てない時、チームの雰囲気があまりよくない時、「どうしたらいいかな」「何が問題なのだろう」と、キャプテンなら原因を探り、考えるでしょう。
そしてその問題を解決するために、試行錯誤をして取り組むはずです。
その問題を発見する力と、解決するために地道に動く行動力が、その後の子どもの力になります。
協調性・思いやり
子どものスポーツチームといえども、様々な個性の集まりです。
そのチームメンバーたちを一つの方向に向かせるには、いろいろな意見を聞き、彼らと協調する必要があります。
スポーツに取り組みながら仲間との関わり方を学び、協調性や思いやりの気持ちが育ちます。
失敗から起き上がる力・レジリエンス
キャプテン役を担っていると、「もっとこうしていればよかった」と思うような失敗や後悔も経験するでしょう。
その気持ちに潰されることなく、「次」を意識して行動する。
同じ失敗を繰り返さないように振り返り、改善点を考える。
そんな気持ちが、失敗にめげない強い心・レジリエンスを育てます。
時間管理能力
チーム全体のタイムスケジュールを把握したり、試合への出発時間を連絡したり…チームを時間通りに動かすのも、キャプテンの役割のひとつ。
そのためには時間から逆算して行動することが必要です。
また自分のことよりも、チームを優先して時間がなくなることもあるでしょう。
先を見越してチームや自分の動きを考えるうちに、時間を管理する能力が育まれます。
子どものキャプテンシーを育てるために親ができるサポートは?

子どもは、キャプテンを任命されて「頑張ろう」と思っている反面、プレッシャーを感じることもあるでしょう。
親はその子どもの「安心できる場所」になって、サポートしていきましょう。
◯ 無条件に努力を認める
◯ 家はとにかく「安全基地」
◯ 話を最後までゆっくり聞く
◯ 感情のコントロールを一緒にトライ
◯ うまくいったことリストをつくる
無条件に努力を認める
「キャプテン」というだけでも、チームの注目が集まる存在で、子どもにはプレッシャーがかかっているはず。
「こうしたらいい」というアドバイスや、「もっとしっかり」という叱咤激励ではなく、とにかく無条件に子どもの努力を認めましょう。
子どもの様子をしっかり観察し、「よく声をかけてたね」「みんなのために動いていたよ」と頑張っていた部分を言葉にして伝えます。
もし課題があると感じても、子どもから聞かれるまでは我慢です。
家はとにかく「安全基地」
家に帰ってきたら、もう「キャプテン」ではありません。
家では一人の子どもとして、リラックスして甘えられるような環境を整えておきましょう。
オンとオフをしっかり区切ることで、チームでのキャプテン職を頑張ることができます。
家は安全地帯であり、スイッチの切り替え場所でもあるのです。
話を最後までゆっくり聞く
キャプテンとしてチームに関わっていると、うまくいかないことや失敗も多々あるでしょう。
そんな時は、子どもの話を最後までゆっくりと耳を傾けます。
途中で話をさえぎらず、アドバイスもせず、子どもの思いをすべて吐き出させることがとても重要です。
子どもが話をするのは、「聞いてほしいから」であり、「アドバイスしてほしいから」ではありません。
「この人ならとことん聞いてもらえる」と子どもに信頼してもらうためにも、親はじっくり話を聞きましょう。
感情のコントロールを一緒にトライ
感情、特に怒りの感情をコントロールするのは、とても難しいもの。
しかしキャプテンを任されていたら、その感情をチーム内で爆発させるわけにはいきませんよね。
そんな時、役に立つのが「感情コントロール法」。
難しいことはなく、
・深呼吸を3回
・その場を離れてジャンプする
・水を飲む
など、一瞬だけその感情と離れることが大事。
口で言っても、なかなか実行するのは難しいので、家で一緒に練習しておきましょう。
うまくいったことリストをつくる
失敗したことや、うまくいかなかったことはいつまでも心に残りますが、うまくいったことは忘れがちです。
だからこそ、子どもの行動がチームのためになった時、子どもが仲間のために動けていた時は、それを具体的に日記やリストに残しておきます。
落ち込んだ時や悩んだ時にそのリストを見返すことで、ヒントになることもあるでしょう。
成功体験をしっかり文章化することで、自己肯定感や自己効力感を感じる助けにもなります。
キャプテンもチームと一緒に育つ!

わが子がキャプテンや主将になると、親は「うちの子にできるかな」「プレッシャーにならないかしら」と心配な気持ちになることもあるでしょう。
しかしドラマに出てくるような、最初から完璧なキャプテンは存在しません。
「選ばれたのは信頼された証」なのですから、親子で自信を持って取り組むことが大切です。
キャプテンを経験すると、時には大変なこともありますが、子どもの精神的な成長のきっかけになります。
そこでやしなわれた責任感や思いやり、感情コントロールの方法は、その後進学し仕事をするようになってもとても役立つ能力。
キャプテンも「チームと一緒に育つ」という気持ちで、その役割に前向きに取り組んでいきましょう。
・キャプテンシーとは、チームをまとめる力。集団を統率する力のこと。
・キャプテンや主将になるのは、子どもが成長するチャンス。
・キャプテンを経験すると、責任感や忍耐力、協調性や問題解決力などの非認知能力がやしなわれる。
(参考文献)
・TORCH | トップアスリートが語る「スポーツが教えてくれたこと」 チーム、キャプテンごとに異なるキャプテン像
・高知工科大学経済・マネジメント学群 | 大学スポーツにおけるキャプテンの役割と在り方とは
・サカママ | チームを引っ張る責任と覚悟…ジュニアサッカーキャプテンの役割について考える