子どもが「食べるのが遅い」悩みを解消するために
投稿日: 2025.09.30

「もう時間がないのに、どうしてこんなに食べるのが遅いの?」
朝ごはんの時間、仕事に出かける前の忙しいひとときに、お子さんがなかなか食事を終えられず、イライラした経験はありませんか。
食べるのが遅いことは、お母さんやお父さんにとっては大きな悩みのひとつ。忙しい日常の中で、「給食の時間は大丈夫なのだろうか」「栄養が足りているのか」と心配になる方も少なくありません。
こちらの記事では、子どもが食べるのが遅い理由や背景を整理し、実践できる工夫や対策を紹介します。食事のスピードを単なる「問題」としてではなく、お子さんの成長や習慣づけのチャンスとして前向きにとらえられるようにまとめました。
もくじ
1. 子どもが食べるのが遅い理由とは?
子どもの食事が遅い背景には、さまざまな要因があります。
身体的な発達の影響
-
口腔機能の発達:噛む力や飲み込む力がまだ未熟な場合、自然と時間がかかります。
消化機能の未熟さ:胃腸が大人ほど強くないため、少しずつ食べる習慣になりやすいです。
環境や習慣の影響
-
おしゃべり:食事中に集中できず、手が止まってしまう。
-
食べ物の好き嫌いや偏食:苦手な食材に時間をかけてしまう。
ながら食べ:スマートフォンやテレビを見ながら食べてしまう。
心理的な要因
-
「早く食べなさい」と叱られることで、かえって緊張して進まなくなる。
-
「食べるのが遅い」と自覚していることで、食事そのものが楽しめなくなる。
このように、遅さには単純な原因だけでなく、体・環境・心が重なり合っているのです。
2. 「食べるのが遅い」と何が問題?

食事に時間がかかること自体は悪いことではありません。実は「よく噛んで食べる」という点ではむしろ理想的です。
ただし以下のような場合には注意が必要です。
-
栄養が不足する:食べ終わる前に時間切れで残してしまう。
-
学校生活に支障が出る:給食を時間内に食べられず、午後の授業に影響する。
-
生活リズムが乱れる:朝食に時間がかかり、登校時間がギリギリになる。
「遅い=悪い」ではなく、困りごとにつながっているかどうかを見極めることも大切です。
3. 食べるスピードを改善する工夫
ここからは、家庭でできる実践的な工夫を紹介します。
① 環境を整える
-
テレビやスマートフォンを消す:食事中は「食べること」に集中できるように。大人も同様に気をつけましょう。
-
食卓を整える:テーブルの上を片づけ、食べやすい空間をつくる。手の届く範囲に「食べる」ことの邪魔になってしまうものはおかない。これは衛生面でもとても大切です。
② 食べやすい料理にする
-
一口サイズに切る:大きな肉や野菜は食べやすくカット。特に野菜は繊維の向きに注意してきります。(繊維を断ち切る向きに切ると食べやすい)
-
柔らかく調理する:噛む力が弱い子には煮る・蒸すなどでやわらかく。
-
苦手な食材はアレンジ:細かく刻んでスープや卵焼きに混ぜる。
③ 楽しく食べる工夫
-
「あと3口でおしまい!」など小さなゴールを決める。
-
兄弟や家族で「同じおかずを競争」するように声をかける。
-
食べられたら「今日はここまで食べられたね」と肯定的に伝える。
④ 時間を意識させる
-
砂時計やタイマーを使う:10分だけ集中するなど、遊び感覚で意識できる。
-
「朝ごはんは20分以内で食べよう」など、見える形でルール化。

4. 食事スピードと成長の関係
小学生になると、学校給食という新しい環境で「時間内に食べる」ことが求められます。これは単なる栄養摂取だけでなく、集団生活の一部としての学びでもあります。
ただし家庭では「食べる楽しみ」を大切にしたいもの。親が焦って「早く食べなさい」と繰り返すと、かえって食事がいやになる可能性もあります。
大切なのは、
-
家庭では「安心して食べられる時間」
-
学校では「時間を意識して食べる経験」
この2つをバランスよく経験できるようにサポートすることです。
5. 忙しいお母さん・お父さんでもできる工夫

仕事や家事で忙しい中、子どもの食事にじっくり付き合うのは難しいもの。そこでおすすめの方法を紹介します。
-
朝食はシンプルに:肉巻きおにぎり、パンケーキ+牛乳、シリアルとフルーツ、パン+卵+具たくさんのスープ、白米+卵焼き+焼き鮭、丼ものなど栄養を押さえつつ食べやすいメニューに。まずはお皿の数を少な目から始めましょう。
-
前夜に下ごしらえ:薄切り肉を茹でておく、肉に下味を漬けておく、野菜をカットしておく、洗わなくて良いカット野菜を使うなど。火にかけるだけにしておけば朝も楽ちんです。
-
時短レシピを活用:レンジでできる蒸し野菜や具だくさん味噌汁はおすすめ。
-
「完食」にこだわらない:全部食べることよりも「元気に出かけられること」を優先。
-
叱らず、待つ姿勢:食事は楽しい時間であることを忘れない。自分は時間通りに準備を進める。
-
褒めるポイントを探す:「昨日より早く食べられたね」と成長を言葉にする。
-
お手本を見せる:親が楽しそうに食べる姿は、子どもの食欲や集中力を高めます。
「開けるだけ」食材:納豆、もずく、豆腐など開けるだけで副菜になるおかずを買っておく。
6. 「食べるのが遅い子ども」への接し方のコツ
まとめ:食事の時間は「栄養」と「心」を育てる機会
子どもが食べるのが遅いのは、多くの家庭で共通する悩みです。
しかし、その背景には発達や環境、心理があり、必ずしも悪いことばかりではありません。
大切なのは「どうして遅いのか」を理解し、無理のない工夫を取り入れること。家庭の食卓は、栄養をとるだけでなく「食べることを楽しむ」場所です。
お母さんやお父さんが少し工夫することで、子どもは安心して食事に向き合い、やがて自分のペースで食べ進める力を身につけていきます。
「食べるのが遅い」という悩みも、子どもの成長過程のひとコマ。親子で向き合う時間を楽しみながら、食事を通して元気な心と体を育てていきましょう。


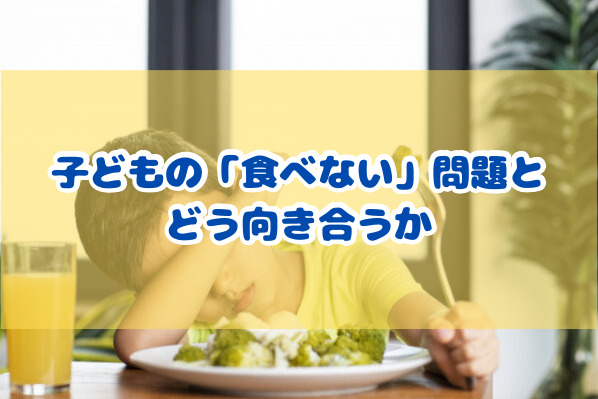

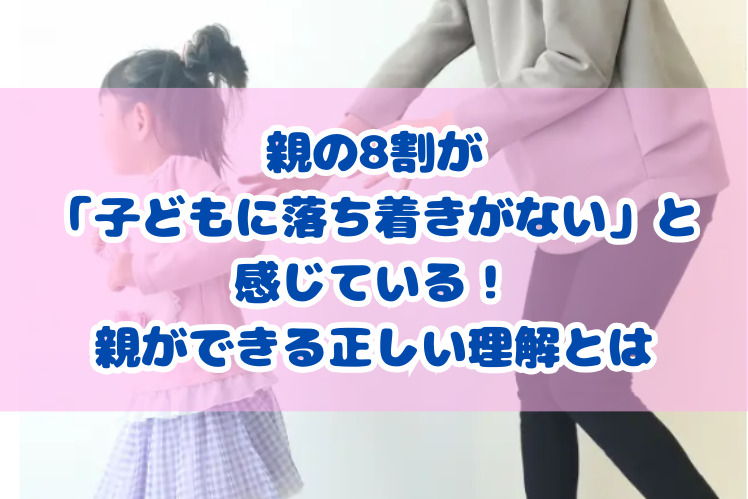
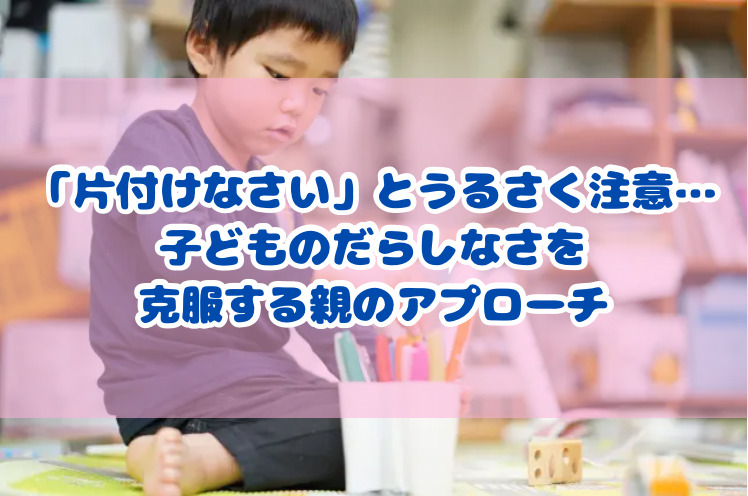
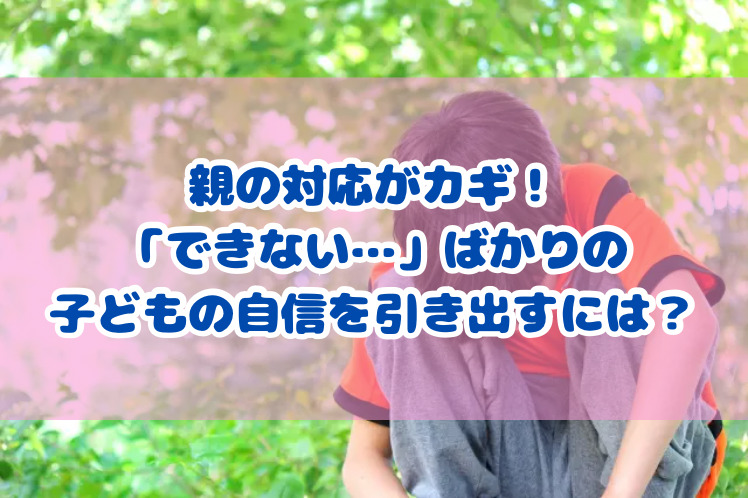
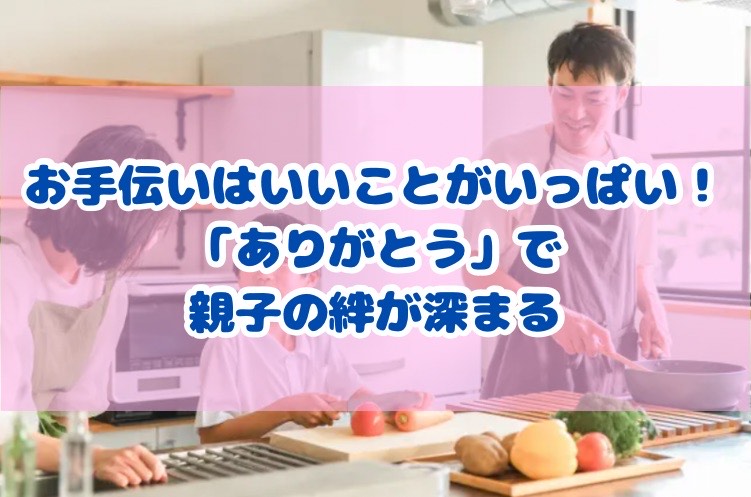











専門家コメント
スポーツを頑張る子どもを持つ母親として、子どもたちの体つくり、怪我予防、健やかな成長に欠かせない大切なことを 広く伝えていくべく活動をしています。保護者の皆様がお子さんの一番のサポーターとなれるよう、お子さんの成長を末長くサポートできるよう、「お母さんが、無理をしない」をモットーに掲げて 毎日のごはん作りはもちろん、2018年からはスポーツを頑張るお子さんをお持ちのお母さんの個人サポートに取り組んでいます。