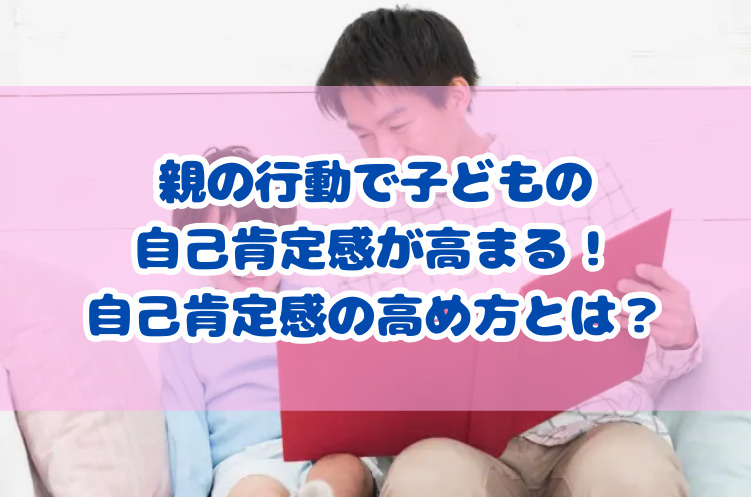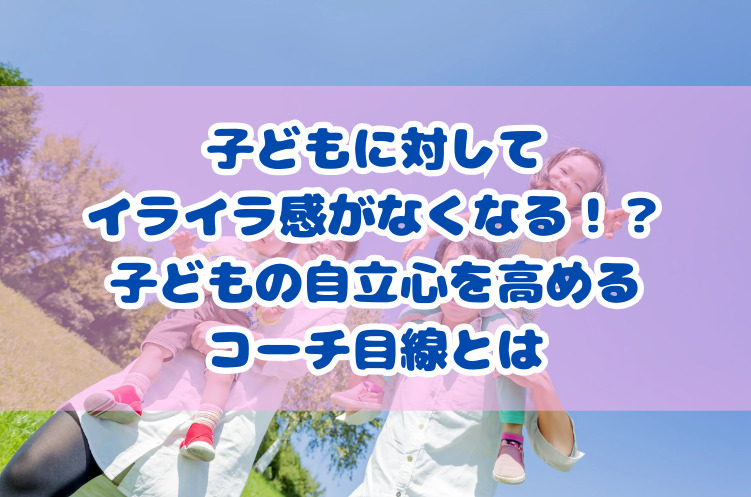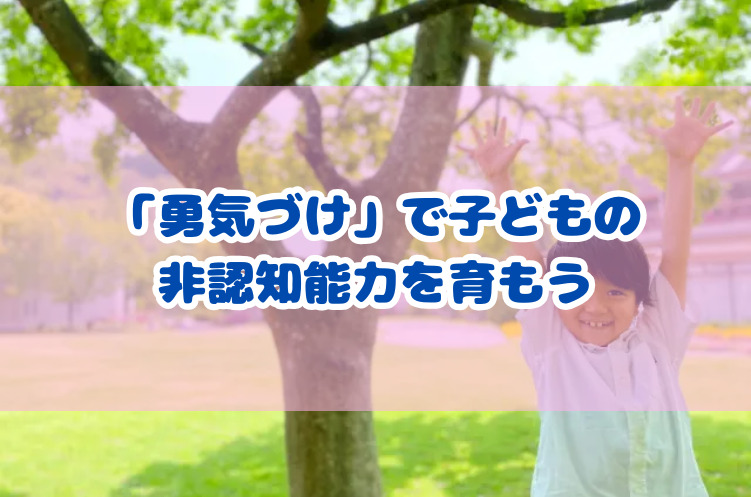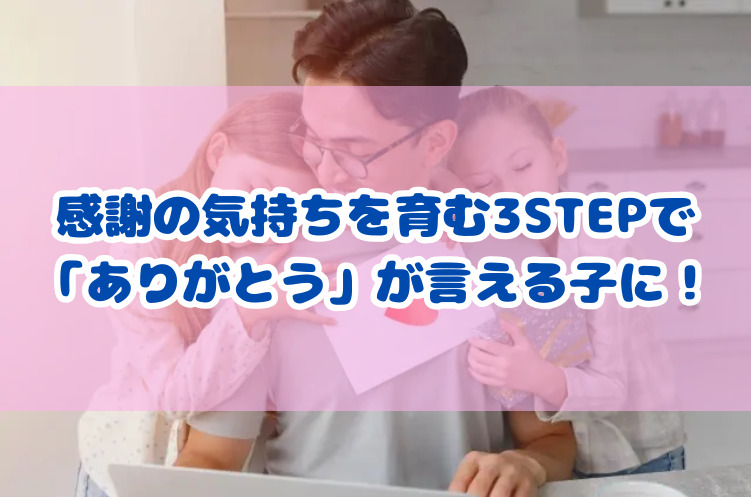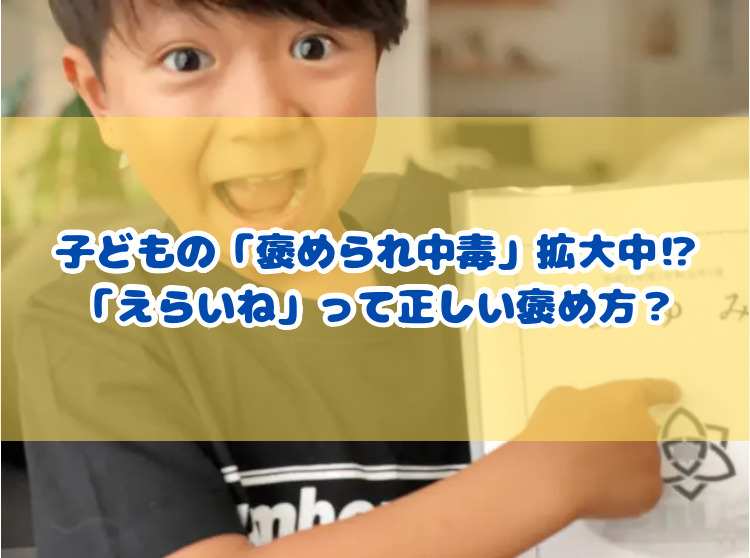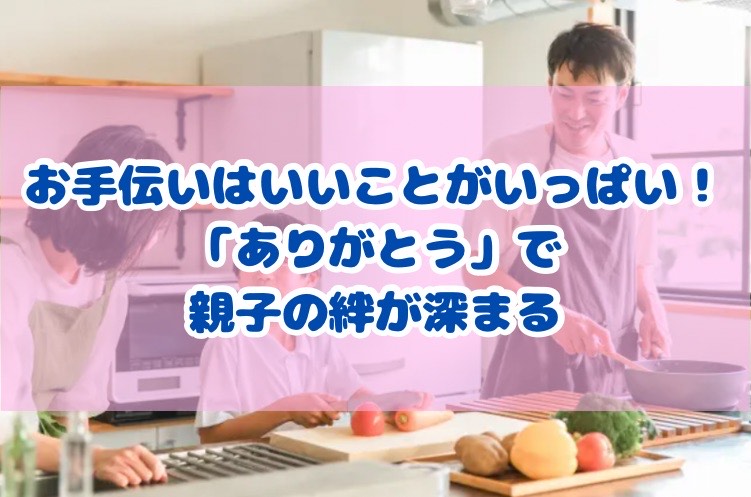子どものやる気を100倍にする褒め方とは?
投稿日: 2025.09.02
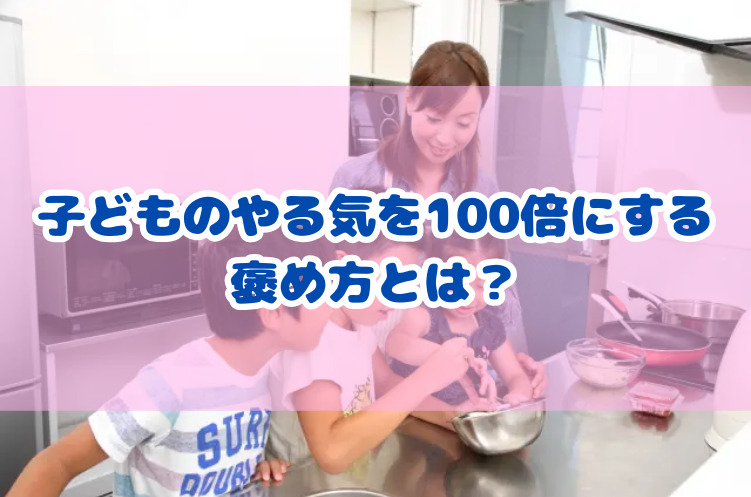
「子どもは褒めて育てよう」とよく聞くけれど、いざ実践しようと思うと「どうやって褒めたらいいの?」「うちの子には響かないな…」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
褒めるよりも先に、「宿題を全然やらない…」「何度言っても片付けをしてくれない…」「ご飯の時間になっても、ゲームやYouTubeをやめない…」などから、「いつになったら宿題やるの?」「早くかたづけなさい!」と、つい日常的に叱ってしまいますよね。
「子どもを叱り続けるよりも褒めたほうがいい」ということは体感としてわかっているものの、子どもを「褒める」ことが、子どもの成長にどんな影響を及ぼすのか、イメージが湧かない保護者の方が多いかもしれません。
ここでは、子どもの褒めどころの見つけ方や、褒め上手になるための親の心の持ち方、子どものやる気をますますアップさせる褒め方について、紹介します。
もくじ
子どもは褒められことで主体性が高まり、自己肯定感の土台ができる

まずは日々の育児を振り返り、どんな場面でどのような言葉でわが子を褒めているのか、考えてみましょう。
・ お手伝いをしてくれた時に、「ありがとう、助かったわ」と声をかける。
・ スポーツなどで、今までできなかったことができるようになった時に、「すごいね!できるようになったね! 頑張ったね!」と褒める。
・ 苦手な食べ物がひとつでも食べられるようになった時に、「今まで嫌いだったのに、食べられたね。すごい!」と褒める。
さまざまな光景が思い浮かびますね。
チャレンジがうまくいったとき、子どもが望むのは、親の笑顔と褒め言葉です。
子どもは褒められることで自分に自信をもち、主体性が高まります。
自己肯定感の土台を作ることができ、「自分ならできる!」「頑張れる!」と、やる気をアップさせることができるのです。
こんな褒め方だと、子どものやる気はダウン!

親はよかれと思って褒めているつもりでも、褒め方や褒め言葉によっては、子どものやる気をかえってダウンさせてしまう場合もあります。
ここでは、NGパターンの褒め方を紹介します。
褒め方がいつも同じ
絵を描いたり工作が完成したときに、子どもから「見て、見て!」といわれることが多いと思います。
忙しいとつい、「すごい!」」「上手!」など、褒め言葉がワンパターンになってしまいがちですが、子どもながらに「また同じ・・」と、内心がっかりしていることも多いものです。
「この線がすごくきれいに描けたね」「この部分、すごく工夫して作られているね」など、具体的に褒めましょう。
褒めたあと、ひと言余計なおまけがつく
子どもがお手伝いをしてくれたときに、「ありがとう。今度は洗濯物たたみもよろしくね。」、運動会のかけっこで1位になったときに、「すごかったね! 次はサッカーの試合でシュート決めようね」など、余計なひと言はNGです。
子どもは余計なひと言のほうが気になって、素直に喜ぶことができません。
褒めたあと、恩にきせる
「テストで100点とれたよ」と報告してきた子どもに対し、「やったね! すごい!ママが一生懸命教えてあげたからだね」など、「子どもの成功は親のおかげ」という気持ちをおしつけ、恩にきせるような褒め方もNGです。
子どもの嬉しい気持ちが冷めてしまいます。
子どものやる気を100倍にする褒め方のポイント5つ

子どものやる気をアップし、主体性を高めることができる褒め方のポイントを、5つご紹介します。
「できないこと」でなく「できるようになったこと」に注目する
これまでピーマンをひと口も食べられなかった子どもが、ひと口でも食べることができたら、それは大きな進歩です。
「ピーマン、ひと口食べられたね!」と褒めることができます。
小さな「できるようになったこと」に注目してもらえた子は自信がつき、自己肯定感が高まります。
「結果」よりも「過程」に注目する
何かができたとき、結果が良かったときに「すごいね!」「おめでとう!」などと褒めるのはもちろんOKですが、結果だけでなく、「過程」に注目するようにしましょう。
結果が良くなかったときは、「残念だったけど、一生懸命頑張ってたね」などと声をかけてあげることが大切です。
「当たり前のこと」を探して褒める
食事の前に手を洗った、元気に学校に行けた、夕食をもりもり食べたなど…
普段当たり前のようにやっている行動の中に、「褒めどころ」が隠されています。
「食事の前に手が洗えたね。えらい!」
「元気に学校に行けているね。いいね!」
「おいしそうに食べているね」
このような言葉だけでも子どもの心は満たされ、自己肯定感を高めていくことができます。
親の「気持ち」を伝えて褒める
「いい子ね」「すごいね」……といった評価の言葉よりも、「食器を運んでくれてありがとう。ママは嬉しいよ」「お友達と楽しそうに遊んでいる⚪⚪ちゃんが大好きよ」など、親の「気持ち」を伝える言葉を増やすことを意識しましょう。
これも、子どもの自信や主体性を育みます。
他の子と比べず、子ども自身の成長に注目して褒める
友だちやきょうだいと比べるのはNGです。
「昨日は問題を解くのに10分かかったけど、今日は7分でできたね。がんばったね!」など、過去の自分に比べてできるようになったことに注目し、褒めてあげましょう。
年齢別の声かけ例:子どもの成長に合わせた褒め方
 子どもの成長段階に合わせて褒め方を工夫することで、子どものやる気をより引き出し、自信を育むことができます。
子どもの成長段階に合わせて褒め方を工夫することで、子どものやる気をより引き出し、自信を育むことができます。
ここでは、幼児期、小学生低学年、小学生中〜高学年と、3つの成長段階に即した褒め方の一例を紹介します。
幼児期:具体的な行動を短い言葉で褒める
この時期は、自己肯定感の土台を築く大切な時期です。結果だけでなく、「やってみようとしたこと」や「できたこと」そのものを褒めましょう。
具体的な行動を短い言葉で褒めるのがポイントです。
「靴下を自分で履けたね!すごい!」「お片付けできたね、ありがとう!」のように、行動の直後に褒めることで、「自分はできた!」という達成感を味わうことができます。
「パズル、最後まで諦めないで頑張ったね!」「ご飯をこぼさずに食べようとしてるね、えらいね!」と、頑張っている過程や努力に注目して、共感的に褒めましょう。
「お友達に『貸して』って言えたね、優しいね」のように、優しい気持ちや行動を具体的に褒めることで、社会性や共感性を育みます。
小学生低学年:過程に注目して褒める
この時期は、できることが増え、自分の力で物事を成し遂げたいという気持ちが強まります。
結果に加え、「どのように達成したか」という過程にも注目して褒めると、子どもの思考力や工夫する力を伸ばすことができます。
「〇〇くん、学校の準備を全部自分でできたんだね!ママ、すごく助かったよ、ありがとう」「難しい漢字を一生懸命練習してるね。その頑張る気持ち、パパは嬉しいな」のように、行動を具体的に褒め、親がどう感じたかを伝えることで、子どもの行動が誰かの役に立っていることを実感できます。
「この絵、色鉛筆を何色も重ねて、すごくきれいな色になってるね!」「この問題、こうやって考えたんだね!面白いやり方だね!」と、子どもが試行錯誤した点や、独自のアイデアを褒めることで、考えることの楽しさを教えられます。
「縄跳び、逆上がりができなくても大丈夫。毎日練習している〇〇ちゃん、本当にえらいね!」のように、結果が出なくても、努力している姿勢や挑戦する気持ちを評価しましょう。
小学生中〜高学年:内面的な成長を認める
この時期は、友だちや周囲の評価を気にするようになります。
褒められることへの照れくささも出てくるため、大げさに褒めるよりも、努力の過程や内面的な成長を認めてあげるような、落ち着いた声かけが効果的です。
「この前のテスト、苦手だった算数の計算ミスが少なくなってるね。毎日ドリルを頑張っていた成果だね」と、過去の自分と比べて成長した点を伝えます。努力が結果につながっていることを実感させてあげましょう。
「自主的にゴミ出しをしてくれたんだね、ありがとう。〇〇くんが手伝ってくれるようになって、家の中がすごく助かってるよ」「発表会、緊張しただろうけど、最後まで堂々と発表できたね、素晴らしいよ」と、行動の背景にある子どもの気持ちや責任感を褒めます。
「友達のことで悩んでいたけど、〇〇な考え方をして、ちゃんと向き合えてえらいね」「相手の気持ちを考えて行動できたんだね。本当に優しい子だね」のように、内面的な成長や考え方を褒めることで、子どもは「自分はこれでいいんだ」と自信を持つことができます。
ぜひ、今日から実践してみてくださいね。
・ 子どもは褒められることで自分に自信がつき、主体性を育むことができる。
・ ワンパターンの褒め言葉、ひと言多い褒め言葉、恩にきせるような褒め言葉、に注意!
・「結果」よりも「過程」に注目し、子ども自身の成長を見つけてあげよう。
子どものやる気は、できる!頑張れる!と思える自信が大切であることが分かりました。
また、子どものやる気は、親の何気ない一言に左右されます。
どんなに小さなことでも、子どもができるようになったことを見逃さず、その過程を大切にすると共に、親の気持ちを伝えながら、その子自身に注目してみましょう。
(参考文献)
・ガミガミ言うより笑顔だけで子どもが変わる(著者: 原坂一郎 出版:PHP研究所)
・失敗しない褒め方(監修:西東桂子 出典:りんごちゃんのおけいこラボ)
・叱りゼロで子どもは自分でできるようになる!(著者:原田綾子 出版:PHP研究所)