子どもが胃腸炎になったとき、食事でできること
更新日: 2025.08.19
投稿日: 2025.08.29
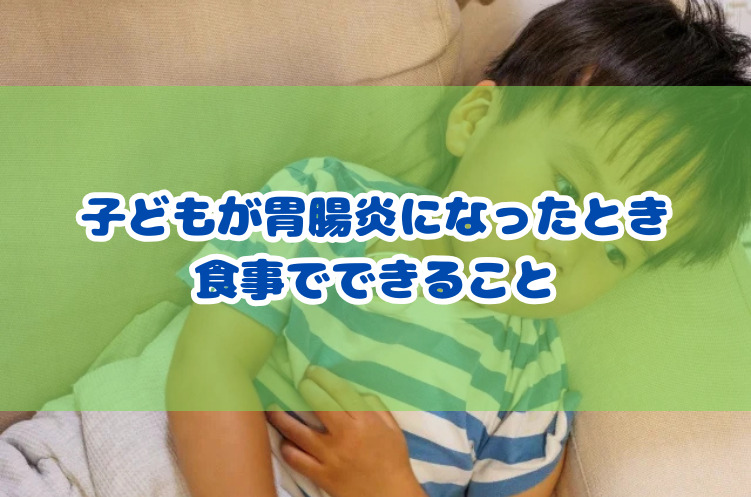
子どもが突然の嘔吐や下痢で苦しんでいる姿を見ると、親としては心配でたまらなくなります。
特に胃腸炎の場合、「何を食べさせていいの?」「水分だけでいいの?」「食べたがるけれど止めるべき?」など、食事に関する疑問や不安が押し寄せてくるかと思います。
こちらの記事では、感染性胃腸炎にかかったお子さんへの適切な食事のタイミングと食事のメニューや注意点を、ご家庭で出来る実践的な内容を交えて解説します。
食事はただの栄養補給ではなく、回復を支える大事な機会です。
親御さんができるサポートのヒントをお届けします。
もくじ
1. 胃腸炎とは?その原因と症状
小児でよく見られる「胃腸炎」とは、胃や腸の粘膜が炎症を起こしている状態のことです。
主な原因はウイルス感染(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど)で、これらは飛沫や接触を通じて感染します。
主な症状は、
・下痢
・腹痛
・発熱
・食欲不振
症状は数日で治まることが多いものの、胃腸炎により体力が低下しているお子さんにとっては水分や栄養のバランスが崩れやすいため、油断は禁物です。
ウイルス感染の食中毒の発生件数が多いのは気温が低く乾燥している寒い季節。「寒い時期は食中毒が発生しにくい」といわれてきましたが、今は冬でも部屋が暖房等で暖かいので注意が必要です。
ウイルス感染以外の食中毒は細菌(ブドウ球菌、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、大腸菌、腸炎ビブリオなど)、自然毒(フグ、毒きのこなど)があります。
高温多湿の夏の時期は細菌による食中毒に注意が必要です。
2. 胃腸炎時は「水分補給」が最優先
嘔吐や下痢により失われる「水分と電解質」を補うことが、まず最初に取り組むべきことです。
「電解質(でんかいしつ)」という言葉はむずかしく聞こえますが、実は私たちの体にとってとても身近な存在です。
電解質とは、体の中の水分に溶けている大切な成分のこと。
代表的なのは、ナトリウム(塩の仲間)・カリウム(野菜や果物の成分)・カルシウム・マグネシウムです。
これらは体の水分バランスをととのえたり、筋肉を動かしたり、心臓をリズムよく動かすなど、大事な働きをしています。
水分補給のポイント
糖と電解質が適度に含まれており、吸収率が高い。。
一度にたくさん飲ませると嘔吐を誘発します。
嘔吐が落ち着いてから、15~30分後に小さじ1杯(5ml)ずつスタート。飲めない場合は無理に与えず、医師の判断で点滴が必要になることも。
※水やお茶だけでは電解質が不足し、脱水を助長する可能性があるため注意が必要です。

3. 「食事再開」のタイミングと考え方
症状が落ち着き、水分を問題なく摂取できるようになってきたら、飲むだけではなく食事をしましょう。
ただし、いきなり固形物を食べ始めるのではなくお粥などやわらかいものから始めます。
食事開始のサイン
食べたがるからといってすぐに普段のご飯を与えるのではなく、「消化の良いもの」「胃腸に負担をかけないもの」から段階的に始めることが大切です。
そして冷たいものではなく、温かいものを。
冷たいものだと胃腸がぎゅっと縮こまってしまうので回復するまでは温かいものを心がけましょう。
4. 胃腸炎時におすすめの食事ステップ
ステップ1:液体状の食事(初期)
※いずれも少量ずつ、温かい状態で提供します。冷たいものは避けましょう。

ステップ2:軟らかい半固形食(中期)
※脂質は控えめに、味付けは薄めに。お子さん自身が「おいしい」と思える味で、無理なく進めます。
主食類:おかゆ(全がゆ・5分がゆ)、柔らかいうどん
野菜類:よく煮たにんじん、じゃがいも、かぼちゃ
たんぱく質類:鶏ささみ、白身魚(タラ・カレイなど)、卵(固焼き)
果物類:バナナ、すりおろしリンゴ(加熱済み)
乳製品:回復期に少量のプレーンヨーグルト(無糖)
飲み物:経口補水液、麦茶、白湯
調味料・油分:少量の塩、だし
主食類:パン(特に菓子パン)、油で炒めたご飯、玄米
野菜類:生野菜、繊維の多い野菜、(ごぼう・セロリなど)
たんぱく質類:豚肉・牛肉、揚げ物、半熟卵、加工肉(ウインナーなど)
果物類:柑橘系(オレンジ・グレープフルーツなど)、生の果物
乳製品:牛乳、チーズ、アイスクリーム
飲み物:スポーツドリンク(糖分過多)、ジュース、炭酸飲料
調味料・油分:バター、マヨネーズ、こってりソース類
ステップ3:消化しやすい通常食(後期)
※少しずつ普段の食事に近づけていきます。
生野菜や刺身、脂っこいもの、甘すぎるもの、冷たいものはしっかり治るまで控えましょう。
5. 「食べたがらない」ときの対応
胃腸炎の回復中は、無理に食べさせる必要はありません。
体が「休みたい」と感じているサインでもあります。
対応のヒント
- 無理に3食にこだわらず、1日を通して数回に分けて食事の機会をつくる
- 一口だけでも「食べた」という経験が自信につながる
- 親の焦りは子どもに伝わりやすいため、安心感をもって接する
- 手洗いの徹底(特にトイレ後・食事前)
- 食器やタオル、歯ブラシコップの共有を避ける
- 治るまでは使い捨てペーパータオルを使用
- 嘔吐物・便の処理は手袋・マスクを使用
- 朝食をしっかり摂る
- よく噛んで食べる習慣をつける
- 加工食品や冷たい飲食物の摂りすぎに注意
6. 「再発予防」のための家庭でできること
感染予防
胃腸にやさしい食生活
体調が良くなってからの食生活にも注意することで、再発のリスクを大きく減らすことができます。

まとめ:食事は「治す力」を育てる時間
子どもが胃腸炎になったとき、親として最も大切なのは「慌てず」「焦らず」「見守る」ことです。適切なタイミングで、水分と食事を整えるだけで、子どもの回復は確実に早まります。
また、食事を通して「お母さんがそばにいてくれる安心感」や「食べる楽しさ」が伝わることも、回復に大きく関わってきます。
「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」「誰と食べるか」も大切にして、胃腸炎という一時的な不調を、親子で一緒に乗り越えていきましょう。




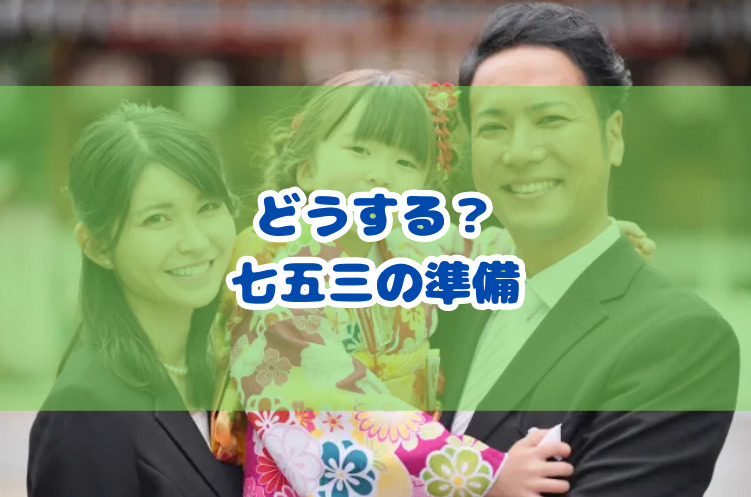
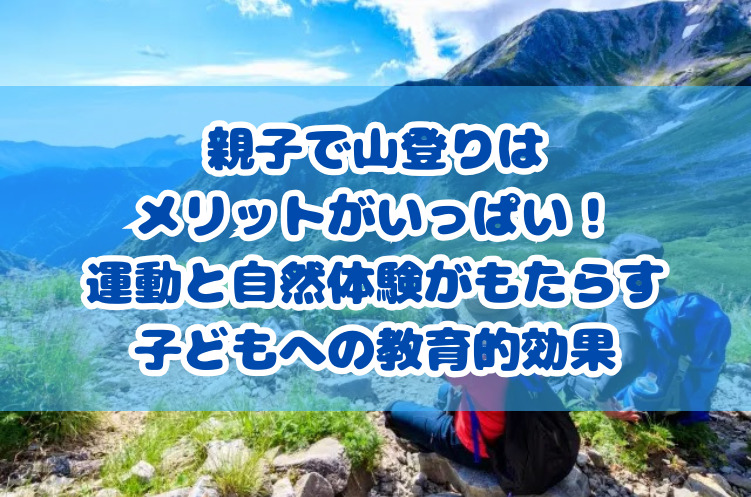
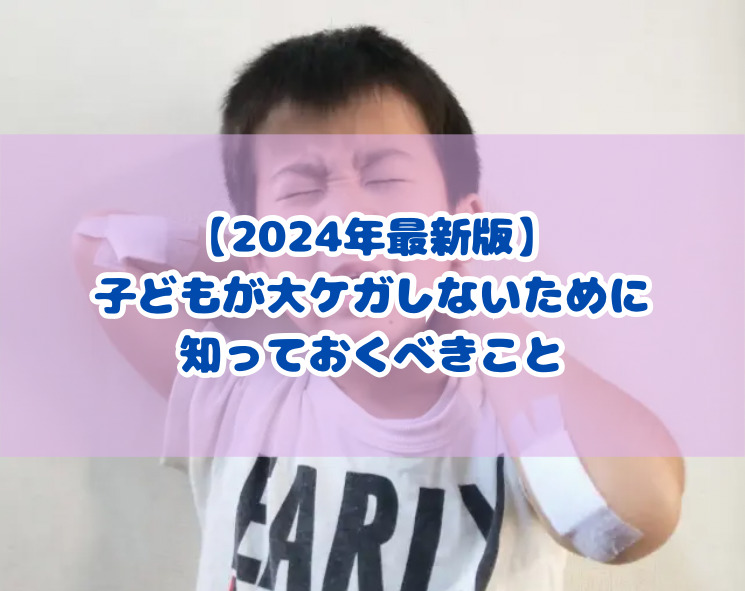











専門家コメント
スポーツを頑張る子どもを持つ母親として、子どもたちの体つくり、怪我予防、健やかな成長に欠かせない大切なことを 広く伝えていくべく活動をしています。保護者の皆様がお子さんの一番のサポーターとなれるよう、お子さんの成長を末長くサポートできるよう、「お母さんが、無理をしない」をモットーに掲げて 毎日のごはん作りはもちろん、2018年からはスポーツを頑張るお子さんをお持ちのお母さんの個人サポートに取り組んでいます。