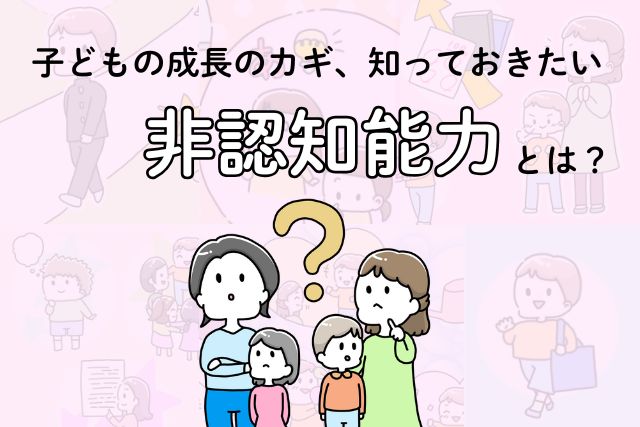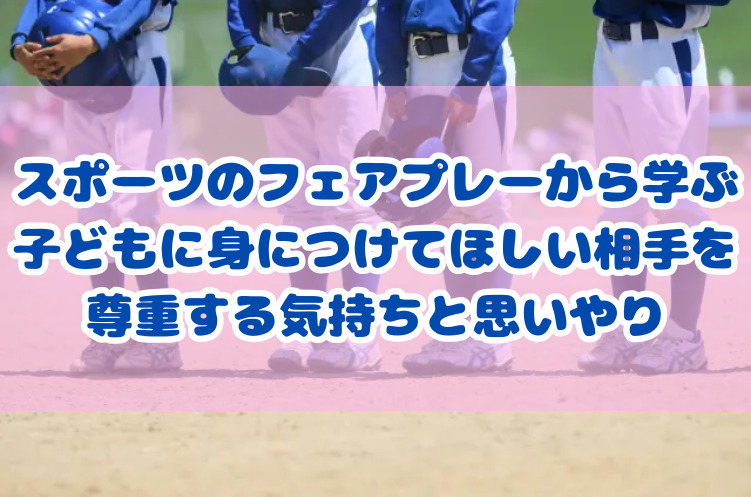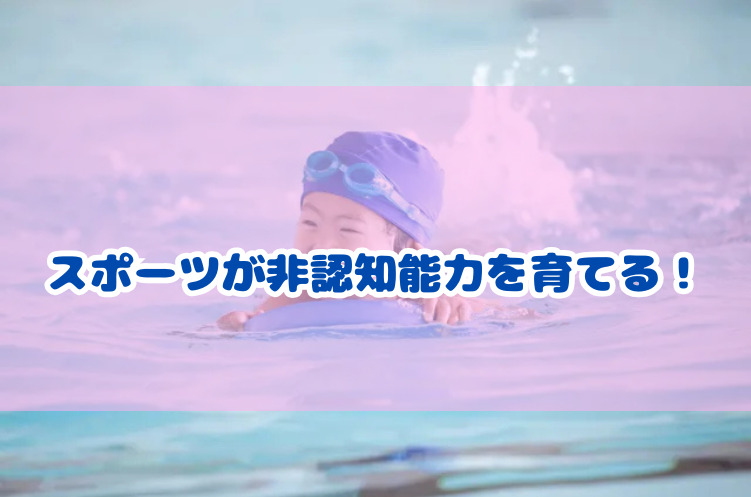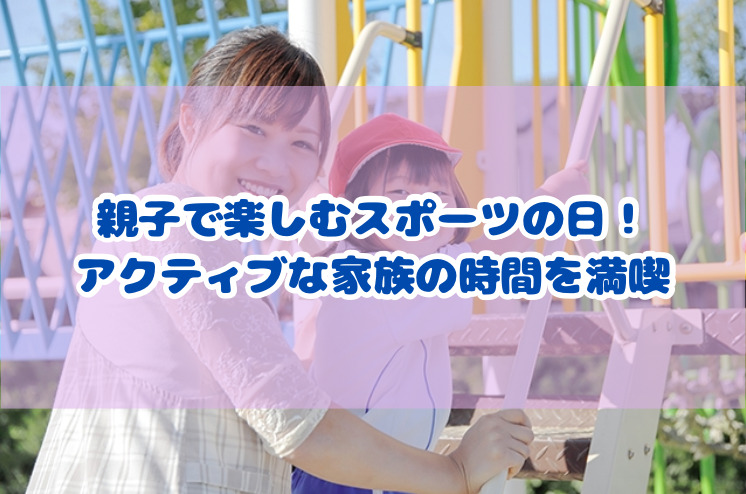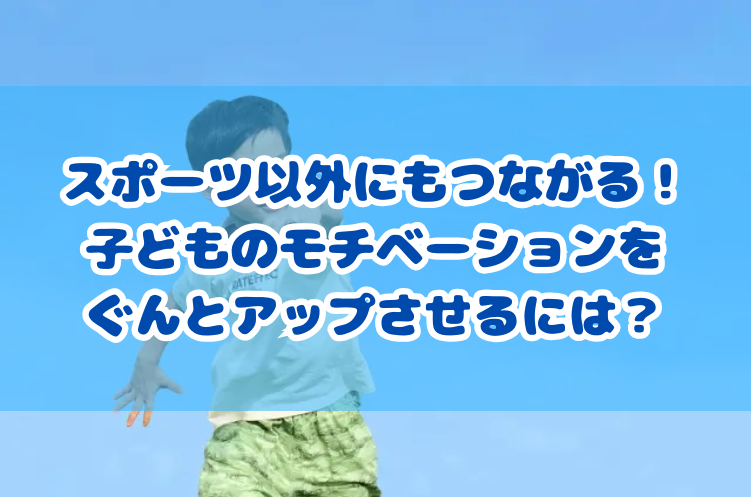スポーツで身につけたい「心の体力」 親の関わり方のコツは?
更新日: 2025.08.19
投稿日: 2025.08.26
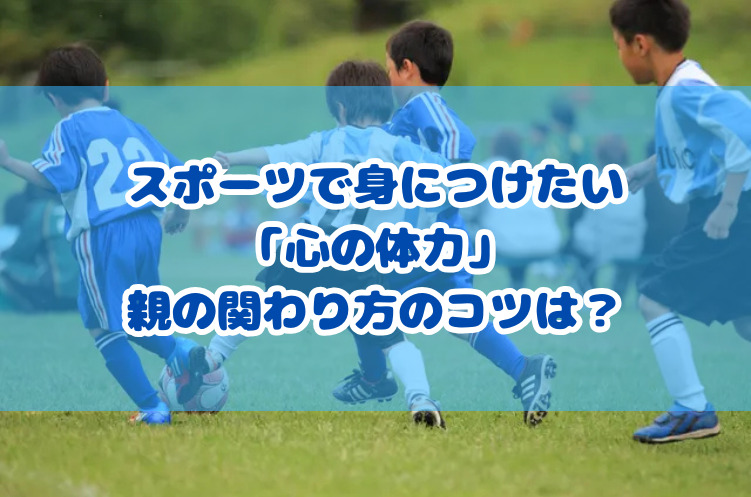
みなさんのお子さんは、なにかスポーツをしていますか?
スポーツに取り組んでいると、精神力やレジリエンス、集中力、挑戦心などの非認知能力が身につきやすいといわれます。
実はこの多くの非認知能力が養われることで、子どもの心の体力が育つのです。
心に体力がつくと、中学→高校→大学と進学し、社会人になった後もストレス耐性がついたり、周囲とのコミュニケーションが円滑になったりと、いいことがたくさん。
今回は、スポーツで子どもに「心の体力」をつけるための、親の関わり方を考えていきます。
もくじ
心の体力はなぜ必要なのか?

「心の体力」がつくと、子どもにとってどんなよい面があるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
◯ ストレスに強くなる
◯ 人間関係がスムーズになる
◯ 失敗してもめげない
◯ 気持ちに余裕ができる
◯ 自分に自信が持てる
ストレスに強くなる
スポーツでも勉強でも、試合前やテストなどプレッシャーがかかる場面が訪れます。
しかし心に体力があると、大変な時や辛い時でもプレッシャーに押しつぶされずに前向きに対処できるでしょう。
人間関係がスムーズになる
心の体力とは強さでもあり、柔軟さでもあります。
心に体力があると、相手の気持ちを汲み取ったり、自分とは違う考え方の人と意見を調整したり、感情の押し引きを上手にできるようになるでしょう。
人とぶつかることが減るので、人間関係がスムーズになり、人に好かれるようになります。
失敗してもめげない
スポーツをしていると、試合で失敗したり、なかなか上達しなかったりと思い通りにならないことがあります。
心に体力があると、うまくいかないことがあって、「自分はダメだ」「もうやめたい」などの後ろ向きな感情にとらわれることが少なくなります。
「こうしたらどうかな」「次は頑張るぞ」とポジティブな気持ちを持ち続けられるようになるのも特徴です。
気持ちに余裕ができる
心に体力がつき、前向きで大らかなメンタルになると、心に余裕ができて行動全体が寛容になるでしょう。
平常心で過ごすことができ、落ち着いた行動が増えます。
自分に自信が持てる
心に体力がつくと、
プレッシャーにも押しつぶされない。
コミュニケーション力があがり、周囲との関係性もよくなる。
ポジティブな気持ちを持ち続けられる。
などの行動が増えるでしょう。
心の体力がしっかり根付くと、子どもは自分自身に自信が持てるようになります。
自己肯定感や自己効力感が高まり、さらに心の体力が強化されるというプラスのスパイラルになっていきます。
スポーツで身につく心の体力は「非認知能力の束」

例えば、一般的に「体力」といえば、
・持久力
・俊敏性
・柔軟性
・瞬発力
・適応力
などの様々な力が総合的に強くなると、「体力がある状態」になります。
では心の体力は、どんな力の集合体なのでしょうか。
自分のプレーで失敗したり、試合に負けてしまったり、メンバーに選ばれないなどの辛い局面でも、立ち直り前向きな気持ちになれる「心の回復力」のこと。
「ドリブルが上手くなりたい」「もっとシュートを決めたい」など、今の自分よりもレベルアップしたいという気持ちを持つこと。そしてそのために努力する心。
練習が辛くても、思い通りにならなくても、途中で投げ出さずに最後までやり抜く力のこと。「投げ出してしまいたい」という心の誘惑に勝てる強い気持ち。
自分の意見はしっかり持ちながらも、周囲の意見を聞いたり、コーチの指示に耳を傾けたり、目標に向かって協力し合う力。
余計なことを考えすぎたり、過去の失敗や迷いに惑わされず、今自分がやるべきことに集中して全力を尽くすこと。
自分にはまだ難しいことにも、「やってみたい」「やってみよう」と前向きに取り組む力。そして失敗しても、何度もトライする強い気持ち。
自分の気持ちを伝えて、同時に相手の考えも理解する力。またコミュニケーションを通じて問題を解決し、結束力なども高められること。
など、多種多様な力が束になって心の体力が養われることがわかります。
またそれぞれの力を見ると、学力や数値では測れない「非認知能力」とほぼ重なります。
そうです。心の体力は多くの非認知能力を集めて束にしたものなのです。
子どもの「心の体力」を育む、親の関わり方とは

子どもの「心の体力」は放っておいても自然に育つものではありません。
また短期間に身につくものではなく、日々積み重ねていくものです。
日常的な親の関わり方にポイントがあるので、見ていきましょう。
◯ 安心感を与える
◯ 失敗しても責めない
◯ 子どもの意見に耳を傾ける
◯ 挑戦を後押しする
◯ 子どもとの時間を楽しむ
安心感を与える
親や周囲に受け入れられている・愛されているという安心感は、子どもが新しいことに挑戦したり、「失敗しても大丈夫」と思える心の安全基地になります。
その土台があってこそ、様々な非認知能力を身につけていくことができるでしょう。
子どもの心の体力は、トライ&エラーを繰り返して少しずつ身につくものなので、安心感は大きな役割を果たします。
失敗しても責めない
子どもは失敗を繰り返して成長していきます。
それを「なにやってるんだ!」「お前のせいで試合に負けた」と責めてしまうと、子どもは失敗をしないように、挑戦も冒険もやめてしまうでしょう。
そのように小さく固まった心では、「心の体力」は身につきにくくなってしまいます。
「失敗しても次がある」と思える柔軟な心が、強い気持ちや心の体力の元になります。
子どもの意見に耳を傾ける
子どもが自分の思っていること、感じていることを自分の言葉で伝える機会を増やすと、子どもは感情の表現が少しずつできるようになります。
そして子どもが自分で決めることも増やすと、少しずつ自分に自信がついて自己肯定感も養われていきます。
また親も自分の意見を子どもに伝えるようにすると、「いろいろな意見がある」「人の意見も参考になる」ことがわかり、さらにコミュニケーション力も身につくでしょう。
挑戦を後押しする
子どもが新しいことに挑戦するのは「失敗したらかわいそう」「危ないのではないか」など、心配なこともありますね。
しかしいつも同じことを繰り返していたのでは、子どもの心に体力をつけることはできません。
積極的に新しいこと・未経験のことへの挑戦を後押しし、うまくいかなくても「次は大丈夫」と励ましたり、「どうしたらうまくいくかな」と対策を一緒に考えてみましょう。
挑戦を応援してもらえると、子どもは「次もやってみよう」と挑戦をポジティブに捉えられるようになります。
子どもとの時間を楽しむ
家の中が暗い気持ちやネガティブな感情に溢れていると、子どもは元気がなくなり、心の体力は育ちにくいですね。
失敗しても、「大丈夫!次があるさ」
不安になっても、「あなたならできるよ!」
落ち込んでいたら「話、聞かせて」
と、親が子どもと過ごす時間を大切にし、楽しんでいると、子どもは心の体力を蓄えられるでしょう。
大変なことも多い子育てですが、子どもとの時間を大切にすることで、子どもは「受け入れられている」と安心感を感じられます。
スポーツをすることで心がグッと強くなる!

スポーツをしていると、仲間と意見交換をしたり、新しいプレーに挑戦したり、自分の感情をコントロールしたりと、子どもが成長する機会が多くあります。
時にはメンバーから外れてしまったり、試合に負けてしまったりすることで、悔しい思いや後悔をすることもあるでしょう。
しかし子どもはその気持ちを糧に、「もっと練習をしよう」「次は負けたくない」と次に向けて心を強くしていきます。
スポーツに真剣に取り組むことで、様々な感情を体感し、仲間たちと交流することができ、心の体力を養うことにつながります。
親は子どもを信じて、子ども主体でスポーツに取り組むようにすると、子どもはぐんぐんと心の体力をつけていくでしょう。
・スポーツをしていると心の体力が身につきやすい。
・心に体力がつくと、ストレスに強くなったり、人間関係がスムーズになったり、自分に自信が持てるようになる。
・心の体力とは「非認知能力」の束のようなもの。
・心の体力を身につけさせるため、普段から親は子どもに安心感を与えて、子どもの意見に耳を傾け、挑戦を後押しするといい。
(参考文献)
・スポーツ安全協会 | スポーツパフォーマンスを高める子どものメンタルヘルスとは
・スポーツ活動による子どもの心身への影響 | 西村吉弘・永田惠
・日本アイケン | スポーツが持つ力は体だけではなくメンタルにも