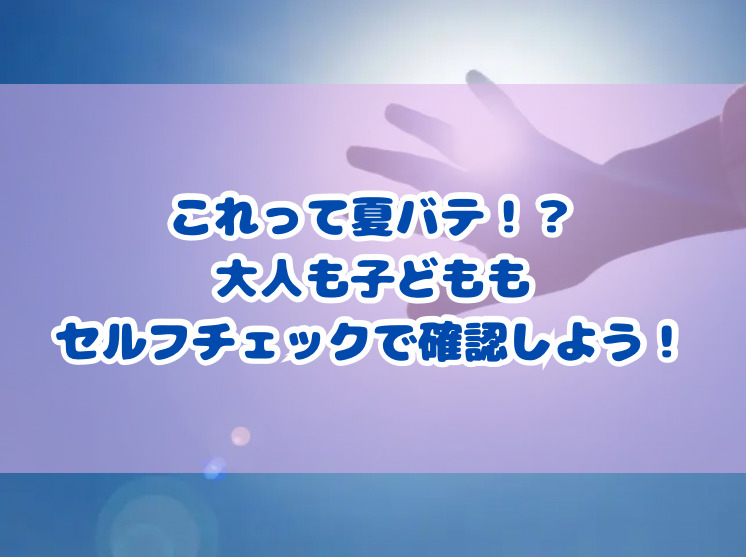夏バテする子としない子の違いは? 夏でもスポーツを快適に楽しむ方法
更新日: 2025.07.31
投稿日: 2025.08.08

今年の夏も厳しい暑さが続きそうですね。
お子さんの夏バテ、心配ではありませんか?
「うちの子は夏になるといつもぐったりしてるけど、あの子は毎日元気に外で遊んでいるな……」などと感じたことはありませんか?
この記事では、夏バテしやすい子とそうでない子の違いはどこにあるのかについて解説します。
そして、暑い夏でも子どもたちが安全に、そして快適にスポーツを楽しむための秘訣を紹介。
夏バテ知らずでアクティブに過ごしましょう!
そもそも夏バテって? 夏バテの症状と原因

夏バテとは、その名の通り「夏の暑さによって体が調子を崩してしまう状態」のことです。
医学的な病名ではありませんが、暑い季節に感じるさまざまな不調の総称として使われています。
夏バテとして、以下のような症状が挙げられます。
・食欲がない、胃もたれがする
・頭が重い、めまいがする
・やる気が出ない、集中力が続かない
・寝つきが悪い、眠りが浅い
・イライラする
子どもは体温調節機能が未発達で、大人よりも暑さに弱いため、夏バテになりやすいと言われています。
また、大人と比べて子どもの方が水分の割合が大きいため、汗で水分を多く失ってしまうとあっという間に脱水状態に陥り、夏バテなどの体調不良になってしまいがちです。
夏バテの主な原因は、以下の3つです。
気温差と湿度による自律神経の乱れ
夏の暑さから逃れるために、冷房の効いた涼しい部屋に入るとホッとしますよね。
でも、この屋外の暑さと冷房の効いた室内を行き来することが、体には大きな負担になります。
体には、体温を一定に保つための「自律神経」という司令塔があります。
しかし、急激な温度変化が繰り返されると、自律神経が混乱してしまい、夏バテの症状が出てしまうのです。
大量の汗による水分・ミネラル不足
夏は、体温を下げるためにたくさんの汗をかきます。
汗と一緒に、体に必要な水分だけでなく、カリウムやナトリウム、マグネシウム、カルシウムといった大切なミネラル(電解質)も体の外へ出ていってしまいます。
水分やミネラルが不足すると体のバランスが崩れ、夏バテしやすくなります。
食欲不振と栄養の偏り
暑いと食欲が落ちて、冷たい麺類やそうめんなどで済ませてしまうことが増えますよね。
アイスやジュースばかりを欲しがるお子さんも少なくないでしょう。
でも、これだけだと体に必要な栄養が十分に摂れません。
体が本来持っている回復力が落ちてしまい、夏バテの症状がさらに悪化してしまいます。
その他、
・ 夏休みによる生活リズムの変化
・ 強い紫外線の浴びすぎ
などが、夏バテの原因になることもあります。
夏バテしやすい子って、どんな子?

夏バテしやすい子には、いくつかの特徴があります。
特に注意したい子どものタイプを見ていきましょう。
汗をかきにくい子
「うちの子、暑がりなわりに汗をあまりかかないな」「ちょっと外に出ただけで、顔が真っ赤になっている」と感じることはありませんか?
こうした子は、体温調節機能がうまく働かず、夏バテになりやすい傾向があります。
偏食気味で栄養が偏りがちな子
「好き嫌いが多くていつも同じものばかり食べている」「夏休みに入って、冷たい麺類やアイス、ジュース類ばかり欲しがる」といった子も、いわゆるエネルギー不足になりやすく、夏バテのリスクが高いです。
夜更かしなど生活リズムが乱れがちな子
夏休みに入ると、つい夜更かしをしてしまったり、朝寝坊したりと、生活リズムが崩れがちになりますよね。
このような子どもも自律神経が乱れやすく、夏バテしやすいタイプといえます。
体力がない、運動不足の子
体力がない子は、暑さに対する体の抵抗力も低い傾向にあります。
少しの暑さでも体に負担がかかりやすく、すぐにバテてしまいます。
また、運動不足の場合、疲労物質を効率よく排出する機能が十分に働かず、一度疲れると回復に時間がかかります。
これが夏バテの症状を長引かせる原因になります。
外に出たがらず、冷房の効いた部屋に長時間いる子
冷房は、体を外から冷やします。
特に長時間冷房の効いた部屋にいると、知らず知らずのうちに体が芯から冷えてしまうことがあります。
手足の末端だけでなく胃腸も冷やされてしまうと、消化機能が低下し、食欲不振や消化不良、下痢などの症状が出やすくなります。
これは、夏バテの代表的な症状でもあります。
夏バテ知らずでスポーツを楽しむ6つのポイント

夏バテを防ぎ、子どもたちが元気にスポーツを楽しむためには、特別なことをする必要はありません。
以下、6つのポイント紹介します。
時間帯の工夫:早朝や夕方の涼しい時間帯を選ぶ
真夏の昼間は想像以上に気温が高く、地面からの照り返しも強烈です。
このような時間帯に運動すると、熱中症のリスクが格段に高まります。
できるだけ早朝や夕方の、比較的気温が下がる時間帯を選んでスポーツを楽しみましょう。
午前中の早い時間や、日が傾き始める夕方は、日差しも弱まり、体への負担を減らすことができます。
服装の選択:吸湿速乾性素材や帽子を活用する
汗をかいてもすぐに乾く吸湿速乾性のある素材のウェアを選ぶことで、汗冷えを防ぎ、快適さを保てます。
また、直射日光から頭部を守る帽子は必須アイテム。
つばの広いものを選び、首の後ろまでカバーできるタイプだとさらに安心です。
水分補給の徹底:飲むタイミングと内容に気をつける
「喉が渇いた」と感じた時には、すでに体は水分不足の状態です。
喉が渇く前に、こまめに水分補給をすることが何よりも大切。
水だけでなく、汗で失われがちな塩分やミネラルを補給できるスポーツドリンクや経口補水液も効果的です。
特に、30分以上の運動をする場合は、スポーツドリンクなどを活用しましょう。
休憩時間だけでなく、運動中も定期的に水分を摂るように促してください。
休憩の重要性:日陰での休憩と体を冷やす工夫を
夢中になると、ついつい休憩を忘れがちですが、暑い中での運動では定期的な休憩が不可欠です。
日差しを避けて日陰で休み、可能であればベンチなどに座って体を休ませましょう。
さらに、冷却タオルや濡らしたタオルで首筋や脇の下などを冷やす、保冷剤や冷却スプレーを活用するなど、積極的に体温を下げる工夫を取り入れると、疲労回復が早まります。
食事と睡眠:夏バテ予防に効果的な食事と質の良い睡眠を
夏バテしない体を作るには、毎日の食事と睡眠が基本中の基本です。
夏バテ予防には、エネルギー源となる炭水化物、筋肉の材料となるタンパク質、体の調子を整えるビタミンやミネラルをバランス良く摂ることが大切です。
食欲が落ちやすい夏でも、さっぱりと食べやすい工夫を凝らしたり、旬の野菜を取り入れたりしましょう。
また、寝苦しい夜でもエアコンなどを上手に使って質の良い睡眠を確保することが、疲労回復と翌日の元気を支えます。
「汗をかく」習慣:シャワーだけでなく湯船に浸かり、適度な運動を
意外に思われるかもしれませんが、普段から適度に汗をかく習慣をつけておくことも夏バテ対策になります。
毎日シャワーで済ませがちな夏でも、週に数回はぬるめの湯船にゆっくり浸かることで、汗腺の働きを促し、体温調節機能を高めることができます。
また、ウォーキングなどの軽い運動を継続的に取り入れることで、無理なく汗をかき、暑さに強い体を作っていくことができます。
最近は、夏場のスポーツを快適にするための便利なグッズがたくさんあります。上手に活用して、熱中症対策や快適さアップにつなげましょう。
・冷却スプレー/シート:休憩中に体に吹きかけたり、貼ったりするだけでひんやり感が得られます。
・ネッククーラー/冷感タオル:首元を冷やすことで、体全体のクールダウンに効果的です。水で濡らして使うタイプや、USB充電式のものなど種類も豊富です。
・UVカット機能付きウェア/アームカバー:強い紫外線から肌を守り、日焼けや体力消耗を防ぎます。
・携帯扇風機:コンパクトで持ち運びやすく、休憩中に顔や体に風を送って涼むのに便利です。
保冷機能付き水筒/ボトル: 飲み物を長時間冷たいまま保ってくれるので、いつでも冷たい水分補給が可能です。
・子どもは大人よりも夏バテになりやすい。
・夏バテしやすい子には特徴がある。
・食事、睡眠、休憩に気を配ることで夏バテは防止できる。
参考文献)
「夏バテする子としない子の違いは?ジュニアアスリートに必要な栄養について」(出典:たんぱく質ヘルスケアコラム)
「夏バテ・熱中症になりやすい子どもの特徴。「暑さに強い体づくり」の要はココにある!」(出典:こどもまなびラボ)
「夏バテ」(出典:大正製薬)
「夏バテしやすい子供の半数以上は生活リズムの乱れ 小児科医調査」(出典:リセマム)