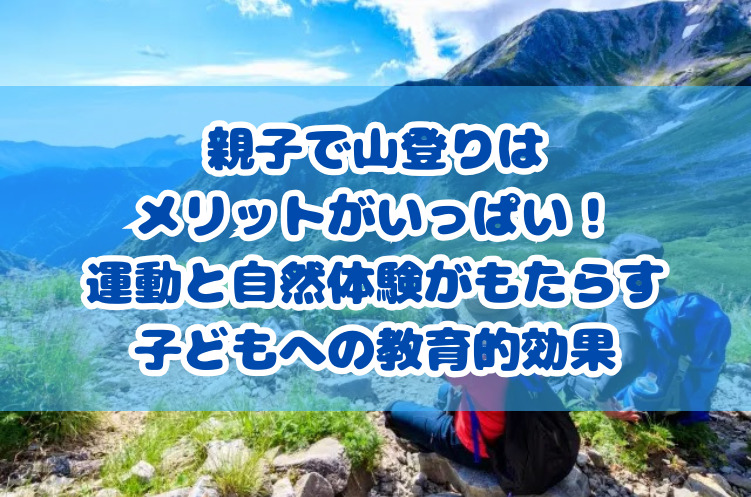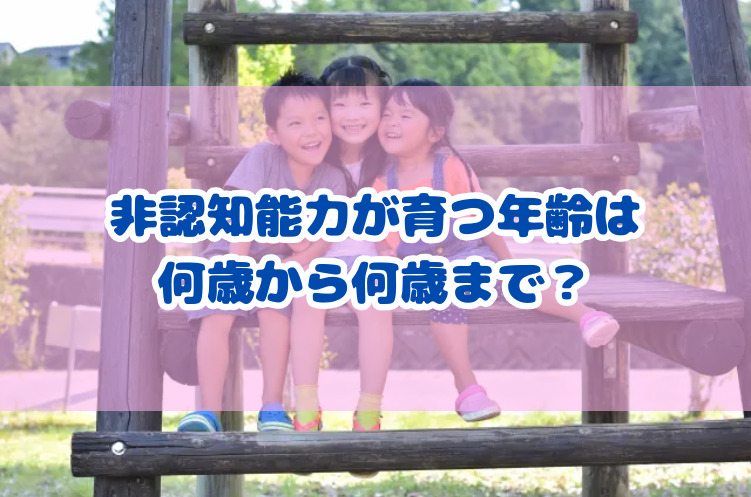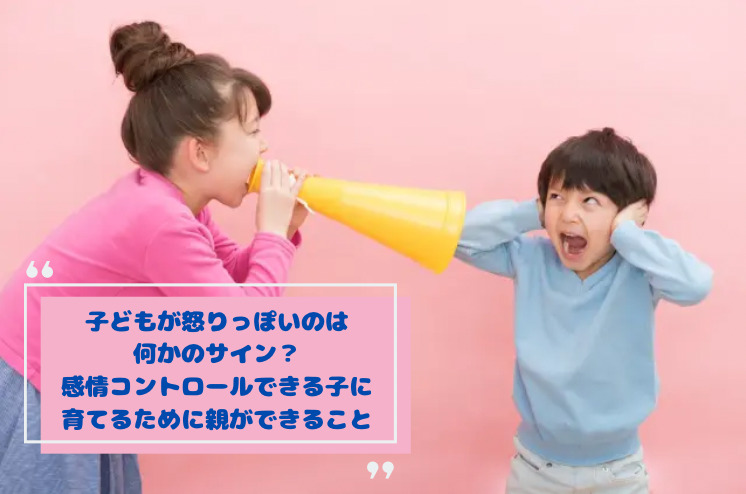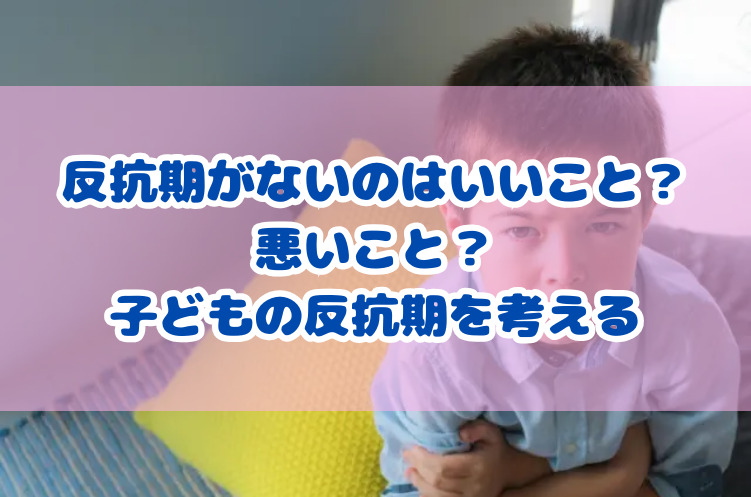また「イヤイヤ」? 子どもの中間反抗期の乗り越え方
更新日: 2025.07.24
投稿日: 2025.07.15
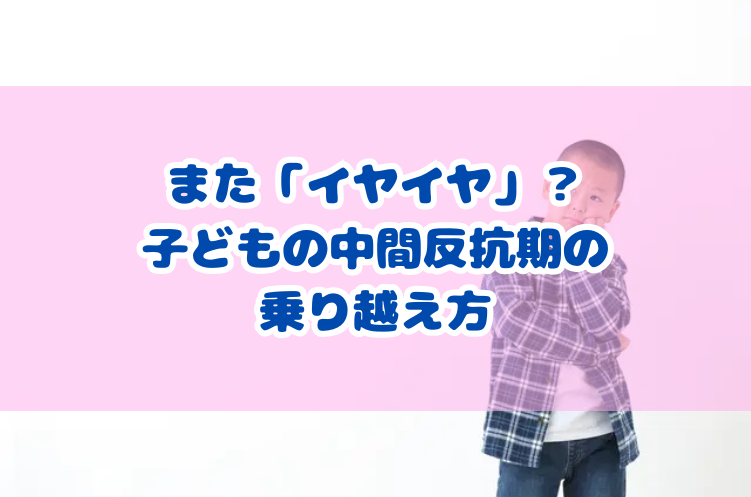
「中間反抗期」という言葉、聞いたことはありますか?
年長さんから小学校3年生ごろに訪れる“プチ反抗期”を表し、親の干渉を嫌がったり、親に口答えをしたりなど手を焼くお母さんお父さんも少なくありません。
中間反抗期の原因や特徴、親としての対応のポイントについて紹介します。
もくじ
中間反抗期っていつ訪れるの? その原因は? どんな行動が見られる?

子どもの発達は、直線的ではなく、「ところどころガタガタと停滞するときがある」と想像するとわかりやすいでしょう。
本格的な思春期を迎える前兆ともいえる中間反抗期の時期は、これまで順調に育っていたわが子が荒れているように見えるかもしれません。
子どもの反抗期としてよく知られているのは、2〜3歳ごろの「第一次反抗期」と、小学校高学年〜中学生の思春期に訪れる「第二次反抗期」。
・第二次反抗期(小学校高学年〜中学生):自立心が芽生え、親や大人を否定して自分の価値観や自我を確立していく時期。
中間反抗期はこの2つの時期の中間、幼稚園年長頃から小学生中学年の間に起こると言われており、子どもによってその程度やタイミングは異なります。
幼稚園年長頃から小学生中学年くらいの時期は、言語能力が増し、子ども同士のコミュニケーションもより活発になります。
「自分はなんでもできる」という万能感にあふれ、「自分で考えて、自分で行動したい」という気持ちがより強くなり、親の干渉や手助けを嫌がるようになるのです。
また、この時期は、周りが見えるようになるいっぽうで、没頭できることを見つけられなかったり、何かに一生懸命になれない“つまらなさ”に対する漠然とした不安やモヤモヤが出やすく、不機嫌のもととなることが多いようです。
・注意しても、聞かない、無視をする。
・わざと乱暴な言葉遣いをする。
・親に隠し事をしたり、嘘をついたりする。
などが、中間反抗期によく見られる子どもの行動です。
親としては「早く終わらないかな」「いつまで続くの…?」と思いますが、反抗期が訪れる時期や期間は子どもそれぞれ。
数ヶ月で着ぐるみを脱ぐように終わる子もいれば、中間反抗期からそのまま第二次反抗期に移行する子もいます。
親としては辛い時もありますが、「成長過程の必要なプロセス」と考えて、片目をつぶって見守りましょう。
中間反抗期の子には、否定語ではなく「肯定語」で

反抗的な子どもを前にすると、つい「◯◯しないで」「ダメでしょ」といった「否定語」で注意してしまいますよね。
しかし子どもが否定語を理解する時は、一度「してはいけないこと」を想像してから、それを否定する2段階でイメージするため、注意されたことがスッと理解できないことがあります。
また否定的な言葉は、子どもを傷つけたり、自己肯定感を低くしてしまうことがあるので、できれば肯定的な言葉で声をかけるといいでしょう。
子どもを否定しない言い換え例
否定語から肯定語に変換するとシンプルになるので、中間反抗期の子どもへの声かけにはぴったり。
同じニュアンスを伝える時でも、柔らかい肯定の言葉にすることで、伝わり方に大きな違いが出ます。
一度習慣化してしまえば、簡単に変換できるので試してみましょう。
例えば…
「走ったらダメ」→ 「静かに歩こうか」
「やめて!」「なにやってるの!」→「一度ストップしてみよう」「どうしてこうなったか、教えて」
「なんでわからないの?」「学校で習ったでしょ」→「どこが難しい?」「一緒にやってみよう」
「うるさい!」「黙って!」→「小さい声で話して」「テレビの音が聞こえないよ」
子どもがすんなり理解できれば、困った行動も減るかもしれません。
肯定語の声かけは、中間反抗期の子との対話においてちょっとしたコツになるでしょう。
子どもの中間反抗期とどう向き合う? 5つのポイント

子どもの中間反抗期というのは、心身の成長に伴い、内面的にも周りとの関係についてもこれまでのバランスのとり方では対応できなくなり、
・ 自分自身の変化に慣れようとしている時期
と、とらえることができます。
中間反抗期は、子どもが成長するうえで必ず通る道のようなもの。
心配しすぎず、温かく見守ることが大切です。
では、親は子どもの中間反抗期とどのように向き合えばよいのでしょうか。
◯ 中間反抗期は「成長の努力期間」と受け止める
◯ 子どもに選択肢を与える
◯ ルールを明確にする
◯ 子どもの思いを尊重しじっくり話を聞く
◯ 親の気持ちはシンプルな言葉で
中間反抗期は、「成長の努力期間」と受け止める
私たち大人も、新しい環境になじまなければいけないとき、落ち着かなかったり、不安な気持ちになったりしますよね。
それは子どもも同じです。
反抗は子どものわがままと受け止められることが多いのですが、子どもは子どもなりに、今の状況になじもうと頑張っているのかもしれません。
中間反抗期は、「次なる成長のための努力期間」ととらえ、親はどっしり受け止める覚悟が必要です。
子どもに選択肢を与える
「カレーに入れる野菜、どれにする?」
「お風呂と夕食、どっちを先にする?」
「どの練習着を持って行く?」
など、子どもに決めさせてもOKな選択肢は、日常生活にたくさんありますね。
「子どもに聞くと面倒なことになる」という場面も多々ありますが、人は自分がコントロールしている時に「自己効力感」や「自己決定感」を感じてポジティブな気持ちになります。
時には選択肢を与えることで、子ども自身が「自分が決めた」と感じられます。
子どもに小さな責任感を持たせることで、「約束を守る」「話がスムーズになる」といった行動が期待できるかもしれません。
ルールを明確にする
子育て中はルールを決めてもなかなか守れなかったり、守らせるのが難しい時もありますね。
しかし子どもからすると、
「この前はOKだったのに、今日はどうしてダメなの?」
「子どもには守らせようとするのに、大人は約束を守らない」
など、不条理に感じることがあると、反抗心に火がついてしまいます。
ルールは明確にして、子どもにもわかりやすいようにしておき、大人も必ず守りましょう。
ルールを決める時は大人が一方的に考えるのではなく、必ず子どもと話し合って決めるのもポイント。
その際、「何がOKで、何がダメか」「なぜダメなのか」を子どもにしっかり伝えることが大切です。
理由が理解でき、納得できると、子どももルールを守りやすくなります。
子どもの思いを尊重し、じっくり話を聞く
「なんてことしてるの!」「やめなさい!」などと命令するばかりだと、大人が思っている以上に子どもの心は傷ついてしまいます。
子どもの思いを尊重し、「あなたの話をしっかり聞くよ」という雰囲気をつくることで子どもの心も落ち着き、反発で意思を貫こうとするよりも、話し合うことを選ぶようになるでしょう。
親の気持ちはシンプルな言葉で
親からみて不快な子どもの言動を目にすると、ついカッとしてしまいがちですが、親が感情的に子どもを叱りつけるのは、中間反抗期の子どもにとっては逆効果です。
「あなたが〇〇して、ママは悲しいな」「あなたが危険な目に遭ったらと思うと心配だから、注意したのよ」など、お母さんお父さん自身の気持ちや考えをシンプルな言葉で伝えるよう心がけましょう。
また「◯時には出かけなきゃいけないから」「音が聞こえないから」など、具体的な理由もしっかり伝えると子どもは納得して行動に移しやすくなるでしょう。
そのままの子どもを受け入れ、親もいっしょに成長しよう

中間反抗期の子どもは、まだまだ「ママやパパに甘えたい」という気持ちも持ち合わせています。
だからこそ、
・ 「勝手にしなさい!」など突き放すような言葉を繰り返す。
・ 子どもを無視する。
・ 「こんな子に育てた覚えはないわ!」など、ネガティブな言葉をかける。
などの言動はNGです。
子どもは親に対して「自分を受け入れてもらえない」「自分はダメな子なんだ」という思いを抱くようになり、より反抗的な態度をとったり、自分の気持ちを隠したりするようになることがあります。
子どもが荒れているときというのは、とても傷つきやすく、弱々しい状態です。
まずは親自身が、
「わが子が突然反抗的になって不安に思っている」
「これまでの子育てがいけなかったのではないかと焦っている」など、
自分自身の今の気持ちを受け入れつつ、「子ども自身も、もがいている最中なんだ」ととらえましょう。
その上で、夫婦で相談したり、先輩ママの体験談を聞いたり、同じように中間反抗期の子どもに手を焼いているママ友やパパ友と情報交換をするのもいいかもしれません。
そうすることで、子育てのヒントをもらえたり、気持ちがはれたりすることもあります。
中間反抗期はいつか終わるもの。
それだけ子どもが成長した証、「子どもにとって、親が安心して気持ちをぶつけることができる存在である」という証でもあります。
わが子の見方を少し変え、親自身の気持ちも受け入れながら、成長を見守っていきましょう。
・第1次反抗期と第2次反抗期の中間に訪れる「中間反抗期」は年長〜小学校中学年
・中間反抗期は「子どもの成長の証」。どっしり受け止める
・親自身の不安な気持ちも受け止め、一人で抱えず周りに相談を
参考資料)
「子どもの心が荒れる時期の受け止め方」(監修:袰岩奈々、出典:PHPのびのび子育て)
「中間反抗期とは?接し方や声掛けのコツは?突き放すのは逆効果」(出典:ベネッセ教育サイト)
「無視、口答え、逆ギレ…親も子もつらい「中間反抗期」の特徴と対応のコツを知って上手く乗り越えよう!」(出典:CONOBAS)
「小学入学前後に来た中間反抗期の5つの特徴とは?」(出典:マイナビ子育て)
「保育士が子どもに使う魔法の言葉! 否定語から肯定語への言い換え方とは?」(出典:CONOBAS)