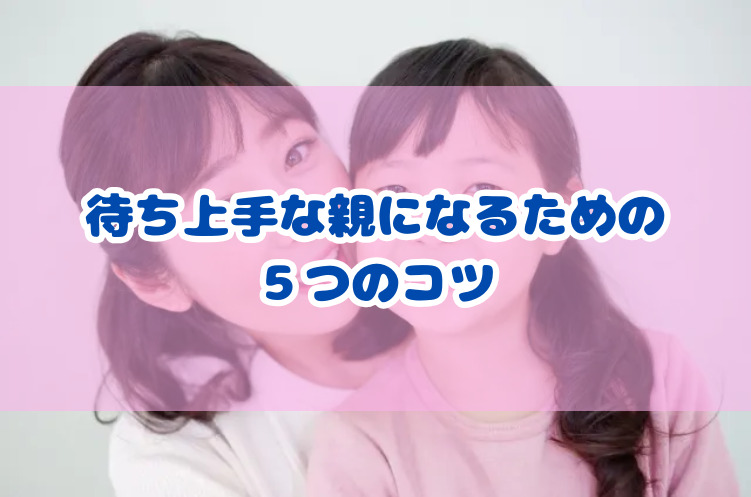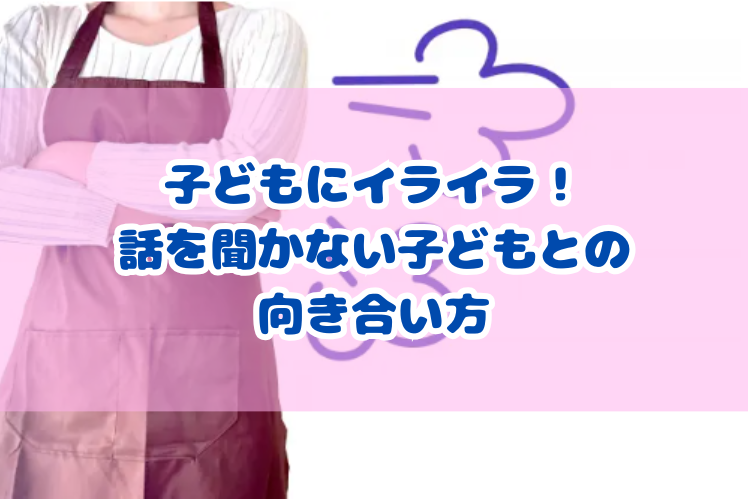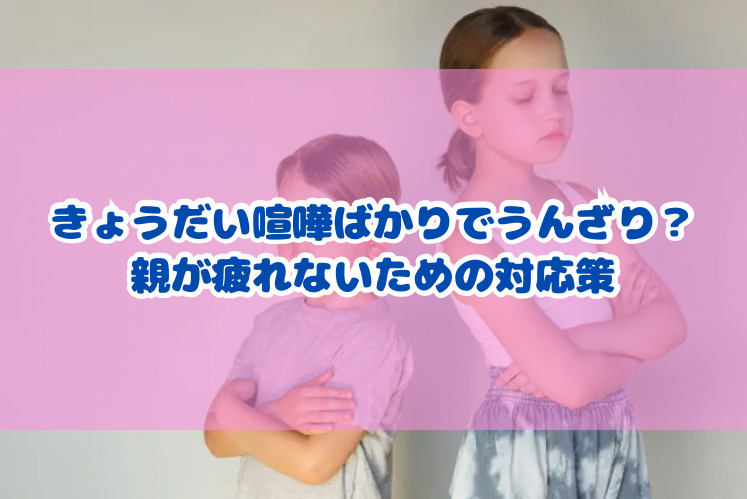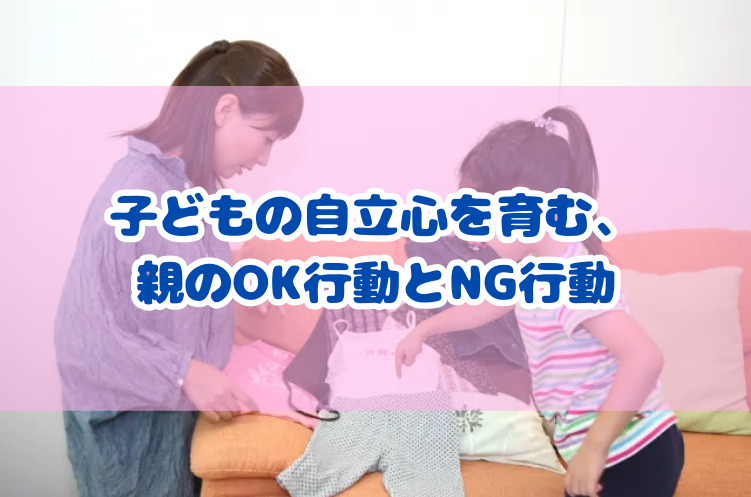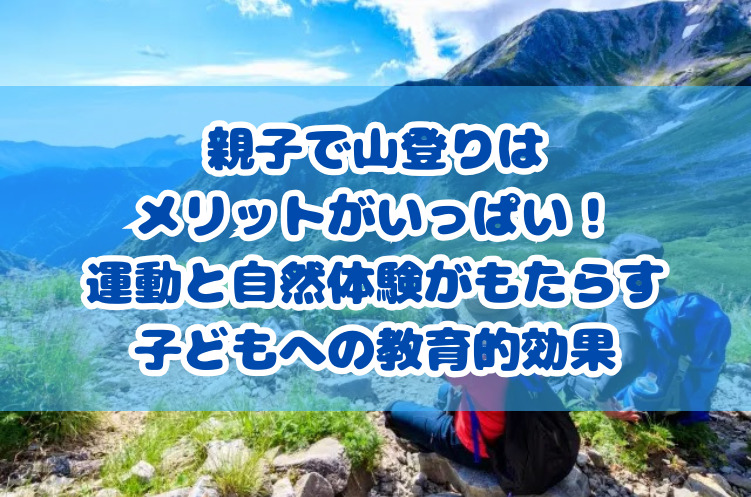備えておけば安心! 【子どもの年代別】準備しておきたい防災グッズ
更新日: 2025.07.08
投稿日: 2025.07.04
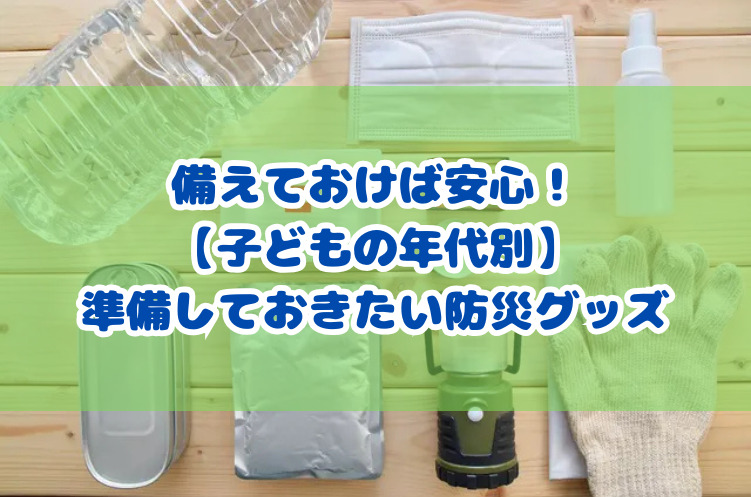
周囲を海に囲まれた島国で7割が森林、そして河川も多い日本は、世界でも有数の自然災害大国といわれています。
自然災害の被害に関するニュースが流れると、子育て世代は「子どもをどう守ったらいいのか?」「何を準備すべき?」と気持ちが焦りますよね。
災害は避けることができないので、私たちができる最良の対策は「防災準備」。
実際、防災グッズなどを準備して備えておくことで、生存率が高まるともいわれています。
今回は子どもの年代別に、用意しておきたい防災グッズを紹介します。
もくじ
子どもの年齢に関係なく備えておきたい基本防災グッズ

まずはどの家庭でも共通して用意しておくべき、基本的な防災グッズをおさえましょう。
最低で3日分、できれば1週間分用意できるとベストです。
・非常食(カンパン、アルファ米、缶詰など)
・簡易トイレ
・カセットコンロ
・モバイルバッテリーとケーブル
・現金(災害時はカードなどは利用不可なため)
・懐中電灯(予備電池も)
・携帯ラジオ(予備電池も)
・ティッシュペーパーとウェットティッシュ
・救急セットや薬
・マッチやライター
・カッターナイフ
・ビニール袋(大きいものは防寒にも使える)
・新聞紙
・防寒具(ダウンジャケットやブランケット、カイロなど)
都市部などでは避難所に入れず、自宅避難になる人が多くなると予想されています。
自宅で1週間ほど過ごすことを想定して、準備をしておきましょう。
赤ちゃん(0歳児)がいる場合

おむつや離乳食、抱っこ紐など、赤ちゃん用の準備品が増えます。
また赤ちゃんは免疫力が低いため、衛生面を強化する防災グッズも用意しておきましょう。
・ミルク、哺乳瓶
・抱っこ紐
・ベビーカー
・肌着、着替え
・おくるみ、バスタオル
・消毒グッズ、ウェットティッシュ
・ガーゼハンカチ
・お気に入りのおもちゃ
授乳スペースが確保できない場所でも授乳できるように、ケープなどがあるとさらに便利です。
避難する時はベビーカーではなく抱っこ紐を使い、さまざまなケースを想定して避難経路も確認しておきましょう。
乳幼児(1〜5歳児)がいる場合

自分で動けるようになり、自我が出てくるため、目が離せない乳幼児の時期。
子どものお気に入りのおもちゃなども、すぐ持ち出せるようにしておくといいでしょう。
幼稚園・保育園の頃になれば、自分専用の持ち出しリュックなどを用意すると、災害への意識づけになるかもしれません。
・着替え
・おもちゃ、絵本
・子ども用の食器
・消毒グッズ、ウェットティッシュ
・迷子札、連絡カード
お父さんとお母さんの名前は、万が一の時にも言えるように練習しておくといいでしょう。
4〜5歳になっても、抱っこ紐があるとスピーディに避難できることがあるので防災グッズの中には入れておくといいですね。
子どもを不安な気持ちにさせないために、大人がパニックになったり、取り乱したりしないようにしましょう。
小学生(6〜12歳児)がいる場合

学校でも防災訓練などが始まり、防災への意識が少しずつ身に付く時期です。
日頃から家族で災害時の話をするように心がけ、いざという時は「まずは自分の身の安全を第一に」「自分の防災リュックを持って避難する」など、大切なことを子どもに伝えておきましょう。
「学校で被災した時はどうするか」「お父さん・お母さんと会えなかったら、どこに行くか」など、連絡方法や行動指針を決めて共有しておくことも大切です。
・学習用品、本
・漫画、ゲームなど
・おこづかい(小銭程度)
防災時は子どもが自分でリュックを持ち出せるように、普段から中身や置き場所を確認しておくようにしましょう。
この頃になると、ストレスを感じても「心配をかけないように」「自分がわがままを言ってはいけない」などと抱え込む子も出てきます。
お父さん・お母さんは子どもの話をよく聞き、安心できるようなサポートを心がけましょう。
中学生(13〜15歳児)がいる場合

中学生以上になったら子ども用の防災リュックを用意し、災害用のグッズを準備しましょう。
非常時にはSNSで情報収集をしたり、安否確認などの役割をお願いするのもいいですね。
・ヘルメット、ヘッドライトなど(安全に避難するためのもの)
・軍手、ナイフ
・おこづかい
思春期にさしかかり、日頃は意思疎通が難しい時もあるかもしれませんが、災害時にはきっと大人さながらの役目を果たしてくれるはず。
災害時のストレスは大人よりも子どもに影響しやすいといわれています。
辛い気持ちを共有したり、話を聞いたり、ストレスケアも忘れないようにしましょう。
防災意識を日常に取り入れよう!

日頃から防災の意識があるか・無いかで、大きな差がついてしまう災害時。
日常生活においても、いくつか気を付けるポイントがあります。
○ 防災家族会議を開く
○ 非常時の連絡方法をマスター
○ 部屋の片付け
防災家族会議を開く
防災対策というと、「言わなくても分かっているはず」「そんなことわざわざ話し合わなくても…」と思う人もいるかもしれませんが、子どもは緊急時にどう行動していいかわからなくなってしまいます。
しかも子どもと防災準備をするとなると、「何をしたらいいかわからない」という人も多いはず。
そこでおすすめなのが、月に1回「防災家族会議」を開くこと。
会議といっても、皆が揃った「食事の席で話す」だけで十分です。
内容は…
・避難経路を確認する
・非常用持ち出し袋の中身を更新
・災害時の役割分担を決める
・住んでいる地域の災害について
簡単なことを話しておくだけで十分なので、子どもと知識や情報を共有しておきましょう。
非常時の連絡方法をマスター
子どもが小学校高学年や中学生になると、親と別々の行動も増えてきます。
そんな時、自分の無事を知らせたり、家族の現状を知るために、緊急連絡の方法を覚えておいた方が安心です。
災害伝言ダイアル(117)や災害用伝言板(web171)のほか、携帯電話会社の災害用伝言板があります。
災害用伝言ダイアルは、「伝言を録音する機能(登録)」と「伝言を聞く機能(確認)」に分かれます。
使い方は、
① 171に電話
② ガイダンスが流れたら「1」を押す
③ 連絡を取りたい人の電話番号を押す
④ 発信音の後に伝言を入れる(自分の名前と安否、どこにいるかなど)
① 171に電話
② ガイダンスが流れたら「2」を押す
③ 連絡を取りたい人の電話番号を押す
④ 再生されるメッセージを聞く
確認する電話番号は、家族内でそれぞれ決めておきましょう。
災害伝言ダイアルは、NTTが「非常時」と判断した時に使えるようになるので、普段は使えません。毎月1日に「体験利用日」があるので、操作に慣れるためにも試してみるといいですね。
部屋の片付け
災害は昼間に起こるとは限りません。
夜中、停電中に避難しなければいけなくなった時、物につまずいたり、子どものおもちゃを踏みつけたりしないように、寝室や部屋、廊下などは日頃から片付けておきましょう。
2024年1月1日に起きた能登半島地震では、亡くなった人の40%が家具の転倒や家屋倒壊などによる圧死でした。
倒れる可能性のある高い棚などは転倒防止の固定具をつけ、寝室には重い家具や背の高い家具は置かないようにしましょう。
準備することで守れる命がある!

親子で一緒にいられる時なら安心ですが、保育園や幼稚園、小学校に行っている間に被災する可能性もあります。
いつ・どこで被災するかわからない以上、親も子も防災の意識を持って心の準備をしておくことが大切です。
子ども自身が「命を守る行動」を取れるかどうか、冷静に対応できるかは、日頃の意識づけにかかっています。
「怖いから考えたくない」「そのうちやろう」と、準備を先延ばしにしていると、もっと怖い思いをすることになりかねません。
この機会に、子どもと一緒に防災グッズの準備を進めましょう。
・自然災害が多い日本では、子育て世代こそ防災グッズを用意しておこう。
・子どもは免疫力が低くストレスも受けやすいので、子どもの年代別に被災時の準備をしておくことが大事。
・家族で防災会議を開いたり、部屋を片付けておくことが、いざという時に役立つ。
(参考文献)
・学研 | 災害時に子どもを守る「防災グッズ」 年齢別に準備しておきたいグッズもあわせてご紹介
・三井住友海上 | 片付けで生存率が高まる!? もしものとき、あなたの家は大丈夫?
・