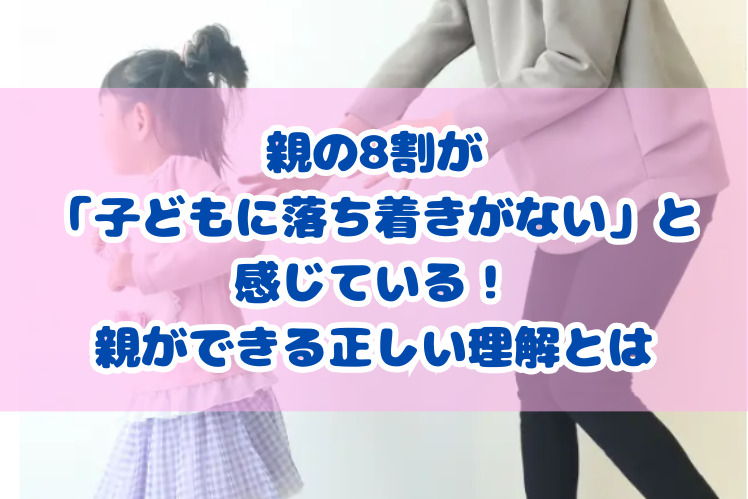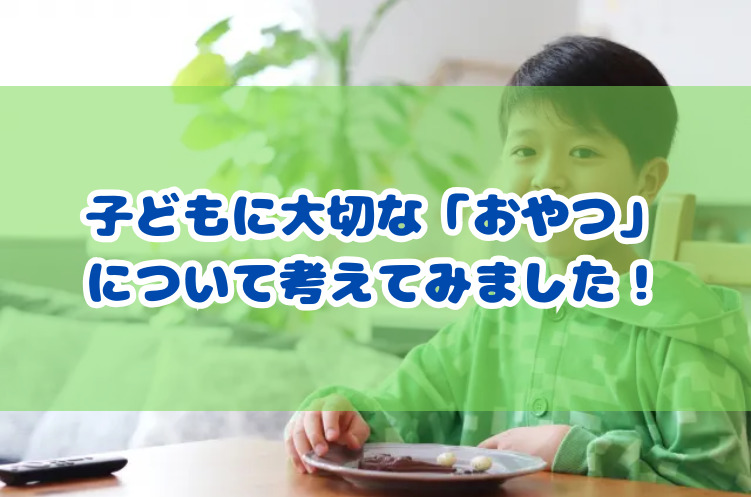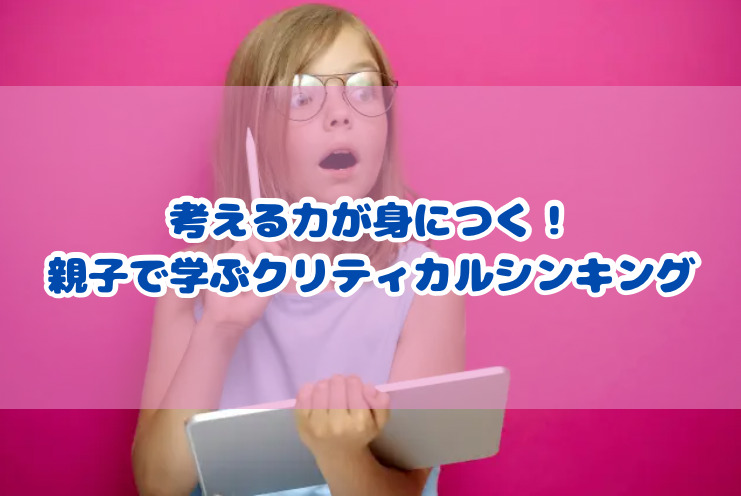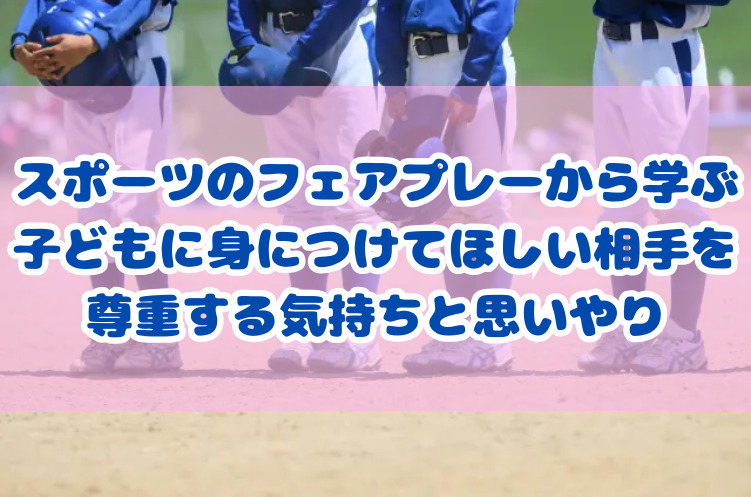子どもを伸ばす「よいストレス」とはなにか
更新日: 2025.05.14
投稿日: 2025.05.16
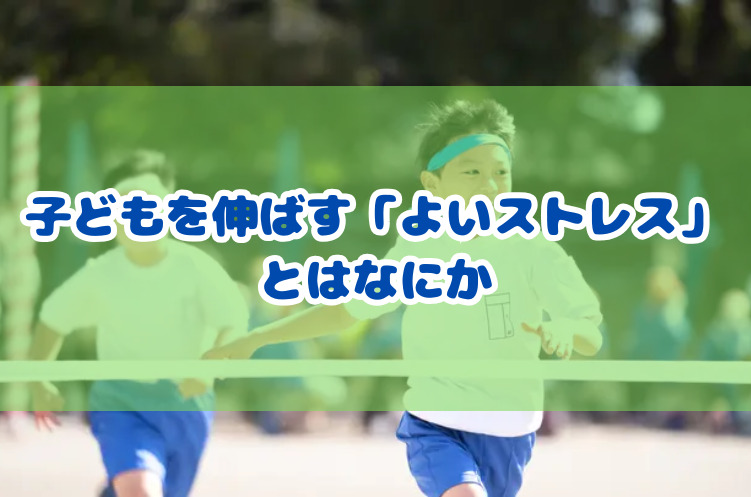
大人と同じように、子どももストレスを感じていることは、よく知られています。
ストレスと聞くと「プレッシャー」「心身に悪い影響がある」と考えてしまいがちですが、実はストレスにはよいストレスと悪いストレスがあるのを知っていますか。
今回はストレスのよい面について考えていきましょう。
もくじ
そもそもストレスってなに?

日常的に使う「ストレス」という言葉は、もともと物理学で物体に圧力をかけた時に生まれる「ひずみ」を表していたのだそうです。
そこからプレッシャーを感じたり、過度に緊張がかかることを「ストレス」と呼ぶようになりました。
しかしストレスには2種類あり、ほどよい緊張感をもたらす「よいストレス」と、子どもの心身に強いプレッシャーをかける「悪いストレス」があります。
心理学では、よいストレスのことを「eustress」、悪いストレスのことを「distress」と呼ぶそうです。
そもそも「お腹がすいた」「暑い(寒い)」といったものもストレスであり、これがないと「食事をとろう」「寒いから上着を着なきゃ」といった体を守る行動ができなくなってしまいます。
また「次の試合は勝ちたいから、練習を頑張る」「テストのために勉強するぞ!」といった気持ちも、「試合に勝つ」「テストで点を取る」といったストレスに対する反応。
つまり「よいストレス」は生きるために必要なもので、適度な緊張感があり、やる気をアップさせる力があるのです。
反対に悪いストレスは、過度なプレッシャーを受けて後ろ向きな気持ちになったり、自信を失ったり、気分が落ち込んだりしてしまいます。
私たちが日々「ストレス」と呼ぶものは、この「悪いストレス」を指していることが多いでしょう。
よいストレスは子どもを成長させる

人はストレスを感じると交感神経が活発になり、体温が上昇して、ストレスから逃れるため体が準備を始めます。
逆にストレスがまったくない状態が続くと、気温の変化に合わせて汗を出したり、鳥肌になるなどの体温調節機能が低下したり、暗示にかかりやすくなるなど、心身のバランスが崩れがちに…。
このような身体的なストレスは、古代から受け継がれてきた人が命を守るための警報システムのような役割を果たしているのです。
また
「ピアノの発表会の前に緊張する」
「試合の前にドキドキする」
というのも、プレッシャーというストレスです。
しかし、その緊張を乗り越えて「緊張したけどいつもどおりにピアノが弾けた」「ドキドキしたけど試合でよいパフォーマンスができた」という経験をすると、子どもは自信をつけ、ひとまわり大きく成長します。
つまりよいストレスには、
・やる気がアップする
・パフォーマンスが向上する
・自信がつく
など、子どもにはプラスに働くことが多いといわれています。
「プレッシャーを感じても乗り越えられる」という経験を重ねて、「自分はプレッシャーに強い」「よいプレッシャーなら時々経験する方がいいかも」というマインドに変化できれば、しなやかで強い心に育つでしょう。
悪いストレスを「よいストレス」に変える考え方

「子どもにはあまりストレスを感じてほしくない」
「なるべくストレスからわが子を遠ざけたい」
と親なら誰でも思いますよね。
しかし子どもが成長していくうえで、悪いストレスを感じる可能性はゼロにはなりません。
この「悪いストレス」も考え方やとらえ方を変えると、心身に受ける負荷を減らすことができます。
これはストレスから自分を守る方法なので、大人でも覚えておくといいですね。
・ ◯か×だけで答えを出さない
・ 「やらされ感」を減らす
・ 「ここまででOKライン」を決める
・ いいところを探す
・ 時には誰かのせいにしてみる
◯か×かだけで答えを出さない
「0か100か」「◯か×か」だけで極端な判断をすると、達成できなかった自分を許せず、自分で自分に悪いプレッシャーをかけてしまいます。
なにかの結果が出た時や日常生活で、「100点じゃないけど、頑張ったからよし」「完璧でなくてもOK」と、白か黒かではなくグレーの受け止め方ができるようになると、プレッシャーが減らせます。
友だちやきょうだいに対しても、よい「あいまいさ」で優しく接することができるようになるでしょう。
「やらされ感」を減らす
有名なネズミの実験で、自発的に輪の中を走ったネズミは長距離を走っても問題がなかったにも関わらず、自動で動かした輪の中を強制的に走らせると、ストレス反応が高くなるという結果が出たそうです。
つまり同じ行動でも、「自分から望んでする」のと「人からやらされる」のでは、かかるストレスに大きな差が出ることがわかっています。
しかし、「仕方なくでもやるべきこと」はありますよね。
ならば…
・「早くねなきゃ」→「明日、元気に起きられるぞ」
・「部屋の片付けしなきゃ」→「必要なものが早く見つかるかも」
と、プラスに転換する習慣をつけると「やらされ感」が減り、行動を起こすためのよいストレスになるでしょう。
「ここまででOKライン」を決める
完璧を求めると、必要以上にプレッシャーがかかり「もっと頑張らなきゃ」「失敗したら終わり」という思考にハマります。
「ここまでできたらOK」のラインを決めて、それが達成できたら大成功という考え方にすると、悪いストレスが軽減されるでしょう。
例えば、マラソンなら「完走したらOK」、スポーツの試合にも「出場できたらOK」、勉強も「前回より1点でも増えたらOK」。
目標を高く掲げすぎると、達成後の次の目標設定がどんどん苦しくなるので、少しずつステップを上がるようにしましょう。
いいところを探す
苦手な友だちを苦手なままにしておくと、その存在自体が大きなストレスになったり、嫌いな勉強も「嫌だな」と思いながら取り組むと、全然頭に入ってこなかったりします。
苦手意識は負のスパイラルに入って、本人がどんどん辛くなります。
「あの子は苦手だけど、この前消しゴムを貸してくれた」
「国語は嫌いだけど、絵本を読むのは好き」
など、一つだけでも「いいところ」「好きになれるところ」を探してみましょう。
よい面に注目するようになると、意外な突破口が開けたり、「イヤイヤ」だったものが楽しくなる可能性が出てきます。
時には誰かのせいにしてみる
責任感の強い子や真面目な子は、「失敗したらいけない」「悪いのは自分だ」と思いがちです。
時には「隣の子がくしゃみをしたから気が散った」「お気に入りの靴じゃなかったからできなかった」など、何か別の理由を当てはめてみてもいいかもしれません。
真摯に取り組んだり、反省する習慣はいいことですが、あまり度が過ぎるとマイナス思考に陥り負のストレスを感じすぎてしまいます。
「私はベストを尽くした」「これ以上は無理」と考えることも、時には必要です。
子どもの「よいストレス」を大人が「悪いストレス」にしないために

よいストレスは子どもの集中力を高め、自信とやる気をもたらします。
しかし本当は緊張感のあるよいストレスなのに、「もっと頑張れ」「失敗しないでね」「それじゃダメだ」などと周囲の大人が心無い言葉をかけたことで悪いストレスに変わってしまう可能性もあります。
また言葉に出さなくても、子どもに完璧を求めたり、結果を気にしすぎたりすると、子どもはより深刻なプレッシャーを感じてしまうでしょう。
発表会やスポーツの試合、注目される場面など、子どもにとってストレスを感じる場面は意外と多いもの。
日頃から「あなたは大丈夫」「いつも頑張ってるからできるよ」「信じてるよ」と、子どもを認めて肯定する言葉がけをすることで、子どもは自信を持ち「よいストレス」を前進する力に変えることができるでしょう。
何気ない言葉や態度で子どもの成長機会を奪ったり、よいストレスを「悪いストレス」に変化させないようにしたいですね。
・ストレスには「よいストレス」と「悪いストレス」がある。
・よいストレスはほどよい緊張感で集中力を高め、やる気をアップする力がある。
・悪いストレスの負荷を減らし、よいストレスに変化させるには、「やらされ感を減らす」「OKラインを決める」など、気持ちの転換が必要。
・大人の何気ない一言が、「よいストレス」を「悪いストレス」に変えてしまうことがある。
(参考文献)
・日経ビジネス |良いストレスと悪いストレス
・日本医療政策機構 | 子どものストレス
・日本経済新聞 | 心身がラクになる、「考え方のクセ」の直し方
・こどもまなびラボ | 子どもを伸ばす「良いストレス」と心身を追い込む「悪いストレス」の違いとは