小学生の友達関係、親が知っておくべき距離感とは?
更新日: 2025.05.21
投稿日: 2025.05.13

子どもが小学生になると、友達との関係が広がるぶん、親としては心配ですよね。
また、学年が上がるにつれて友達との付き合い方も変化していきます。
どこまで介入していいのか、どんな距離感で見守るのが良いのか、悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、小学生の友達関係における親子の距離感について、具体的な例を交えながら、くわしく紹介します。
子どもの成長を見守り、より良い友達関係を築けるよう参考にしてみてください。
もくじ
子どもの年齢によって遊び方も友達関係も変わってくる

子どもの遊びは心身の発達段階と深く結びついており、年齢が上がるにつれ、その内容も変化していきます。
保護者が子どもの遊びの変化を理解することは、成長に合わせた関わり方を考える上で、とても大切です。
以下、低学年、中学年、高学年で一般的に見られる子どもの遊びと友達関係について紹介します。
低学年
この時期は、ごっこ遊びや簡単なルールのある遊びが中心です。
⚫️ごっこ遊び:園時代の延長で、身近な大人の真似をしたりアニメやゲームの登場人物になりきったりして遊ぶ子が多いようです。
お店屋さんごっこ、お医者さんごっこ、家族ごっこなど、友達と役割を分担し、簡単なストーリーを作りながら遊ぶことを楽しみます。
⚫️簡単なルールのある遊び:集団で遊ぶ中で、じゃんけんや順番を守るなどの簡単なルールを理解し、それを守って遊ぶことを学びます。
鬼ごっこ、かくれんぼ、色鬼、ドッジボールなどが代表的です。
⚫️自然の中での遊び:公園でかけっこをしたり、虫を追いかけたり、落ち葉を集めたりと、自然に触れ合う遊びに夢中になることもあります。
住んでいる場所が近かったり、学校で席が隣だったり、親同士が親しかったりといった、物理的な距離の近さがきっかけで子どもたちは自然と仲良くなります。
保護者にとっても子どもの友達関係を把握しやすいと言えるでしょう。
中学年
中学年になると遊びの内容はより複雑化し、ルールのあるゲームやスポーツ、趣味的な活動へと広がります。
⚫️ルールのあるゲーム:戦略を立てたり相手の動きを読んだりする思考力を駆使しながら、より複雑なルールを持つカードゲーム、ボードゲームなどを友達同士で楽しむようになります。
⚫️スポーツ:サッカー、バスケットボール、野球などのチームスポーツや縄跳びなど、体を動かす遊びもますます活発になります。
⚫️趣味的な活動:自分の興味関心が高まる時期。漫画やアニメ、ゲームなどの共通の趣味を持つ友達と交流したり、工作や手芸、音楽などの個人的な趣味に没頭したりする子も出てきます。
⚫️秘密基地作り:公園の隅や空き地などで、友達と協力して秘密基地を作る遊びもこの時期によく見られます。
「ギャングエイジ」ともよばれる中学年になると、子どもたちは共通の趣味や気が合う仲間とグループを作り、一緒に遊ぶようになります。
自分たちだけのルールを作って共有することで、仲間意識や連帯感を深めていきます。
友達との絆が強くなる一方で、親や兄弟姉妹と過ごす時間が少しずつ少なくなり、人間関係が家庭の外へと広がり始める時期と言えるでしょう。
高学年
高学年になると、遊びはさらに多様化し、より高度なルールや作戦を必要とするもの、仲間との協力や役割分担が重要なものへと発展します。
⚫️本格的なスポーツ:スポーツスクールや地域のスポーツ少年団などで専門的な指導を受けながらスポーツに取り組む子は、一緒に頑張る仲間と遊ぶ機会が増えることが多いようです。
⚫️本格的な趣味の活動:共通の趣味を持つ友達同士で協力しあって成果物を発表したりなど、仲間と主体的に行動する子も増えてきます。
⚫️SNSやオンラインゲーム: スマートフォンやタブレットの普及に伴い、オンラインでの友達との交流が増えてくるのもこの時期です。
心身ともに大きく成長し、個性が際立ってくる高学年になると、子どもたちはより気の合う仲間とグループを形成するようになります。
また、中学受験をするかどうかといった進路選択も、友達関係に影響を与えることがあります。
この時期になると、子どもたちは保護者と過ごす時間よりも、友達と過ごす時間を大切にするようになり、親に何でも話すことが少なくなる傾向があります。
保護者からわが子の友達関係が見えにくくなり始めるのもこの頃です。
子どもの友達関係、親はどこまで踏み込む?

小学生の子どもの友達関係は、成長とともに変化していきます。
親としてどこまで関わるべきか悩むところですが、子どもの発達段階に合わせて、適切な距離感で関わることが大切です。ここでは、年代別の関わりについて解説します。
中学年くらいまで(低学年〜中学年)
この時期は、友達との関わりを通して課題解決力を学び始める大切な年代。
わが子がどんな友達と遊んでいるのかを把握し、安全な遊び場を提供するなど環境づくりを心がけましょう。
・ 順番を守る。
・ モノの貸し借りはしない。
などの基本的なルールやマナーを教えることも大切です。
もし友達との間で困ったことが起きた様子が見られたら、まずは優しく話を聞き、子ども自身がどうすれば良いかを一緒に考える姿勢を示しましょう。
子ども同士の小さな喧嘩や意見の衝突は、課題解決力を学ぶ上で必要な経験となります。
親がすぐに解決するのではなく、まずは子どもたち自身で話し合うように促しましょう。
また、子どものプライバシーを尊重し、友達関係を詮索しすぎないことも大切です。
中学年以降(中学年〜高学年)
中学年から高学年になると、子どもは自立心が強まり、友達との関係もより深く複雑になります。
また、親に干渉されることを嫌がるようになる子も増えてきます。
基本的には見守る姿勢が大切になりますが、普段からコミュニケーションを密にし、子どもが悩みを打ち明けやすい信頼関係を築いておくことが重要です。
低学年〜中学年と同様、友達関係について親が直接介入することは、よほどのことがない限り避けるべきです。
ただし、いじめなどの兆候が少しでも見られた場合は、適切なサポートを検討する必要があります。
その際も、まずは子どもの気持ちに寄り添い、頭ごなしに指示するのではなく、一緒に解決策を探る姿勢が大切です。
SNSやオンラインゲームの利用についても、一方的に禁止するのではなく、
・ 「夜⚪時以降はやらない」など利用終了時刻
・ 食事の時間はスマートフォンをさわらない
など、親子でルールを決めましょう。
子ども同士のトラブルにどこまで関わる? 子どものこんなサインに注意!

気の合う子同士でつながる中学年〜高学年の友達関係は、より深くなるからこそトラブルも発生しやすくなるものです。
加えて、子どもも保護者に相談することが少なくなるため、トラブルに気づくのが遅れないよう注意が必要です。
以下、気をつけたい子どものサインと対処法を紹介します。
モノのやり取りが増える
頻繁に何かをもらってきたりあげたりしている場合は、少し注意が必要です。
どんなやり取りをしているか、さりげなく聞いてみましょう。
スマホばかり気にするなど落ち着きがない
スマホを気にしていたり、通知が来るたびにそわそわしているようなら、LINEなどSNSで何かトラブルが起きているかもしれません。
スマホの使い方や友達とのやり取りについて、話を聞いてみましょう。
親と話したがらない、部屋に閉じこもりがちになる
急に口数が減ったり、自分の部屋に閉じこもることが多くなったりしたら、何か悩みを抱えているサインかもしれません。
無理に聞き出そうとせず、「何かあった?いつでも話してね」と声をかけて、安心できる雰囲気を作りましょう。
言葉づかいが極端に変わる
これまで使わなかったような言葉づかいをするようになった場合、特定の友達グループから影響を受けている可能性があります。
「最近、〇〇な言葉を使うようになったね」などと声をかけつつ、変化の理由をさりげなく聞いてみましょう。
体調不良を訴えることが増える
これまであまりなかった体調不良を頻繁に訴えるようになったら、精神的なストレスが原因かもしれません。
学校や友達関係で何か困っていることがないか、心配していることを伝えながら話を聞いてみましょう。
日頃からできる子どもとの関わり方

どの年代の子どもにも共通して大切なことは、友達とトラブルが起こったとき、子どもの気持ちに寄り添い、共感すること。
そして、親がすぐに解決策を押し付けるのではなく、子ども自身がどうしたいのか、どうすれば良いのかを一緒に考えることです。
家庭がいつでも安心して帰ってこられる場所であることが、子どもの心の支えとなります。
子どもの成長に合わせて適切な距離感を見つけ、温かく見守っていくことが、親の最も大切な役割と言えるでしょう。
友達とトラブルがあった時は、以下のような声かけが大切です。
「そうだったんだ。〇〇ちゃんはどんな気持ちだったかな?」(相手の気持ちを想像させる)
「あなたは本当はどうしたかったの?」(子ども自身の気持ちを聞く)
「どうすればよかったと思う?」(主体的な解決を促す)
「もしよかったら、一緒にどうしたらいいか考えてみようか?」(必要に応じてサポートする姿勢を見せる)
わが子が安心して親に相談できるような環境づくりを

子どもたちは、親の知らないところで、友達と時にはぶつかり合い、時には助け合いながら、生きていく上で大切な社会性や課題解決力を育んでいます。
だからこそ、親としてできることは、子どもたちの人間関係を温かく見守ることでしょう。
そのためにも、お子さんのプライバシーを尊重する姿勢は不可欠です。
その上で、誰とどんな時間を過ごしているのかを、さりげなく把握するように心がけましょう。
「何をしているか」という行動そのものよりも、「どんな友達と関わっているのか」を知ることで、子どもの成長をより深く理解できるはずです。
そして、わが子が安心して親に相談できるような環境づくりも大切にしましょう。
「いつもあなたの味方だよ」「あなたのチャレンジを応援しているからね」というメッセージをタイミングをみて伝え続けることで、困った時や悩んだ時に、きっと心を開いてくれるはずです。
親子の信頼関係があればこそ、子どもは自らの力で人間関係を学び、成長していくことができるでしょう。
・中学年~高学年にかけ、子どもの遊び方や友達関係は変化していく。
・友達づきあいの基本的なルールやマナーはしっかり教えよう。
・まずは子どもの気持ちに寄り添い、共感することが大切。
・子どものプライバシーを尊重しながらも親に相談しやすい環境をつくる。
参考文献)
「小学生の友達関係 親はどう関わる?」(出典:ココロコミュ)
「子どもの友だち関係について、保護者が押さえておくべきポイントとは?」(出典:ベネッセ教育情報)
「子どもの友達関係は年齢で変わる!小学校低学年~高学年までトラブルから守るための対処法」(出典:ベネッセ教育情報)



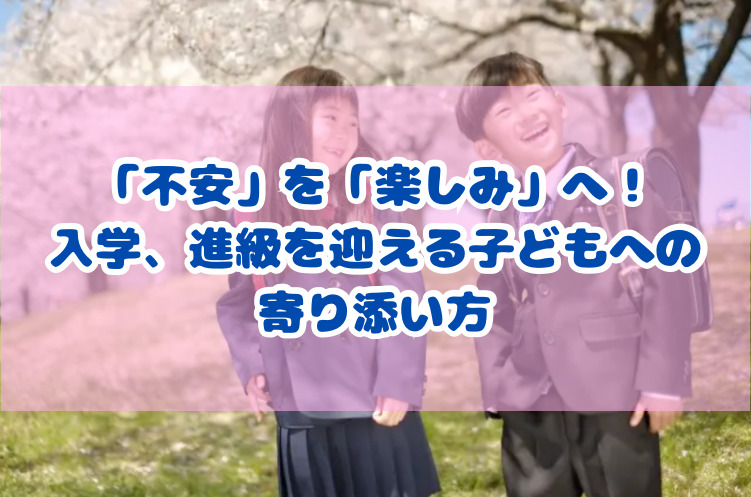
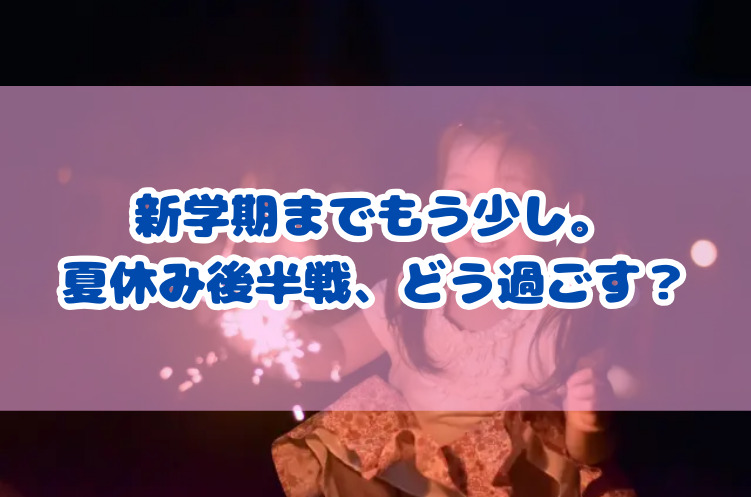
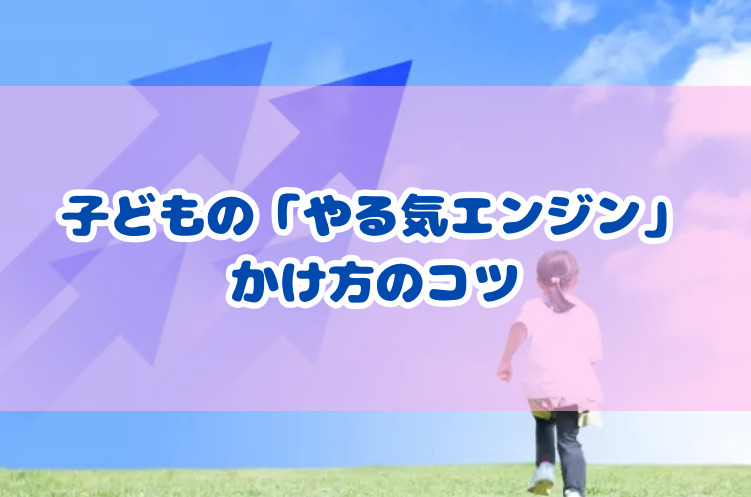
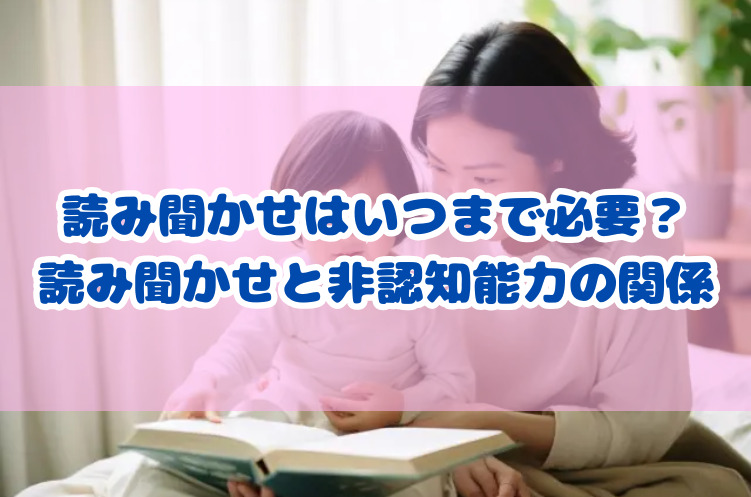
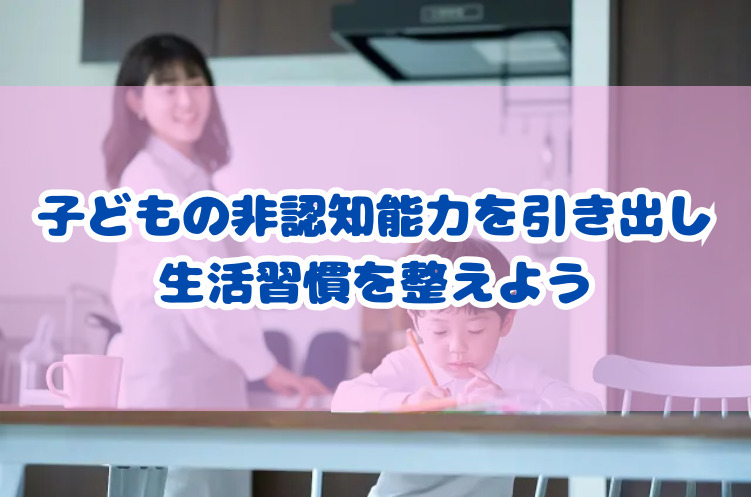










専門家コメント
フリーライター・エディターとして、育児、教育、暮らし、PTAの分野で取材、執筆活動を行っています。息子が所属していたスポーツ少年団(サッカー)では保護者代表をつとめ、子ども時代に親子でスポーツに関わることの大切さを実感しました。PTA活動にも数多く携わり、その経験をもとに『PTA広報誌づくりがウソのように楽しくラクになる本 』(厚有出版)などの著作もあります。「All About」子育て・PTA情報ガイド。2 児の母。