子どもが園、学校生活のことを話してくれない!そんな時の対処法5つ
更新日: 2025.04.03
投稿日: 2025.04.11

園や学校でどのように過ごしているのか、先生やお友達と楽しく関わることができているのかなど、子どもが園や学校生活のことを話してくれず、様子がわからずに困っている保護者も多いのではないでしょうか。
こちらから聞いても「忘れた」「知らない」などの1点ばりだと、不安になってしまいますよね。
しかし、コミュニケーションの方法を少し変えてみると、話してくれるようになることも多いものです。
家庭での親子のコミュニケーションは、非認知能力の大きな土台づくりにつながります。
子どもの園や学校の様子を知るために、子どもから園や学校での様子を聞くときのポイントを、「親子のコミュニケーション」の視点から紹介します。
もくじ
子どもが園、学校のことを話さない理由とは

園や学校から帰宅した子どもに、「今日は何してきたの?」と聞いても、「楽しかった!」のひと言だけ、あるいは「うーん、わからない」などのつれない返事をされることも多いと思います。
なぜ、子どもによっては、園や学校のことをあまり話さないのでしょうか。
その理由として考えらえるのは、以下の5つです。
園や学校生活を振り返る余裕がないから
園や学校で夢中で遊んだり、さまざまな勉強をしたり、先生や友だちと関わる子どもたちは、いろいろな体験、いろいろな感情がごちゃまぜの状態で帰宅することが多いため、帰宅してからしばらくは、自身を客観的に振り返って、人に話す心の余裕がない状態であることがあります。
親から聞かれても、何を答えて良いかわからない
「今日はなにがあったの?」「園(学校)どうだった?」などと漠然と聞かれても、幼い子どもにとっては質問の対象が広すぎて、何を答えて良いかわからない場合も考えられます。
その結果、「いろいろあった」「わかんない」など、漠然とした返事に至っていることもあります。
親からの質問を負担に感じているから
園や学校から帰宅してほっとしているときに、「今日は何してきたの?」と矢継ぎ早に聞かれることが毎日続くと、子どもは無意識のうちに「また聞かれた」「答えるのが面倒」などと感じているのかもしれません。
それが、素っ気ない答えにつながっていることもあります。
疲れているから
園や学校での活動は、子どもにとって想像以上に体力と精神力を使うものです。
特に、友達との複雑な関係や、先生とのやり取りなど、対人関係の悩みは大きな負担となります。
帰宅後は心身ともに疲れ果て、「何も話したくない」と感じている可能性があります。
おとなしい性格だから
全ての子どもが積極的に自分のことを話したがるわけではありません。
中には、おとなしい性格で自分の気持ちや出来事を話すのが苦手な子もいます。
園や学校であったことを話すのが苦手な子は、内向的な性格の子に多い傾向があります。
子どもが園や学校のことを話してくれない時に引き出す5つのコツ!

子どもに園や学校のことを聞きたいときは、親の関わり方が大切です。
以下、5つのことを心がけましょう。
答えを急かさない
子どもが帰宅したら、「おかえりー」の言葉で迎え、まずはリラックスする時間をもうけましょう。
一緒におやつを食べながらたわいもない話をし、「そういえば、今日は園でどんなことしたの?」など、自然な流れで聞くようにすると、子どもも心が落ち着き、話しやすい雰囲気になります。
「オウム返し」が効果的
話し言葉の一部をオウムのように繰り返すことを「オウム返し」といいます。
子どもが「楽しかった」とひと言言ってきたら「楽しかったのね」と返します。
すると、子どもは「聞いてくれている。共感してくれている」と感じ、話しやすくなります。
子どもが答えやすい質問を意識する
「今日は園でどんなことしたの?」ではなく、「園のお便りをみたら、最近粘土遊びを始めているようだけど、今日は何か作ったの?」、「今日の給食は何だった?」ではなく、「今日の給食のおかずは、お肉だった?お魚だった?」など、できるだけ具体的に質問することを意識すると子どもも答えやすくなり、その後の会話も続きやすくなります。
親が自分のことを話す
子どもに答えを求めるばかりでなく、親自身が、「今日ママね、⚫⚫したんだけど、それがすごく楽しかったよ」など、その日の出来事や嬉しかったことを話すようにすると、子どももそれに呼応するように「僕は(私は)、今日園で△△したよ!」と、自然な形で話してくれることもあります。
お風呂の時間や寝る前の時間に話す
お風呂の時間や寝る前は、親子でコミュニケーションがとれるひとときでもあります。
湯船につかりながら、絵本を読む前後に添い寝しながら1日の出来事を振り返るような時間を習慣的につくることで、園や学校のことを話しやすくなるでしょう。
それでも話してくれないとき、どうする?

上記の対応を心がけても、園や学校のことを話してくれないときは、以下の方法を検討しましょう。
園や学校の先生に相談する
園や学校の先生にわが子の性格や行動の特徴、家庭での様子などを伝え、連携して見守っていく体制を作りましょう。
園や学校に直接電話をする前に、まずはお便り帳や連絡帳に相談したい旨を記載し、回答を待つことをおすすめします。
電話では、先生が授業中などの可能性があり、落ち着いて話せない場合があります。
お便り帳や連絡帳に記載する際は、相談内容を簡潔にまとめ、先生が回答しやすいように配慮しましょう。
同じ園や学校に通う保護者に様子を聞く
同じ園や学校に通う子どもを持つ保護者との情報交換により、わが子の状況を多角的に把握することができます。
しかし、個人情報の取り扱いには十分注意が必要です。
他のお子さんの個人情報やプライバシーに関わることは、話さないようにしましょう。
また、得られた情報は鵜呑みにせず、あくまで参考程度にとどめることが大切です。
子育て支援センターなど専門機関に相談する
園や学校の先生に相談しても状況が改善しない場合や、より専門的なアドバイスが必要な場合は、子育て支援センターなどの専門機関に相談することも検討しましょう。
子育て支援センターでは、専門の相談員が、お子さんの発達や心理に関する相談に応じてくれます。また、必要に応じて、専門医や臨床心理士などの専門家を紹介してくれる場合もあります。
子どもの話を聞く環境づくりを

ここでは、子どもの話を聞く環境づくりのポイントについて、紹介します。
スマホを置いて目を合わせ、向き合う
お子さんの話を真剣に聞くためには、スマートフォンや他のデバイスを置いて目を合わせ、うなずきや相槌をしながら向き合うことが大切です。テレビを見ながら、スマートフォンをいじりながらなど、他のことをしながら聞く「ながら聴き」は避け、「ちゃんと聞いてもらえている」と感じられるよう、集中して聞く姿勢を示しましょう。
「いつでも話を聞くよ」などと折りにふれ伝える
子どもがすぐに話してくれなくても、焦らず「いつでもあなたの味方だよ」「どんなことでも話してね」と伝え、話したいときにいつでも受け止める準備があることを示しましょう。
言葉だけでなく普段からわが子に関心を持ち誠実に接することで、「自分の話を聞いてくれる」という安心感や信頼感を与えることが大切です。
日頃から、子どもの様子を観察する
子どもの様子を日頃から注意深く観察し、表情、行動、言葉遣いなどの小さな変化に気づくことで、気持ちや悩みに寄り添うことができます。
また、好きなことや興味のあることに積極的に関わり、一緒に遊んだり話をしたりすることで、より深く理解することができるでしょう。
家ではよく話すけど、園や学校では話さない…ということも

子どもが、家庭ではよく話すのに園や学校では話さないという状況は、いくつかの要因が考えられます。
まず、新しい環境、特に集団生活に慣れていない場合、不安や緊張から話せなくなることがあります。
先生や他の子どもたちとの関係がまだ築けていない場合も同様です。
また、いじめや人間関係のトラブルなど、学校や園でのストレスが原因で話せなくなることがあります。
さらに、学習面での困難を感じている場合も、自己表現を控えることがあります。
「家ではよく話すから大丈夫」と安心していても、園や学校で口数が少ない場合は、何らかのネガティブな原因が潜んでいることもあります。
個人面談の機会などで、わが子の様子をしっかり確認しましょう。
親子の会話を通してコミュニケーション能力を育もう

園や学校生活についてだけでなく、子どもの会話力を高めることは、非認知能力のひとつであるコミュニケーション能力の向上につながります。
会話力を高めるためにまず大切なことは、子どもの話に共感することです。
子どもが話したことに対し、「それは辛かったね」「大変だったね」などと共感することで、子どもは感情を落ち着かせることができ、安心して自分の気持ちを伝えることができるようになります。
また、仕事や家事で忙しい毎日だとは思いますが、以下を意識することで会話が生まれやすい環境を整えることができます。
・食事はいっしょにとる
・スキンシップをとる
・お手伝いしてくれた時などは、感謝の気持ちを伝える
子どもと実際に話すときは、以下を心がけましょう。
・子どもと目線を合わせ、相づちをうちながら聞く
・話をさえぎらない
・子どもの話を追求、評価しない
家庭での親子の会話は、非認知能力の大きな土台づくりにつながります。
ゆったりとした気持ちで、日々わが子との会話を楽しみましょう。
・子どもが園や学校のことを話さないのには、理由がある
・親の関わり方次第で「話しやすい雰囲気」を作ることができる
・子どもの会話力を高めることは、非認知能力の向上につながる
親としては、子どもが1日に園や学校でどうだったのか知りたいのは当たり前のことですが、親の思ったような返答が子どもから来ないことも多いですよね・・・
ですが、そんな時は、親自身が自分を振り返ってみましょう!
子どもの様子を見て、「今日も頑張ってきたみたいで疲れているから、落ち着いたタイミングで聞いてみよう!」「今日は確か体育の時間があったみたいだから体育どうだったか聞いてみよう!」など、
子どもに聞く前に、親自身が事前に子どもの様子や雰囲気を見て、どのように話しかけてあげるかを考えてみましょう!
(参考文献)
・非認知能力の育て方(ボーク重子:著 小学館)
・All About|子供とのコミュニケーションのコツ 会話術10のポイント(上野緑子:執筆)
・保育士くらぶ|年齢別 幼児期のコミュニケーションのポイント 能力の発達のためには?
・家men|【子どもの園生活】親に保育園・幼稚園での出来事を話してくれない?子どもと上手に会話するコツとは



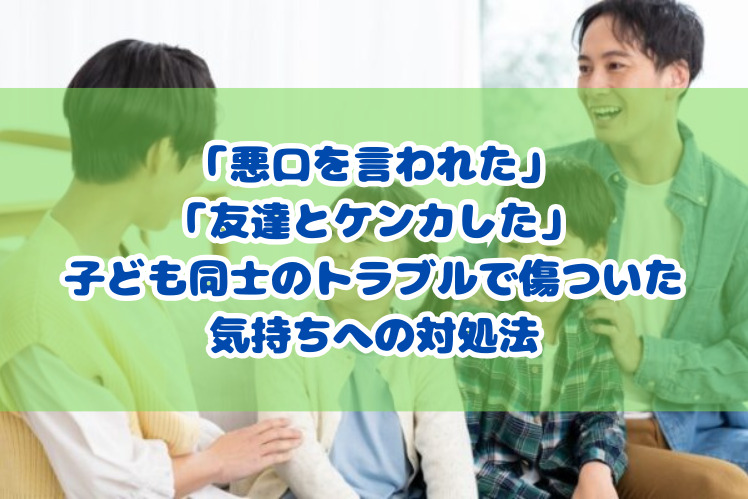
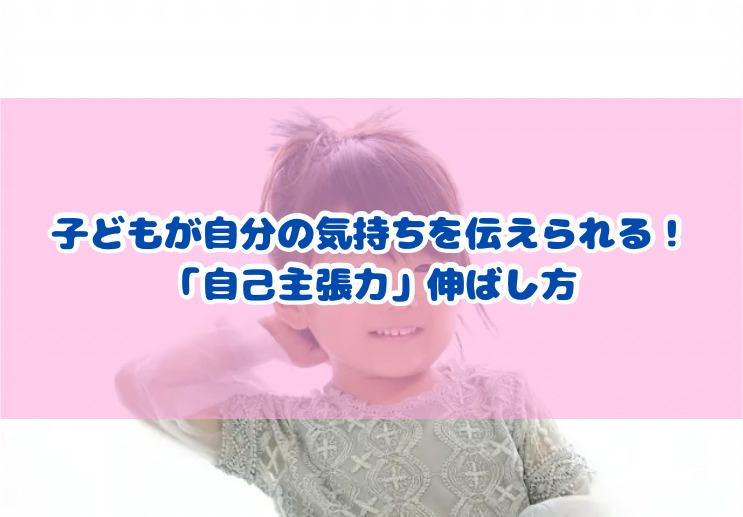
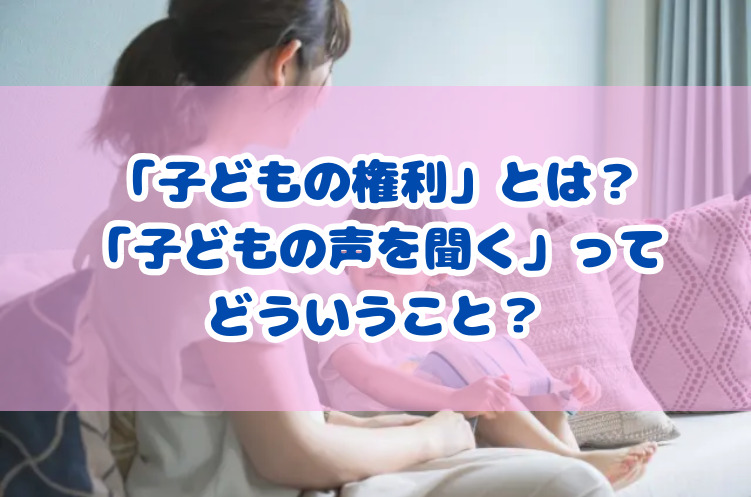
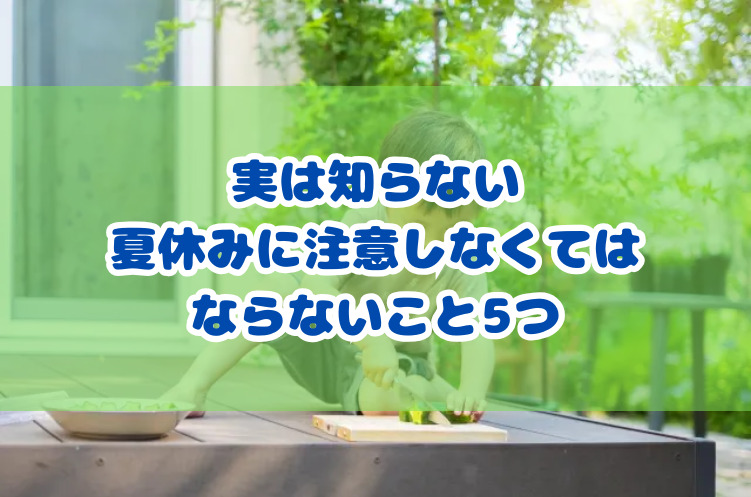
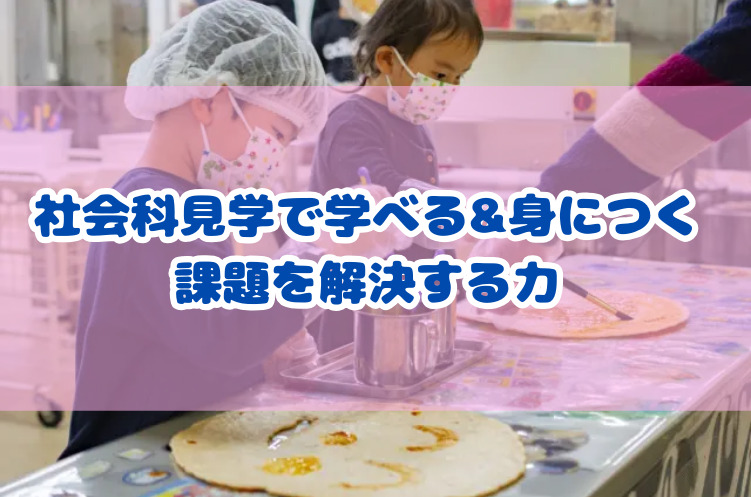










専門家コメント
フリーライター・エディターとして、育児、教育、暮らし、PTAの分野で取材、執筆活動を行っています。息子が所属していたスポーツ少年団(サッカー)では保護者代表をつとめ、子ども時代に親子でスポーツに関わることの大切さを実感しました。PTA活動にも数多く携わり、その経験をもとに『PTA広報誌づくりがウソのように楽しくラクになる本 』(厚有出版)などの著作もあります。「All About」子育て・PTA情報ガイド。2 児の母。