「不安」を「楽しみ!」へ!入学、進級を迎える子どもへの寄り添い方
更新日: 2025.04.02
投稿日: 2025.03.11
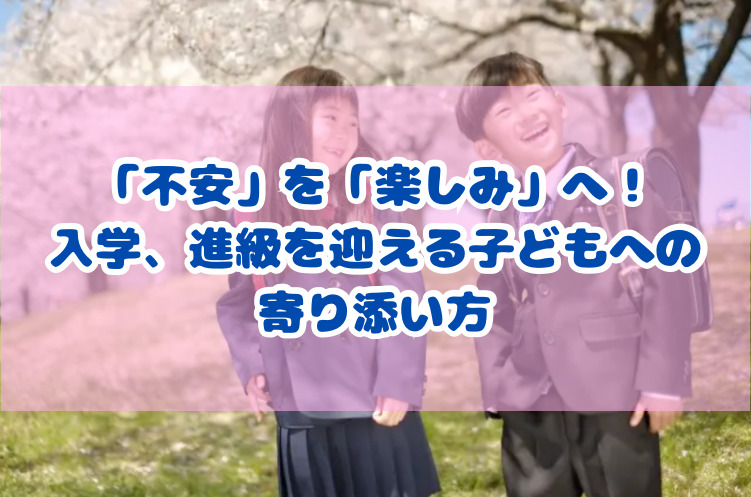
春は、入学、進級の季節です。
これまでの環境ががらりと変わることや、先生や周りの友達関係が変わることを受け入れられず、気持ちが不安定になる子も少なくありません。
この時期は、不安な気持ちから、だだをこねたり、ちょっとしたことで泣き出したりなど、いつもとは違う様子が見られることもあります。
「これまであんなに元気だったのに・・」など、親のほうも心配になってしまいますが、こんな時こそ大きく成長できるチャンスです。
入学、進級といった環境の変化を不安がる子どもに親はどう寄り添えばよいのか、非認知能力の視点も交えて、紹介します。
もくじ
入学、進級。この時期の子どもの気持ちは?

入学、進級。新学期の子どもたちは、新しい学校、新しい先生、新しい友達という慣れない環境のなかで、緊張したり、不安な気持ちを抱いたりしていることが多いものです。
帰宅すると、ほっと安心してゴロゴロしたり、それまでためこんでいた不機嫌な気持ちを親にぶつけてきたりなど、これまでとは異なる様子が見られることが多いでしょう。
この時期は、親のほうも、子どもに「早く新しい環境に慣れてほしい」という気持ちが先立ってしまいがちです。
つい、「お兄ちゃん(お姉ちゃん)になったのだから、しっかりしなさい!」「今日はどんなことしたの?」など、発破をかけたり質問攻めにしたりしてしまいますが、
まずは、「この時期の子どもたちは、緊張のせいで心身ともに疲れやすい」ということを、親が意識することが大切です。
園・学校生活が始まったばかりのこの時期は、「オン」(=園や学校)と「オフ」(=家庭)の切り替えがうまくできないことが多いものです。
帰宅したらゆっくり休み、子どものペースで過ごせる時間を意識してつくるように心がけましょう。
中には、新生活が始まっても、これまでと様子が変わらずのびのび過ごせる子もいます。
このような様子を目にすると、親は安心しますが、子どもなりになんらかのストレスは抱えているはずです。
子ども自身は気づいていないけれども、この時期、子どもが不安に感じがちな要素は、以下の3つです。
友達関係
新しいクラス、新しい学校、新しい先生..。入学した子どもにとって、新しい環境は未知の世界です。
「友達ができるかな?」「仲間外れにされないかな?」などのいった不安を感じやすくなります。
特に、人見知りの子、これまで仲の良かった友達と離れてしまう子は、不安を感じることがあります。
また、進級すると、周りの友達との関係性も変化します。
これまで仲が良かった友達と疎遠になったり、新しいグループができたりすることもあり、そうした変化に戸惑い不安を感じることがあります。
生活リズム
入学・進級すると、時間割や通学時間などが変わり、生活リズムが大きく変化します。
特に、朝早く起きるのが苦手な子や新しい環境に慣れるのに時間がかかる子は、生活リズムの変化にストレスを感じやすくなります。
学習面
入学してしばらくすると、授業が始まります。「どんなことを勉強するのだろう」と楽しみな気持ちがある反面、初めて経験する「学び」に対する漠然とした不安感を抱きがちです。
また、進級すると、学習内容が難しくなります。
「授業についていけるかな?」「宿題をちゃんとできるかな?」といった不安を感じやすくなることもあります。
新しい環境に不安がる子への寄り添い方のポイント5つ

入学、進級の時期、不安がる子への寄り添い方のポイントを5つ紹介します。
親子でのんびりする時間を意識してもつ
子どもは学校でさまざまな体験を重ね、さまざまな思いを胸に抱いて帰宅します。
親がその思いを受けとめられるような、親子でのんびりする時間を意識してもつようにしましょう。
いっしょにおやつを作ったり、本を読んだり、トランプなどで遊びながらリラックスタイムを過ごすことで子どもは安心し、本来の自分に戻ることができます。
外遊びや散歩などでリフレッシュ
疲れてぐったりしているときは無理に連れ出す必要はありませんが、少し余裕があるようなら外遊びや散歩などでリフレッシュを。
自然にふれる時間をもつことで子どもも気分転換になり、感情コントロール力が高まっていきます。
親以外の理解者をつくる
小学校に入学すると、子どもは親以外にも、学校や地域などいろいろな大人と関わる機会が増えていきます。
学校の先生、習い事の先生、地域の人などだれでもok。その子にとって、“親以外の理解者”をつくれると安心です。
子どもは世界が広がりますし、親は何かあったときに相談にのってもらえ、心の安定につながります。
子どもが学校生活のイメージを持てるような会話を心がける
学校の楽しい行事や得意なことが活かせる活動など、肯定的な情報を積極的に伝えつつ、「どんな先生かな?」「どんな授業があるのかな?」「どんなお友達ができるかな?」など、学校生活について具体的なイメージを持てるような会話を心がけましょう。
不安な気持ちを話しきたら、「そうだね、不安だよね」と共感し、受け止めることも大切です。
入学・進級後はいつも以上に子どもの様子を観察する
入学・進級後しばらくはいつも以上に子どもの様子に注意を払うことも大切です。
「表情が少し暗い」「体調を崩しているわけでもないのに食欲があまりない」「夜なかなか寝つけない」など普段と違う様子が見られたら、「何かあったのかな?」と、やさしく声をかけましょう。
入学・進級は、子どもだけでなく保護者にとっても環境が変わり、不安や心配を感じるのは当然のことです。
「うちの子だけなのではないか」「私がしっかりしないと」などと一人で抱え込まず、パートナーや家族、友人など、信頼できる人に相談しましょう。
同じように不安を感じている保護者も多いはずです。
学校や地域で開催される保護者会や懇親会などに参加し、情報交換をしたり、お互いの不安や悩みをわかち合ったりすることで、気持ちが軽くなることもあります。
新しい環境になじむスピードは、子どもによって大きく異なります。
すぐに友達ができる子もいれば、時間がかかる子もいます。
「早く友達を作りなさい」「もっと積極的に」などと焦らせるのではなく、わが子のペースを尊重し、温かく見守りたいですね。
学校生活で困っている様子があれば話を聞き、必要に応じて担任の先生に相談するなど、適切なサポートを心がけましょう。
この時期の子どもに必要なのは、「自己管理力」

入学、進級など、自分の周りの環境が大きる変わる時期の子どもにいちばん必要なのは、「自己管理力」です。
自己管理力は、非認知能力の一つとして知られており、文字どおり、「自分を律し、管理し、コントロールする能力」のことです。
決められた時間割に沿って集団で過ごすことが多い学校では、「相手やルールに合わせる」という機会が多いものです。
好きな科目の授業や休み時間に友達と過ごすなど楽しい時間がある反面、窮屈さを感じることもあります。
自己管理力の高い子は、新しい環境に慣れていくにつれ、状況に応じてルールやマナー、約束を守り、相手の気持ちを考えて行動できるようになっていきます。
「しっかり授業を聞き、休み時間にはリラックスする」といった過ごし方ができるようになり、時がたつにつれて落ち着いた学校生活が送れるようになるでしょう。
子どもの自己管理力の芽が育ってくるのは、自己主張の時期を過ぎた3歳ごろと言われています。
自己管理力は、子どもが小さいうちから、親が子どもの気持ちや言葉に共感したり、スキンシップを重ねたりなど、子どもの心が安定するような関わりをくり返していくことで、少しずつ育まれていきます。
また、自己管理力は、親だけでなく、園・学校の先生や友達、習い事の先生や友達などさまざま人との関わりによって、少しずつ発達していくものです。
さまざまな場面で心の中にわき上がる感情や衝動とうまく向き合い、調整し、自らが心地よい状態にもっていけるような“感情をコントロールする力”を幼児期から育んでおくことが、心地良い学校生活につながります。
・入学、進級の時期の子どもは緊張で疲れやすく、精神的にも不安定になることが多い
・自己管理力が育っていると、新しい環境にもなじみやすい
・入学、進級後しばらくは、親子でのんびりする時間を意識してつくる
新年度となる4月の季節は、子どもたちにとって、大人以上に気持ちの浮き沈みが激しい時期になることが分かりました。
特に、小学校へ入学する新1年生にとっては、幼稚園の時と比べて想像以上の大きな変化となります。
親は、子どもたちの気持ちの変化や様子の変化を読み取ることを意識しながらも、子どもの気持ちが安定する生活リズムで過ごせるように心がけましょう。
また小学生になったことで、自分をコントロールする「自己管理力」を身に付けることで、自分で生活リズムを作っていくことにも繋がります。
そのためには、親とのコミュニケーションやスキンシップが大切になっていくため、子どもたちに寄り添った関りをしてみましょう!
(参考文献)
・自分の気持ちとうまく向き合う子にするために(青木紀久子監修「PHPのびのび子育て」)
・ガマンの芽を摘むNG対応育てるOK対応(小笠原恵監修「PHPのびのび子育て」)
・親力講座 入学直後は疲れている・・家庭ではリラックスを 入学&新1年生のために(親野智可等著「親力」)


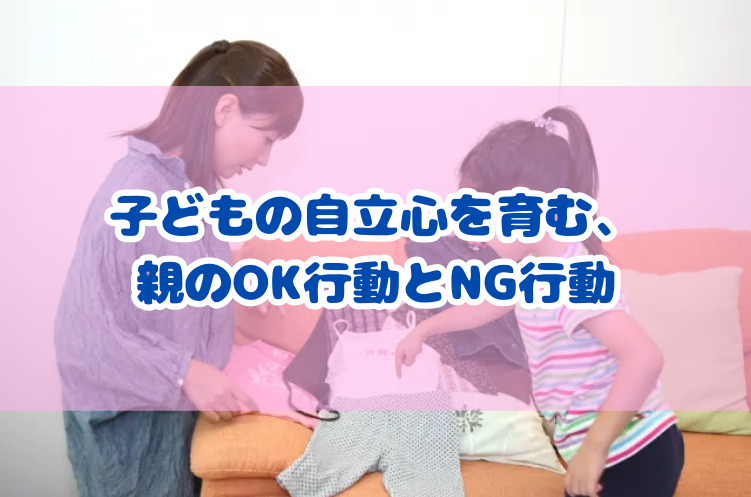


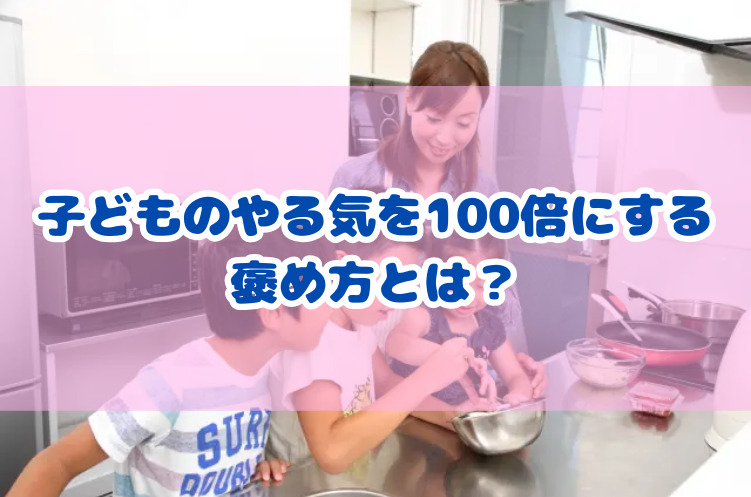
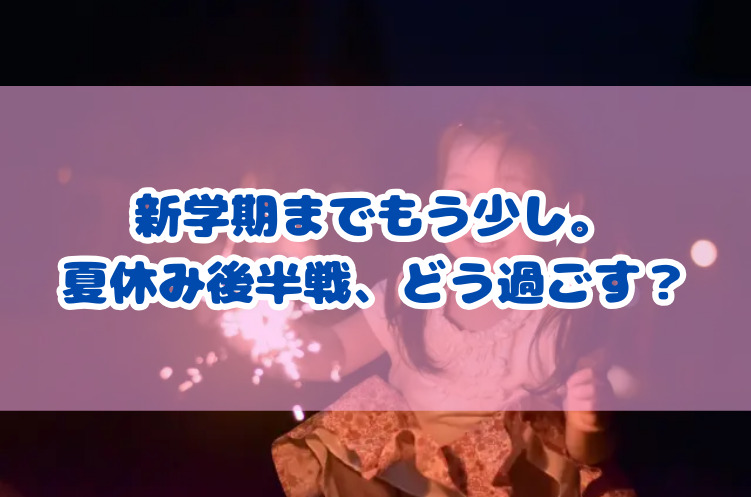

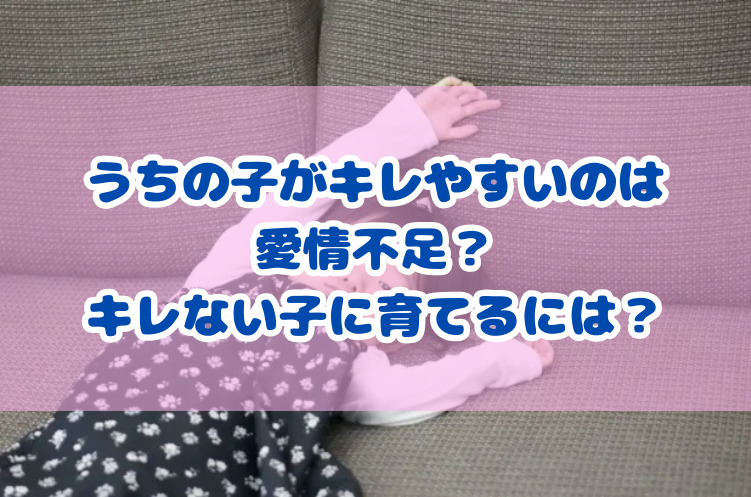
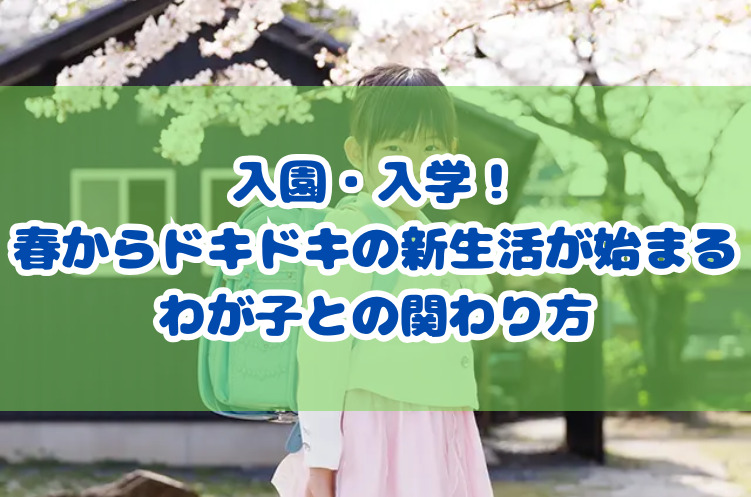










専門家コメント
フリーライター・エディターとして、育児、教育、暮らし、PTAの分野で取材、執筆活動を行っています。息子が所属していたスポーツ少年団(サッカー)では保護者代表をつとめ、子ども時代に親子でスポーツに関わることの大切さを実感しました。PTA活動にも数多く携わり、その経験をもとに『PTA広報誌づくりがウソのように楽しくラクになる本 』(厚有出版)などの著作もあります。「All About」子育て・PTA情報ガイド。2 児の母。