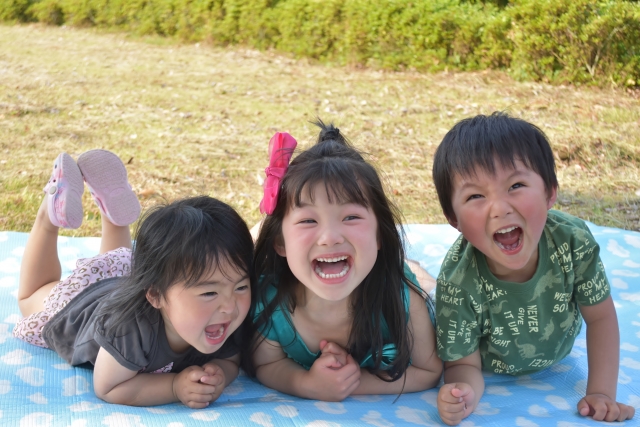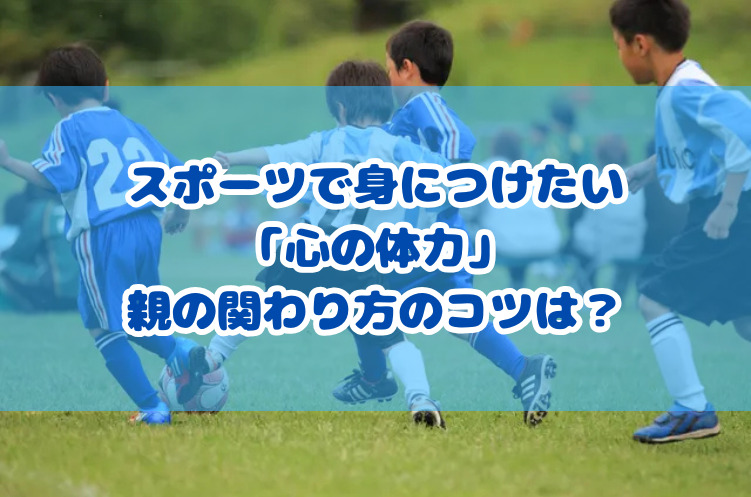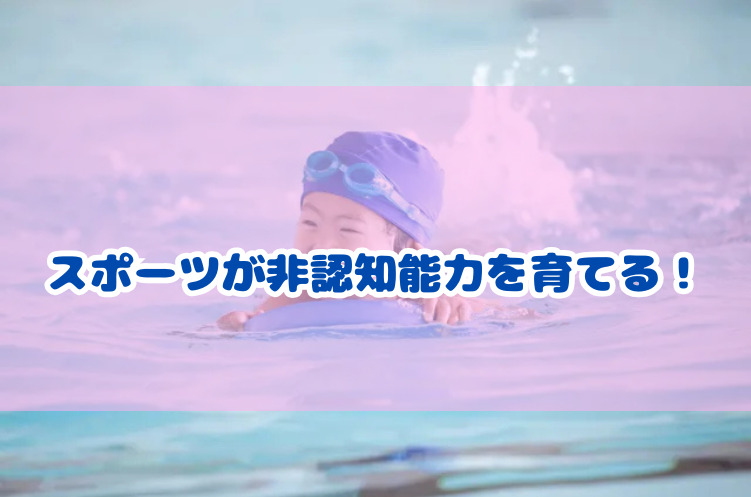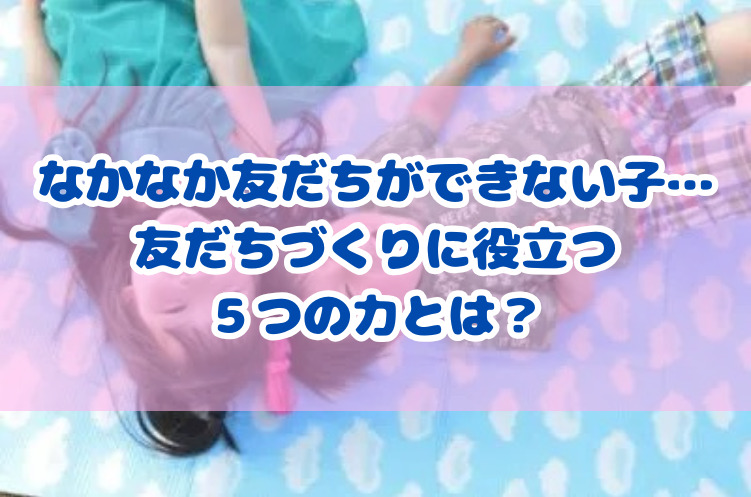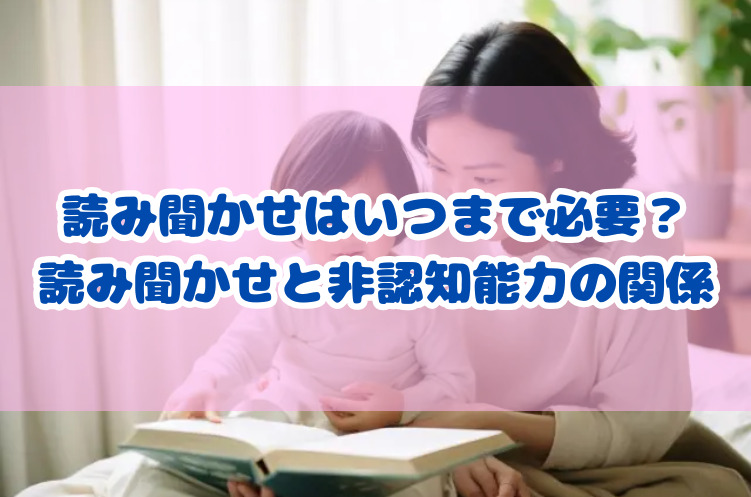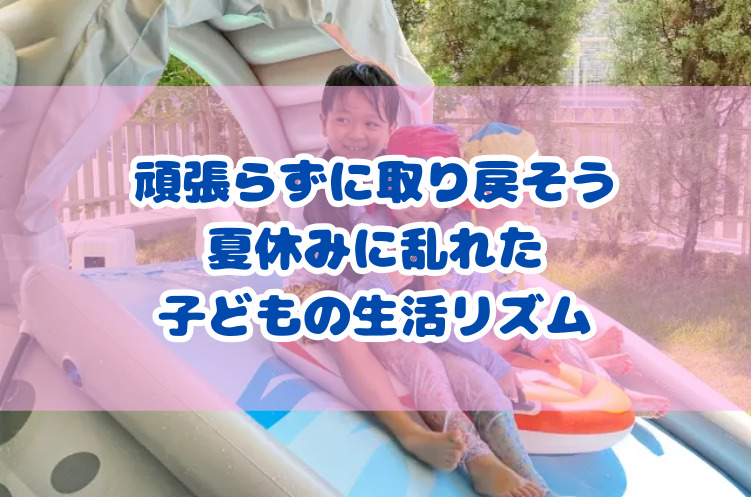今、必要な「共感力」をどう育てる?
更新日: 2025.11.14
投稿日: 2021.04.23
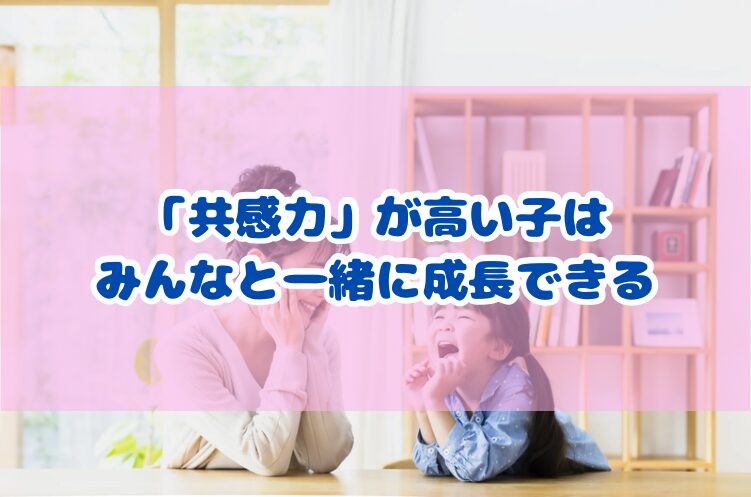
人と接するときの基本は、相手を理解し、相手を受け止め、自分の考えを述べることです。
そのために必要なのは、他人事を自分ごととして理解する「共感力」です。
当たり前ですが、小さな子どもの頃から、親や先生、友達など周りの人と上手に関わることはできません。
騒ぎすぎて周りから迷惑がられたり、いやな思いをしたり、嬉しい気持ちを味わったりなど試行錯誤を重ねながら共感力を学んでいきます。
共感力を育て、人を思いやれる子にするために親ができることについて、考えてみましょう。
もくじ
共感力とは、「相手を理解し思いやる力」

そもそも「共感力」とはなんでしょう。
共感力とは、ひと言で表すと、「相手を理解し思いやる力」です。
共感力には、周りに悲しそうな顔をしている友達がいたら「どうしたのだろう?」などと思う力に加え、「周りの人の気持ちと自分の気持ちは異なることもある」と受け入れる力、「感情には、喜びや悲しみ、怒りや不安だけでなくさまざまな種類がある」と知る力などが含まれます。
幼児期は、園や学校、習い事の教室など家庭とは異なる場で、楽しさや心細さ、友達関係での軋轢などたくさんの感情を体験し、「相手の気持ちを理解すること」を少しずつ身につけ始めていく時期です。
この時期は、自分が思ったり感じたりしたことを、一方的に表現することが中心となります。
相手の気持ちを理解するまでにいたらず、いざこざがおきたり友達に手が出てしまったりすることもあります。
しかし、成長するにつれ、自分の気持ちを言葉にしながらも相手の言葉に耳を傾けることができるようになり、小学生くらいになると、周りの人とのコミュニケーションが少しずつ上手になっていきます。
心の成長が著しい幼児期から学童期は、子どもの共感力を育むのにもっとも適した時期です。
この時期に共感力を育むことが、社会で豊かにたくましく生きる力であり、学校や塾などの学力テストでは計ることのできない力として世界的に注目されている「非認知能力」の育成につながります。
共感力を育てるには「学童期」がポイント!

6歳〜12歳の学童期は、「前頭前野」や「側頭葉」などの、自分以外の人の気持ちや見方を理解するための神経回路がもっとも育つ時期。
少しずつ「自分のことばかり考える時期」から卒業し、「自分とは違う考え方の人がいる」ことを理解して、相手の立場になってものごとを考えられるようになります。
それは脳が「共感すること」を覚える時期であり、この頃に共感の体験をたくさんさせることで、共感力が大きく育つのです。
同時に、友だちとの関わりが増え、意見が食い違ったり、友だち同士のケンカの仲裁をしたりといった、「相手に共感する」チャンスがぐんと増えます。
日々こうした経験を重ねることで、子どもは他者に共感することを覚えて、共感されることが「嬉しい」「気持ちが楽になる」と実体験します。
なぜ共感力が大事なの?

共感力は学校でも、社会に出た後でも、「人と関わり合うための土台」になるもの。
相手の気持ちを推しはかり、想像することは、人の気持ちを理解するうえで大切な力になります。
共感力があると、友だちや先生、習い事での仲間たちと付き合いやすくなり、トラブルが起こっても、話し合いなどで解決しやすくなるでしょう。
また共感力が育つことで、自分の気持ちを表現したり、反対に「悲しかったよね」「つらいね」などと相手の気持ちを代弁できるようになります。
そうすることで意思疎通の力がつき、さらに感情のコントロールも上手にできるようになります。
つまり「共感力」は、社会のなかで多くの人と関わり合いながら生きるうえで、大切な力といえます。
共感力が育まれると…

共感力が身につくと、子どもにはどんな変化があるのでしょうか。
◯ 人間関係がスムーズになる
◯ 人から信用・信頼されるようになる
◯ 話し合いで解決できるようになる
◯ リーダーシップが育つ
◯ ストレスに強くなる
人間関係がスムーズになる
相手の気持ちに共感できるようになると、思いやりのある行動ができるようになります。
思いやりのある人には安心して付き合えるようになるため、人間関係がスムーズになるでしょう。
また共感力が身につくと、「相手の気持ちを想像する」ことができるので、ものごとを第三者的に冷静に見られるようになります。
このように共感力は、周囲の人たちと円滑なコミュニケーションを生むのです。
人から信用・信頼されるようになる
共感力が高い人は、相手の気持ちに寄り添う言動が多くなるので、相手は「自分の気持ちが理解された」と安心します。
また相手を尊重できるので、誠実さや公平さが伝わり、信用されるようになるでしょう。
共感力が身につくと、「相手とつながる力」が強くなり、周囲の人との信頼関係が構築しやすくなります。
話し合いで解決できるようになる
共感力が身につくと、相手の立場に立った言動ができるようになり、互いの違いを認められるようになります。
感情的にならずに相手の話を聞くので、相手も安心して本音を話せるようになるでしょう。
するとさまざまな問題も話し合いで解決できるようになり、ケンカや争いが起こりにくくなります。
共感力は、平和的な解決を導く力になるのです。
リーダーシップが育つ
リーダーシップは強い力でグングンと人を引っ張る力だと思われがちですが、実は周囲の人たちを巻き込み、「人がついてくる力」。
命令や指示をして周囲を動かすのではなく、相手を理解し、安心感を与えて「この人と一緒に頑張ろう」という気持ちにさせるのが本来のリーダーシップです。
共感力があると、自然に周囲に人が集まり、リーダー的な存在になることも多いでしょう。
共感力が強い人がいると、いつのまにか意見や方向性がまとまるようになります。
ストレスに強くなる
共感力が身についていると、自分の「疲れてるな」「無理してる」という気持ちにも気づきやすくなります。
また周囲との関係もよい状態なので、相談したり、本音を話したりする人間関係もできているはず。
また家族にも相談しやすい雰囲気ができているので、ストレスを抱え込まずに済みます。
共感力がある子の特徴とは?

生まれつき共感力が高い子もいれば、成長するうちに自然と身につける子もいます。
共感力のある子には、どんな特徴があるのでしょうか。
人の話をよく聞く
共感力のある子は、相手がなにを感じて、何を言おうとしているのかを、理解しようとします。
そのため人の話を最後までよく聞き、じっくりと考える傾向があります。
感情的になりにくく、思いやりのある心のやわらかな子どもであるといえます。
争いごとを避ける
共感力が高い子は、人が安心して過ごせる雰囲気、調和した場を好みます。
相手の「痛み」や「怒り」を理解する力が強い分、ギスギスした空気には敏感だからです。
争いごとや言い争いなどもできるだけ避け、相手の気持ちを大切にしようとするでしょう。
気持ちが優しく、争いごとを避けようとして、自分の気持ちを押さえ過ぎてしまうことがあるので、親がフォローをしてあげたいですね。
人を傷つけない言動
相手の気持ちに共感する気持ちが強いので、人を傷つけたり、嫌な気持ちにさせるような言動はあまりしません。
少し言い過ぎたかな…という場面でも、すぐにフォローしたり、「ごめんね」が言えたり、その場の雰囲気を整えるでしょう。
共感力の高い子は想像力があるので、「自分が言われたら嫌なことは人に言わない」を徹底できるのです。
子どもの共感力を育むために親が意識したいこと
わが子の共感力を、無理なく自分らしく育んでいくには、親はどのように関われば良いのでしょうか?
ポイントを4つ、紹介します。
子どもが自分の気持ちに気づけるような働きかけをする
人の気持ちを理解するためには、まず最初に、自分の気持ちを理解できるようになることが大切です。
なぜなら、私たちは常に、「自分だったらどのように感じるか」を手がかりにして、相手の気持ちを想像するからです。
子どもが自分の気持ちに気づけるようにするためには、周りからの「そういうときって、こんな気持ちになるよね」という言葉や「そうだね、わかるよ」という働きかけが大切です。
日常のさまざまな場面で、子どもに対し、「⚫⚫️ができるようになって嬉しいね」「くやしくて思わず怒っちゃったんだね」など、「気持ち」を表す言葉を意識して使うことで、子どもは自分の気持ちを十分感じることができ、相手を思いやれるようになっていきます。
ネガティブな感情を否定せず、受け入れる
嫌なことをされると腹がたって、「ちきしょう!」という言葉を発したり、悲しいことがあると、わんわん泣いたりなど、さまざまな行動で表してます。
子どもがネガティブな感情を表すと、親はつい「そんなことでいちいち怒らないの!」「泣くのをやめなさい!」などと言ってしまいがちです。
しかし、嫌なことをされて腹が立ったり、悲しいときに涙が出てきたりするのは、自然なことです。
「いやなことをされて、くやしかったんだね」「⚫⚫⚫で悲しかったんだね」など、子どものネガティブな感情を否定せず、受け入れてあげましょう。
親が「共感する姿」を見せる
共感力が高い子を育むには、「教える」よりも、お手本を見せるのが近道。
子どもの話を聞いたり、テレビなどを見ている時などに、「◯◯ちゃんは、こんな気持ちだったのかもね」「この人は辛かっただろうな」と相手の気持ちを想像する姿を見せましょう。
共感する力は、能力ではなく「習慣」です。
普段から相手の気持ちはもちろん、自分の気持ちにも寄り添って、それを伝えるようにしましょう。
家庭内で共感する習慣があれば、子どもも自然と相手の気持ちに寄り添う言動ができるようになるでしょう。
子どもの話は最後までゆっくり聞く
忙しいと「要点を言って」「何が言いたいの?」などと、子どもの話をつい急かしてしましますね。
子どもは語彙が少なく、全体を俯瞰して見るのが不得意なため、要領を得ない話し方をしてしまうこともあるでしょう。
しかし子どもの中から出てくる言葉を待って、さえぎらずに最後まで聞いてもらえると、子どもはとても安心します。
そして今度は「相手の話も聞こう」と思えるようになり、相手の気持ちに共感することができるようになります。
共感力アップにつながる! 家庭でのおすすめ習慣

子どもの共感力アップにつながる、家庭でのおすすめ習慣を紹介します。
読み聞かせで登場人物の気持ちを親子で話し合う
絵本や児童文学の読みきかせのあと、「⚪⚪⚪のとき、主人公はどんな気持ちでいたと思う?」など、親子で登場人物の気持ちを想像しながら話し合ってみましょう。
子どもの考えを否定せず、「なるほど、△△ちゃんはそう思ったんだね。ママは️️️〇〇だと思うよ」など、対話を楽しみながら、相手の気持ちを想像するスキルを育んでいきましょう。
ごっこ遊びを楽しむ
おままごとで赤ちゃんのお世話をするお母さんになったり、学校ごっこで先生役になったりなど、ごっこ遊びを楽しむことは、異なる立場の人の気持ちを理解する助けになります。
日々の会話の中で、親自身も自分の気持ちを表現するよう意識する
子どもがお手伝いしてくれたら「ママ、⚪⚪ちゃんがお手伝いしてくれて嬉しいよ」「お片づけの約束守ってくれなくて悲しいな」など、子どもとの会話の中で、なるべく親自身の気持ちを表現するよう心がけましょう。
昨今、心理学者や教育学者の間でも、「子ども時代に共感力を育むことがいじめ防止につながる」という声が高まりつつあります。
また、高い共感力を持つ人は社会性にすぐれ、学業や仕事面においても成果を発揮しやすいと言われています。
非認知能力にもつながる共感力を、親子で育んでいきましょう。
子どもの共感力を高めるには、親が子どもに共感することが大切

子どもは教えたことよりも、親の行動の真似をします。
つまり子どもの共感力を高めたければ、親が家族や友人たちに共感する姿を見せるのが一番よい方法です。
言い合いになった時でも、「あなたは今、こういう気持ち?」など、相手の心に寄り添う。
黙っている子どもに対して、「話したくない時もあるよね」と共感する。
など、一度立ち止まって、俯瞰して相手を見る習慣を家庭内で持ってみましょう。
子どもの共感力は短期間ではやしなわれません。
毎日の小さな共感の積み重ねで子どもを共感力の高い、しなやかで気持ちのやわらかな人に育てたいですね。
・共感力とは相手を思いやる力で、主に幼児期から学童期に育まれる
・子どもが自分の気持ちに気づけるような働きかけを意識する
・子どもの共感力を育てるには、親が共感する姿を見せるのが近道
・読み聞かせやごっこ遊びで共感力を育もう
共感力を育むことは、社会に出た時に人と関わっていく中で、絶対に必要不可欠な力であり、非常に重要な力であることが分かりました。
またこの共感力を子どものうちから育むことで、大人になった時に相手の気持ちや思いをより深く想像し、感じることができるようになります。
共感力を育むためには、子どもが小さなうちから、○○をしたら人はどのような思いをするのかを大人が言葉で伝えることが大切です。
他の人の立場に立ち、常に○○をしたら、〇〇をされたら、どの様な気持ちになるかを考え、想像するような環境をたくさん作っていってあげましょう!
(参考文献)
・個性をのばしながら、人とうまく関われる子に(袰岩奈々監修・PHPのびのび子育て)
・All About|思いやりを育てる・・大人が子供に教える共感力を育むヒント(長岡真意子執筆)
・いじめっ子を育てない方法:共感の初期のルーツ(マイア・サラヴィッツ執筆・TIME)
・子育て&教育ひと言コラム 伸芽’Sクラブ|子どもの共感力とは思いやり。子どもの思いやりを育てるには何が重要
・コノバス|子どもの共感力はどうやって育つ?思いやりのある子が育つ3つのポイント
・こそだてまっぷ|【思いやりのある子になってほしい!】共感力はどう育てる?