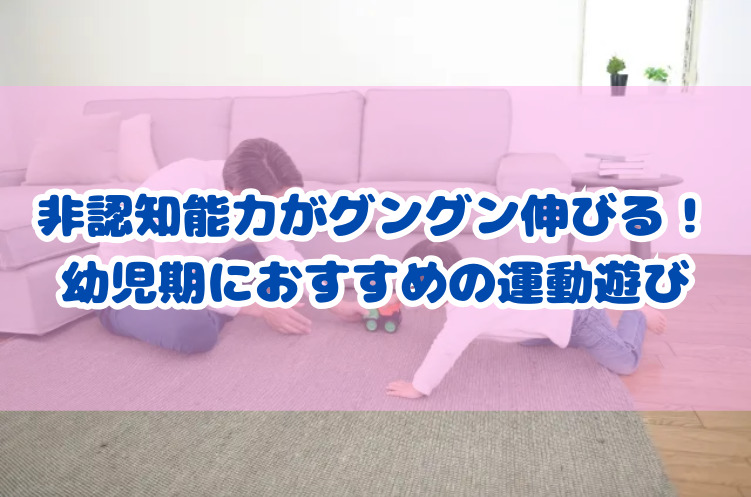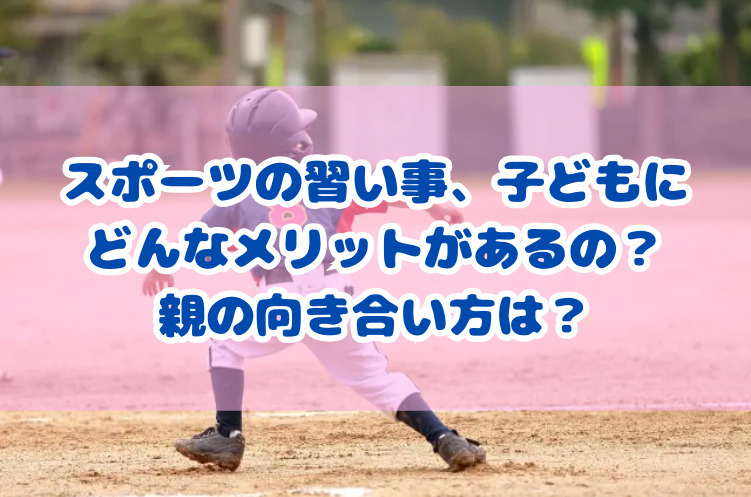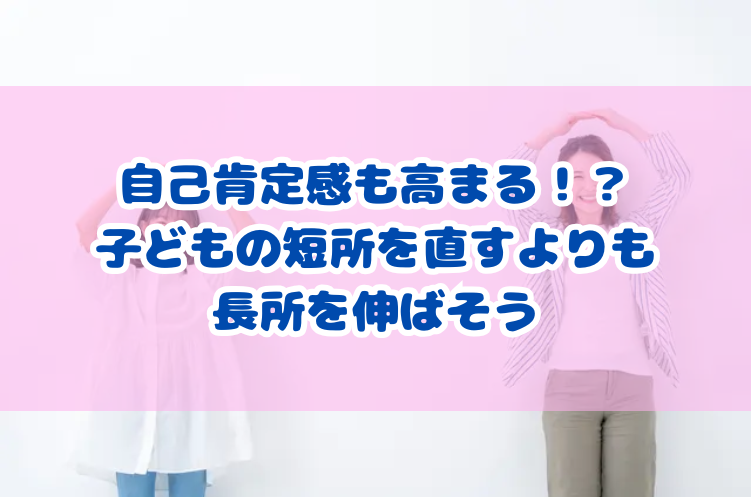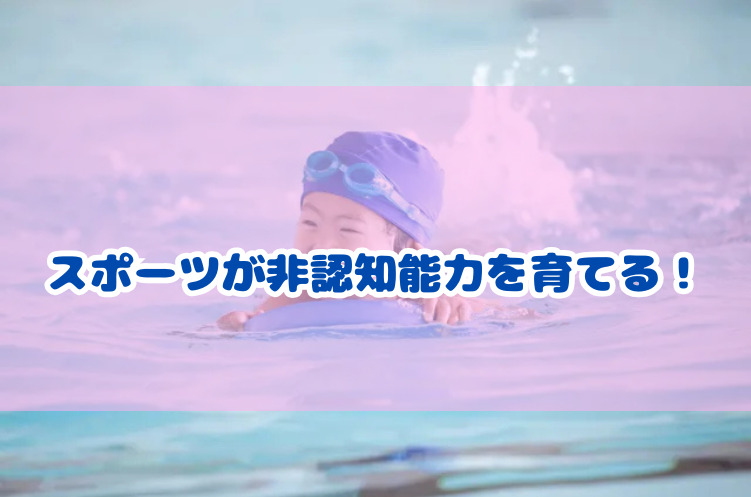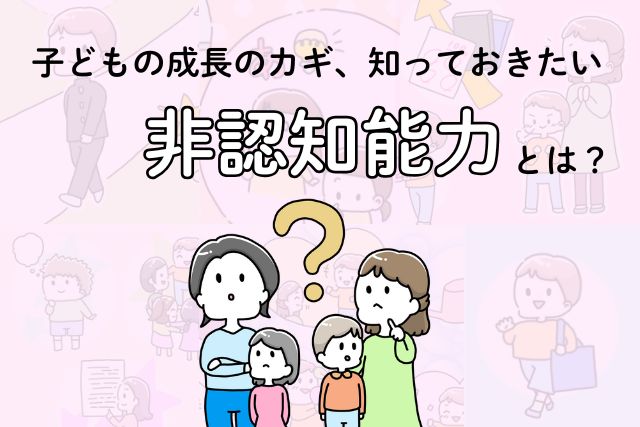“運動する子”と“しない子”でこんなに違う!非認知能力を育むスポーツの力
更新日: 2025.10.20
投稿日: 2025.10.17
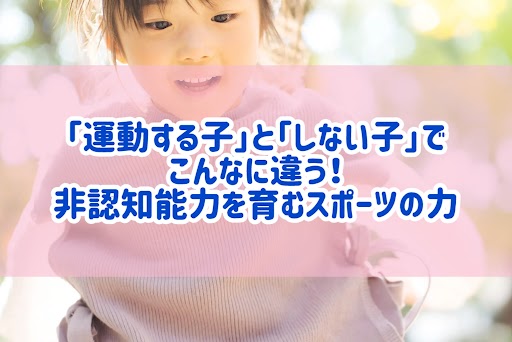
子どもの頃から運動やスポーツに親しむことで、体の発達だけでなく、脳の成長を促すことや人間関係、コミュニケーションがスムーズになることがわかっています。
公園や広場で遊ぶこともよい運動になりますが、スポーツの習い事をするのもおすすめです。
その理由は、
・協調性やルールを学べる
・身体の使い方の基本が身に付く
などのメリットがたくさんあるからです。
また同時に、これからの時代を生き抜くために必要な「非認知能力」も、運動によって育まれます。
運動と非認知能力の関係について、考えていきましょう。
もくじ
思い切り体を動かすことで、心身の回復力が増す

自尊心、自己肯定感など「自分に関する力」と、協調性、共感する力、思いやりなど「人と関わる力」などからなる非認知能力は、いわば、「心の土台」となるものです。
乳幼児期に非認知能力を育み、心の土台をしっかり作っていれば、その後も着々と積み上げていくことができます。
この時期の子どもは、面白い遊びを発見すると、集中します。
自分が好きな遊び、興味をもった遊びにとことん集中することで、主体性や意欲といった非認知能力が身についていきます。
さまざまな失敗を経験しながらも、その遊びに「一生懸命取り組む」という体験を重ねることも大切です。
また外での運動遊びは、どんなことを、どの程度したら危ないのかを知ることができ、自分の身体能力を理解できるようになります。
それを全身で感じることによって、自分にとっての「限界」がわかるようになり、危険を予測して回避する力やリスクに対応する方法を自然と身につけるでしょう。
運動をする子としない子では、どんな違いが生まれるの?

近年、教育や運動生理学の分野でも、運動する子としない子には、多くの点で違いがあることがわかっています。
ではその両者にどのような差が生まれるのでしょうか。
◯ 体の成長
◯ 脳の成長
◯ メンタルの強さ
◯ 社会性
◯ 自己肯定感
体の成長
体がもっとも育つ幼児期から小学生の時期に運動すると、神経と筋肉の連携がうまく取れるようになり、思ったように体を動かすことができるようになるといわれます。
また体を動かすことで、骨密度が高まり、筋肉のバランスも整います。
この年齢はプレゴールデンエイジ・ゴールデンエイジにあたり、運動が神経発達に大きく影響するため、その後の人生の運動能力を大きく左右するでしょう。
反対に、この時期に運動をしないと姿勢や体幹が不安定になりやすく、体を動かすことに苦手意識が生まれてしまうかもしれません。
脳の成長
運動をすることで脳への血流が促進され、酸素や栄養がたっぷり供給されることで、脳の働きが活発になるといわれます。
特に神経細胞の結びつきが強まり、アメリカの研究では定期的に運動する小学生のテスト中の集中力持続時間は、運動しない子に比べて20%も長いという研究結果もあるほどです。
運動は単に体を動かすことではなく、「脳も一緒に育てている」のです。
運動やスポーツの習慣がないと、脳への血流増加の機会が少なくなるため、脳が活性化するチャンスが減ってしまうことになります。
メンタルの強さ
運動中には、心を安定させる物質「セロトニン」や、幸福ホルモンといわれる「エンドルフィン」などの脳内物質が分泌されやすくなります。
また運動することでストレス解消になり、一般的にスポーツをする子は気持ちの切り替えが早いというデータもあります。
一方で、運動不足の子はイライラや不安を感じやすいという文科省の調査結果があるほど、運動やスポーツは子どものメンタルに影響を及ぼします。
運動をすることで、体だけでなく子どもの「心」も育つのです。
社会性
社会性とひとことで言っても、コミュニケーション力や思いやり、あいさつ、規律や順番を守る、協調性など、さまざまな非認知能力が必要になってきます。
スポーツをすることで、これらの力が少しずつ、体験を通して自然と身につきます。
しかも「こうしなさい」と強制されるのではなく、仲間や指導者との関係を通じて自ら「こうしたほうがいいかな」「こうしよう!」と自主的に考えるようになります。
社会で生き抜く力は、その後の学校生活や社会生活でも役に立ちます。
自己肯定感
スポーツをすることで、試合に勝ったり、出来なかったことができるようになったり、仲間と気持ちを共有できたり…さまざまな経験をするでしょう。
その経験が、「楽しい」「自分にはできる」「信頼できる仲間がいる」といった気持ちにつながり、自己肯定感や自己効力感が高まります。
運動経験が少ないと、成功体験を積むチャンスがあまりなく、「自分には無理かも…」「できない」「難しそう」と挑戦する気持ちが削がれ、自己肯定感が育つ機会が減少してしまうかもしれません。
自己肯定感を感じるには、「できた!」という経験が何よりも大切になります。
運動遊びが非認知能力を高める

近年、スマートフォンやゲームの普及などの影響により体を動かす機会が減り、「子どもの運動能力は低下傾向にある」といわれています。
休みの日など、保護者が自ら「子どもといっしょに楽しもう」という気持ちで運動遊びをすることで、子どもの運動不足を解消するだけでなく、非認知能力を育むことができます。
なかでも昔ながらの運動遊びは足腰を鍛えることができ、判断力や問題解決能力なども鍛えることができます。
公園などで少人数でできる遊びを紹介します。
・鬼ごっこ
鬼から逃げるために走り回る「鬼ごっこ」は、想像以上にハードな運動遊びです。
走り込むことで瞬発力や筋力、空間認知力などの運動能力も、格段にアップするでしょう。
同時に、状況を判断する力や社会性などの非認知能力も鍛えることができます。
・ボール蹴り
公園でボールを蹴り合うだけでも、バランス感覚や体幹、重心のコントロールなどを鍛えられます。
特に幼児期〜小学校低学年の子にとっては、「片足で立って体を保ち、ボールを蹴る」という一連の動きが、神経系の発達を促すよいトレーニングになります。
親子でボール蹴りを楽しむうちに、判断力や協調性がやしなわれ、「自分もできる」と自己肯定感を感じることができるでしょう。
・ドロケイ
鬼ごっこの応用編でもある「ドロケイ」は、泥棒と警察のチームに分かれて遊ぶ、これもまたランニング要素の多い運動遊びです。
チームごとに作戦を決めて戦うため、チームワークや戦略的思考も同時に鍛えることができるでしょう。
また自然と役割分担が決まり、責任感やリーダーシップなども芽生えるはずです。
・かくれんぼ
「どこに隠れたら見つからないかな」と考えて、探されるまでドキドキする気持ち、そして「見つかった!」という安心感など、さまざまな感情を味わえるスリルのあるかくれんぼ。
その「緊張」と「緩和」から、思考力や相手への信頼感などを感じられます。
同時に、空間認知能力や想像力、考える力などをやしなうことができます。
・ 縄跳び・ゴム跳び
縄跳びやゴム跳びは、体幹や持久力、下半身の筋力、心肺機能、リズム感などを同時に鍛えられる、とても効率的な運動遊びです。
友だち同士や親子で楽しむこともでき、一人でコツコツと練習することもできます。
目標を設定して頑張ることや、粘り強さを身につけることもできるでしょう。
どれもシンプルな運動遊びですが、運動能力のみならず、さまざまな非認知能力を身につけることができます。
スポーツ体験で「社会性」という非認知能力を身につける

スポーツ体験は、「非認知能力」の育成には欠かせないといわれています。
子どもはスポーツ体験により、「勝ち」「負け」を経験し、嬉しさや悔しい思いをしっかり味わいます。
負けることによって、「なぜ負けてしまったのか」「勝つためにはどうしたらよいのか」などを考え、「失敗から立ち上がる」という、とても大切な非認知能力も身につけることができます。
また、スポーツには、ルールがあります。
スポーツを通じて「ルールを守ろう」とする姿勢を身につけることは、社会性を身につけるうえで、非常に効果が高いのです。
興味のあるスポーツに出会い、スクールなどに通うと、指導者による適切な指導で上達を感じることができるという利点もあるでしょう。
ではスポーツで、どんな非認知能力を身につけられるのででしょうか。
・サッカー
一瞬ごとに状況が変わっていくサッカーは、パスや役割変更を繰り返しながら、仲間との連携が必須なスポーツ。
自分が「こうしたい」と思う気持ちを抑えながら、仲間と一緒にゴールを目指すので、感情のコントロールや自己抑制力を学べるでしょう。
またチームとしての協調性、チームワーク、リーダーシップや先読みの力がやしなわれるといわれます。
・野球
野球は守備位置も一人一人決まっており、「打つ」「走る」「攻撃する」「守る」という競技の流れも決まっています。
だからこそ、「次はこうしよう」とチームとして戦略的に試合を進めることができます。
ピッチャー対バッターで緊張感や集中力を体験し、自分のポジションで役割を果たす責任感を学ぶことができるでしょう。
また選手として出ていなくても、ベンチから仲間に声をかけたり、応援をするサポートの大切さも体験できます。
・バスケットボール
コート内で、ディフェンスとオフェンスがくるくると入れ替わるバスケットは、素早い判断や気持ちの切り替えが必要なスポーツ。
次々と状況が変わるため、試合の流れを読む力や鋭い感覚がやしなわれるでしょう。
またフリースローなどで注目を集める場面でのプレーを積み重ねることで、プレッシャーにも強くなります。
・チアリーディング
チアリーディングはメンバーで動きを合わせ、お互い支え合いながら演技をするスポーツ。
決して一人では成り立たず、「メンバー全員でつくりあげる」という協働性や、仲間の意見を調整しながら進めるコミュニケーション力がやしなわれます。
また、「応援する」「元気づける」という役割もあるため、サポートをする気持ちや応援する気持ちもしっかり育ちます。
仲間への信頼や助け合いの気持ちと、表現力を同時に学べるスポーツです。
武道
柔道・剣道・空手などの武道は、「心・技・体」に重きを置いた伝統的な競技。
試合で勝ってもはしゃいだりせず、最後まで平常心で相手への礼節を重んじます。
それは相手を「敵」ではなく、自分を高めてくれる「修行相手」と考える武道の精神が基本になっているから。
武道を続けることで、集中力や精神力、平常心を保つこと、また相手への敬意を払うという社会性が身につきます。
このように、スポーツをすることで「昨日までできなかったことができた!」「今度は⚪⚪に挑戦したい!」といった自尊心や自己肯定感、挑戦する力が育ちます。
そのスポーツを長期間かけてやり抜くことで忍耐力が育まれ、練習を繰り返すことで、自分と向き合いながら取り組んでいく勤勉性も養われます。
子どもが好きな運動遊びやスポーツに出会ったら、とことん楽しめる環境をつくり、応援してあげましょう。
スポーツで社会性やチャレンジ精神を育もう!

子どもは家族で運動遊びをしたり、ボール遊びをするのは大好きです。
遊びのなかで見つけた「これをやってみたい」「このスポーツを習いたい」という感覚を、ぜひ大切にしましょう。
スポーツで育まれるのは、「体力」や「筋力」「ルールなどの知識」だけではありません。
仲間と切磋琢磨して励むことで、共感力や責任感、コミュニケーション力、失敗しても立ち上がるレジリエンスを自然に身につけます。
子どもの「やりたい」という気持ちこそが、それらの力を身につける近道です。
親が見守りながら、子どもの「チャレンジしたい」という気持ちを尊重しましょう。
・思い切り体を動かすことで、心身の回復力が増す
・「鬼ごっこ」などの運動遊びは足腰を鍛えるだけでなくさまざまな非認知能力を養う
・スポーツ体験により、社会性、自己肯定感、協調性、思いやりなどが育つ
スポーツや運動を行うことは、多くの非認知能力を育んでくれることが分かりました。
普段の遊びの中やスポーツスクールといった様々な環境で身に付けることができ、一番大切なことは、それらを楽しむことです。
子どもたちが楽しめる環境を親が応援し、作ることで、非認知能力を伸ばすことができます。
(参考文献)
・非認知能力の育て方(著・ボーク重子 小学館)
・足をいちばん鍛える遊び(監修・瀬戸口清文 edu 小学館)
・MEROS|非認知能力を鍛える運動遊びを紹介(著・赤堀達也)