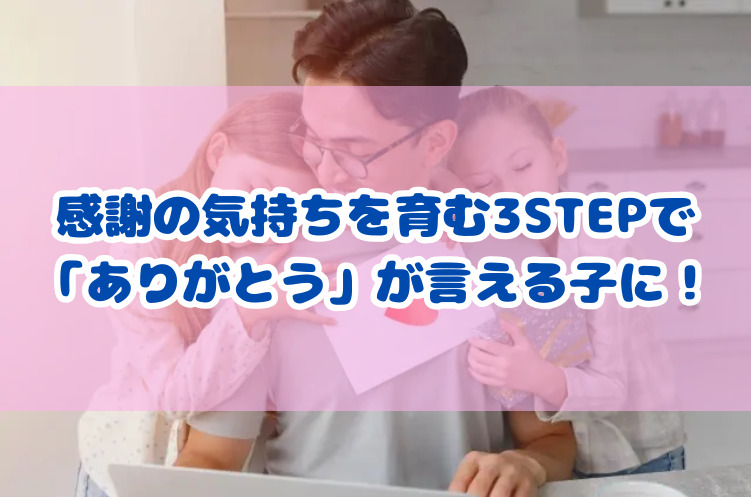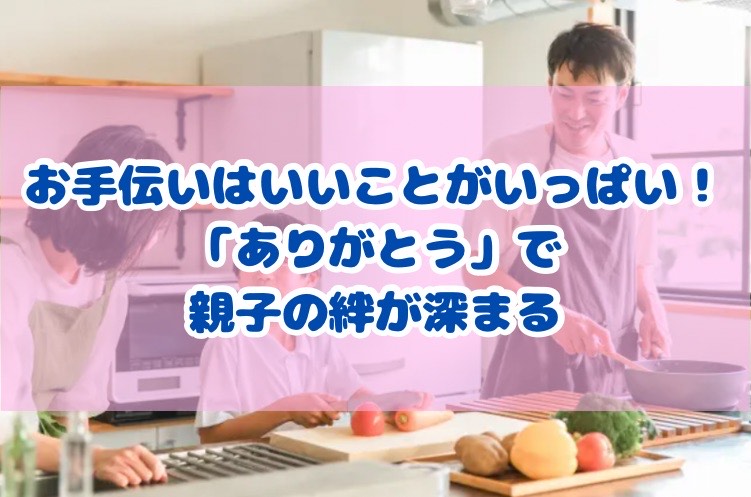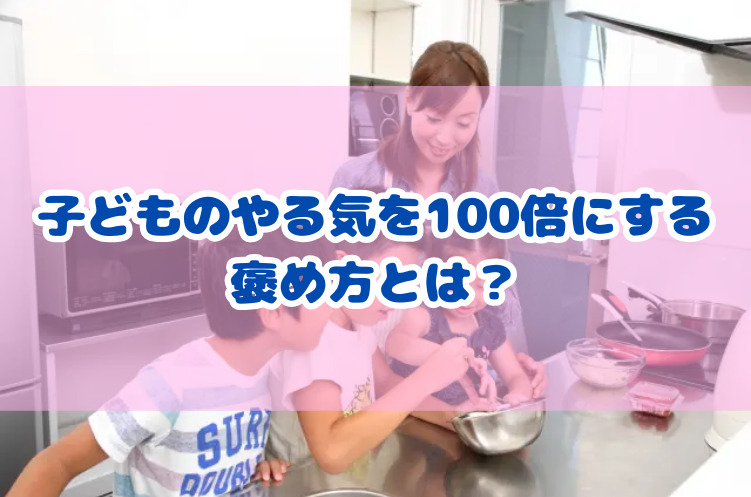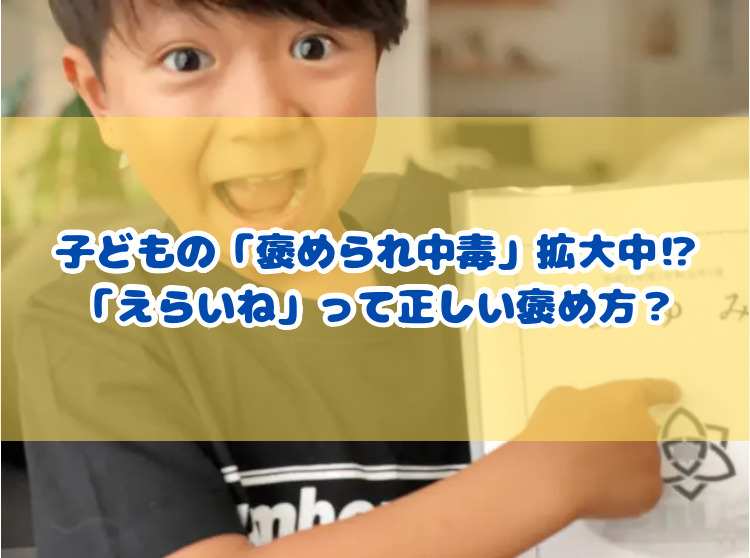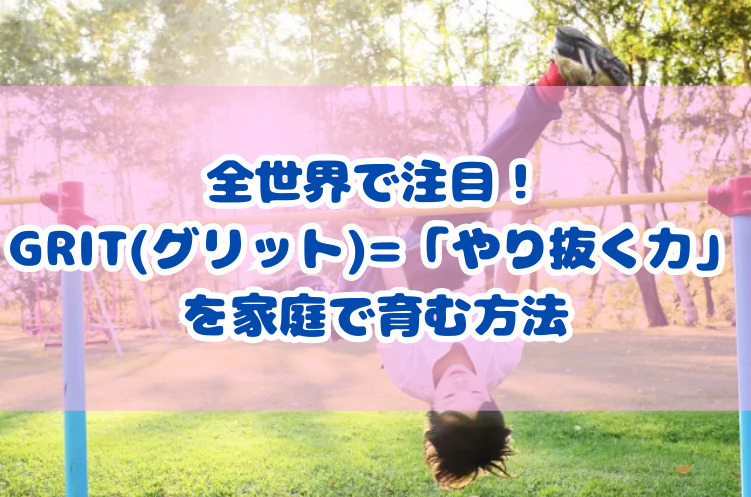ママのイライラ、パパのモヤモヤを解消する夫婦の歩み寄り方Q&A
投稿日: 2025.10.14
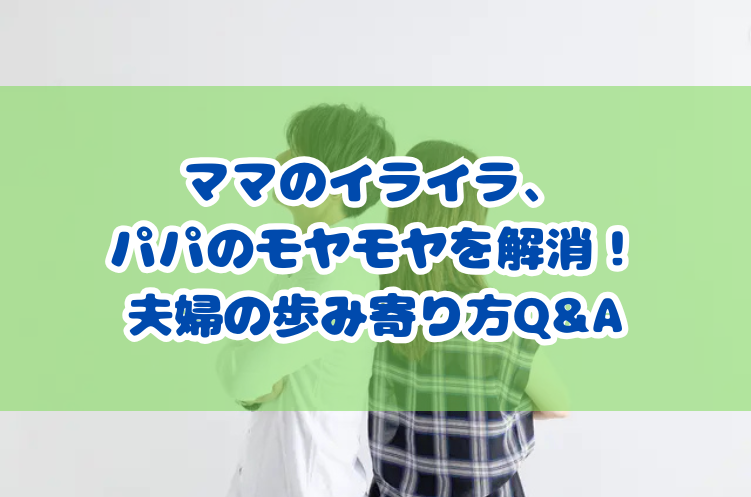
子どもが生まれると、夫婦の生活は一変します。
「自分だけが頑張っている気がする」「パパはもっと協力してほしい」――ママのこのような不満が積もる一方で、「自分なりに頑張っているのに認めてもらえない」というモヤモヤを抱えるパパも少なくありません。
夫婦のすれ違いを放置すれば、お互いへの小さな不満が大きな溝に変わってしまいます。
ここでは、令和のママパパが抱えるリアルな悩みに答える形で、夫婦の歩み寄り方のヒントを紹介します。
夫婦間の悩みQ&A

夫婦間の悩みは、お互いの価値観や状況の違いから生じることが多いもの。
良く聞かれる「ママ目線」と「パパ目線」の悩みを取り上げ、それぞれの言い分を整理し、改善策を考えていきましょう。
Q1.子どもの体調不良の対応は、どうしてもママ任せに…
「急な発熱時の病院対応は、自然と私の役割になってしまう。私にも予定があるのに」
良く聞くパパの声
「仕事があるし、妻の冷たい視線が気になることもあるけれど、正直どう対応していいか分からない」
子どもの急な体調不良は、夫婦のどちらにとっても大きな負担となります。
でも、子どもに罪はありません。「こんな時に熱を出して」など、子どもにぶつけるのはNGです。
「ママが病院に」「パパが仕事を調整」と固定してしまうと負担が偏りがち。
夫婦で、子どもが病気になった時にどちらが迎えに行くかなど、シミュレーションしましょう。
「パパが子どものかかりつけの小児科に行ったことがない」ということがないよう、かかりつけの小児科をパパも把握しておくことが大切です。
共働きの場合、ママもパパも普段の働き方が大切です。急に休むことになってもチームでサポートし合える体制が作れていると安心ですね。
病気の子どもを預かる病児保育施設や病児保育サービスも増えています。住んでいる地域の状況を把握しておきましょう。
多くの場合、事前登録が必要です。
病気に備えて事前に登録申請しておくと安心です。
Q2.家事と育児の優先順位が夫婦で違って、イライラします
「食器を洗うより子どもを寝かせたいのに、パパは掃除を優先」
良く聞くパパの声
「自分なりに頑張っているのに、ママにやり方を否定されてしまう」
夫婦で家事のやり方が違うのは当たり前。
「違いがあるのは当たり前」と認め合うことが第一歩です。
ただし「今は子どもを寝かせるのが第一」「明日の弁当準備は最優先」といった優先順位の合意があれば、すれ違いは減ります。
家事アプリや付箋などを活用して「今日の優先リスト」を夫婦で共有するのも有効です。
Q3.夫婦で家事・育児について話し合っても改善されないのはなぜ?
「パパに何度お願いしても変わらない」
良く聞くパパの声
「ママに責められている気がして、聞きたくなくなる」
「もっと家事して!」「どうしてやってくれないの?」という「要求」よりも「週3回、食器洗いをお願いしたい」「〇〇をお願いできたら助かるな」など、「お願い」を具体的に伝えましょう。
さらに「あなたがやってくれると、私も休めて嬉しいわ。ありがとう」と感謝の気持ちを伝えると、お互いを受け入れやすくなるでしょう。
Q4.「イクメン」意識が強すぎるパパに困る…
「ちょっと育児をしただけで“俺ってイクメン”と満足されても…」
良く聞くパパの声
「頑張っているのに認めてもらえない」
育児は「ママを手伝う」ものではなく、親として一緒に担うもの。
ママはパパの育児参加について「親として当然」と思いつつも、「ありがとう」を忘れずに伝えましょう。
パパは、育児を「手伝う」から「共に担う」へと、意識を切り替えることが大切です。
Q5.子どもが生まれても、パパの生活リズムが独身時代のまま…
「パパは飲み会や趣味を優先。私だけが制約されている」
良く聞くパパの声
「少しは息抜きしたい。全部我慢するのはつらい」
子育ては持久戦。夫婦それぞれのリフレッシュ時間の確保は、「家族の幸せのための投資」とも言えるくらい、とても大切なこと。
でも、だからといって、パパのリフレッシュの時間の方が多いと、不公平感がつのります。
「月〇回はパパの自由時間、この日はママの自由時間」など、夫婦で話し合ってルールを設け、お互いの一人時間を確保しましょう。
Q6.パパが、保護者同士の付き合いやコミュニティの参加に消極的です。
「保護者の集まりにパパが参加してくれない」
良く聞くパパの声
「ママ友の輪に入るのは、正直ハードルが高い」
保護者の集まりなどに無理に参加させる必要はありませんが、運動会や発表会などの子ども主体のイベントにはできるだけ夫婦で参加したいもの。
そこで一緒に応援したり見学しているうちに、家族同士の交流が生まれることもあります。
子どもを介して「家族ぐるみ」の関係性があると、ママの孤立も防げます。
パパは、「ママ友に会う」のではなく「子どもの友達家族と交流する」と考えると、気持ちがラクになれるのではないでしょうか。
Q7. 夫婦の金銭感覚の違い、どう折り合いをつける?
「子どもへの投資は惜しまないけど、生活費の使い方で対立」
感覚の違いは感情論になりやすいですが、数字で共有することが解決の近道です。
そこでおすすめなのが、家計簿アプリ。
家計簿アプリのメリットは、レシート読み取りや銀行口座連携による手間を省いた入力、自動集計とグラフ表示による支出の「見える化」、そしていつでもどこでも記録・確認できる手軽さにあります。
アプリを夫婦で一緒に見ながら「ここは削れる」「ここは投資したい」と話し合えば、建設的に対話できるのではないでしょうか。
「節約してほしい」ではなく「将来のためにこう貯めたい」と前向きに対話することで、不満より安心感が生まれます。
子育ての悩みQ&A

子育ての悩みは、正解がひとつではないからこそ迷いやすいもの。
しつけ、習い事、親子の距離感……。
夫婦で意見が分かれる場面でも、子どもにとって安心できる環境を整えるにはどうすればよいのでしょうか。
Q1.子育ての方針が合わない時。どうしたらいい?
「毎日の早寝早起きは大事」
良く聞くパパの声
「休みの日などは多少夜更かししてもいいのでは?」
子育ての方針が違うとき、大切なのは、「どちらが正しいか」で戦わないことです。
まずは、お互いの意見の根っこにある「子どものためにこうしたい」という最終目標を共有しましょう。
その上で「早寝早起き」で健康な体を願うママの気持ちと、「たまにはゆっくり一緒に過ごしたい」というパパの気持ち、両方が大切にできるルールを決めましょう。例えば、平日の就寝時間は「お家の絶対ルール」としてママの希望を優先する代わりに、金曜や土曜の夜だけは「パパとのスペシャルタイム!」として例外的に夜更かしを認める、という具合です。
お互いが納得できる形で、「これだけは守る」という一貫性を子どもにも示しましょう。
Q2.「パパイヤ期」(子どもがパパを拒否する時期)をどう乗り越える?
「パパが落ち込んでしまう、ママの負担が増える」
良く聞くパパの声
「子どもに抱っこも拒否され、悲しい」
多くの場合、「パパイヤ期」は一時的なもの。
無理に関わろうとせず、見守りつつできることを続けることが大切です。
パパは、「寝かしつけは拒否されても読み聞かせはできる」など別の関わり方を探しましょう。
ママも「パパを頼りにしている」と伝えることで、パパの孤独感を和らげることができるでしょう。
Q3. しつけの仕方で意見が合わない
「危ないことをしたら、その場できちんと叱ってほしい」
良く聞くパパの声
「頭ごなしに怒るのではなく、優しくさとす方がいいと思う」
育ってきた家庭環境によって「しつけの基準」は大きく違います。
どちらか一方の正解に寄せるより、「両方のよさを認め合う」 視点が大切。
子どもにとっては「多様な価値観を知る」経験にもつながります。ただし、道路への飛び出しなど安全に関わることについてはその場で厳しく伝える、挨拶、片づけなど生活習慣や日常のマナーについては穏やかに根気よく促す、など、しつけの内容ごとに夫婦で対応のトーンを統一できるといいですね。
Q4.子どもの習い事や進路で意見が分かれる
「ピアノもスイミングも英語も! 今のうちにいろいろ経験させたい」
良く聞くパパの声
「費用もかかるし、送り迎えも大変。無理のない範囲でいいのでは?」
最も大切なのは「子ども自身がどう感じているか」。
「やりたい!」「楽しい!」という本人のモチベーションを最大限に引き出す一方で、詰め込みすぎると疲れて続きません。
夫婦で話し合う際は、まず費用や送迎時間を一覧にして「無理のない範囲」を数字で見える化し、お互いが共通認識を持つことが重要です。
その上で、「将来のためにやらせたい」という親の希望よりも、「子どもが興味を持ち、生活リズムを崩さずに続けられるか」を基準にしましょう。
親が熱心でも、子どもがストレスを抱えては本末転倒です。
体験教室から始める、半年単位で見直すといった柔軟な姿勢を持つことが、夫婦の衝突を和らげ、子どもにとってより良い選択につながります。
ママもパパも「相手の立場や気持ちになって考える」気持ちの余裕を

夫婦がうまくいかない原因の多くは「考え方の違い」ではなく「気持ちのすれ違い」です。
ママもパパも「相手を変えたい」ではなく、「相手の立場や気持ちになって考える」ことが第一歩。
子育ては、夫婦が同じ方向を向いて初めてスムーズに回ります。
完璧を求めず、「できることを分け合い、感謝し合う」。
その積み重ねが、子どもにとっても安心できる家庭の土台になります。
・ママパパお互いのリフレッシュ時間を確保することが、円満の近道。
・子育ての最終目標を夫婦で共有しよう。
・お互い完璧を求めず、「できることを分け合い、感謝し合う」ことが大切。
(参考文献)
【パパ育児】「ママのダメ出し」が辛い人こそ必見! 脳科学で考える目からウロコの「解決方法」(出典:コクリコ)
【子育てママの本音調査】80%以上は「仕事と家庭の両立に悩みがある」coconeから毎日頑張るママたちへエールをお届け(出典:PRTIMES)
【400名男女調査】「夫婦関係がうまくいかない」と感じる人は60%以上!原因や修復方法を調査。夫婦円満の秘訣とは?(出典:PR TIMES)
「誰もが共感! 子育てのよくある悩み15選。全国のママパパから学ぶ解決法を紹介」(出典:こそだてマップ)