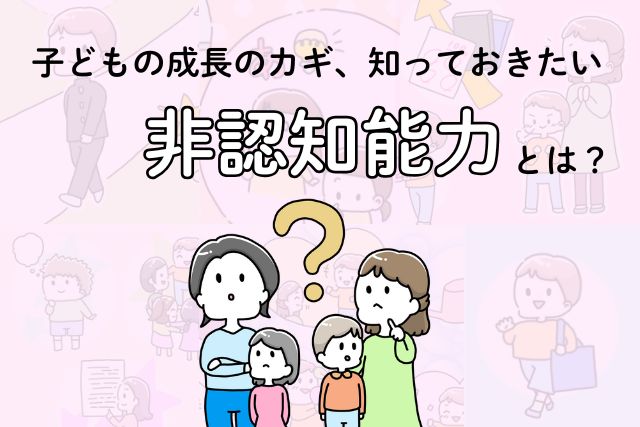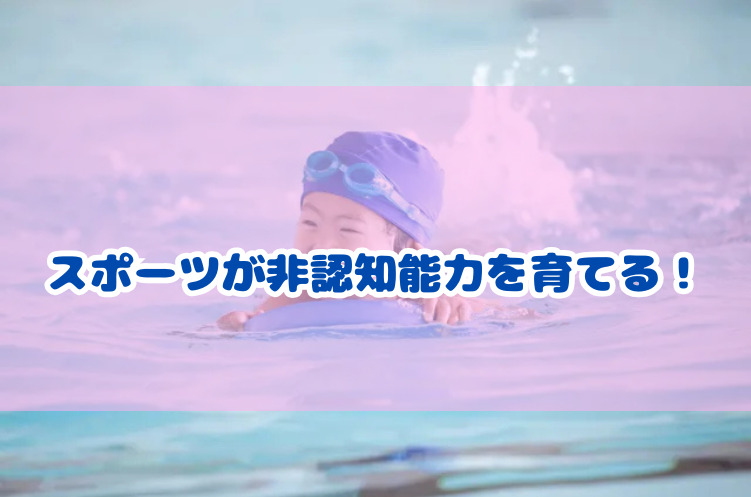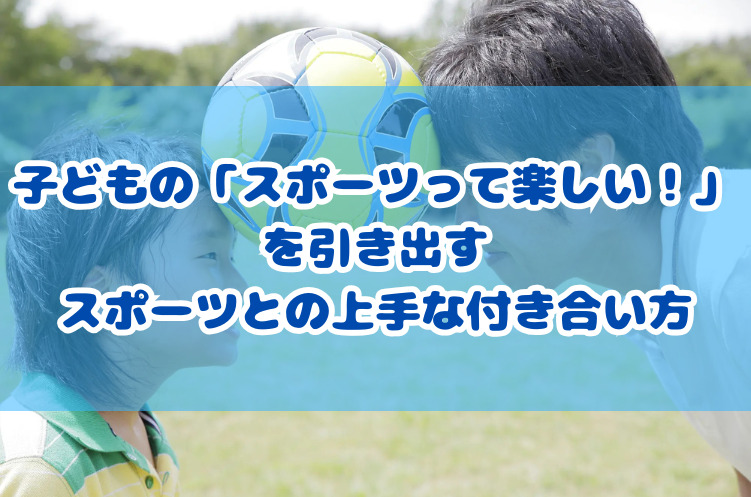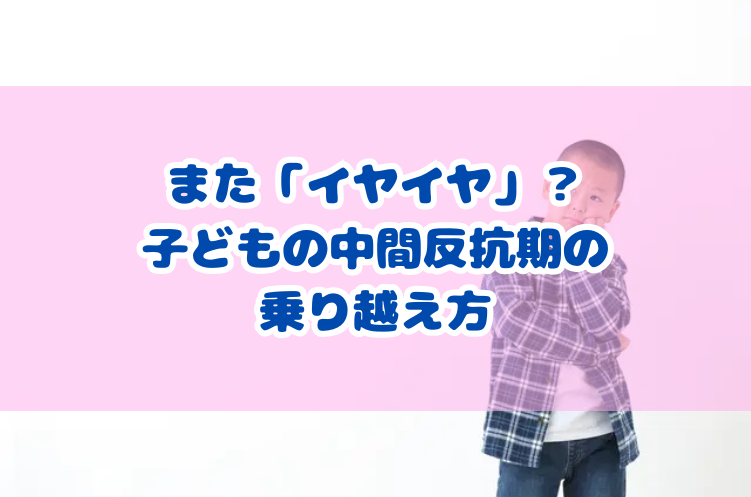子どものスポーツ、どこまで関わる?|子どもの成長をサポートする方法
更新日: 2025.10.02
投稿日: 2025.10.01

「子どもにスポーツをさせたいけど、親はどう関わればいいの?」
そんな疑問を持つ親御さんは多いのではないでしょうか。
スポーツは身体を強くするだけでなく、自信・協調性・やる気といった将来につながる力も育ててくれます。
ですが、親のサポートが行きすぎると、子どものやる気をなくしてしまうことも…。
この記事では、子どものスポーツを応援したい保護者の方に向けて、スポーツを楽しみながら子どもの成長を伸ばす親の関わり方をわかりやすくご紹介します。
もくじ
親が守りたい3つの基本ルール

1. 子どもに見返りを期待しない
「プロ選手になってほしい」「試合で勝ってほしい」といった期待は、子どもにとって大きなプレッシャーになります。
→ 「楽しんでくれたらOK!」という気持ちで応援することが大切です。
2. ポジティブな声かけをする
失敗を責めるのではなく、「ここが上手にできたね!」と良い部分に目を向けましょう。
→ 具体的に褒めることで、子どもはもっと頑張りたい!という気持ちになります。
3. コーチと協力する
コーチの指導を尊重し、親子で共有することで一貫したサポートが可能になります。
→ 親がコーチの指導に対して否定的な言動をすると、子どもが混乱してしまいます。
年齢ごとのサポートの仕方

3〜6歳(幼児期)
遊び感覚で体を動かす楽しさを伝える。勝ち負けよりも「やってみよう!」の気持ちを大切に。
ボールを蹴れた、転ばずに走れた、先生の話を聞けたなど、小さな成功体験をたくさん褒めましょう。
結果ではなく、頑張った過程を褒めることが大切です。
7〜9歳(小学校低学年)
基礎的な動きや協調性を学ぶ時期。「続けることの大切さ」も意識してみましょう。
この時期に「続けること」と「協力すること」の楽しさと大切さを体験することで、子どもはスポーツだけでなく、学校生活や将来にわたる人間関係においても、大きな財産となる力を身につけることができます。
10〜12歳(小学校高学年)
心身ともに大きく成長し、技術や戦術の理解度も深まります。また、周囲の評価やライバル関係を意識し始め、精神的に不安定になることもあります。
失敗や挫折の経験は成長のチャンスだと伝えましょう。「この悔しさがあるから、次はもっと頑張れるね」と、子どもが前向きに捉えられるよう話してみましょう。
スポーツで育つ5つの力(非認知能力)

挨拶・礼儀
挨拶・礼儀とは、社会性を身につけ、人間関係を築く上での根っことなる「挨拶や感謝の気持ちを伝えられる力」、「人を尊重し、物を大切にする力」、「規律を守れる力」の3つの軸から成り立ちます。
リーダーシップ
リーダーシップとは、「自分や仲間のことを考えることができる力」、「自分や仲間のために行動に移せる力」、「仲間をまとめることができる力」の3つの軸から成り立ちます。
協調性
協調性とは、「仲間を思いやる力」、「仲間と協力する力」、「仲間に手を差し伸べ、支える力」の3つの軸から成り立ち、集団行動においては不可欠な力です。
自己管理力
自己管理力とは、「自分の気持ちをコントロールする力」、「諦めず、やり続ける力」、「気持ちを抑え、ルールに従い、行動に移す力」の3つの軸から成り立ちます。
今まで経験したこともないような壁にぶつかっても、心が折れることなく試行錯誤しながらもやりぬくためには、この自己管理力が必要です。
課題解決力
課題解決力とは、「課題を発見する力」、「課題を解決する方法を発見する力」「課題を解決するために実行する力」の3つの軸から成り立ちます。
これらは将来の勉強や仕事にも役立つ一生ものの力です。
子どもが「スポーツ嫌い」にならないために避けたいNG行動

結果ばかりを気にする
試合の勝ち負けや得点ばかりを重視すると、子どもは「楽しむためのサッカー」から「怒られないためのサッカー」に変わってしまいます。小学生年代では、まず「できた!」「楽しい!」という成功体験を積み重ねることが何より大切です。
他の友だちやきょうだいと比較する
「〇〇くんは上手なのに」「△△ちゃんはできるのに」と比べられると、子どもの自信を奪ってしまいます。成長スピードは人それぞれ。比べる相手は友達ではなく、昨日までの自分です。
練習に口を出しすぎる
「もっと走れ!」「なんでできないの?」と細かく指示すると、サッカーが“監視されるもの”になってしまいます。家庭では口出しよりも「頑張ってたね」「楽しそうだったね」と見守る声かけが効果的です。
コーチを批判する
練習方法や試合の采配に不満をぶつけると、子どもは混乱し、どちらを信じてよいかわからなくなります。コーチへの信頼を子どもと共有することが、安心してプレーに集中できる環境づくりにつながります。
親の夢を押し付ける
「プロになってほしい」「自分が叶えられなかった夢を…」と期待を背負わせると、子どもは重荷に感じてしまいます。まずは「サッカーって楽しい!」と心から思えることが、長く続け、自然と上達する秘訣です。
「楽しさ」、子どもの「好き」という気持ちを一番に考えることが親ができる最大のサポートかもしれませんね。
まとめ|保護者ができる10の応援ポイント

1. 子どもに見返りを期待しない
2. 小さな成長も具体的に褒める
3. コーチの方針を尊重する
4. 年齢に合ったサポートをする
5. 勝敗よりも楽しさを大切に
6. 精神的な成長を意識する
7. いろいろなスポーツを経験させる
8. 子どもの体調やケガに気を配り、無理をさせない
9. 子どもの目標や意思を尊重する
10. 親自身も一緒にスポーツを楽しむ
スポーツは「できる・できない」よりも「楽しむこと」が一番。
親の関わり方次第で、子どもは自信とやる気も変化するため、意識してサポートしていきましょう。