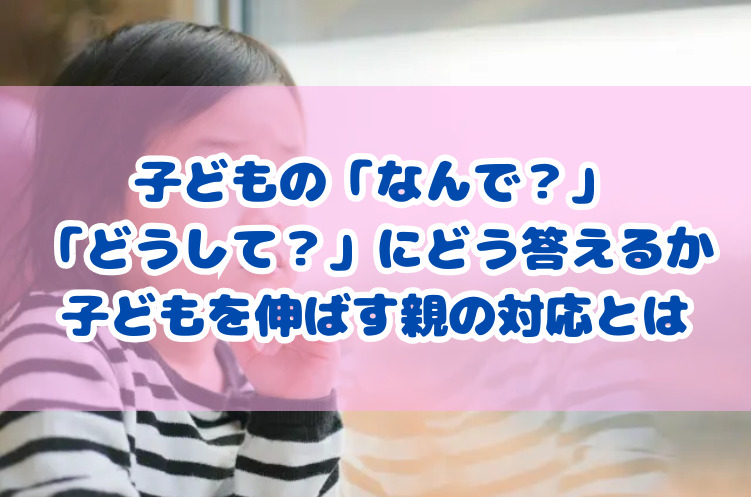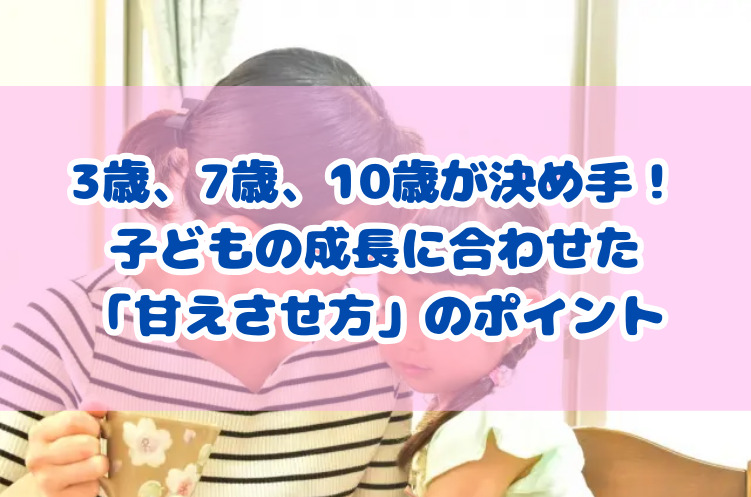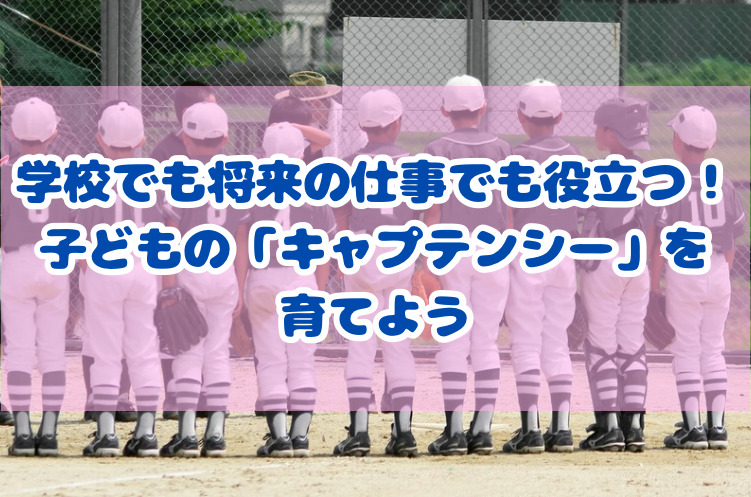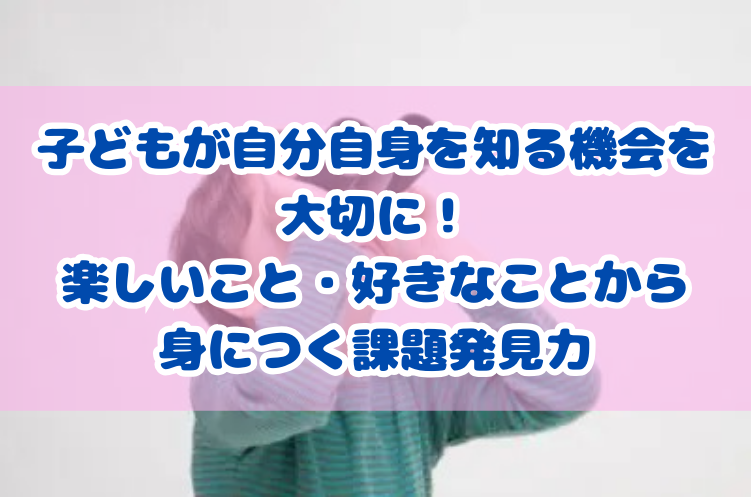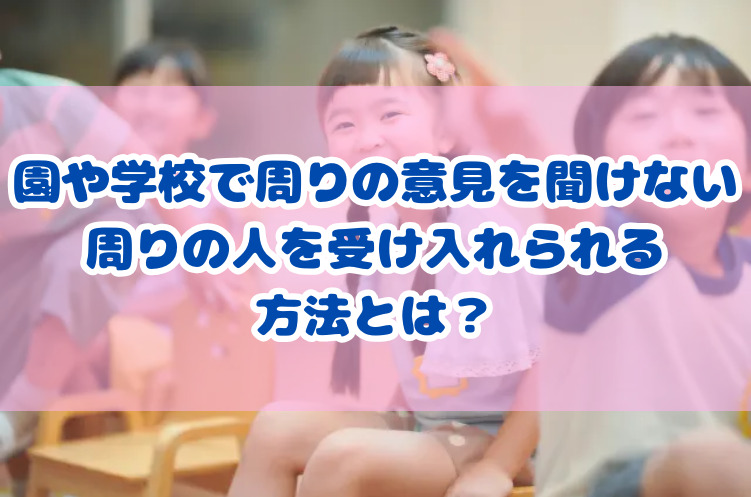心の発達は7歳が分かれ道!感情のコントロールをして「乱暴な子」から「やさしい子」になるには
投稿日: 2025.09.23

思い通りにならないと、物を投げたり手が出たり。
頭にくると、急に乱暴な言葉づかいになったり。
「うちの子って、乱暴なの?」と、親としてはちょっと心配になるものです。
周囲からも親からも、「乱暴な子」と思われてしまう子には特徴があります。
例えば…
・思い通りにならないと感情が爆発してしまう
・強い言葉づかいをする
・すぐに手が出る
・周りの子のことを考えられない
・体の動きが大きくて激しい
・声が必要以上に大きい
「子どもだから仕方がない…」とは思っても、つい親も強く叱ってしまいがちです。
感情のコントロールを上手にできるようになって、わが子には思いやりのある子に育ってほしいですね。
子どもの心の発達や感情表現の方法、気持ちのコントロール力を知り、親としてのサポート法や関わり方について考えてみましょう。
もくじ
7歳が分かれ道! 子どもの年齢別・心の発達を知り、適切な関わりを

幼児期から学童期にかけては、家庭とは異なる人間関係(=園・学校の先生や友だち、習い事の先生や仲間、近所の人など)のなかで、自分をとりまくさまざまな人と関わりながら、心身の成長を遂げる時期。
まだ感情のコントロールが上手にできない幼児期を経て、7歳頃になると相手の気持ちを想像したり、場の雰囲気を感じるようになります。
そして小学校中学年→高学年と感情のコントロール方法を身につけていきます。
ここでは年齢別に子どもの特徴に注目し、その心の発達を探ってみましょう。
幼児期(3〜6歳頃)
幼児期の子どもは、感情や行動をコントロールする脳の前頭前野がまだまだ未発達です。
少しずつルールや順番を理解しはじめますが、自分の気持ちや言動をコントロールすることは難しいでしょう。
まだ「自分が世界の中心」という感覚が強いので、自己主張を感じる行動が多いかもしれません。
言葉で説明できない分、乱暴にしたり、叩く・押すなどの行動に出やすい頃でもあります。
そんな時はなるべく短い言葉で簡潔に、
「貸して、って言ってみよう」
「順番を待とうか」
「やめて、と言ってもいいんだよ」
とやさしく伝えましょう。
子どもは「こういう時は言葉で伝えればいいんだ」」と少しずつ理解し、人との関わり方がわかるようになります。
7歳頃
本格的な集団生活が始まり、ルールや約束に対して理解も進みます。
前頭前野の神経ネットワークも発達しはじめ、少しずつ自分の気持ちを言葉にすることができるようになり、相手のことを想像したり、その場の雰囲気を理解して行動するようになるでしょう。
また仲の良い友だちができはじめて周囲との関係が構築される時期なので、友だち同士で言い合いや意見のぶつかり合いが増えるかもしれません。
勉強やゲーム、遊びの中で友だちとの「勝負」にもこだわる年齢です。
この時期にさまざまな人と接して、コミュニケーションの機会を増やすことで、人の気持ちを想像したり推しはかる習慣が身につくでしょう。
親はと子どもの気持ちを代弁したり、相手の気持ちを想像させながら、
「早くやりたかったね…でも順番は守ろうね」
「叩かれた◯◯くんは、痛かったかもね」
など、ヒントを与えるような声かけをすると、子どもなりに気づきがあるかもしれません。
ポイントは「共感」と「言語化」です。
子どもに対して「わかる」と伝えて共感し、「いやだったんだね」などモヤモヤした気持ちを言葉にしてあげましょう。
小学校中〜高学年
前頭前野も発達し、感情のコントロールが少しずつできるようになってくる時期です。
同時に自尊心が高まり、周囲から「認められたい」「理解されたい」という気持ちが強くなってくることで、乱暴な言動が顔を出すことも。
友だち同士のグループでの役回りや、立ち位置が気になる年齢で、親に話さないことが増えたり、仲間同士の意識が強まります。
ちょっぴり生意気な態度も増えてきますが、あまり強い口調で注意すると親をシャットアウトしてしまいます。
基本的には子どもの話に意見を言ったり批判したりせず、ゆっくりと聞きましょう。
また相手を傷つけた時の態度や、関係修復の方法を学ばせるのにはよい時期です。
得意なスポーツや習い事をやらせることで、自己肯定感や自己効力感を育てるといいですね。
気持ちをコントロールする方法

子どもにとって、気持ちをコントロールして行動につなげるのは、難しいこと。
しかし「感情をコントロールできるかどうか」は持って生まれた性格ではなく、トレーニングによって身につけるスキル。
周囲がちょっとしたサポートをしながら練習すると、少しずつできるようになります。
子どもが感情をコントロールできるようになる方法を、いくつか挙げてみましょう。
◯ 今の気持ちを言葉にしてみる
◯ 深呼吸を3回
◯ 他のことに気持ちを移す
◯ 「どうして?」を考えてみる
◯ 次を想像する
今の気持ちを言葉にしてみる
気持ちを言語化することは、感情をコントロールするうえで、一番の近道。
これは大人も同じです。
「僕のおもちゃを使われて、嫌だった」
「お母さんがお姉ちゃんばっかり優しくして悔しい」
など、自分の気持ちを言葉にする習慣が身に付くと、自分の気持ちに気づけるようになり、コントロールできるようになります。
深呼吸を3回
誰でも何か嫌なことを言われたり、思い通りにならない時はカッと頭に血がのぼります。
その感情をそのまま表に出すのではなく、一度、ひと呼吸置くことで、衝動的な行動を抑えることができます。
深呼吸の時間ができると、感情のピークをやり過ごすことができ、怒りにまかせた行動を防げるのです。
同時に、深呼吸をすることで副交感神経が優勢になり、戦闘体制だった体がリラックスして気持ちが落ち着きます。
この方法は大人になっても使えるので、覚えておくといいですね。
他のことに気持ちを移す
頭にくることや悔しいことを考え続けていると、いつまでも感情が逆立ってしまいますね。
「そういえば、昨日のテレビでさ…」
「帰ったら、ゲームの続きをやろうか」
など、目の前のことから少し視点をずらす工夫をしてみましょう。
他のことに気持ちが移ると、感情に風穴が空いて少し落ち着けるはずです。
「どうして?」を考えてみる
うまくいかなかった時や失敗した時は、「どうしてこうなったか?」「なぜか」に思いを馳せると、気持ちが落ち着くことがあります。
「失敗」から視点をずらして原因究明をすることで、次につなげることもできます。
また相手に嫌なことを言われたり、意地悪に感じても、「もしかしたら私のことを考えて言ってくれたのかな」と別の角度から見ることもできるでしょう。
「どうして?」を考えることは、状況の整理にとても役立つのです。
次を想像する
今に集中しすぎると、悔しい気持ちや嫌な思いにとらわれてしまいがちです。
「順番が来たら、何をしようかな」
「今は負けちゃったけど、次はどんな作戦で行く?」
など、「今」から離れて次を想像することで、気持ちが切り替えられるようになり、同時に次回の作戦も立てられて一挙両得です。
建設的に次を考えると余裕ができ、気持ちのコントロールもしやすくなるでしょう。
「乱暴かな…」と思った時、保護者はどうフォローするか

子どもの行動が「ちょっと乱暴かな」「感情が爆発しているな」と思ったら、親がフォローすると落ち着くことがあります。
子どもの行動のケースバイケースで、フォローする方法を考えてみましょう。
◾️ごめんなさいが言えない時「素直に謝ればいいのに…」と思うことは多々ありますが、子どもは自分の正しさを理解してほしいと感じています。「いやだったんだね」「悔しいよね」など、「あなたの気持ちはよくわかる」と伝えることで、「理解してもらえた」と感じて、気持ちが落ち着くでしょう。子どもも「自分が悪い」ことはわかっています。一息ついたら、「◯◯ちゃんは、もっと悔しいかも」「謝れるとカッコいいよね」とさりげなく謝罪を促しましょう。
◾️乱暴な言動で周囲に迷惑をかけている時「なにやってるの!」と親も一緒にヒートアップしてしまうと、子どもはさらに興奮するかもしれません。ひとまず安全な場所に子どもを誘導し、子どもと視線を合わせて、「大丈夫」「落ち着こうか」と声をかけながら親子で一緒に深呼吸をしましょう。子どもの感情がしずまったら、「なにがあったか」「なぜ怒っているか」をゆっくり聞き出して、解決方法を一緒に考えます。
◾️泣き出して手がつけられない時「なんで泣いてるの?」「どうしたの!?」と質問責めにせず、まずは泣き止むまで待ってあげましょう。そして少しずつ気持ちをほぐしながら、話を聞きます。その時、「それはあなたが悪い」「◯◯ちゃんのせいだわ」などと大人が判断をしないことが大切。「悔しくて泣いちゃったんだね」「次は泣かないで、○○って言えるといいね」と言葉で伝える練習を手伝ってあげましょう。
「乱暴な子」「やさしい子」と決めつけるのはNG。親としてのサポートポイント3つ

多くのお母さん、お父さんたちは、わが子の言動を見て「乱暴な子」「やさしいけど気が弱い子」などと決めつけてしまいがち。
しかし、マイナスのレッテルを貼り、否定してばかりでは、子どもの自己肯定感を育むことはできません。
子どもの性格や気質は、成長とともに変化していくものです。
自分の感情の対処の仕方や周りへの働きかけ方を学ぶこの時期は、わが子を「乱暴な子」「やさしいけど気が弱い子」などと決めつける前に、
・自分の感情を言葉にする方法
・自分の感情をコントロールする方法
を根気強く教えていくことが大切です。
このために、親としてどんなサポートをすればよいのでしょうか。
ポイントを3つ、紹介します。
〇自分の気持ちに気づけるようにする
〇ネガティブな感情を否定しない
〇「家庭は安心していい場所」というメッセージを届ける
自分の気持ちに気づけるようにする
子どもの話に耳を傾け、「友だちとおもちゃの取り合いになった」などと言ってきたときは、「それは悔しかったね」と言葉にしてあげましょう。
これを繰り返すことで、「このモヤモヤは悔しさなのか」など、自分の気持ちに気づけるようになります。
ネガティブな感情を否定しない
「怒り」「悲しみ」の感情は否定されがちですが、イヤなことをされて腹が立ったり、別れが悲しかったりするのは自然なことです。
しかし、怒りを暴力などで表現するのNG。
「イヤなことをされて腹がたったんだね」と受け入れつつ、「暴れなくてもイヤな気持ちは表現できると思うよ。どうしたらいいと思う?」など、子どもといっしょに考えるようにしましょう。
「家庭は安心していい場所」というメッセージを届ける
「何か心配なことがあったらお母さんに言ってね」などとおりにふれてわが子に伝え、「家庭は安心していい場所」「悩みやぐちを言っていい場所」というメッセージを伝えましょう。
個性を伸ばしながら、人とうまく関われる子に

泣いて怒って自分の感情のままに行動する子もいれば、周りの状況をみながら自分の気持ちをおさえこんでしまう子もいます。
繰り返しになりますが、親はわが子の言動を見て「乱暴な子」「やさしい子」などと決め付けず、それぞれの個性と時、場合に応じて自分をコントロールしながら思っていることをうまく表現できるようサポートしていくことが大切です。
・ 乱暴な行動をとる子に「やめなさい!」と大きな声で叱るのでなく、話すトーンをゆっくりやわらかくしながら「どうしたの?」「何があったの?」などと問いかける。
・ やさしいけれど、気弱で引っ込み思案な子に「はっきり言いなさい!」などと命令するのでなく、「どうしたい?」「どっちが好き?」といった言葉がけで本人の気持ちを引き出す
など、子どもの個性に合った対応をするように心がけましょう。
言葉で説明しきれないことや、すぐにできないことは、親がモデルとなって日常生活の中で示していけばいいのです。
子どもはまだまだ成長段階で、ここから失敗を経験しながら感情のコントロール方法を覚えていくので、じっくり見守ることも必要です。
わが子をよく見て、気持ちを理解し、言葉にしてあげることからはじめましょう。
親に見守られ、理解してもらっているという安心感が、子どもの成長の原点となるのです
・ 年齢に沿った心の発達を知っておこう
・子どもが乱暴な行動をしてしまった時は、親や周囲の大人がサポートするとよい
・ 「乱暴な子」「やさしすぎる子」と決めつけない
・ わが子をよく見て、気持ちを理解し、言葉にしてあげよう
親としては、子どもが優しい心を持ってほしいと願ってほしいものですよね?
7歳からが分かれ道ということで、大切なのは3~6歳までの時期にたくさんの感情を経験することだそうです!そのため親が「うちの子どもは〇〇な子」と決めつけるのではなく、ありのままの子どもを客観的に見ることを意識してみましょう!そして、個性として認めて、受け止めてあげることで、子どもたちの心の居場所を作ってあげましょう!そうすることで子どもたちの心に成長に繋がっていきます。
(参考文献)
・絵で見てわかるしぐさで子どもの心がわかる本(渡辺弥生:著、PHP研究所)
・まんがでわかる発達心理学(渡辺弥生:監修、講談社)
・〇のない大人 ×だらけの子ども(袰岩奈々:著、集英社)
・PHPのびのび子育て|脳の発達はどう違う?乱暴な子とやさしい子(加藤俊徳:監修)