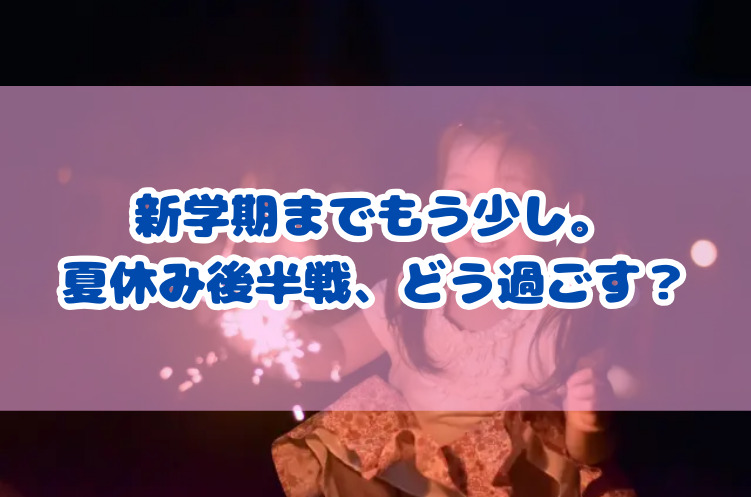「夏休み、どう過ごす?」共働き家庭が抱えるリアルな悩みと解決策
更新日: 2025.07.31
投稿日: 2025.08.01
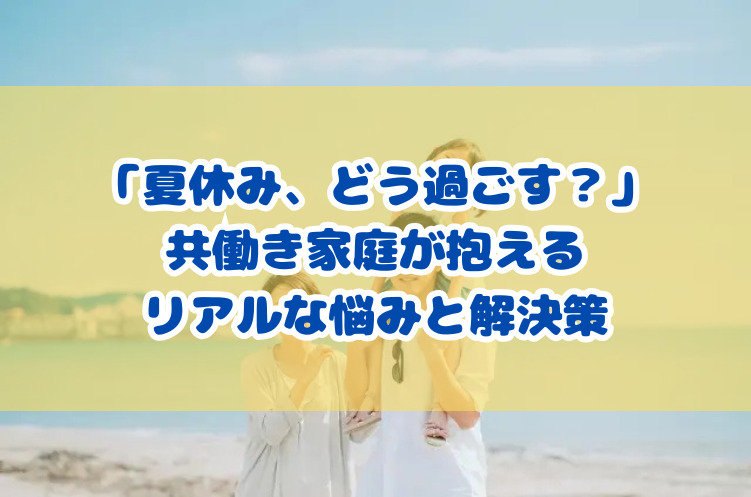
夏休みは子どもたちにとって待ちに待った長期休暇ですが、共働き家庭にとっては頭を悩ませる種となることも少なくありません。
学童保育の利用、祖父母へ預ける、習い事やサマーキャンプの選択、そして何よりも夫婦ともに仕事がある中で、いざという時の子どもの体調不良や急な予定変更の対応など、リアルな悩みは尽きません。
この記事では、そんな共働き家庭が直面する夏休みの課題に焦点を当て、具体的な悩みとその解決策について紹介します。
共働き家庭が抱える夏休みの悩みごと

共働き家庭が抱える夏休みの悩みごとの中で特に問題となるのが、子どもだけでお留守番してもらう時間が増えることです。
低学年のうちは特に、自宅に一人でいることへの不安や寂しさだけでなく、予期せぬ事故やトラブルのリスクもあります。
また、毎日のお昼ごはんの準備も大きな課題です。
栄養バランスを考えながら、子どもが飽きずに食べられるメニューを考えるのは、仕事で疲れて帰ってからでは至難の業です。
そのほか、
・ 連休が取れずに遠出できない
という悩みが多く聞かれます。
夏休み中の子どもの預け先、どうしてる?

共働き家庭が夏休みを乗り切る上で、子どもの預け先の確保は最も重要なポイント。
さまざまな選択肢の中から、家庭の状況や子どもの性格に合わせて最適な方法を見つける必要があります。
以下、保護者の声を紹介します。
学童保育を利用する
夏休み中は朝から夕方まで預かってもらえるので、安心して仕事に行けます。
学童で友達と遊んだり、夏休みの特別イベントに参加したりと、子どもも毎日楽しく過ごしているようです」(小学3年生の保護者)
祖父母に協力してもらう
最初は緊張していたのですがすぐに慣れ、喜んで行くように。
祖父母の家では、ベランダですいか割りなど普段できないような体験をさせてもらったり、手作りのご飯を食べさせてもらえたりと、子どもにとっても良い刺激になっています」(小学1年生の保護者)
習い事や短期教室を活用する
お金がかかりますし送迎も大変ですが、日中体を動かせるので、子どもの体力増進や気分転換につながりますし、親も安心して仕事に集中できます」(小学2年生の保護者)
ベビーシッターやファミリーサポートを利用する
地域の子育て支援サービスを利用する
内容は日によってさまざまで、工作やクッキングなど、普段家ではなかなかできない活動ができるので、子どもも楽しみにしています」(小学5年生の保護者)
実際のタイムスケジュールの一例

夏休み中の子どもの過ごし方は、学年や利用する預け先によって大きく異なります。
2つのパターンを例に、子どもたちの基本的なタイムスケジュールを見てみましょう。
低学年の場合(学童保育利用)
7:00-8:00 起床、朝食
8:00-8:30 登校準備、学童へ出発
8:30-12:00 学童での自由遊び、宿題、読書、集団活動など
12:00-13:00 昼食 お弁当持参または学童で提供される給食
13:00-16:00 学童での外遊び、室内遊び、イベント活動など
16:00-17:00 おやつ、自由遊び
17:00-18:30 保護者のお迎え、帰宅
18:30-19:30 夕食
19:30-21:00 入浴、自由時間、翌日の準備
21:00 就寝
長期休みでも、学童保育を利用していると通常時と同様のスケジュールで過ごす家庭が多いようです。
夏休みの宿題も学童でほとんど終わらせる子が多いようです。
高学年の場合(学童保育利用なし、自宅でのお留守番中心)
7:30-8:30 起床、朝食
8:30-9:30 自由時間(テレビ、読書、ゲームなど)
9:30-11:00 夏休みの宿題、自習
11:00-12:00 自由時間(公園遊び、友達と連絡など)親と連絡
12:00-13:00 昼食(自分で用意できる簡単なもの)
13:00-15:00 自由時間(趣味、読書、動画鑑賞など)、親と連絡
15:00-16:00 おやつ、休憩
16:00-17:00 軽い運動、家の手伝いなど
17:00-18:30 保護者の帰宅
18:30-19:30 夕食
19:30-21:30 入浴、自由時間、翌日の準備
21:30 就寝
高学年になると、学童保育の利用がなくなるケースが多いもの。
自宅でお留守番しながら午前に1回、午後に1回と時間を決めて親子で連絡をとりあう家庭が多いようです。
友達と遊ぶ約束をしている場合、事前に「誰とどこへ行くのか」を伝えることを約束事にしています。
お昼ご飯は作り置きを冷蔵庫に入れて置いたり、近くのコンビニ等で買うためのお金を渡したりすることもあります。
夏休み期間の働き方の工夫

夏休み期間は保護者自身も働き方を工夫することで、子どものケアと仕事の両立を図ることができます。
以下、保護者の声を紹介します。
有給休暇を計画的に取得する
交代で休みを取ることで、子どもが一人になる時間を減らすようにしています」(小学4年生・2年生の保護者)
テレワーク・在宅勤務を活用する
子どもが隣の部屋にいても、すぐに様子を見に行けるので安心です。
お昼ごはんも一緒に食べられるので、子どもの精神的な安定にもつながっていると感じます。」(小学3年生の保護者)
フレックスタイム制を利用する
時短勤務を活用する
子どもの帰宅時間に合わせて退社できるので、日中の預け先探しに奔走することなく、子どもに『おかえり』を言ってあげられるのは大きかったです」(小学1年生の保護者)
職場の理解と協力を得る
夫婦での協力体制を築く
上記の保護者の声からもわかるように、それぞれの職場で利用できる制度は多岐にわたります。
これらの制度を自身の状況に合わせて活用することで、子どもが一人になる時間を減らし、精神的な安定を促したりすることができます。
職場でどのような制度が利用できるのかを詳しく調べ、積極的に活用することを検討しましょう。
また、会社の同僚や上司に夏休み期間の子どもの状況を事前に伝えるなど、職場の理解と協力を得ることもとても大切です。
急な早退や遅刻が生じる可能性を理解してもらうことで精神的な負担が軽減され、安心して仕事に取り組むことができます。
日頃からコミュニケーションをとり、いざという時に協力してもらえる関係性を築いておくことが大切です。
夏休みの過ごし方の工夫

夏休みは、普段できないような体験をしたり、家族でゆっくり過ごしたりできる貴重な機会でもあります。
保護者の負担を減らしつつ、子どもにとっても有意義な夏休みにするための工夫を凝らしましょう。
子どもと過ごし方を考える
夏休みの計画を立てる際には、ぜひ子ども自身も巻き込んでみましょう。
「夏休み中に何をしたい?」と子どもに尋ねて、行きたい場所や挑戦したいことなどをリストアップしてみましょう。
読書、映画鑑賞、工作、料理、旅行など、子どもの興味を引き出すきっかけになります。
目標を設定する
宿題を計画的に終わらせる、特定の分野の本を何冊読む、お手伝いを毎日する、など、夏休み期間中に達成したい目標を設定するのも良いでしょう。
達成感を味わうことで、子どもの自己肯定感を育むことができます。
役割分担を決める
長い夏休み期間、自宅で過ごす時間が増えることで、子どもに家事の一部を手伝ってもらう機会を設けるのも良い方法です。
例えば、洗濯物の取り込み、食器洗い、部屋の片付けなど、できることを一緒に考えて役割分担することで、子どもの自立心を育み、保護者の負担も軽減できます。
家族で夏休みの旅行の計画を立てる
長期休みは、家族旅行を計画する方も多いかもしれません。
そのなかで、目的地を決めたり過ごし方を考えたりと、準備の段階から子どもが参加することで、旅行が思い出深いものに変わる場合もあるようです。
一人で抱え込まず、周囲に積極的に頼ろう

共働き家庭にとって、子どもの夏休みは、時間的・精神的な負担が大きくなる時期。
一人で抱え込まず、周囲に積極的に頼ることが非常に大切です。
自治体の子育て支援サービスや学童保育、ベビーシッターなどの外部サービスを積極的に活用するだけでなく、祖父母や友人、近所の方など、頼れる人には遠慮せずに協力を仰ぎましょう。
また、子ども自身も、自宅にいる時間が長くなると、飽きたりストレスを感じたりすることがあります。
習い事の夏期講習や、地域の夏祭り、短期のキャンプなど、夏休みならではのイベントや活動に積極的に参加することで、子どもの心身のリフレッシュを図り、充実した夏休みを過ごせるようにサポートしましょう。
保護者自身の働き方も柔軟に工夫し、子どもと協力しながら、無理なく、楽しく、夏の思い出をたくさん作りたいものです。
・共働き家庭にとって「夏休みの過ごし方」は悩みどころがたくさん。
「うちだけではない」と知っておこう。
・夫婦で力を合わせ、夏休みの働き方を工夫しよう。
・子どもと一緒に夏休みの過ごし方を考えるのも手。
「小学生の夏休みに共働き世帯はどう対応すべき?働き方や預け先について」(出典:Kids UP)
「幼児・小学生の夏休み 有意義に過ごすためのポイントとおすすめの過ごし方8選」(出典:Gakkenお役立ち情報)
「共働き家庭にとっての夏休みの子どもの預け先。働き方や過ごし方の工夫」
(出典:KIDSNAシッター)
「小学生の夏休み、共働きの過ごし方は?タイムスケジュールや2025年夏のイベント情報も!」(出典:お仕事コンシェルジュ)