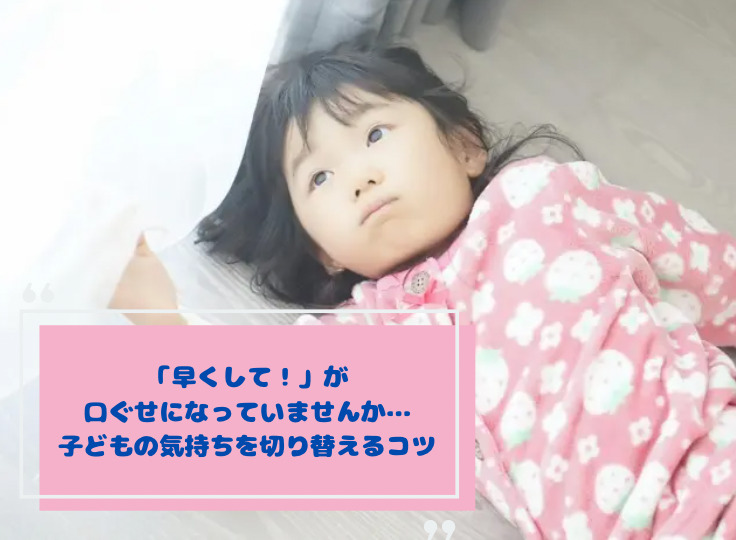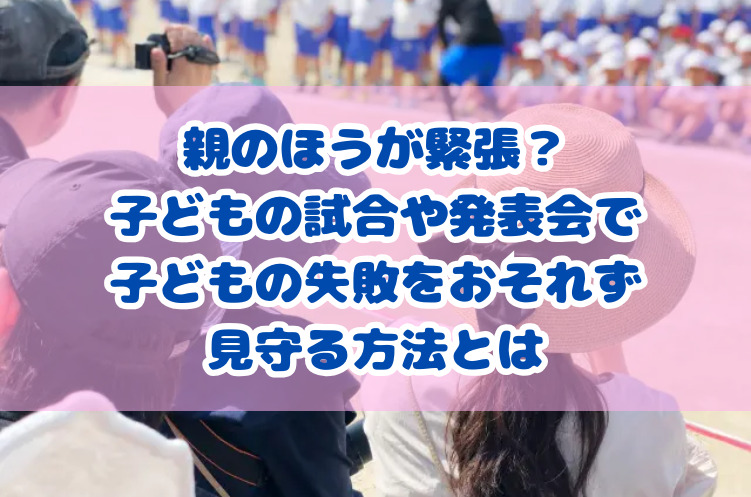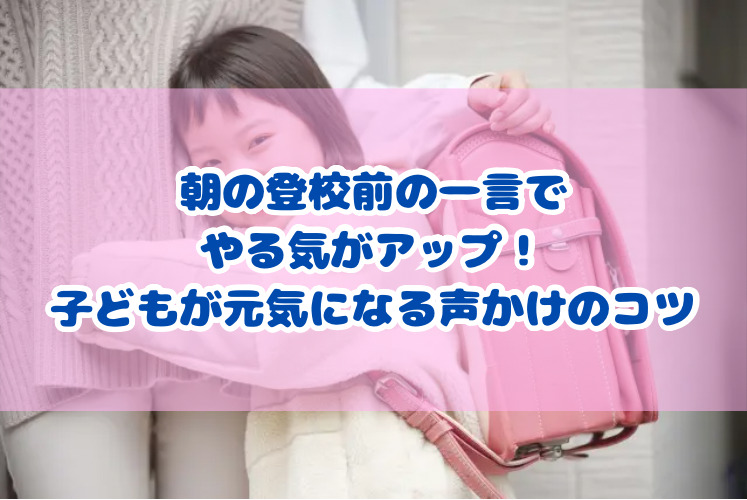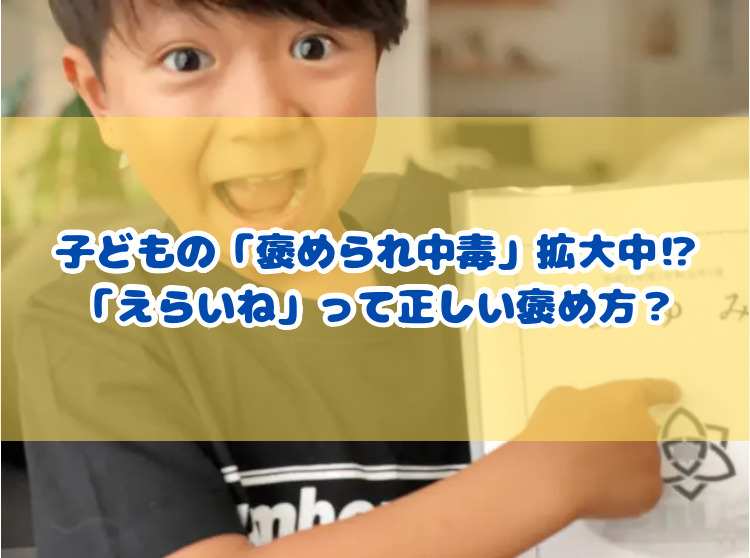“早く早く”の毎日を卒業!子どもの行動が変わる上手な言い換え術
投稿日: 2025.07.08
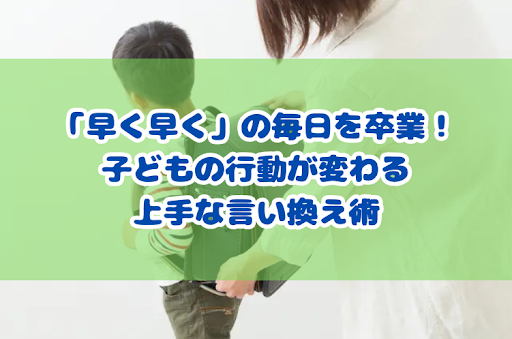
時間に余裕がない時や急いでいる時、つい子どもに「早くして」と言ってしまいますよね…。
子育て中は「園や学校への送り出し」「食事や入浴」「外出の準備」など時間に追われることが多いうえに、時間に余裕がない時に限って、子どもはグズったり、わがままを言ったり…。
本当は言いたくないけれど、つい「早く!」「急いで!」「置いて行くよ」などと、子どもを急かすような言葉を投げかけてしまいませんか?
つい出てしまうこの言葉が、実は子どもにプレッシャーをかけ、様々な影響を与えるようです。
今回は子どもがスムーズに動けるような、上手な言葉の言い換え表現を紹介します。
もくじ
「早くして!」が子どもに与える影響

急いでいる時に、子どもの行動をスピードアップさせるつもりで言ってしまう「早く早く」という言葉。
しかし、いつも「早く!」と言われている子どもは心の成長に、さまざまな影響を受けることがわかっています。
○ 考える力が育たない
○ 自己肯定感が低下する
○ 探究心や好奇心がなくなる
○ 感情を閉じ込める
○ 自主性がなくなる
○ 人を待てなくなる
考える力が育たない
自分で考えながら行動する前に「早く!」「◯◯しなさい!」と言われることが増えると、子どもは自分で考えることをやめてしまい、考える力が育ちません。
そして急かされて行動することが多くなるので、目の前のことに集中する機会がなくなり、集中力も養われにくくなるでしょう。
子どもの「考える力」は、じっくりと時間をかけて自分で考え、そのとおりに行動し、失敗を繰り返すことで育ちます。
常に追い立てられていると、考える力はなかなか身につきません。
自己肯定感が低下する
「早くして」と急かされがちな子は、「自分は行動が遅いんだ」「ダメな子なんだ」と、自分を否定しがちです。
親としては、ただ「早く行動してほしい」と思ってかけている言葉が、実は子どもの自己肯定感を傷つけていることになってしまいます。
探究心や好奇心がなくなる
子どもの探究心や好奇心は、「どうなってるのかな」「こうしたら、どうなるんだろう」と自分で想像したり、行動することで養われます。
しかし頭の中で想像し考えている時に、「早く」「急いで」と言われてしまうと、とりあえずその考えを捨てて、言われた通りに行動することになってしまいます。
親から見るとボーッとしているように見えても、子どもは頭の中でいろいろと世界を広げているかもしれないのです。
感情を閉じ込める
急かされている時の子どもは、心の隅で「わかってるよ」「早くやろうとしてるんだ」と思っていることでしょう。
また追い立てられて自分のペースで行動できないことに、ストレスを感じている可能性も。
しかし、その気持ちを押し殺して、感情を閉じ込めて行動してしまいます。
それを繰り返していると、感情表現をしない癖がついてしまうかもしれません。
自主性がなくなる
いつも急かされている子どもは、とにかく言われたことを終わらせようとします。
また親や周囲から指示を聞き、人に従うことは得意になっても、自主的に行動する機会が減ってしまうでしょう。
自主性のなさは消極的でやる気がないように見えてしまい、いわゆる「指示待ち」の性格になってしまうかもしれません。
人を待てなくなる
親や周囲からいつも「早く」「急いで」と言われていたら、待つという行動のお手本がありません。
人の行動が遅かったら、いつも自分が言われているように「早くして」と急かすのが普通だと思うでしょう。
人を待てるのは、急かされずに待ってもらった経験が必要になるのです。
親が言いがちな言葉を言い換える

つい言ってしまう「子どもにプレッシャーをかける言葉」を、子どもに伝わりやすいポジティブな言葉に言い換えてみましょう。
最初はとっつきにくいかもしれませんが、習慣化すると気持ちのよい声かけが日常的になります。
早くして!
時間が迫っている時、子どもがいつまでも動かない時、つい急かしてしまうことはありますよね。
「早くして!」と大きな声を出しそうになったら、深呼吸をして声のトーンを少し落としましょう。
そして…
・いつまでも動かないようなら、「◯時には出るので、準備をしよう」「次は◯◯をしようか」
・やることが多くて終わらないようなら、「◯と◯だけ終わらせようか」「一番大切なことから取りかかろう」
など、「早くする」という最終段階の指示を出すだけでなく、子どもが行動できるようなプロセスを手伝ってみましょう。
基本は「子どもが決めるのをサポート」という気持ちで、声かけをするといいですね。
ちゃんとして!
この「ちゃんとする」という声かけは、実は多くの子どもを悩ませています。
子どもは何をすればいいのか、何をすることが「ちゃんとする」ことなのかが分からずに行動できないのです。
言い換えのコツは、どうしてほしいかを「具体的に伝える」こと。
成長するにつれ、「ちゃんとする」を理解できるようになるでしょう。
・身だしなみを整えてほしいなら、「シャツを入れて」「靴のかかとを踏まないで」
・勉強や宿題をしてほしいなら「◯時までに宿題終わらせよう」「字を丁寧に書いてね」
・片付けをしてほしいなら「ノートが開けるくらいに机を片付けて」「本を本棚に戻して」
・態度を正してほしいなら「今から話をするから聞いてね」「意見を教えて」
先に行くよ
急かしても子どもが急がない場合、つい「先に行っちゃうよ」などと言ってしまいますよね。
しかし子どもに早く行動させようと「脅し」のようなニュアンスで使っていると、「結局待ってくれている」と効き目がなくなります。
そして本当に置いて行ってしまうと、子どもには危険なこともあります。
・グズグズを止めたいなら、「泣き続けるのとアイス、どっちがいい?」「…(無言で見守る)」
・困っている様子なら、「何か手伝おうか?」「待っているから落ち着いて終わらせようね」
何度言ったらわかるの
何度注意しても聞かない、直らないという時、つい言ってしまいがちなこの言葉。
子ども自身も、どうしたら改善できるか迷っているかもしれません。
・何度も同じことを繰り返すなら、「少し休憩しようか」「もっと楽しいやり方を見つけたよ!」
親子で一緒に解決策を見つけられるといいですね。
子どもの行動がスムーズになる声かけや伝え方のコツは?

つい口にしてしまう「早くして!」「急いで」という言葉ですが、これを言うことで子どもの行動が早くなることはほぼありません。
子どもがスムーズに行動するには、伝え方や言い方が大切。
スピーディな行動を促す声かけのコツを紹介します。
◯ 次を見通せるように伝える
◯ 一つの行動に集中させる
◯ ボードなどで見える化
◯ ゲーム感覚を取り入れる
◯ 子どもに選択肢を渡す
◯ スムーズに行動できたら褒める
次を見通せるように伝える
大人は外出する時間や締め切りから逆算して、準備を始めることができます。
しかし子どもにはちょっぴり難しいかもしれません。
「おもちゃを片付けたら、一緒にテレビを見て、その後はお風呂だね」
「明日は学校から帰ったら、着替えてすぐ習い事に出発だよ」
など、具体的にプロセスを示したり、「次はどうなるか」という見通しを伝えるとスムーズに動けることがあります。
一つの行動に集中させる
一度にいくつも「やるべきこと」があると、子どもは混乱して何から手をつけたらいいのかわからなくなってしまいます。
子どもをスピーディに行動させたい時は、「早く準備をして」と言うよりも、「まずは歯を磨こう」「最初に着替えよう」などと、一つの行動に集中させましょう。
ボードなどで見える化
ボードなどに時計の絵と「やるべきこと」を書き、「この時間までに終わらそうね」と伝える。
出発までにすることを順番にマグネットに書いておき、終わったら一つずつ裏返していく。
など、わかりやすく「デッドライン」や「行動」を見える化することで、子どもも行動に映しやすくなるでしょう。
ゲーム感覚を取り入れる
「どっちが靴を早く履けるか競争ね!」「今日のおもちゃ片付けタイムトライアル、スタート!」など、ゲームや競争の要素を入れ込んでみましょう。
子どもは義務感を感じずに、楽しみながら行動に移せるようになるでしょう。
集中力や注意力、精神力なども同時に養われます。
親も一緒に参加するとより盛り上がるので、おすすめです。
子どもに選択肢を渡す
例えば「出かける時間」や「やること」は子どもが選べなくても、「何を着るか」や「どの道具を使うか」など、子どもが決めてもいいものはありますよね。
子どもに選択肢を渡すことで、子どもは「自分が選んだ」という意識になり、主体的に動けるようになるでしょう。
心理的にも「自分がコントロールしている」と感じると、人は幸福感を感じストレスにも強くなるといわれています。
何かを押し付けられたり、無理に行動させられるよりも、「自分で選んだ」と思うことがポジティブな行動につながるのです。
スムーズに行動できたら褒める
いつもより少し早く行動したとしても、親はつい「もっとできる」「まだまだ」と思いがち。
しかし、少しでも子どもの頑張りが見えたら、
「今日は早く支度ができたね!」
「部屋がいつもよりキレイになってる」
「ゲームをすぐにやめて、宿題できたね」
と、少しの進歩も認めて褒めましょう。
子どもは頑張りを見てもらえた安心感と、認めてもらった嬉しさで「次もやろう」と思うはずです。
よい行動を大人が認めると、それが強化され、子どもはぐんぐんと成長するでしょう。
「早く早く」は逆効果! 急がば回れの気持ちで

「早く」「急いで」といつも急かされていると、自己肯定感が低くなったり、考える力が育ちにくかったりと、あまり子どものプラスにはならないようです。
子どもを追い立てることで、子どもがやる気になったり、行動がスピーディになるならいいですが、逆効果ならイライラするだけ無駄ですね。
もし時間に少し余裕があるなら、具体的に指示したり、やることを減らしたりしながら見守りましょう。
もしいつも行動が遅いようなら、「どうしたら行動が早くなるのか」を親子でじっくり考えてみるのも手です。
つい家の中でだと強い口調でわが子に注意してしまうようなら、「他人の子ならどう言うか」「外でも同じように注意するのか」を意識してみてもいいかもしれません。
「早く!」「急いで!」では、子どもの行動は早くならないと理解し、わが子が動けるようになる工夫をしてみましょう。
・「早く早く」といつも言われている子どもは、考える力が育ちにくく自己肯定感も低くなるなど、悪い影響がある。
・「早く」「ちゃんとして」「先に行くよ」などと言いたくなったら、子どもが行動しやすくなるような言い換えをするとよい。
・子どものスピーディな行動には、「次を見通せるように伝える」「一つの行動に集中させる」などの声かけのコツがある。
(参考文献)
・こどもまなびラボ | 【状況別】「早く!」の代わりに使いたい“魔法の言葉”
・oriori | 子どもに言ってしまう「早くして」が与える影響とは? 代わりに使える効果的な言葉も
・こどもまなびラボ | 「早くしなさい!」は誰のため? 自己肯定感が高い子どもの親の習慣
・HugKum | 「やめなさい!」「早くして!」つい言いがちな声かけを変える!2歳・3歳・4歳向け、ポジティブ言い換えガイド
・天神 | 子どもに対する「早くしなさい!」をポジティブな言葉に言い換えるためのポイント6つ
・コノバス | 「早くして!」と言わずに済む! 親も子もスムーズに動けるようになるコツ