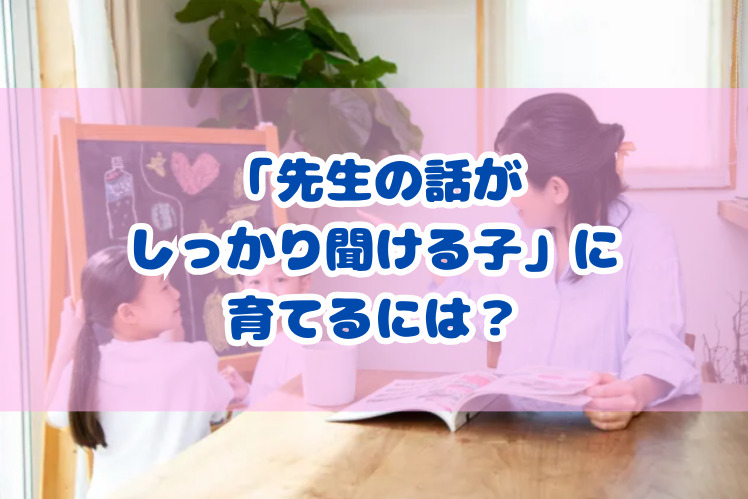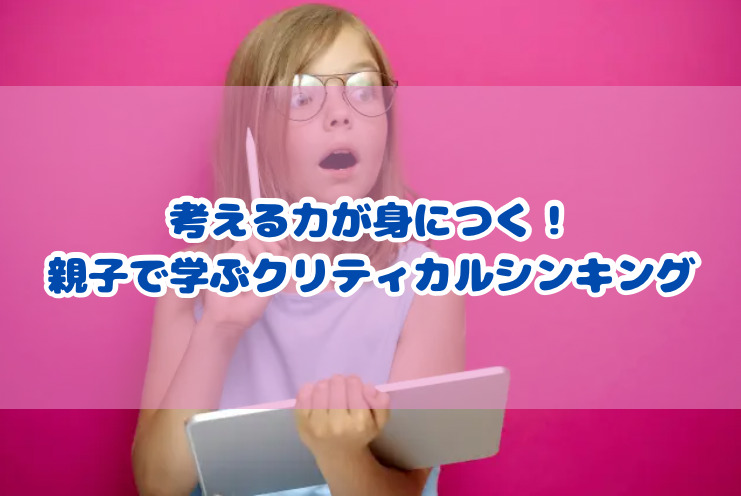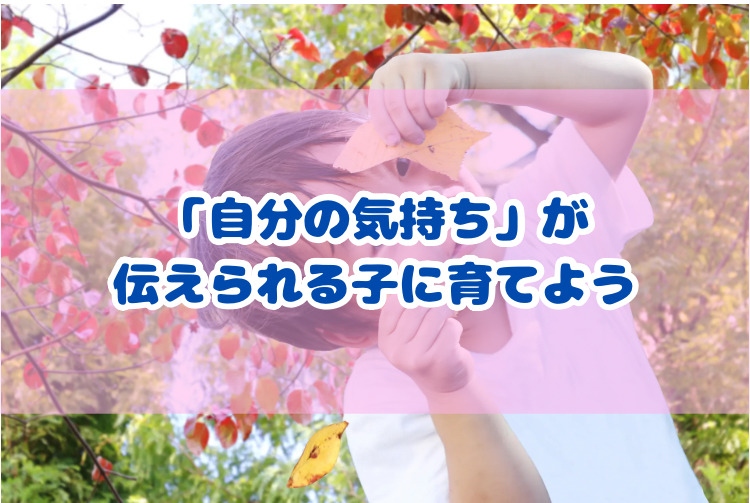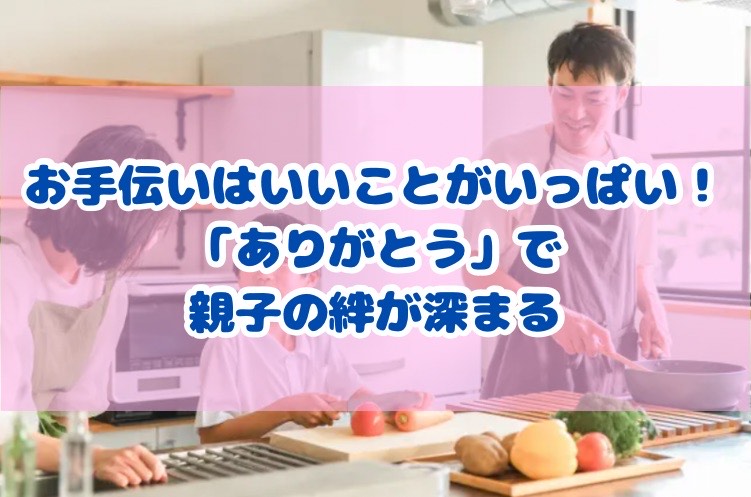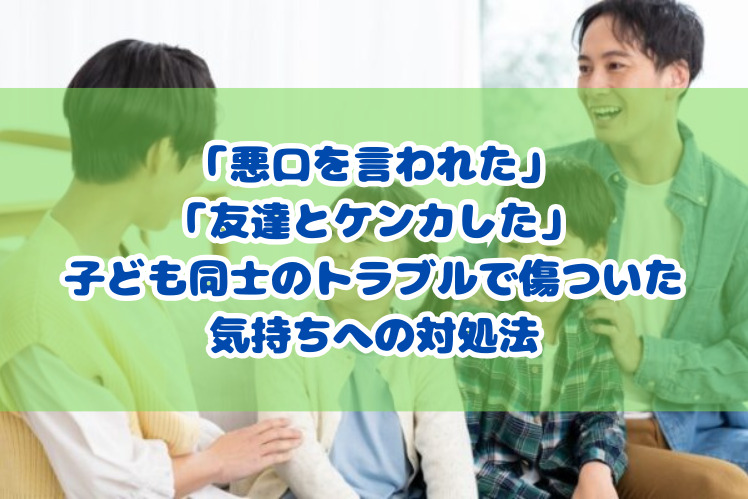子どもと目を合わせていますか?アイコンタクトで親子のつながりを強化する
更新日: 2025.02.25
投稿日: 2025.02.21
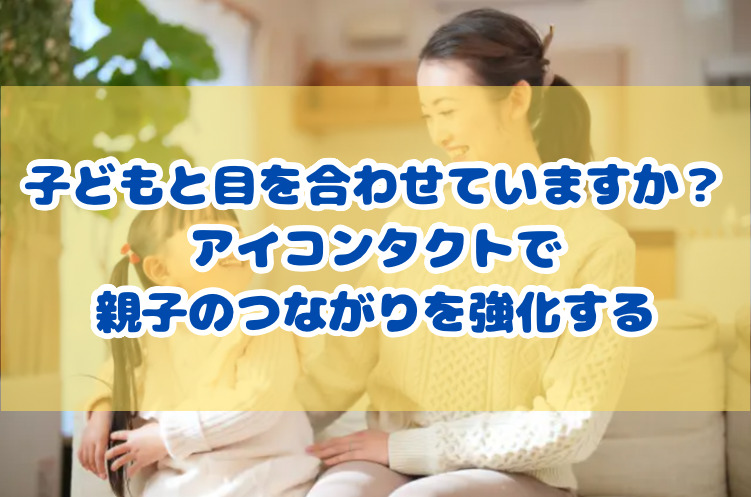
毎日子育てをしていると、
「用事をしながら子どもの話を聞いてしまう」
「スマホに通知がくると、つい気になってしまう」
なんてこと、ありますよね。
しかし相手と目を合わせる「アイコンタクト」は、「あなたの話を聞いてるよ」「あなたを受け入れています」という無言のメッセージであり、コミュニケーションの基本です。
特に子どもはボキャブラリーが少なく、雄弁に話せない分、目で訴えてくることが多いので、子どもの目を見ながら話を聞くことは大切です。
スマホやゲーム機器、PCなどの電子機器が生活に入り込んだことで、アイコンタクトをとりながら話す機会が減り、対面でのコミュニケーションが苦手な子どもも増えています。
今回はアイコンタクトのメリットや、相手と目を合わせるのが苦手な人にそのコツなどを紹介します。
もくじ
アイコンタクトって大切なの?

人と話をする時、目を逸らされたり、目を合わせてもらえないと不安になりませんか?
それは大人も子どもも同じ。
話をする時、伝えたいことがある時は、しっかり相手の目を見て話すと、内容がより伝わりやすくなります。
また話を聞く時も、目を見ながら耳を傾けると「あなたのことを受け入れている」「理解しようとしている」というメッセージになります。
反対に、何か別のことをしながら話を聞いたり、アイコンタクトを取らないままだと「僕に関心がないんだな」「どうでもいいと思ってるんだ」と感じてしまい、次第に話したい気持ちが薄れてしまいます。
話をしたりコミュニケーションを取る時は、目を合わせるアイコンタクトが大切。
ただし、じっと見られることが苦手な子どもや、「どこを見ていいかわからない」という人もいるので、コツを掴んで上手にアイコンタクトをとっていきましょう。
スポーツでも使われる「アイコンタクト」

アイコンタクトには、意思疎通を図るという役割もあります。
例えばサッカーやバスケットボールで、目線を送って「ボールがほしい」と要求したり、反対に「パスするよ」という意思表示をするなど、スポーツ中の合図として使われることが多くあります。
また目線を送ってパスを出すように見せかける「フェイント」として使われることもあるでしょう。
これは戦術などが相手に見抜かれないように、声を出さずに次の動きを指示したり、確認をするためで、普段から綿密なコミュニケーションを取っている仲間同士で行われるテクニックです。
このようにアイコンタクトだけででコミュニケーションが取れるほど、目と目と合わせるだけで意味や感情などの多くの情報がやり取りできるのです。
アイコンタクトをすると、子どもや人間関係が変わる! そのメリットとは

では、親子でアイコンタクトを取るとどんな変化が起こるのでしょうか。
アイコンタクトのメリットを紹介します。
○ 信頼関係が築きやすくなる
○ 集中力や理解力が高まる
○ コミュニケーションが得意になる
○ 自己肯定感が高まる
○ 人に共感できるようになる
信頼関係が築きやすくなる
相手の目を見ることは、「あなたに興味があるよ」「話を聞かせて」という意思表示になるので、相手も話しやすくなり信頼関係が築きやすくなります。
また相手に安心感を与えることができるので、子どもが不安を感じていたり、言いにくいことがあっても、アイコンタクトで緊張をやわらげて話しやすい雰囲気をつくることができるでしょう。
集中力や理解力が高まる
会話の最中に目と目が合っていると、子どもは話をすることにも話を聞くことにも集中できるようになります。
また集中をすることで話を漏らさずに聞くことができ、理解力もアップするでしょう。
これは学校や塾の授業などでも応用でき、理解力アップにつながるので身につけたいスキルですね。
コミュニケーションが得意になる
日常的にアイコンタクトを取って人と話をしていると、話を聞いたり、意見を言うことに苦手意識がなくなります。
すると他者との意思疎通がスムーズになり、対話力やコミュニケーション力が自然と身につくでしょう。
自己肯定感が高まる
親からのアイコンタクトは、「あなたを見てるよ」「大丈夫だよ」「あなたの味方だよ」というプラスのメッセージとなって子どもに伝わります。
それにより子どもは自信がつき、それが「自己肯定感」や「自己効力感」につながるでしょう。
人に共感できるようになる
アイコンタクトが増えると、相手の目の動きや表情から気持ちを察する力や読み取るが身につきます。
相手の気持ちを想像できるようになると、相手への共感力がつき、思いやりの気持ちが育つでしょう。
アイコンタクトが苦手な人や子どもはどうしたらよいか?

アイコンタクトが重要なことは理解できても、どうしても「目を合わせるのが苦手」という人もいるでしょう。
ここでは少しずつアイコンタクトに慣れる方法について考えていきましょう。
アイコンタクトが苦手な「子ども」の場合
怖がりの子どもや恥ずかしがり屋の子どもは、目を合わせるのが苦手というケースも多いでしょう。
そんな時は、
・子どもの好きなぬいぐるみや人形の目を見てもらう。
・鼻や眉間を見るようにアドバイスする
などの方法を試してみましょう。
「ちゃんと目を見なさい」「どうして目を合わせないの!」とアイコンタクトを無理強いしてしまうと、余計に苦手意識を持ってしまい、人との会話がスムーズに行かなくなってしまうことも。
まずは「会話を楽しく」「安心した気持ちで話す」ことをクリアして、少しずつ目を合わせる練習ができるといいですね。
アイコンタクトが苦手な「大人」の場合
意外と多い「アイコンタクトを苦手に感じる大人たち」。
大人になると、仕事や人間関係で失敗した経験なども重なり、余計に苦手意識が強まってしまうこともあります。
まずは「目を見なきゃ」「不安そうに見えたらどうしよう」などと、自分で自分にプレッシャーをかけないようにしましょう。
まずは
・短い間、一瞬だけ目を合わせるようにする。
・眉間や眉毛など、目の周辺を見るようにする。
・目線を外す時は上か下の縦に外すようにする(横に外すと相手を否定しているように見える)。
などを心がけてみましょう。
アイコンタクトが得意な人でも、会話中はずっと目を合わせているわけではありません。
心理学の研究では会話時間の半分ほど目線が合っていれば、最も友好的に感じるというデータもあります。
会話が途切れた時や、話し始める時など、会話の要所で一瞬だけ相手の目を見れば十分です。
そして目を合わせる時は、「睨まずに」「口角を上げて」「やさしい表情」になることも心がけましょう。
心がけるだけで違う! 目と目を合わせた対話を

日本では古来から「目上の人とは目を合わせないのが作法」という慣例あり、アイコンタクトが苦手な文化があります。
しかし現代では、「目を合わせないのは嘘をついているから」「自信のなさの表れ」として捉えられてしまうことも。
実際、子どもと目を合わせて会話をすると、子どもが自信をつけたり、コミュニケーションの苦手意識がなくなったりとよいことがたくさんあります。
目線を合わせることは、相手を受け入れているサインになり、言葉にしなくても相手を肯定し励ます意味にもつながります。
親子だけでなく友だち同士や夫婦でアイコンタクトを取ることで、より絆が深まるはずです。
子どもと話をする際に家事をしながら、スマホを触りながら話をするという方も多いかもしれませんが、忙しくても少しだけ手を休めて、子どもの目を見ながら話を聞いてみましょう。
・相手と目を合わせるアイコンタクトは「コミュニケーションの基本」。
・子どもとアイコンタクトを取りながら話をすると、「あなたを受け入れている」というサインになり、子どもは自信が持て共感力や理解力が高まる。
・アイコンタクトが苦手な場合は、目を合わせる時間を短くしたり、目から少し外れたところを見るなどするとよい。
(参考文献)
・ベネッセ 次世代育成研究所 | 幼児の言動の意味と援助のポイント
・All About | アイコンタクトとは? 効果と苦手な人の対処法
・Direct Communicatiion | アイコンタクトの心理学的な意味とコツ