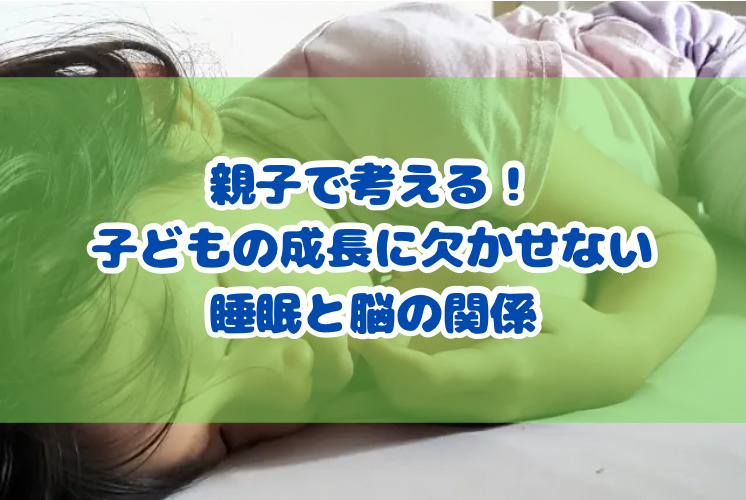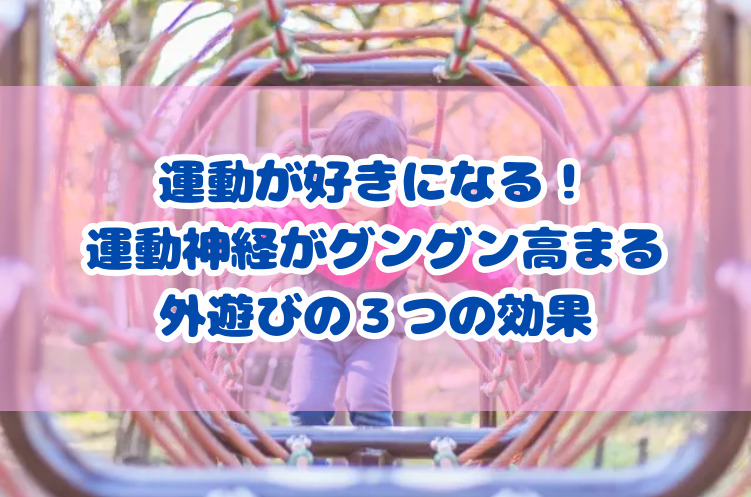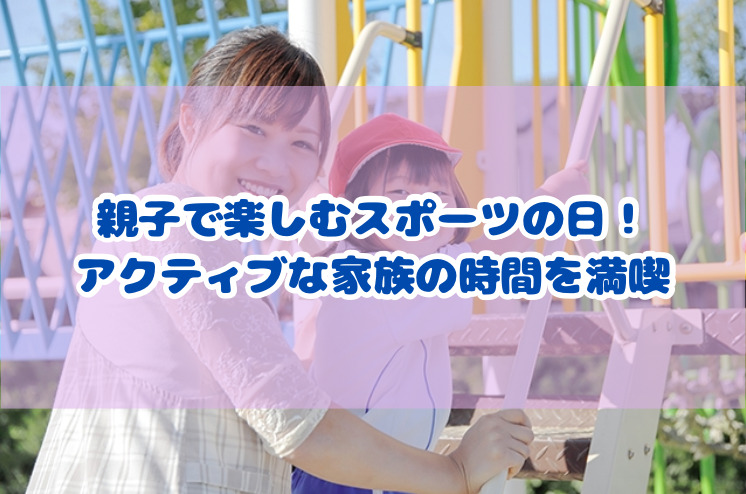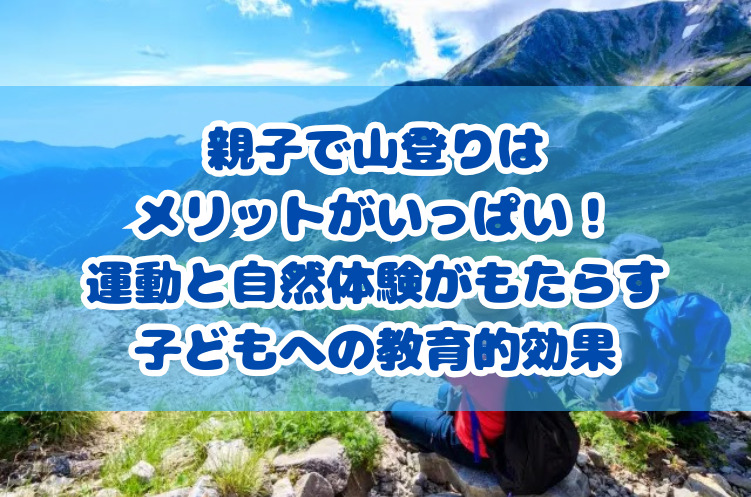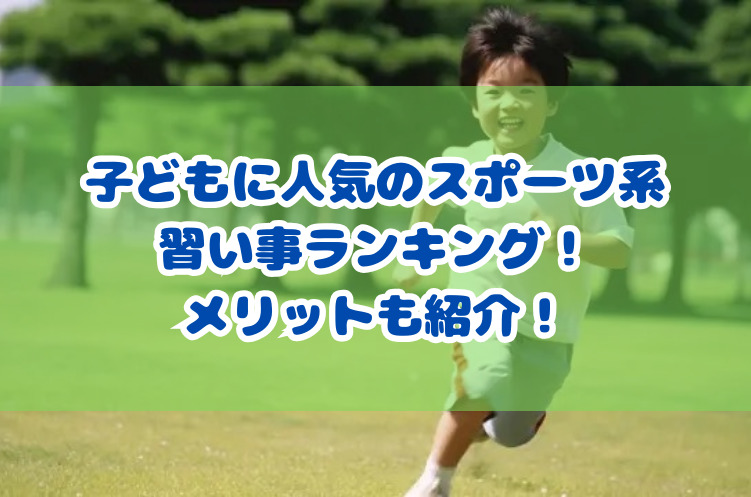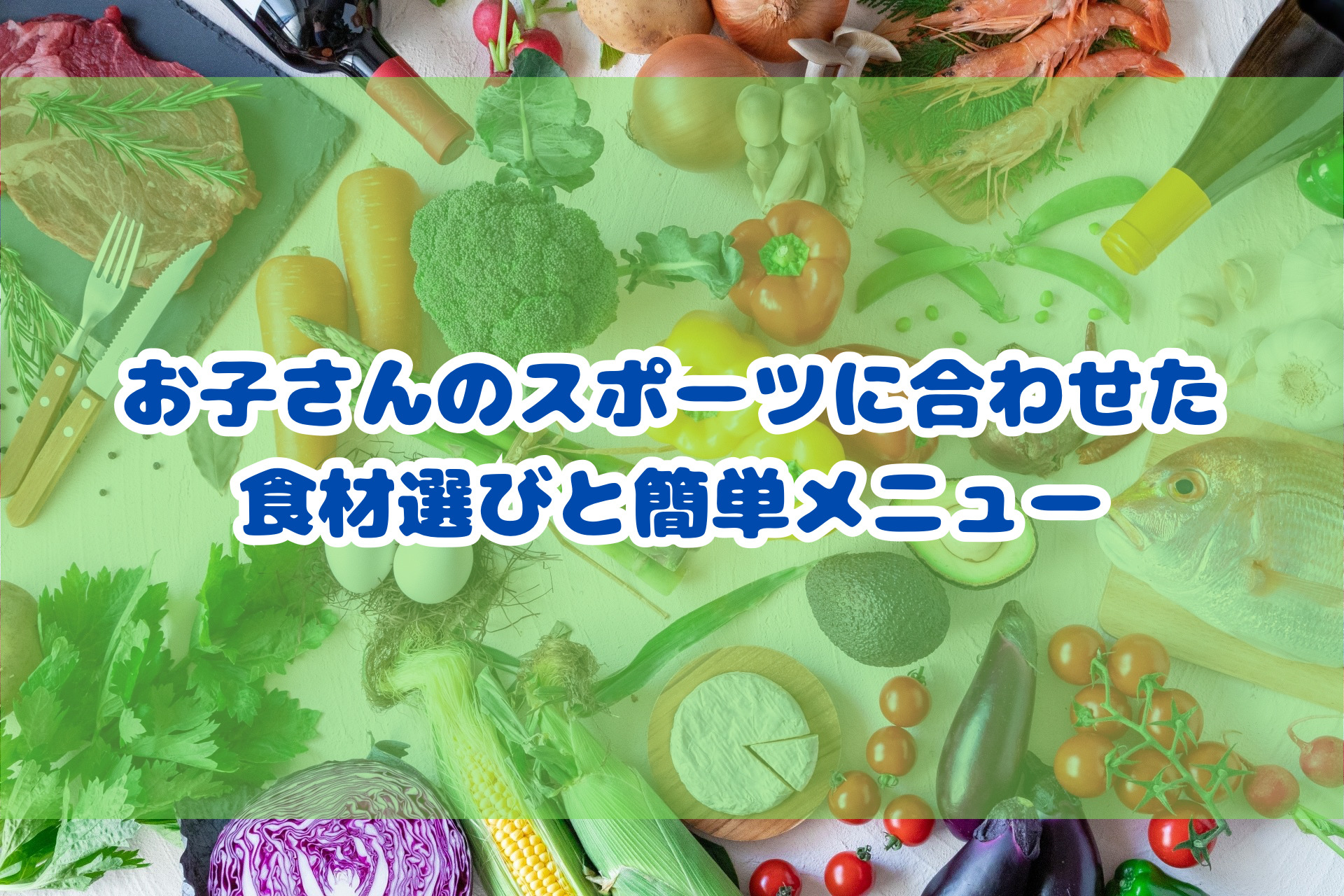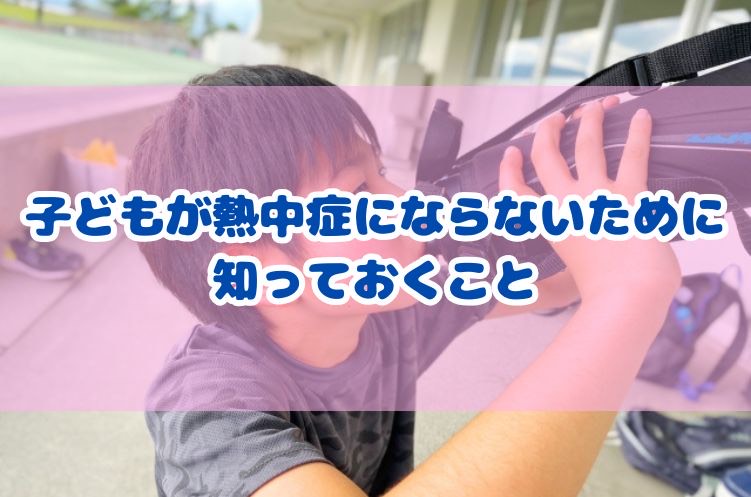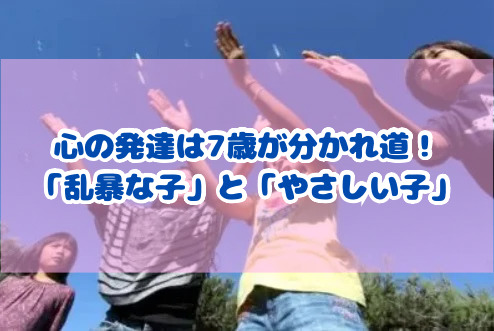持久力強化!子どもの体力低下を止めよう
更新日: 2025.04.14
投稿日: 2023.02.17
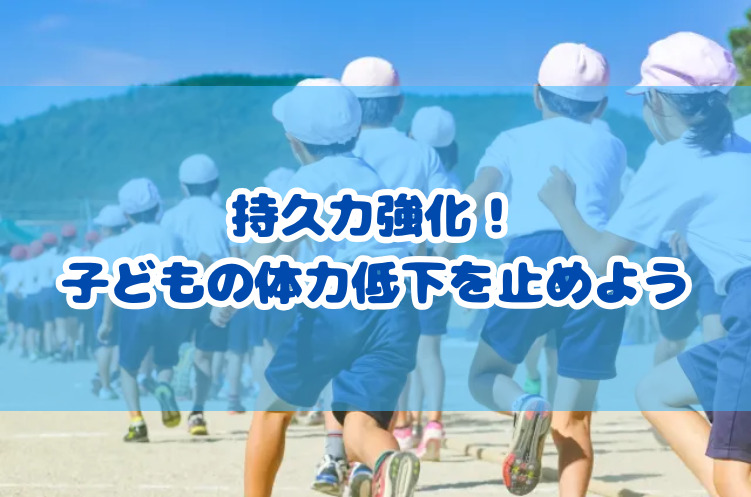
近年、生活環境の変化などにより、子どもの運動不足や体力の低下が指摘されています。
そもそも子どもに体力は、なぜ必要なのでしょうか。
子どもの体力向上のために、なにをすればよいのでしょうか。
文部科学省が制定する体力要因のひとつである「心肺持久力」に着目し、持久力を伸ばす方法について紹介します。
もくじ
運動する子と運動しない子の二極化について

幼少期に適切な運動をすると、丈夫でバランスのとれた体を育みやすくなるといわれています。
特に、運動習慣を身に付けると、身体の発達が促されることにより健康的で活動的な生活習慣の形成にも役立つ可能性が高く、幼少期だけでなく、成人したあとも、生活習慣病になる危険性は低くなると考えられています。
しかし、近年、子どもの運動不足にともなう体力の低下とともに、運動する子としない子の二極化が指摘されています。
まず、子どもの体力低下の直接的な原因として、次の3つがあげられます。
・公園や生活道路といった、子ども達の手軽な遊び場の減少
・少子化や、学校外の学習活動などによる仲間の減少
学校や家庭において、運動の機会が相対的に減少しているのです。
子どもの運動不足にともなう体力の低下は確かに心配ですが、スポーツの習いごとなどで日常的に体を動かしている場合は、さほど気にすることはないでしょう。
問題は、運動する子としない子の二極化です。
保護者の働きや経済状況など家庭環境の変化により、運動する機会が多い子とそうでない子の差が生じているというケースもありますし、子ども自身の運動に対する興味・関心や性格によって、運動習慣の形成に差が生じているとも言われています。
これらを踏まえ、運動する子と運動しない子の二極化を解消するためには、
・子どもたちの体力や運動能力に応じた指導を行う。
・運動が苦手な子どもでも気軽に始められるような学校教育を行う。
以上の取り組みが重要と考えられています。
長距離走が学校行事に取り入れられる理由
運動する子と運動しない子の二極化を解消するための、学校教育における取り組みのひとつとして、長距離走が挙げられます。
文部科学省が制定する7つの身体能力は、「心肺持久力」「筋力」「筋持久力」「瞬発力」「敏捷(びんしょう)性」「平衡(へいこう)性」「柔軟性」。
ちなみに「身体能力」とは、筋力・持久力・柔軟性・俊敏性といった、“既に身体に備わっている能力”をさします。
7つの身体能力のうち、「心肺持久力」とは、運動時に呼吸機能を長時間正常に働かせられる能力をさします。
「有酸素性運動の能力」と密接な関係があり、一定時間の運動を継続することが可能な「体力」や「粘り強さ」も表します。
秋から冬の時期にかけ、「持久走週間」を設けて全校児童で長距離走を行ったり、「持久走大会」を開催し、大会に向けて長距離走の練習を行ったりする学校が多いですが、心肺機能の向上や健康促進などが主な目的と位置づけられています。
「心肺持久力」が著しく高まるのは、ポストゴールデンエイジにあたる中学生の時期といわれていますが、小学生のうちから長距離走を習慣化していくことで、持久力は向上していくと考えられています。
持久力のある子とない子、どこが違う?

持久力のある子とない子。どこが違うのでしょうか。
もちろん、体力の基礎である心肺能力や筋力の有無なども関係してきますが、「ここぞというときに力を発揮し、あきらめない」「どこまで頑張り続けられるか」といったメンタル面の影響も少なくありません。
以下、持久力のある子、持久力のない子の特徴について紹介します。
持久力がある子の特徴
幼少期(1歳~12歳)にたくさん体を動かし、基礎体力がついてることに加え、「あきらめないで、最後までやり遂げたい!」といった粘り強さや、「どこまで頑張り続けられるか」といったチャレンジ精神が豊富が子は、持久力があると考えられています。
食事や睡眠なども、意欲や活動エネルギーに関係してきますので、睡眠時間を十分にとり、規則正しい生活を続けていること、栄養バランスのとれた食生活を送れていることも、持久力につながります。
持久力がない子の特徴
幼少期に「親子で体を動かす遊びを習慣的に行う」など、基礎体力や筋力の土台を作っておかないと、持久力はつきにくくなる傾向があるといわれています。
また、夜更かしが多い、朝ご飯を食べないことがあるなどの生活習慣が続いている子どもは、ここぞというときに体力も気力も続かず、頑張る力を発揮することができません。日々の生活習慣も、持久力と直結しているのです。
子どもの体力・持久力をつける3つのメリットを紹介!

子どもの体力、持久力をつけると、どのようなメリットがあるのでしょうか。3つ紹介します。
運動能力がアップする
子どもの体力、持久力をつけると、タイミングよく動いたり、力の加減をコントロールしたりするなどの運動を調整する能力を養うことができ、運動能力の向上が期待できます。
さらに、走る、しゃがむ、飛び跳ねるなどさまざまな動作によりバランス感覚もアップし、転倒やケガ防止など、自分で危険を回避する能力も向上します。
健康で丈夫な体づくりに役立つ
子どもの体力、持久力をつけることは、健康で丈夫な身体づくりにもつながります。日頃から体を動かして体力をつけることで、心肺機能が鍛えられたり、太陽の光を浴びることで代謝がよくなったりするでしょう。
その結果、ストレス発散や睡眠の質の向上も期待でき、自律神経が整ったり、免疫力が高まったりなど健康で丈夫な身体で日々の生活を送ることができます。
気持ちが安定する
子どもの体力、持久力をつけることは、ストレスや不安の解消、幸福度の向上に貢献し、集中力や効率性を高めることにつながる言われています。
また、スポーツ庁「平成30年度体力・運動能力調査結果」によると、運動頻度が高い子どもほど、精神面が安定している傾向にあることが報告されています。
子どもの時から身体を動かし体力をつけることを積み重ねていく中で、「動くって楽しい」などポジティブな感情や成功体験が生まれ、気持ちの安定につながります。
決定版! 子どもの体力・持久力を伸ばす方法5つ

日々の生活習慣を少し見直したり、「体を動かす」ことを意識したりするだけで、子どもの体力・持久力を伸ばすことができます。子どもの体力・持久力を伸ばす方法を5つ、紹介します。
しっかり歩く
文部科学省では、「できるだけ自分の足で歩くように促すなど、筋力や持久力の発達に対する適度な刺激を与えることが大切」と掲げ、持久力や心肺機能を高めるためにも日頃から歩いたり体を動かしたりする習慣づけを推奨しています。
子どもが疲れるからと、歩ける距離なのに車で移動したりすることもあると思いますが、子どもの運動経験や成長の機会を奪っていることになりかねません。
体調に問題がなければ、移動の際はなるべく自分の足で歩く機会を増やすことを意識しましょう。
ちなみに、中京大学スポーツ科学部教授の中野貴博先生は「体力、生活習慣の獲得のためにも、幼児期には1日1万3,000歩程度の活動量を目標としてほしい」と述べています。
しかし、ただ歩くだけではすぐに飽きてしまい、「疲れた」「抱っこ」などと甘えてくることもあるでしょう。
遊び場をいくつか用意し「次は〇〇へ行こう!」と誘ってみるなど、子どもが飽きずに歩ける関わりを心がけましょう。
楽しく歩くためには、靴選びも大切です。
足の発達が著しい時期にサイズの合っていない靴を長時間履いていると、足が変形してしまう恐れがあります。
長時間歩く場合は、サイズの合った靴を選ぶようにしましょう。
正しい姿勢を意識する
姿勢がいいと、目的動作を行うために効率の良い関節の動きがしやすくなり、瞬発力や持久力を伸ばすことができます。
壁に後頭部・肩甲骨・お尻・かかとをつけ、腰の後ろの隙間に手のひらがギリギリ入るくらいの状態が、正しい姿勢の目安です。
背骨を伸ばして座ったり立ったりすることで、持久力だけでなく、腹筋や背筋、足の筋肉を鍛えることができます。
食事の時間やいっしょに散歩している時間などに子どもの姿勢をチェックし、姿勢がよくないと感じた場合は声をかけてあげましょう。
外遊びを増やす
鬼ごっこやボール遊び、縄跳びなど外遊びを増やすことにより、持久力だけでなく、空間認知能力、瞬発力、柔軟性などを育むことができます。
※空間認知能力とは、自分のからだと自己を取り巻く空間について知り、体と方向、位置関係(上下・左右・前後・高低)を理解する能力
短い時間でも、集中して遊ぶことができればOK。
親子で楽しみながら、外遊びの時間を過ごしましょう。
家の中で体を動かす
外に出かける時間はなくても、家の中で体を動かすことはできます。
・室内用トランポリン、バランスボールなどの室内遊具を活用する。
・大人の腕に子どもがぶらさがったり、お馬さんごっこをしたり、親子で“じゃれあい運動”をする。
など、さまざまな方法があります。
運動系の習い事をする
運動能力の伸びしろがある時期に、たくさんの運動を経験することで持久力を育むことができます。
運動系の習い事に取り組むことで、日常生活とは異なる動きや経験を積み重ねることができます。
運動系の習い事にはたくさんの種類がありますが、自分に合うものを選ぶことで、子どもは「楽しい」が原動力になり、自ら積極的に体を動かすようになるでしょう。
体を動かす楽しさを知る経験を重ねることが大切

子どもの体力や持久力を伸ばすためには、運動を続けることがとても大切です。
しかし中には、運動を苦手に感じる子どももいます。
運動が苦手な子どもに、「持久力がつくから」といって、無理強いをするのはかえって逆効果。
大切なのは、子ども自身が、「体を動かすことが楽しい!」という体験を少しずつ積み重ねていくこと。
サッカー、野球、バスケットボールなど好きなスポーツがある子は、そのスポーツを楽しみながら、思う存分体を動かしましょう。
好きなスポーツが見つからない場合は、近くの公園などで鬼ごっこやかくれんぼ、木のぼりなど、子どもがワクワクする遊びを通して、体を動かしたときの爽快感をたくさん経験させてあげましょう。
・子ども時代に体力・持久力をつけておくことが、健康的で活動的な生活習慣の形成につながる。
・しっかり歩く、姿勢を見直すなど、日々の生活をチェックしよう。
・子どもが好きなスポーツやワクワクする遊びを楽しむ時間を作ることが大切。
参考文献)
「持久力の“ある子”と“ない子”の違い――「頑張る力」が弱くなる生活習慣とは?」
(出典:こどもまなびラボ)
「子どもの身体能力をより効果的に伸ばす方法を紹介します!」(出典:へやすぽnavi)
「1日1万3,000歩、歩いてる? よく歩く子はキレにくく、集中力があり、運動能力も高かった!」(出典:こどもまなびラボ)
「平成30年度全国体力・運動能力調査結果」(出典:スポーツ庁)