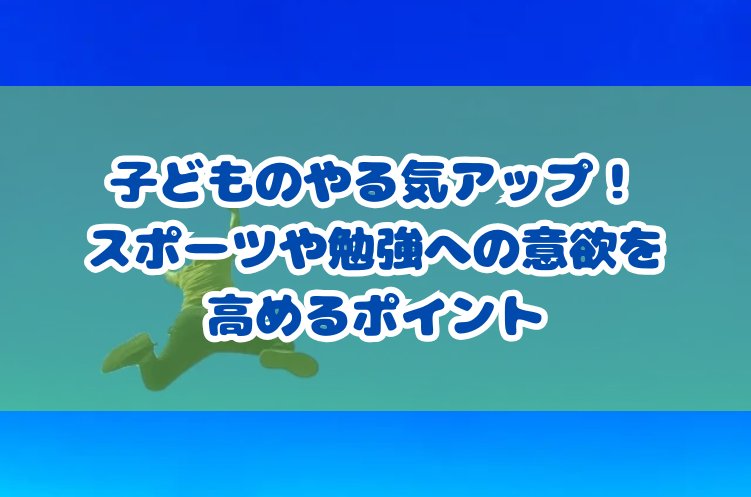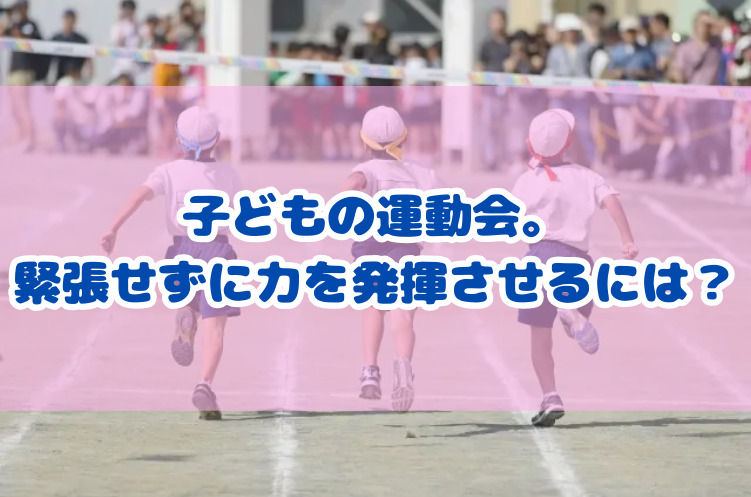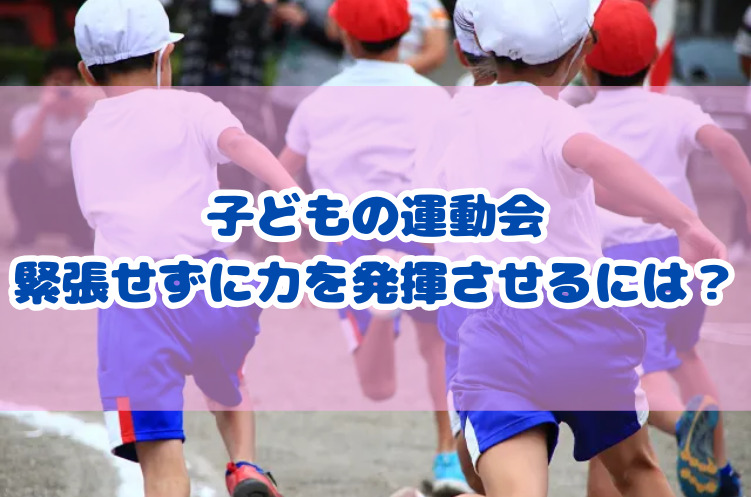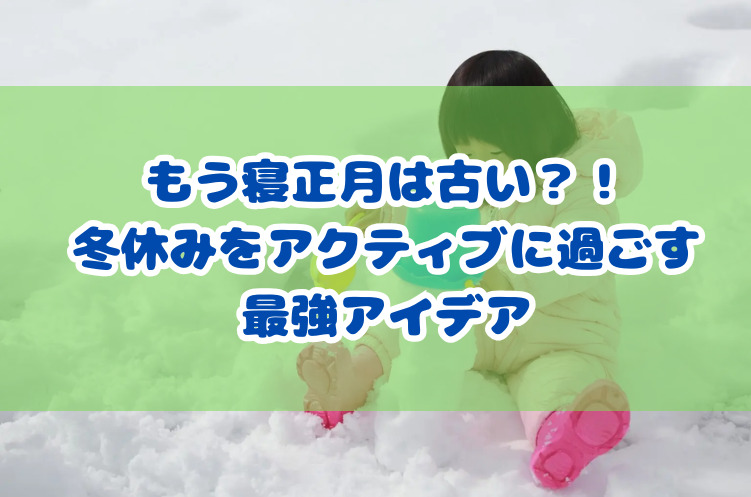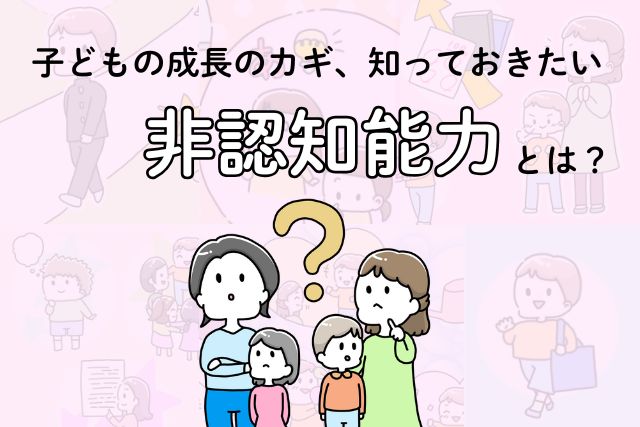つい、NG行動していない?子どもの習い事見学のときに心がけたいこと
更新日: 2025.02.13
投稿日: 2025.02.18
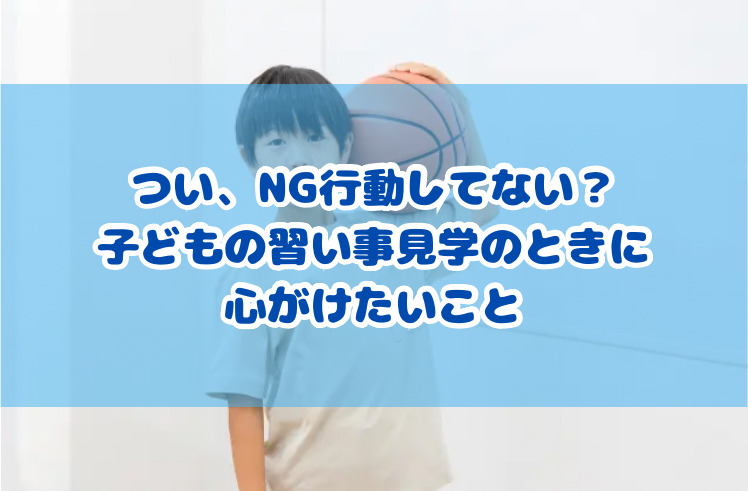
子どもの習い事、見学していますか? 見学のとき、わが子をしっかり見ていますか?
練習中にむやみに声をかけたり、ダメ出しはNG。
この記事では、子どもの習い事を見学するときに心がけたいことを紹介します。
子どもの習い事の目的とは?
見学のとき、親がついやってしまいがちなNG行動

子どもの習い事は、多くの保護者の関心事のひとつ。
わが子が習い事を始めると、「せっかく始めたからには上達してほしい」「子どもの将来に結びついてほしい」など、親としてどうしても、その成果を期待してしまうものです。
しかし、心身の発達途中である幼児期から学童期は、子どもの習い事に過度の期待や無理強いは禁物です。
親があまりに期待しすぎると、わが子のちょっとしたつまづきを受け入れられずにきつく叱ってしまったり、「こんなはずじゃなかった」などの気持ちを抱いたりして親自身が苦痛になるでしょう。
子どもが習い事を始めたら、お母さんお父さんは、できたことを認めて励ましていくことが大切。
習い事の内容に興味を持たず、コーチにまかせっぱなしはNGです。
習い事を親子のコミュニケーションの一貫として日々の生活に取り入れ、子どもがふれた習い事の世界を楽しんで継続できるよう、支えていくことが大切です。
子どもの習い事の送迎ついでに、レッスンを見学する保護者の方も少なくないでしょう。
見学のとき、保護者がついやってしまいがちな行動が、子どものやる気を奪ってしまうことがあります。
以下、子どもの習い事見学時のNG行動について紹介します。
レッスン中に子どもに話しかけ、ダメ出しする
子どもの習い事の指導は、先生やコーチの仕事です。
親としてはつい子どものできないことばかり目についてしまいレッスン中にもかかわらず、「もっと頑張りなさい」「何でそんなこともできないの」などと言いたくなることあるかもしれません。
しかし、親からダメ出しばかりされてしまうと、子どもが習い事自体に苦手意識を抱いてしまう可能性があります。
ママ友とおしゃべりばかりしている
子どもの習い事のあいだ、ついママ友とのおしゃべりに夢中になってはいませんか?
ママ友付き合いも大切ですし、子育てについて悩みを話したり、情報共有したりすることも大切ですが、習い事の主役はあくまで子どもです。
スマホに集中する
習い事の最中に限らず、子どもが何かの活動をしている際に親がスマホの画面ばかり見ていませんか?
子どもは、そんな保護者の姿を目にして「自分を見てもらえていない」と傷ついているかもしれません。
挨拶をしない
「子どもは親の背中をみて育つ」といわれています。
お世話になっている先生、コーチや、同じ教室に通う友だち、保護者などに挨拶をしない親もいます。
積極的に挨拶する姿を見せることをしないと、挨拶をしないと、子どももそれを真似て挨拶をしなくなるかもしれません。
教室のルールを守らない
当たり前のことですが、「レッスン会場では飲食禁止」「駐輪は指定の場所で」「ゴミは持ち帰り」など、教室のルールを守らない行動はNGです。
他の見学者の迷惑になるような行為をする
見学者が多く、スペースがあまりないのに自分の荷物置き場にしたり、レッスン中に大きな声で携帯電話で話したりなど、他の見学者の迷惑になるような行為は避けましょう。
子どもはそんな大人の様子を見ています。
子どもの習い事を見学するときに大切したいこと

ここでは、子どもの習い事を見学するときに大切にしたいことについて紹介します。
笑顔で見守り、見学後に「できていたこと」「頑張っていたこと」をほめる
見学できる場合は、笑顔で見守り、レッスン終了後、「今日はこんなことしていたね?」「何が楽しかった?」などと話しかけましょう。
「○○できるようになったね」「今日の△△は難しかったね。ママと一緒に練習してみる?」など、できるようになったことに目を向けてほめたり、共感し、できるようになるためのアドバイスを伝えましょう。
「教室全体」を見て、子育てや子どもとの遊びに取り入れる
わが子の様子に注目することももちろん大切ですが、周りの子どもたちの様子や表情、指導するコーチの様子や表情、レッスンの流れなど、「教室全体」を見るよう意識しましょう。
コーチの子どもへの関わり方や声のかけ方が、日頃の子育てのヒントになることもあります。
また、子どもが楽しく取り組んでいたプログラムを、可能な範囲で子どもとの遊びに取り入れるのもおすすめです。
気になること、わからないことがあれば、コーチに相談する
わが子の様子、どんな練習をすればうまくできるようになるのかなど、レッスンを見学した上で気になること、わからないことがあれば、コーチに相談しましょう。
ただ、コーチが次のレッスンを控えている場合もあります。
相談する際は、「少しお時間大丈夫ですか?」など、コーチの予定を確かめるとよいでしょう。
子どもの習い事の見学は、「よい塩梅」が大切

子どもの成長を願う親にとって、習い事の見学は子どもの頑張る姿を見たり、先生やコーチとのコミュニケーションを図る上で大切な機会です。
しかし、熱心すぎる見学は子どもにプレッシャーを与えてしまう可能性も。
子どもの成長段階や性格、そしてその日の様子をよく観察しながら、適切な距離感を保つことが重要です。
幼少期:見守る温かいまなざしを
幼少期は、親の存在が子どもにとって大きな安心感を与える時期です。
見学は、子どもの頑張りを間近で感じ、共に喜びを分かち合う良い機会となります。
いっぽうで、常に監視されているような圧迫感を与えないよう温かいまなざしで見守ることが大切です。
反抗期:見守りつつ、そっと目を離す
成長とともに、子どもは親から自立したいという気持ちが芽生えます。
特に反抗期には、親の見学を嫌がることもあるでしょう。
そのような時は、無理に見学を続けるのではなく、子どもの気持ちを尊重し、そっと目を離すことも大切です。
送り迎え:親子のコミュニケーションタイム
見学を控える代わりに、送り迎えの時間を活用するのも良いでしょう。
習い事の感想や、学校生活の話など、子どもとのコミュニケーションを図る良い機会となります。
時には休憩も大切
保護者も人間です。常に子どもの習い事に付き添うことは、体力的にきつい時もあるでしょう。
時には休憩を取り、自分の心と体の状態を整えることも大切です。
子どもの習い事の見学は、親として子どもの成長を応援したいという気持ちの表れです。
しかし、熱心すぎる見学は、子どもにプレッシャーを与えてしまう可能性もあります。
子どもの気持ちを尊重し、成長段階に合わせて適切な距離感を保つことが大切です。
時には見学を控え、送り迎えの時間を利用するなど、工夫しながら「よい塩梅」を見つけていきましょう。
・子どもの習い事に興味を持たず、先生にまかせっぱなしはNG。
・習い事を見学するときは、最低限のマナーを守ろう。
・コーチの子どもとの関わり方など親の「学ぶ」姿勢が大切。
・熱心すぎる見学はほどほどに。子どもの様子をみながら関わろう。
「子どもの習い事への関わり方。習い事のメリットと親のNG行動」(出典:oriori)
「子どもの習い事をどう考える?」(出典:育児情報誌miku)
「【全然知らなかった…】見学しない方がいいママの特徴」(出典:ニューゲートゴルフ)