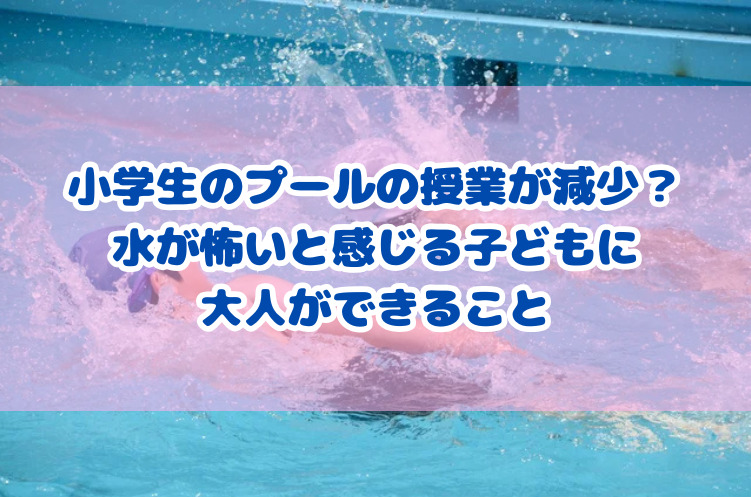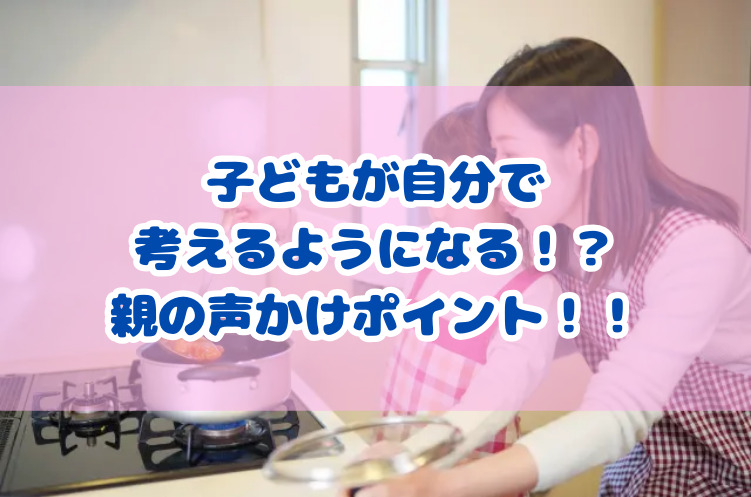昔と今の違いにビックリ!? 令和の小学校の新常識
更新日: 2024.12.03
投稿日: 2024.12.17
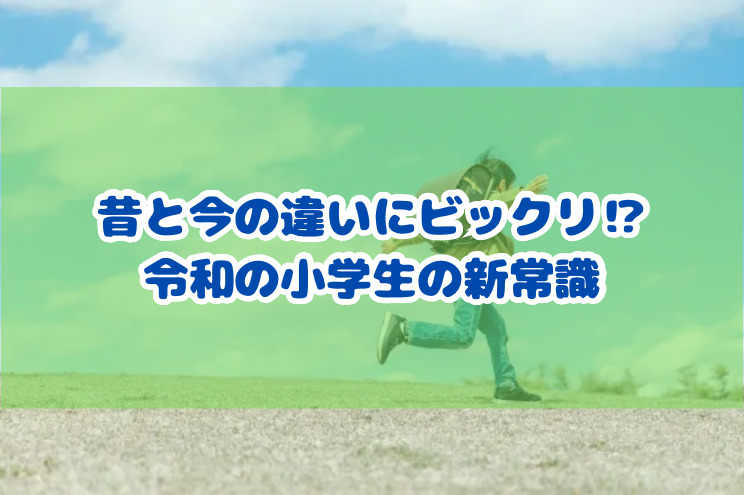
「わが子が通う小学校、自分が子どもの頃とは全然違う!」と驚く保護者の方も多いはず。
令和の小学校では、タブレットを使った授業やプログラミング教育が当たり前になり、昔とは様変わりしています。
子どもたちの学び方から保護者の関わり方まで、令和の小学校の“今”をいっしょにのぞいてみましょう。
もくじ
【学習編】タブレット学習、教科書の記載内容・・・昔と違う3つの大変化

タブレットを使って授業を受けたり、教科書の内容が変わってきていたり。
昔は考えられなかったような勉強方法や学習内容が、令和の小学校では当たり前になってきています。
ここでは、学習面での3つの変化について紹介します。
一人1台端末が支給され、デジタルによる学びが主流に
2020年よりGIGAスクール構想がスタートしてからは、児童ひとり一台のコンピューター端末と高速ネットワークが整備され、デジタルを活用したICT教育が推進されるようになりました。
タブレット端末を用いて自宅でオンライン授業を受けることができたり、宿題に取り組めたりなどの利点があり、音読の宿題も「自宅で動画撮影→タブレット経由で送信」という形式の学校も。
鎌倉幕府の成立は1192年ではない? 教科書の記載が変化
「いい国つくろう鎌倉幕府」と覚えた保護者も多いはず。
長らく1192年とされてきた鎌倉幕府の成立年ですが、新たな史料の発見や分析を通じて「鎌倉幕府の成立時期は1192年よりも早いのではないか」という説が有力視され、1185年と表記されるようになりました。
教科書の記載や内容も、新しい学説を反映して変化しつつあります。
以下、昔と比較して変わっている教科書の記載について、一部紹介します。
⚫鎌倉幕府が成立した年は? 【昔】1192年→【今】1185年
⚫日本最古の貨幣は? 【昔】和同開珎→【今】富本銭
⚫アメリカの第16代大統領は誰? 【昔】リンカーン→【今】リンカン
⚫世界最古の人類は? 【昔】アウストラロピテクス→【今】サヘラントロプス・チャデンシス
⚫狭い湾が複雑に入り込んだ沈水海岸は? 【昔】リアス式海岸→【今】リアス海岸
⚫日本で工業の盛んなエリアは? 【昔】四大工業地帯→【今】三大工業地帯
⚫太陽系の惑星の数は? 【昔】9個→【今】8個
プログラミング教育が必修化
2020年から、小学校でプログラミング教育が必修化されました。
「プログラミング教育」と聞いてピンとくる人はなかなかいないのではないでしょうか。
保護者世代が子どもだった頃にはなかった授業ですし、イメージが湧かないのも仕方ありません。
プログラミング教育が必修化するのは、「プログラミング的思考をやしなうため」。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、つまりは「順序立てて考え、試行錯誤し、ものごとを解決する力」と捉えればいいでしょう。
「プログラミング」という科目が新設されているわけではなく、
4年生(社会)・・・都道府県の特徴を組み合わせて、名称と位置を学習
5年生(算数)・・・プログラミングを通して正多角形の意味を把握し、その理解に基づき正多角形を描く学習
など、「教科の学習のなかでプログラミング思考を養う工夫がされるようになった」ととらえるとよいしょう。
【生活編】宿題は保護者が丸つけ、水筒持参・・・保護者の日常も変化

「宿題は自分でやるもの」そんな当たり前だった考え方が、少しずつ変化しています。
保護者による宿題の丸つけや、水筒の持ち運びなど、子どもたち、保護者の日常は新たな様相を見せています。
宿題は保護者が丸つけする
「宿題は自分でやるもの」という従来の考え方が変わりつつあり、保護者が子どもの宿題を丸付けするルールの学校が増えています。
その背景には、ていねいな学習指導を求める声や、複雑化する学習内容への対応の難しさなどが挙げられます。
保護者と子どもが一緒に学習することで、より深い理解につながるというメリットも期待されています。
水筒は年中持参
衛生面への意識の高まりや、脱水症予防のため、年間を通して水筒を持参することが一般的になりました。
以前は夏の暑い時期に水筒を持参するルールを設ける学校が多かったのですが、地球温暖化が進み、気温が上昇した結果、水筒は年中欠かさず持って行く持ち物の1つになっています。
クラスの連絡網がない
従来、クラスの連絡網は紙媒体で配布されることが一般的でしたが、現在は個人情報保護の観点から、電話番号や住所などの情報が無断で開示されることはありません。
便利になった反面、「新しく仲良しになった友達の保護者との連絡がとりづらい」などの声も。
欠席などの連絡がオンラインに
欠席などの連絡は、オンラインで行うことができる学校が増えています。
先生と直接話す機会は減っているとも言えますが、学校側にとっても保護者にとっても便利な仕組みが広がっています。
ランドセルの横フックは使わない
ランドセルの横フックは、体操着袋などを掛けるために広く利用されていましたが、近年では使用しない家庭が増えています。その理由として、引っ張られたり引っ掛かったりして転倒するなどの事故防止が挙げられます。
家庭訪問がない
家庭訪問は、教員が児童の家庭を訪問して保護者と面談を行うもので、従来は年1回程度実施されるのが一般的でした。
しかし近年では、新型コロナウイルス感染症の影響や、教員の負担軽減、保護者の多忙化などを背景に、家庭訪問を実施しない学校が増えてきています。
「置き勉」OKに
学校により方針が異なりますが、重量のあるタブレットをはじめ、教科書などを教室へ置いておくことが認められている場合もあります。
忘れ物防止にもなりますし、登下校の負担が少しでも減ると、保護者としても安心ですよね。
【番外編】出席番号が男女混合、部活動の指導が外部指導員に・・・まだまだある! 令和の新常識

ここでは、出席番号は男女混合、部活動の指導は外部指導員が担うなど、中学校も含めた学習面、生活面以外の変化について紹介します。
出席番号が男女混合
出席番号は、男女別で五十音順順が主流だったのではないでしょうか。
ところが令和時代の小学校では、「男女混合の名前順」や「誕生日順」など、学校によってさまざまな方法が採用されています。
いずれの方法でも「男女混合」というのは基本の考え方のようです。
部活動の指導は外部指導員が担う
ひと昔前は、部活動の指導は主に学校教員が行っていました。
しかし昨今、教員の長時間労働の問題などから、中学校の部活動指導の外部委託が動き出しており、外部指導員が担っている地域もあります。
いかがですか?
今回紹介した事例以外にも、英語教育の必修化やカリキュラムが前倒しされ難易度が上がっていることなど、昔と今ではさまざまな違いがあります。
驚くことも多いですが、「ママやパパのときはこうだったよ」と家族で話してみると、会話が盛り上がるかもしれません。
さまざまな面から便利になっている令和の小学校ですが、学校や担任の先生との接点が少なくなっている部分もあります。
学校とのコミュニケーションを大切にしながら、わか子の学校生活をサポートしていきましょう。
・令和の小学校は、タブレット学習、プログラミング教育などデジタル化が進んでいる。
・コロナの影響、教員の多忙化などにより、保護者のサポートもさまがわりしている。
・担任の先生や学校とのコミュニケーションを大切にわが子の学校生活をサポートしよう。
参考文献)
【うそ!? 変化する教科書】鎌倉幕府の成立は西暦何年? 「マヂか? 」「これびっくりです! 」
(出典:マイナビニュース)
「昔と大違い?!令和の小学生あるある5選」(出典:ベネッセ教育情報)
「入学してびっくり!昔の小学校と違いに気づいて驚いた7つのこと」(出典:サンキュ!)
「ここが違う! 平成の小学校と令和の小学校」(出典:こそだてまっぷ)