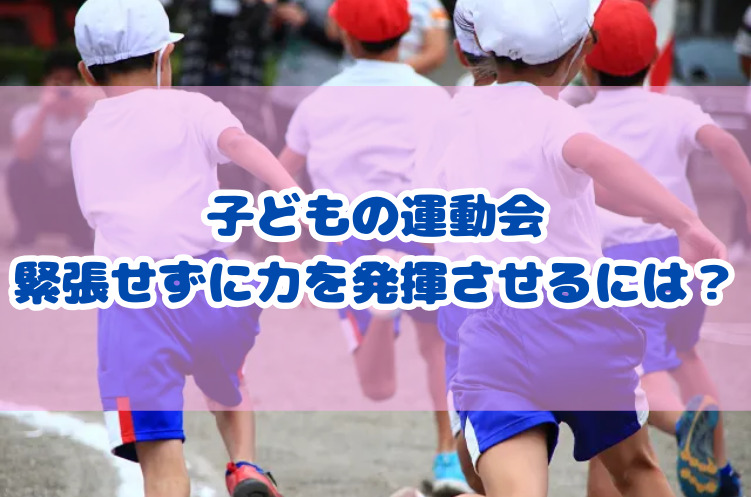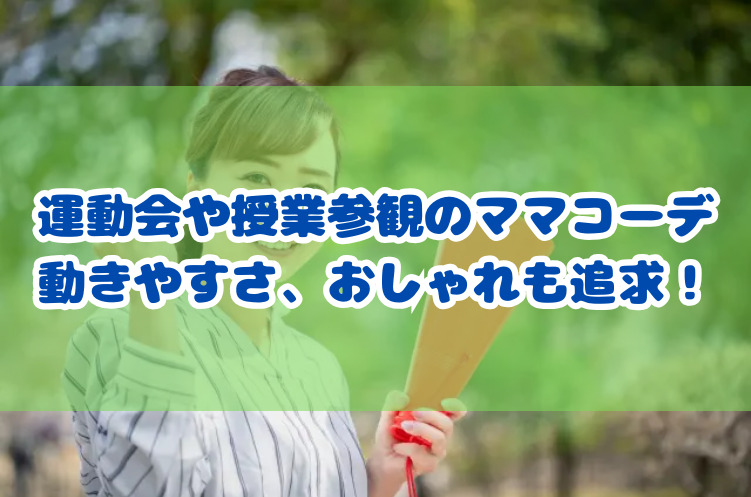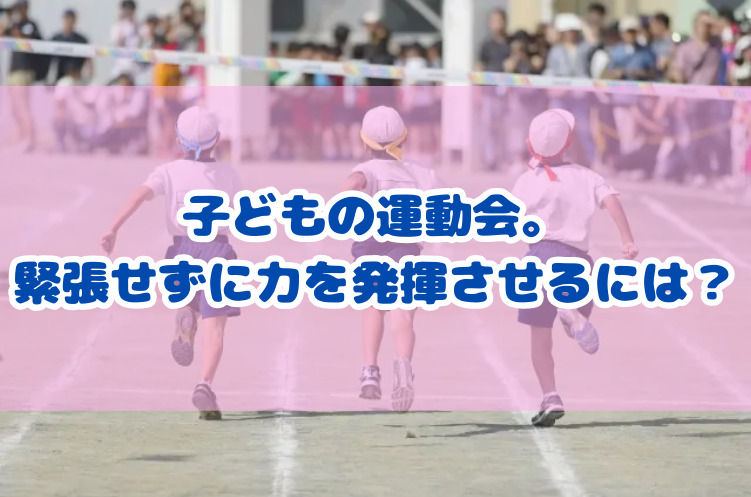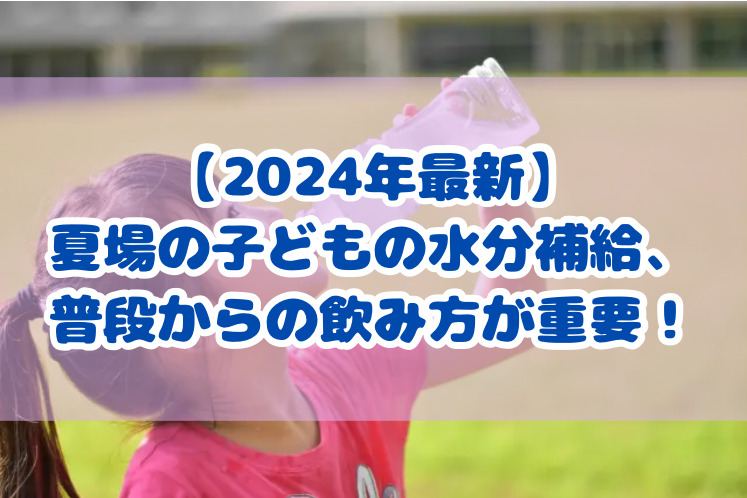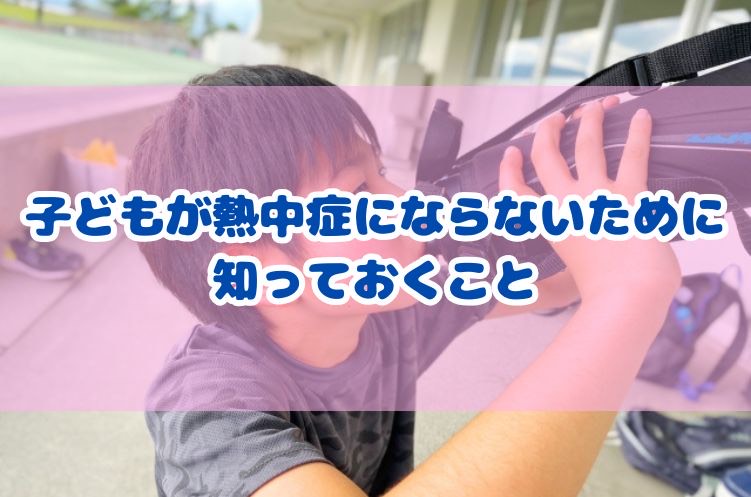今と昔の運動会事情を比較!家族で楽しむための準備を紹介
投稿日: 2024.04.12

ここ数年、コロナの影響で競技の縮小や時間の短縮をせざるを得なかった「子どもの運動会」。
コロナ禍を経た今、気候変動による真夏日の増加や学校教育のあり方の見直しに加え、
「学校や保護者の負担が大きい」「家族の形の変化」など、さまざまな理由から、考え方や運営スタイルが変わりつつあります。
運動会の最新事情と、家族で楽しむための準備についてご紹介します。
もくじ
最新の運動会事情

運動会は、日本の学校教育において重要な行事です。
しかし、近年では、猛暑、共働き家庭の増加、運動会の意義の見直しなどにより、昔と比べてさまざまな変化が見られます。
中でも多いのは、競技の数が減り、「午前中のみの開催」など短縮傾向にあること。
これは、温暖化で気温上昇が年々進み、熱中症対策を重視するためです。
また、徒競走やリレー、騎馬戦など勝ち負けを競う風潮が薄れ、運動会が単なる「競技の場」ではなく、「子どもたちが仲間と協力し、達成感を味わう場」として認識されつつあることも、大きな特徴といえるでしょう。
共働きの家庭が増えたことから、1日がかりで運動会を開催する場合でも、「お昼は子どもたちは教室でお弁当、保護者は一旦家に帰る」など、昔は一般的だった「親子で食べるお弁当タイム」が廃止された学校も多く存在します。
さらに、誰でもSNSにアップできる風潮を鑑み、「写真や動画の撮影が禁止」という学校もあります。
以下、最近の運動会の具体的な傾向を紹介します。
・競技の数が減り、「午前中のみの開催」など短縮傾向にある。
・時間を区切り、学年別で開催するなど開催スタイルが変わる傾向にある。
・勝利を重視する風潮は薄れ、順位をつけない競技が増えた。
・お昼は親子別々で食べる。
・保護者による写真や動画の撮影が禁止の学校もある。
時代の変化に伴い、運動会のスタイルも変化していますが、運動会は、子どもたちの成長を祝う大切な行事に違いありません。
春の運動会を楽しむためのポイント

運動会は非日常のイベントなだけに、普段使わないアイテムを持って行ったり、準備が必要なこともあります。
ここでは春の運動会を楽しむためのコツをご紹介します。
失敗しない持ち物リスト
運動会は、子どものみならず親にとっても一生の思い出になる行事。
「あれを持って来ればよかった!」とならないように、持ち物リストを作っておくと便利です。
持ち物リスト
- カメラ
- 今はスマートフォンでも十分な写真・動画が撮影できます。写真係と動画係に分かれて撮影するなど、あらかじめ分担を決めておくとスムーズです。
- モバイルバッテリー
- フル充電で準備をして、電池切れの悲劇は避けたいもの。スマートフォンで撮影予定の場合は、必ず持参を。
- プログラム
- 学校から配られる演目のプログラムのほかに、走る順番やダンスでの立ち位置などが記入されたものがあれば忘れずに。
- 三脚
- カメラを固定できるので便利な反面、アングルを決めて放置すると知らぬ間にズレて地面が映っていた…なんてことも。
- 除菌シート(ウェットシート)
- 運動会は砂ぼこりとの戦い。手指はもちろん、カメラのレンズやメガネなどもサッと拭けて便利。
- ビニール袋
- 大きいビニール袋は、ちょっとした荷物置きにもなります。ゴミ袋や濡れたもの入れに小〜中サイズも持参しましょう。
- 日焼け止め
- シミやシワの原因になる紫外線は5月が最大量。日焼け止めクリームはもちろん、帽子や日傘、サングラスもあると便利。
- 虫除け・虫さされ
- 日陰は春でも蚊がいることが多いので、虫除けはあった方がベター。
服装について
保護者競技に出なくても、運動会中は子どもの撮影や観覧席の移動など意外に動かなければいけない場面が多いもの。
運動会の服装は、動きやすいパンツスタイルにスニーカーが定番です。
校庭が土や砂ではなく、芝生やゴム製の場合など、ヒール禁止の通達が学校から届くこともあるので必ず学校の指示に従いましょう。
天気が変わりやすく温度も変動する春の運動会には、さっと脱ぎ着して温度調節ができる薄手の羽織りやストールなど、小物を持って行くと重宝します。
そして、あくまでも運動会の主役は子どもなので、派手なデザインや露出度の高い服装にならないように気をつけましょう。
お昼時間の過ごし方
子どもの昼食はお弁当や給食になっていることが多いので、保護者は家に帰るか外食を済ませて、午後の運動会に備えます。
近隣のお店は混雑が予想されるので、もし外食予定なら予約しておいた方が安心です。
運動会は、子どもの友だちのお母さんやお父さんとコンタクトを取れる貴重なチャンス。
この機会に、普段はできないお友だち家族との交流ランチを計画してみてもいいかもしれません。
小さな弟・妹を連れて行く場合
幼い弟や妹を連れての運動会参加は、飽きさせないような配慮が必要になります。
上の子が競技に出ていない間は、「思いっきり遊ばせる」「校外に出て気分を変え、競技開始のタイミングで戻る」など、我慢をさせるのはわが子の競技の間だけと決めて、それ以外は比較的自由にさせてストレスを溜めないようにしておきましょう。
大人しく待っていられるタイプであれば、「お絵描きセット」「絵本」「新しいおもちゃ」などを持参して、お兄ちゃん・お姉ちゃんの出番の前にさっと出す。
じっとしていられないタイプなら「小袋のお菓子」「キャンディー」など、最終兵器で乗り切るのも手です。
可能であれば、「学年の違う仲良し家族で預け合う」という技もありますね。
自分の子どもを素早く見つける方法
体操服や帽子はお揃いなので、背が高い(低い)などの特徴がない場合は、わが子を見つけるのは至難の業ですね。
基本的には子どもの立ち位置を事前にチェックして、その場所を基準に探しましょう。
オペラグラスや双眼鏡も役立ちます。
そして靴下を「ハイソックスにする」「ボーダーなど目立つ色合いにする」、靴の色を「蛍光色や珍しい色にする」だけでグッと探しやすくなります。
また女の子なら髪型をツインテールにしたり(帽子が被れる程度に)、リボンやシュシュをつけても目印になります。
運動会でのスマホ撮影のコツ
運動会の撮影がOKな場合は、手軽に使えるスマホを活用するのもおすすめ。
最近のスマホカメラは高性能で、ポイントをおさえれば運動会の撮影にも大活躍します。
運動会での撮影のポイントは…
◯ ズーム機能は使わず、近くから撮影
スマホでズームしてしまうと極端に画素数が落ち、手ブレの元になります。スマホ撮影は「近くから」が基本です。遠くから撮るなら外付けの望遠レンズが便利。
◯ 動きを追わずにカメラを固定
子どもの動きに合わせて追いかけて撮影しても、「いい写真が一枚もない」ということになりがち。「徒競走はコーナーで撮る」「ダンスは最後の決めシーンで」など、撮影ポイントを決めると成功率がアップします。
◯ 連写機能を使う
動きが大きい運動会は連写機能が便利。不要な写真は後から削除すればいいので、とりあえず枚数勝負でたくさん撮影しておけば安心です。
◯ 機内モードにしておく
動画撮影中に電話がかかってくると、せっかくの撮影が中断されて電話を優先してしまいます。運動会中は機内モードに設定しておけば失敗はありません。
◯ 手ブレ防止の工夫
スマホの手ブレ防止機能を使うことはもちろん、ネックストラップをつけてピンと張った状態で固定すると手ブレしづらくなります。またグリット線(スマホ画面を分割する線)を出して、子どもの位置の目安にするだけでも有効です。
運動会での安全対策
 春の運動会とはいえ、気温の上昇により、熱中症や食中毒のリスクもあります。ここでは、運動会での安全対策について紹介します。
春の運動会とはいえ、気温の上昇により、熱中症や食中毒のリスクもあります。ここでは、運動会での安全対策について紹介します。
熱中症・日焼け対策
過ごしやすい印象の春ですが、実は1日の寒暖の差が激しく、日中は30度近くまで気温が上がることも。
暑熱順化(暑さに慣れること)ができていない体は、汗をかいて体温を下げたり、皮膚血管を拡張させて熱放散させることができず、熱中症の危険性が高まります。
運動で普段から汗をかく習慣をつけておく、こまめな水分補給をするなど、熱中症対策をしっかり行いましょう。
また4〜5月から急激に増える紫外線UV-A波は、シミやシワの原因になります。
日焼け止めクリームはもちろん、帽子や日傘、サングラスなどの日焼け対策は万全にして臨みたいですね。
食中毒対策
子どもにお弁当をもたせる場合、お弁当用に作ったおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰めるようにしましょう。
温かいままお弁当に詰めてふたをすると、湯気で湿度と温度が上昇し、細菌が増殖する環境になります。
また、おかずの汁気はよく切ってからお弁当に詰めることで、細菌の増殖を防ぐことができます。
揚げ物や焼き物など、もともと水分が少ないおかずを入れるのも良いでしょう。
完成したお弁当には保冷剤も忘れずに。
冷たい空気は上から下に流れるので、保冷剤はお弁当の上に置くと全体を効率的に冷やせます。
感染症対策
運動会は多くの人が集まるため、感染症の予防も重要です。以下の対策を徹底しましょう。
手洗いを徹底する
手洗いは、感染症予防の基本です。
運動会の前後や、トイレに行った後は必ず手を洗いましょう。
マスクを着用する
人混みの中では、マスクを着用しましょう。
マスクは、鼻と口を覆うようにしっかりと着用しましょう。
体調管理を徹底する
睡眠不足や体調不良の子どもは、無理に参加させないようにしましょう。
運動会当日は、体調を整えて参加しましょう。
これからの新しい運動会を家族そろって楽しもう

コロナ禍を経て、さまざまな背景から簡略化・短縮化傾向にある「運動会」。
みんな揃ってのお弁当タイムや昔ながらの競技を懐かしむ声もありますが、子どもにとっては今も昔も一世一代の晴れ舞台です。
子どもが頑張る姿を親子で楽しみにつつ、新しいスタイルの運動会を楽しみましょう。
・コロナ前から縮小・短縮傾向にあった運動会は、以前とは違った形での開催が増えている。
・保護者たちの声、教職員たちの負担軽減を理由に、開催時間の短縮や演目の変更などをする学校も多い。
・運動会は普段とは違うイベントなので、持ち物や服装、日焼け対策などは万全に。
・子どもの撮影は、ポイントさえおさえればスマホでもしっかり撮れる。
(参考文献)
・ベネッセ教育情報 | 待ちに待った運動会。当日のお弁当はどうしてる?
・学研こそだてまっぷ | 【withコロナの運動会事情】幼稚園・保育園・小学校で変わったこととは?
・KDDIトビラ | プロに学ぶ「運動会のスマホ撮影テクニック」
・学研キッズネット | 【令和の運動会あるある】昔と今の違いベスト5!全国の小学校・中学校事情を調査