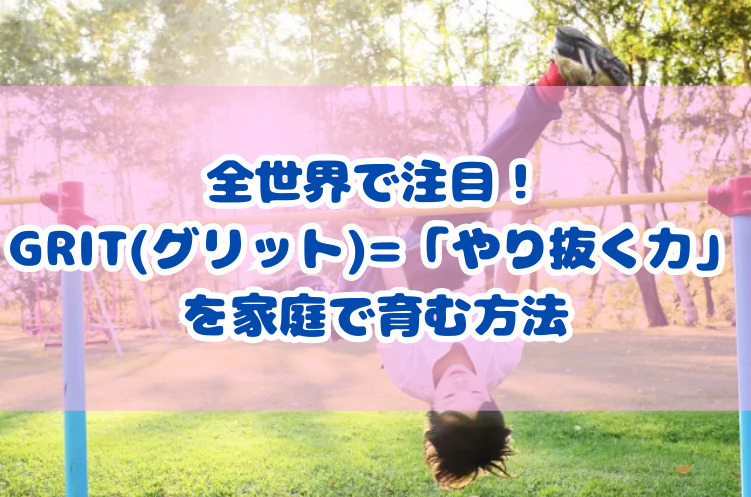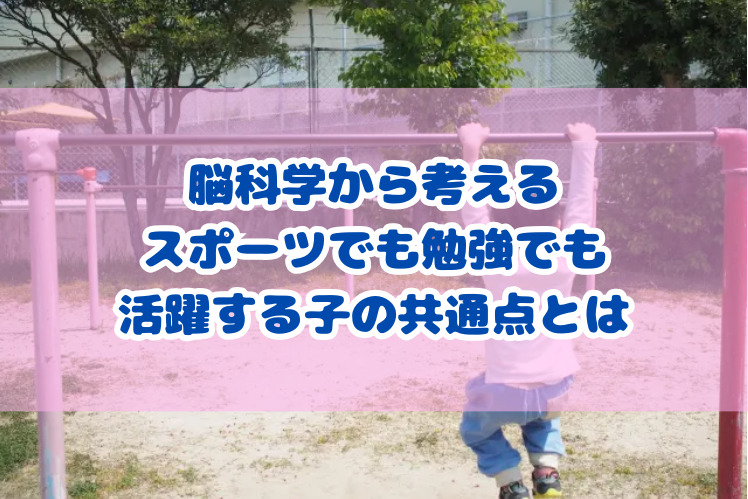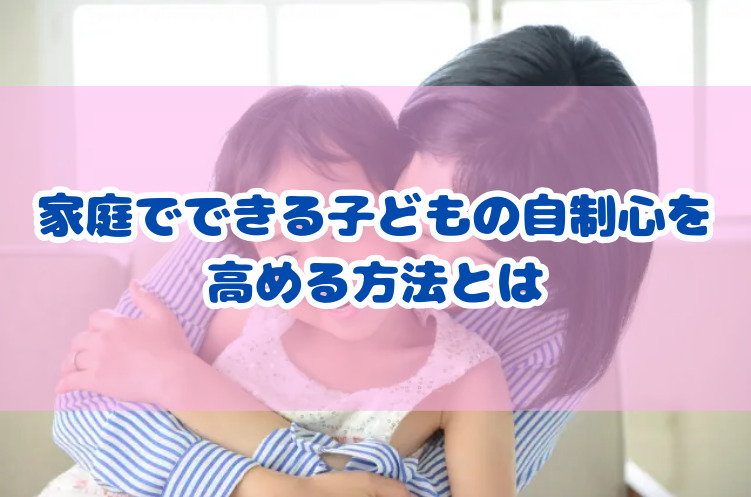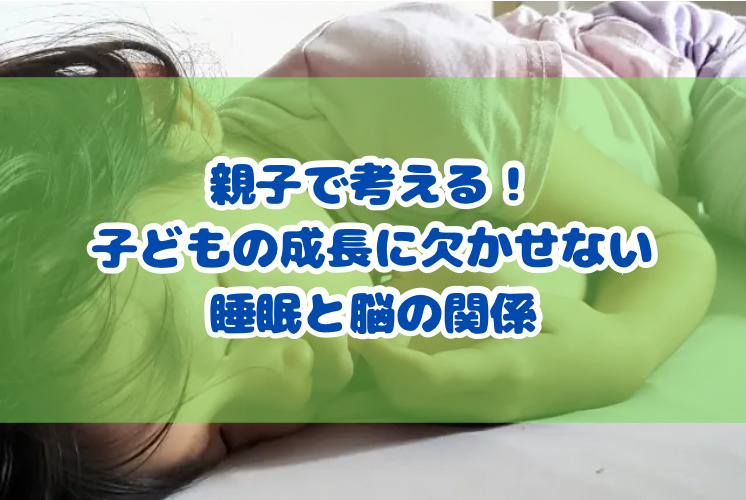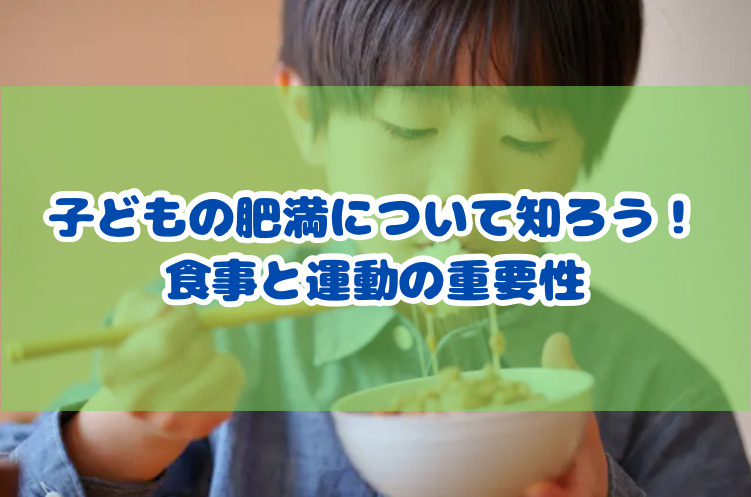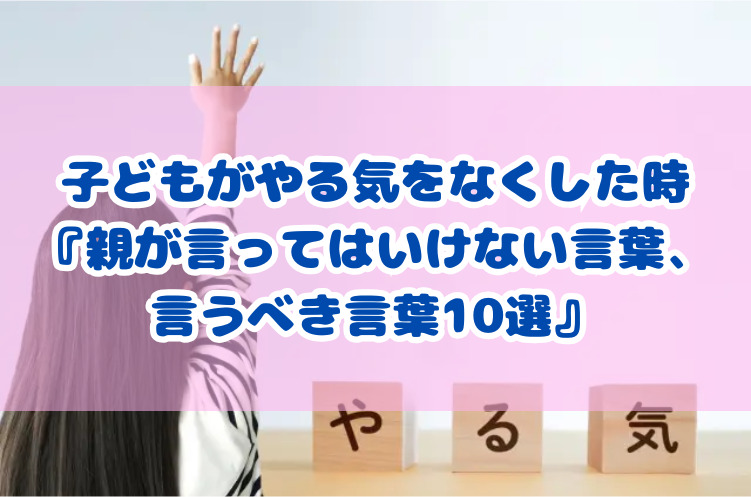運動不足も解消! 親子でふれあい遊びをしながら非認知能力を高める方法
更新日: 2025.04.16
投稿日: 2023.03.24
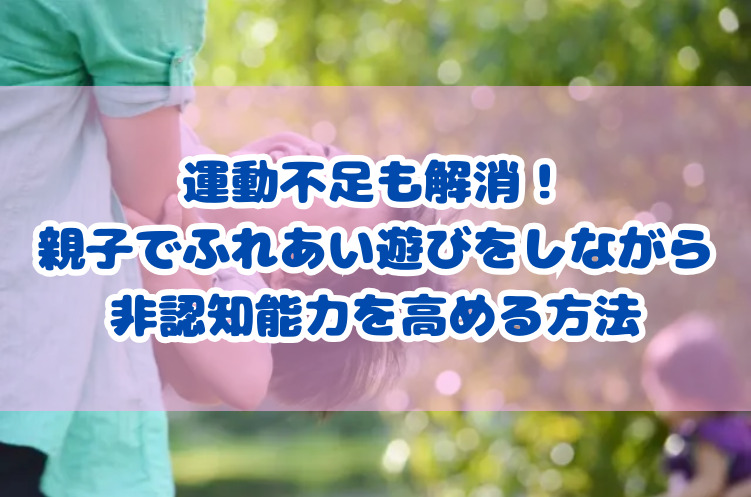
感染症対策やマスクの装着が長引き、子どもの外遊びの機会が少なくなっています。
またリモートワークやオンラインの仕事によって外出が減っている大人も、運動不足気味の人が増えているようです。
運動不足は「筋力を衰え」や「肥満」のほか、子どもの意欲低下にもつながります。
親子で一緒に体を動かし、「ふれあい遊び」をしながら非認知能力を高めましょう。
もくじ
なぜふれあい遊びが非認知能力を高めるのか

屋外で体を動かすことは、体力や筋力のみならず、子どもの意欲や好奇心、自己効力感や判断力を育むといわれます。
鬼ごっこや縄跳び、ボール投げなどの一見「遊び」に見えるような運動でも、非認知能力を高めるためには有効です。
特に親子でスキンシップを取ったり、競争しながら楽しくふれあい遊びをすることでアタッチメント(愛着)が生まれます。
そして夢中になって遊んでいる間、子どもは「フロー状態(時間を忘れて没頭している状態)」になり集中力や創造性が育まれるのです。
それには大人も真剣に、全力で楽しむことが大切。
フルスロットルで遊べば、大人の運動不足もあっという間に解消します。
年齢別 親子のふれあい遊びを紹介!

体を動かす楽しさは、幼い頃から身につけておけば一生の宝物になります。
ここでは同じ遊びでも、年齢ごとに少しやり方を変えて難易度を調整できる遊びを紹介します。
まねっこ遊び
親子で相手のポーズや動きを同じようにまねる遊びです。
相手の真似をすることで、観察力や集中力、想像力が鍛えられます。
アイデアを絞って真似されづらいポーズを考えるのも、頭の体操になります。
【幼児】大人と子どもが交代でポーズを決めて、まねし合いましょう。少し大きくなったら、動物のまねをして当てっこゲームにしたり、つま先立ちや簡単なヨガポーズなど、複雑な動きを加えてみましょう。
【小学生】ポーズを3秒見せたら、元に戻ります。相手はそのポーズを記憶してまねします。指の先や表情など細かな部分まで覚えることで、記憶力も鍛えられるでしょう。
リフティング遊び
サッカーの技術と思いがちなリフティングですが、実は遊びの要素が満載。
ボールを落とさないようにするには、瞬発力、バランス力、俊敏さ、体をコントロールする力が養われ、親子で回数を競えばさらにエキサイトしますね。
【幼児】ビニール袋に空気を入れて膨らませ、ボール代わりにしてリフティングに挑戦してみましょう。足で行うのが難しければ手でもOK。慣れてきたら柔らかいゴムボールや風船を使ってもいいですね。
【小学生】ボール以外のもの、お手玉やトイレットペーパーなどを使ってリフティングすると、予想外のバウンドをするので楽しめます。リフティングしながら親子でしりとりをするなど、頭と体を同時に鍛えるのも有効です。
背中ぴったり
2人組になって背中同士を合わせて座り、腕を組んでお互い背中を押しながら立ち上がります。
自分だけで立ち上がろうとせず、適度に相手の背中を押すのがポイント。
体幹やバランス能力など、全身がまんべんなく鍛えられる運動です。
【幼児】大人と子どもの2人組だと体重差が大きく立ち上がるのが難しいので、親子混合のグループで行いましょう。
【小学生】大人と子どもで行う場合、大人は力のかけ方を工夫しましょう。簡単に立てるようになったら、中腰のまま移動したり、回ってみたり、片足でできるか挑戦してみてもいいですね。
しっぽ取り
ズボンの後ろ部分にタオルやリボンを入れて、お互いに取り合う「しっぽ取り」。
人数が増えても面白いので、友だちの家族などと一緒に行っても盛り上がります。
体全体の筋肉を鍛えられ、相手の動きを予測する力や瞬発力、持久力、俊敏性を養えます。
ただの鬼ごっこよりもゲーム性が高く、楽しく長く遊べるので、よい運動になります。
【幼児】最初は大人にだけしっぽをつけて、子どもに追いかけさせてもOK。大人のしっぽは長く、子どものしっぽは短くするとバランスが取れます。
【小学生】チーム分けをして本数を争うなど、ゲーム形式にすると楽しめます。
遊びながら、もっと非認知能力を高める方法

屋外で体を使って遊ぶだけでも十分ですが、もっと効率よく非認知能力を高めたい時は、下記のポイントに気をつけてみましょう。
◯ 親子で作戦を立てる
◯ 子ども主体で遊ぶ
◯ 少しずつ難易度を上げる
親子で作戦を立てる
どうしたらもっと楽しくなるか、年齢が違う人が一緒にやるにはどうすべきかなど、親子で考え、話し合って作戦を立ててみましょう。
「少し難易度を上げると、もっと面白くなる」
「小さい子と一緒にやる時は、ハンデが必要」
など、さまざまな気づきがあるでしょう。
「作戦を立てる=よりよくするための工夫」なので、思考力や好奇心、やり抜く力、挑戦する気持ちが自然に育ちます。
子ども主体で遊ぶ
最初は親子で遊んでいても、つい大人の方が熱くなりすぎたり、特定のスポーツのトレーニングになってしまったり…いつの間にか、子どもが置いてきぼりになることも。
「子どもが楽しんでいるか」「親が指導者のように教えていないか」を常に意識して、子ども主体で遊ぶようにしましょう。
そして子どもが選択権を持ち、自分で「やめる・続ける」のタイミングを決めるようにすると、自立心や責任感が育ちます。
子どもが主役になることで、意欲や主体性も養われるでしょう。
少しずつ難易度を上げる
運動も遊びも簡単にできてしまうと、やる気や意欲が奪われます。
簡単にできるようになったら難易度をちょっぴり上げて、挑戦するレベルで行うようにしましょう。
この時、「難しくてできないレベル」までグンと上げてしまうと、それはそれでやる気が削がれてしまいます。
少しずつ難易度を上げて、一つずつ達成するように設定すると、達成感が感じられ、探求力ややり切る力、自己効力感が身に付きます。
・親子で行うふれあい遊びではアタッチメントが形成され、非認知能力を高める。
・大人も子どもも真剣にふれあい遊びをすることで、運動不足解消にもなる。
・「まねっこ遊び」や「しっぽ取り」などの「遊び」に夢中になることでフロー状態になり、集中力や俊敏性が同時に鍛えられる。
・親子で作戦を立てたり、子ども主体で遊ぶことで、より強く非認知能力を身につけられる。
(参考文献)
日本スポーツ協会 | アクティブ・チャイルド・プログラム
非認知能力 Lab | 非認知能力を鍛える6つの遊び!今日から親子で実践できる方法を紹介
こどもまなびラボ | 「思いっきり遊ぶ」とフロー状態に入れる!?無敵の能力を身につける3つのコツ